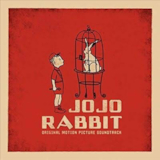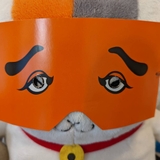ある男のレビュー・感想・評価
全556件中、321~340件目を表示
普通の仮面を持っている事の有り難さ
私は某国が大キライです。
こう言うと、私は差別主義者のレッテルを貼られるかも知れませんね?
キライになった理由も、事情もあるけど、キレイな一般常識社会は其処を考慮しない。
だから外見や、出身や、経歴、立場で人を差別しません。って常識という仮面を被ってる。普通のヒトで。
酷い過去のある方なら尚更、仮面が必要。
その人が何者であるかより
どんな人で、どんな性格かは
肩書きの仮面では分からない。
分からないから怖い。
だから様々な印象を判断材料として
人を視て判断しないといけない。
安全かそうで無いかは重要だから。
イケメンのヒトは良いように見られ易い。
無愛想なヒトは不気味に見える。
話して付き合っていっても解らないのにね。
良い仮面が欲しい人は沢山いるよなー。
そんな事を考えさせられた映画です。
無題
重く深いテーマを娯楽作品として見事に構築した面白い作品でした。
映画サイトも高評価が多いのだけれど、評論やレビューを読んでも具体的にこのドラマの何処が良かったのかを言及している書き込みは極端に少なく、言語化するのが難しい作品だったのかも知れません。ベースが推理サスペンス形式のドラマだったので、物語に引き込まれ面白く感じただけの人も多くいたでしょうしね。
“自分の過去を消し去りたい”というというモチーフで、私は今の日本の社会問題である“宗教2世問題”を想起しましたが、他にも“加害者家族”“前科者”や“犯罪被害者への二次的被害”等々、一度過去を全て消し去りリセットしたいというモチーフは、面白い作品が非常に多くある気がします。
その理由は何故か?なのですが、本作では柄本明の役(レクター博士の役割)がその象徴であり、いわゆる現実の人間社会は“性悪説”で成り立っているという事なのでしょう。
だからこそ更に“善”の部分が美しく感じるという事なのだと思います。
居場所
ここ最近の邦画は少し後回しにしていた感じがあったので、重い腰を上げて鑑賞してきました。平日の昼間は人が少なくて観客側としては大助かりです。
結構面白そう…と思ったのですが、個人的にはあまり合いませんでした。脚本家の方の作品を見ると過去にあまり好きではない作品が揃っていたのでなるほどなと思った次第です。
合わなかった理由として強いのが、差別的な要素を突然入れてきて、それらが物語に直結しているように思えなかったからです。北朝鮮だったり、在日だったり、ある男の身元探しのはずなのに突然何を言い出すんだ?とぽかんとしてしまいました。ラストの方の奥さんの不倫や、身分を偽ってみたという不思議な終わり方もスッキリしなくて今まではなんだったんだ?と思わざるを得なかったです。
役者陣はこれでもかというレベルの豪華な布陣で、少ないシーンの中でも河合優実さんの魅力ががしがし発揮されていました。窪田正孝さんの何役も演じ分けていて、しかも筋肉ムッキムキ、恐れ入りました。
役者陣は最高ですが、お話がそぐわなかったです。これもう少し削れたよな…。
鑑賞日 11/29
鑑賞時間 13:25〜15:35
座席 A-2
安藤サクラの演技が光る。
その人の何を知っていて、何を愛して、何が真実なのか
何年も暮らした夫が死後、まったくの別人だとわかったら?めちゃくちゃ重かった…でも安藤サクラ、窪田正孝、妻夫木聡、3人ともハマり役で上手すぎて、あっという間の2時間。過去が明らかになる様も同時進行のやりかたも丁寧でよかったし、脇を固める役者たちも皆素晴らしかった。
少しだけ出てくるような脇役まで、驚くほど豪華だったな。清野菜名、眞島秀和、仲野太賀、でんでん、きたろう、柄本明、真木よう子、河合優実…隅の隅まで笑っちゃうほど豪華で盤石の布陣だった。そりゃ見応えあるわけだわ〜
なのでほんと無駄も隙もなく緊張感を保ちながら良作に仕上がっています。
しかし最後の最後のオチはちょっとやりすぎな気もした?どうだろ、あれが面白く感じる人もいるかもですね。妻の浮気や民族的ヘイトからくるストレスで、名前変えてまで逃げる必要あるかしら?結局、帰化したものの元在日であることを否定的に捉えてたとも考えられるし…
そして最後の息子くんの「お父さんはしてもらいたかったことを…」とか「僕が話してやるよ」とかはちょっと台詞すぎて気に掛かりました。
これらの終盤での一部以外は良かったですね。
作中に出てくるこの絵、ハマスホイかルネ・マグリットっぽいなーと思って後で調べてみたらマグリットでした。絵のタイトルがまた絶妙で、「複製禁止」。粋だなあと思いました。
偽らないと生きられない人がいる
自分を偽らないと生きられない人間がいる。
城戸の強い叫びがずっと頭で反芻している。
その人の存在、幸せだった時間どれが事実で人を救うのか考え続けてしまう映画だった。
本作は人のアイデンティティを問う作品でその人となりどう生きたかまでが分かるほど人物の解像度が高く、迷い込んでしまった。
何と言ってもキャスト陣の掛け合いは凄まじく、窪田正孝の絶望、狂気、壊れてしまいそうなほどの脆さと穏やかさ全てが入り混じった演技は本作のMVPだったと思う。
本作の主演である妻夫木聡の哀愁、何かに囚われ続けている表情がこの映画の雰囲気を作り上げていた。
決壊した時の凄まじさが彼にしか出せない迫力だった。
柄本明の悩み続ける城戸を常におちょくり、深い闇に誘う怪演はこの映画のハイライドだと思った。
出てくるだけで凄みがあって、一気に引き締まってた。
血のつながり、その人自身のアイデンティティ、実際に過ごした時間どれが人を表せるのか最初から最後まで全編通して見る人に訴えかけられた気がした。
理解はできないけど
登場人物の気持ちになってみたら
もし自分が同じ立場だったら…どうしただろう、どう思っただろう。
そんなこと考えながら見てました。
もし、自分を変えることができたなら…私も今すぐ変わってみたいとも思いました。
で、最後のシーンは結局そういうことなんだよね?
妻夫木聡さんって
"測り難きは人心"他人が羨む経歴にこそ闇がある... 令和版のサラリーマン"蒸発"物語の映画
とある女性が再婚するもその相手と数年後に死別。告別式にて初めて対面した親族の証言で彼が全くの別人で名を騙っていたことが解り、彼女が知人の弁護士と共に彼の正体を探っていく中でその入り組んだ複雑な事情と人間模様が明らかになっていくミステリー。
数々の文学賞を受賞している平野啓一郎さんの小説を原作に、『愚行録』
『蜜蜂と遠雷』で知られる石川慶監督の手で映画化された作品で、特にラストの主人公の人間性に観客が惑うような不穏な展開は、同じ妻夫木聡さん主演作品ということもあり、『愚行録』のそれに通ずるものを感じました。
人一人が過去を捨てて別人として生きる…というと、例えばとんでもない額の負債を抱えるとか重大犯罪を犯してしまうとか、大半の人間が経験し得ない"積み"状態の末の已むに已まれぬ究極の選択のように思えてしまいます。
しかしながら本作を俯瞰すると、人間誰しも自らの置かれた境遇に往々にして満足よりも閉塞感を見出してしまい、しかも傍から見るとそれと理解出来ないために当人が余計に孤独を深くする、という構造は遍く人間関係に存在するのかも、と思えます。
正体不明の人物の素顔を追うミステリー展開だけでもなかなかに重厚でしたが、そこに石川監督らしいモラルを揺さぶる捻りが加えられたなんともシニカルなどんでん返しも待ち構えていて唸らせられました。
いわゆる"胸糞映画"の類にも属するかもしれず、人によっては純然たるミステリー要素だけを期待して結果消化不良となるかもしれません。
しかしながら実力派キャスト陣の力演によってその出演尺に関わらず各キャラクターに奥行きが出ており、それぞれの登場人物が何故今のようになってこれからどうなるのか、といった余韻も生まれる秀作だったと思います。
役者さんが良かったです。
出自
なるほど
私は何者?
【鑑賞のきっかけ】
原作は未読でしたが、既にご覧になられた方の評価も高く、ミステリ的な物語展開に興味を惹かれて、鑑賞してきました。
【率直な感想】
<アイデンティティーを巡る物語>
本作品の物語の出だしは、離婚歴があり、息子と暮らす里枝(安藤サクラ)が、谷口大祐と名乗る男性(窪田正孝)と知り合って再婚。
その後、女の子が生まれ、仲睦まじく暮らしていたところ、夫・大祐は不慮の事故で亡くなってしまう。
弔問に訪れた親族は、仏壇の写真を見て、「大祐ではない」と断言。
果たして、夫は何者であったのか?
里枝から依頼を受けた弁護士(妻夫木聡)は調査を開始するが…。
ということで、ミステリの手法を用いた物語展開はとても興味深く鑑賞することができました。
鑑賞しながら思ったことは、本作品のテーマは、「アイデンティティー(自己同一性)」ではないか、ということでした。
つまり、自らの人生をひとつの連続体として支えているもの、本当の自分とは何者であるのか、という問いかけです。
谷口大祐と思われていた「ある男」は、自らの戸籍(本名)を捨て、谷口大祐の戸籍を手に入れて里枝と結婚生活に入っていたのですが、自分の名前を捨てるというのは、よほどの理由がないと出来ることではないように思います。
私は、ネット空間では、このサイトだけではなく、読書感想のレビューを載せる別サイトでも同じハンドルネームです。
ハンドルネームは、いわば単なる符合でしかありませんが、恐らく、映画鑑賞や読書の結果として、レビューを執筆し、掲載するというネット空間での人生で、アイデンティティーを保つための手段として、同じハンドルネームを使っているのでしょう。
現実世界の私は、もちろん他人の戸籍を手にして、名前を変えるなどということは考えたことはないけれど、やはり、生まれてからずっと名前が同じということで、自分のアイデンティティーを保っているのかな、と考えています。
<アイデンティティーと対峙する登場人物たち>
名前というアイデンティティーについて、真剣に対峙してきた登場人物が、谷口大祐を名乗っていた「ある男」なのですが、本作品には、この他にも、アイデンティティーに対峙する人物が複数登場します。
一人目は、里枝。彼女は、離婚をして、旧姓に復していましたが、再婚して、「谷口」里枝として、三年を過ごしてきました。
ところが、夫が本当は谷口大祐ではなかったことで、「谷口」里枝という三年間の人生が無くなってしまった。
そこで、自分のアイデンティティーを取り戻すために、夫が本当は何者であったのか探ろうとしていると捉えることができます。
二人目は、「ある男」の正体を探る弁護士。彼もまた、私生活では、自らの生い立ちから、アイディティーに疑問を感じ、どう向き合うべきか、悩んでいるという存在です。
三人目は、柄本明演ずる、ある罪を犯して、刑務所で服役中の男。何がきっかけかは分からないけれど、アイデンティティーについて、彼なりに対峙し続け、結果として、犯罪という道を選んでしまった人物です。
四人目は、里枝の息子。少年なので、複雑な心情ではないかもしれませんが、里枝が離婚し、再婚するたびに、苗字が変わって戸惑っていた。そこへ、母が再婚した父・谷口が本名でなかったことで、母・里枝は再び旧姓に戻ると聞かされる。素朴なアイデンティティーへの不安です。僕の本当の苗字は一体何なんだ?
本作品が、娯楽性の強いミステリと大きく違うのは、上記のように、「あの男は何者?」というミステリとしての謎の周辺に、「私は何者?」という疑問を抱く複数の人物設定を施し、深い人間描写を表現する作品となっているところだと思います。
【全体評価】
娯楽性の強いミステリ作品も好きですが、本作品のように深い人間描写を感じさせるミステリも良いものです。
本当の自分というものは、いくら追い求めても見つからないもので、多くの人は、「ある男・ある女」で一生を過ごしていくのかもしれません。
戸籍が人ではない
原作の深みをどこまで表現できるかの挑戦
アイデンティティの揺らぎ
事故で亡くなった夫が名乗っていた姓名とは別人と判明し、人物調査を依頼された弁護士がはからずも自分のアイデンティティの揺らぎを感じ始める話。
戸籍を変えていた夫だけでなく、夫が別人だったと判明し突然苗字が無くなる妻と息子、自分が"在日"であるということにコンプレックスを感じており、確かなものと思っていた家族の愛も揺らいでいくことになる弁護士、それぞれにアイデンティティの揺らぎが生じる。
このアイデンティティの揺らぎ的なモチーフは人物描写だけでなくて、ちょっとした会話にも色々盛り込まれてるみたいで面白かった。例えば、パッと見は全部同じに見える木や魚に名前をつけるという行為は、外部から見た人が勝手につけたものだし、ましてやそれが二度目に聞いた時に同じもののことを言っているのかは会話をしている人達の信じる心次第。
だから、確かな愛に触れた妻と息子は名前が揺らぎながらも自分達のアイデンティティをしっかり取り戻す。一方で、確かな愛だと思っていたものが崩れた弁護士の章良は正反対の結末になる。(このアイデンティティが崩れる直前にビールを妻と交換してそれっきりなのもね!)
でも私的に章良は「アイデンティティを無くした男」というアイデンティティを確立したように見えたんだよなぁ。だって、実際に名前を何度も変えてた夫・大祐は自分の過去のことをあまり話さなかったと言っていたけど、章良はこんなに自信満々に"自分の過去"について話してるんだもん。
結局このラストも飲みの席でただホラ吹いてる男と見るか、アイデンティティを完全に失った哀れな男と見るか、新しいアイデンティティを持った男とするかは見る人全てが各々勝手に名前をつければ良いことなんだろうなぁ。
とにかく、最初「ある男」だと思っていたはずの男は「ある男」ではなくなり、別の男が「ある男」になっていた。これ以上完璧なラストはないと思う!!震えた!
「ある男」ってボクのこと?
皆何かしらの闇を抱えて生きている。そんな自分から逃げ出したくて、話を盛ったり、嘘を吐いたり、いはばプチなりすましをして生きている。ボク自身、原誠ほどの闇は抱えてないけど、ビンボー育ちにはそれなりの劣等感を抱えていて、自分の過去を少し詐称して身の上話をしたこともある(学生時代ね)。小学校しか出てなかった優しい親父は、いつも学歴を詐称していた。
最後に妻の不倫に城戸は気付く。しかし問い詰めたりはしない。問い詰めたって追い詰めれられた妻は自分の心を守るために、結局夫をなじるだろう。自分は悪くない。悪いのはこういう状況に追い込んだあなたなのだ。不倫せざるを得なかった自分になりすますのだ。
そして城戸は自分の心を守るためになりすましを決行する。ボクは群馬の老舗旅館の次男坊谷口大祐です。
最後の里枝の言葉が胸を打つ。
「結局、彼の過去なんてどうでもよかった」
家族として幸せに暮らした3年9か月がすべてだってこと。
ウソだのなりすましだの、どうでも良いことに思えてくる。今目の前に起きていることは自分には知り得ない過去があって、その延長として起きている。だから、今目の前にあることを信じて生きていけば良い。
全556件中、321~340件目を表示