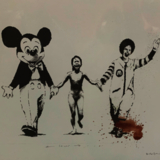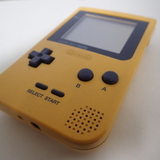こちらあみ子のレビュー・感想・評価
全115件中、61~80件目を表示
あみ子を理解してくれる人や、あみ子の居場所があったら、もっとあみ子...
自分の意思が不変であれば人間は生き続けられる
あみ子から見る世界はけっして壊れていない。
弟(妹)の死は、「生まれてきたもん。生まれてきたけど死んどった」
母親は心の病になり、兄は不良になり、両親は離婚へ。あみ子も不登校に。
端から見ると壊れているのに、あみ子の世界はやはり壊れていない。
そこに、壊れていく運命に翻弄される少女の姿はない。
その類のお涙頂戴の物語は数多くあるけれど。
運命は変えられない。世間の目も変わることはない。
でも自分の意思はいつでも変わらない。
自分の意思が不変であれば人間は生き続けられる。
原作の今村夏子のポリシーが、見事なまでに再現される。
映像でしか描けない、あみ子この一瞬見せる悲しげな表情にぐっとくる。
あみ子のイメージにぴったりの大沢一菜に目が潤む。
待っているよ
文章で読んだ時よりも映像になるとギラギラとしたあみ子がそこにはいた 枠におさまりきらない感情のパワー
乾電池で例えるとあみ子は直列回路で自分を表現するタイプ多くの人はおそらく並列回路
そんな印象
裸足でドタバタ大袈裟に床を歩いてみた
あみ子の気持ちに近づきたくて そしたら少しだけ悲しくなった
応答せよ…こちらあみ子 無関心にされることほど心細いことはないよね あみ子は人と繋がることが苦手というか空気が読めないとこがある でもそこには全く悪意がない だから周りの人は疲れ果ててしまう
あみ子が応答せよと言えば言うほどに人は離れていく ただ世の中はそんな人だけではなく坊主くんみたいな子は必ずいてさりげなく気にかけてくれる
そのことに救われた
付かず離れずのお父さんにも
のり君の「殺す」と坊主くんの「殺す」は同じ言葉でも全く意味合いが違うし「おれだけのひみつじゃ」の言葉はあみ子の心にもさざなみのようにやさしく広がったろう
トランシーバーの波長のようにさざ波があみ子に寄せる
人の違いを尊重し痛みに気付ける世の中へ
あみ子から連絡きたら応答できるかな?
何て応えようかな?
待ってるよ
追記 やはり書いておこう…
高校生の頃バス停で待っていたら小学生の男の子にいきなり抱きつかれたことがある軽くフワッとした感じだったけど
何?と考える間もなく身体が硬直した
すると近くから、やめろやめろと冗談混じりに先生が生徒に言う声がした
別にその時はそれで流したのだけれども…
後から生徒が謝れないなら先生に謝ってほしかったと思ったことがある
もちろん悪意の無い行動だとは分かっていたけれど
今回こちらあみ子を観て思い出した今でも覚えてること
子供時代との決別。
人は皆自分の内なる世界を持っている。同じ世界に住んではいても人々の内なる世界はそれぞれ異なる。社会においては成長する過程において皆が内なる世界を捨て、あるいは外の世界と折り合いをつける術を身に着けてゆく。
あみこはそれが出来ないかあるいは人より遅れている。だからなにかと外の世界では変な子と見られてしまう。
画一化を目指す今の日本の学校教育では天才は育たないと言われる。子供の個性を伸ばすのでなく同じように行動する人間の育成が第一だからだ。かつて軍隊や工場労働者の大量生産のためにはそれでよかったのかもしれないが、現代において新たな発想ができる突出した能力の育成には不向きであろう。
あみこは学校でもつまはじきにされ、家庭も崩壊してゆく。父にも捨てられたあみこは内なる世界の住人と別れを告げる。そうして彼女は子供時代との決別を遂げるのであった。
現実世界の外側で。
観賞後の疲労感足るやなかなかのものでした。予告の限りでは風変わりな女の子と家族が繰り広げるハートウォーミングな日常の物語と思っていたけど、甘かった。
小5のあみ子は落ち着きがなく思い付いた事に猪突猛進。空気が一切読めず一人で喋り続けている。劇中言語化はされていないものの発達障がいを抱えているのは明らかで、家族は四六時中振り回され続けている。
自分が実際家族として関わることを想像すると気持ちが持たないかもしれないと思った。家族はもちろん地域や学校の理解は必須。でもそれがないあみ子の家族は結局崩壊してしまう。母親の違和感。父親の無関心。兄の逃避。なんだかんだ一番の理解者が名前すら覚えていないクラスメイトというのは皮肉だ。この先あみ子がどう成長してゆくのか。壊れたトランシーバーから返信はない。
評論の必要性
大変にモヤモヤする、心の蟠りが消せない作品である。本当に難しく、このテーマに対して毎日、否、毎時間心の中で白黒が入れ替わる"オセロ"のような心情変化を繰り返させる正に普遍な問題である。
表題どおり、こういう作品は絶対に評論が必要だ。感想ではない、プロの評論家のロジスティックな建築的論評だ。そこには自分の気づき得なかった視点や、見えない所へのイマジネーション、そして腑に落とすヒントが示唆されている。
単に脊髄反射の如く、今作品を咀嚼できないという諸兄にはキチンとプロの論評の、感情とは一線を画した冷徹な理論をフィルターとして通すことで、如何に自分が映画を”ボーッと”観ていたかを恥じることになることを体験して欲しい。それでいいと思う。その”恥”を受け入れることで本当の意味の映画ファンにステップアップしていくのだから・・・
毎週、映画評を自腹(真贋は置いておいて)で観てのラジオで発表するラッパーは、7月29日(金)にこう言った。「もしかしたらカメラの視点は、一貫して言及されない誰かかも知れない・・・」と。
今作品、不思議なことに前妻の事は一切触れない。あの隠し事が一切できない(チョコクッキーの件は喋らない都合の良さは否めないがw)主人公が、この件に対して一切台詞として言及していない、又は妹を弟と間違った件も、勝手に妄想するに、過去にいたかも知れない産みの母やかつて存在していた弟が、寄り添うようにこの主人公を見守っている視点で描かれているのではないだろうかと・・・ だからこそ、スタッフロール中のエンディングテーマ中に主人公の問いかけと、曲中の『もしもし・・・』が呼応しているのではないだろうかと・・・ 勿論、パーソナリティはそこまでは発言していない。でも、ヒントをどう取るかは、観客の裁量である。
鑑賞後のティーチインでの今作監督の登壇で、もし質問を受け付けられたら是非訊いてみたい内容ではあったが、でもパンフレットにその答えが載っているかも知れない。私は財布に余裕が無かったのだが・・・(泣)
本当に心の中を語ろうとしないのは誰なのか、を考えさせる一作
たまたま鑑賞した回が、監督や主演俳優の舞台挨拶込みだった、という幸運に恵まれた本作。子供達の生き生きとした姿が印象的な作品でしたが、撮影現場もまったくその通りだったようで、楽しそうに撮影の思い出を語る若い俳優達と、ちょっととぼけた感じでコメントする監督がとても印象的でした。
本作が劇場長編映画の初監督作品となるという森井勇佑監督ですが、そうは思えないような入念な物語構成と計算され尽くされた撮影、そしてテンポの良い編集など、舞台挨拶の穏やかな印象とは異なって、映画に対する強い熱意と愛情、そして経験の厚みが伝わってきました。
劇中ではあまり具体的には言及されていないのですが、主人公あみ子(大沢一菜)は生まれつき、あまり他者との意思疎通ができないようで、家族もあみ子に優しく接しつつ、あみ子の言動に振り回されることに疲労している様子です。学校では級友たちからも「変わった子」と見なされ、友達の輪に加えてもらえない様子ですが、あみ子は周囲の反応をそれほど気にしている様子は見られません。
だがある大きな事件がきっかけで、家族の軋轢が増していきます。実はあみ子は他者に対して共感することは難しくとも、どのような状況にあっても自らの考えについては包み隠さず、率直に伝えていることが分かってきます。一方で、あみ子よりも「正常」と考えている家族の側は、自分の気持ちを正直に周囲に話していたかというと…。しかし正直なあみ子が幸せになっていくのかというと…、と物語は決して期待したような方向に進まず、非常に印象的な着地点を見せます。
あみ子の想像と現実の狹間があいまいになっていく場面、あみ子と真っ正面から向かいあって対話を重ねていくある友人の表情、会話の内容がいつまでも印象に残りました。
面倒臭い子供の映画
原作未読です。
ベタな子供映画の傾向って絶望的不幸の連続からある程度の努力と
強運と良い人過ぎる周りの支援でその不運から脱却して
大団円を迎える安っぽい涙の感動作…なのですが
これは異色過ぎる現実的な話。
人生経験の少ない子供は空気が読めないから残酷な言動も平気だし
周りの迷惑も関係無し。あみ子も身内にはいて欲しくないタイプ。
中盤母親が継母な事が判明しなんとなく子供によそよそしいのも納得。
父親も中学生の息子がグレてもお構い無しの無関心ぶり。
後半ある事がきっかけであみ子と継母との間に埋めようのない溝ができ
祖母の家に預けられ家族離散の危機。
ここで挽回すると普通の話なのだが前記の通り異色作。
ええ〜そこで終わりかよ。
イレギュラーな話は好きだけどこれはどこが映画化する程魅力的なのか
良くわからん話だった。
弟のお墓
おーとーせよ、おーとーせよ
おーとーせよ、おーとーせよ、、、
このあみ子の呼びかけに、
応答しないが見守るよ(とも取れる)という解釈が、
今村夏子原作を映画化する時の高難度のキーワードだ。
言動のピントがずれている主人公に、
カメラもピント(こころの)を合わせない。
今村原作は、
軽妙に戦慄を感じさせながら、
解決不能の人間関係や、
社会問題をぶっ込んでくる、
言葉が闇を纏って刺さってくる、
それが魅力で、なおかつ、
的確な文章で、
行間でピントをぴったり合わせてくる。
映画は全部丸出し。
行間は基本的にはない。
どうやってピントを合わせるか。
今後もどこからか現れてくれるだろう、
ウルトラの兄、
兄自身も育てていた鳩と決別した、
鳩の卵は残した。
ウルトラの妹とはさよならした。
舟に乗っていた、むらさきの、、、、
ではなく赤いスカートの妹。
ウルトラの父と母もう要らない、、、
応答せよ応答せよ、
こちら観客、
大丈夫か?
大丈夫だ。
見事なピントだ。
と解釈した人にとっては傑作。
カットを割って細かく語ると、
今村ワールドが色褪せる、
高難度のキーワードを、
結果的にはだが、乗り切った。
受け入れることができなくても、認めることはできる
『ONE PIECE』を観るために並んだ大勢の人々の間を縫って、目的のシアターに入る。観客は十人に満たない。そりゃそうだろ、こんなめんどくさそうな映画だれが観るんだ。
観終わってため息が出る。なかなか厳しい作品だった。
原作はもっとあっけらかんとしていたように思う。そして、引っ越して行った先の田舎で、居場所を(たぶん)見つけたあみ子のことを、もう少し詳しく描いていたように思う。
あみ子は大人のことがわからない。大人もあみ子のことがわからない。でも、わかってほしい。受け入れることができなくても、認めることはできるだろう。あの丸刈りの少年のように。
井浦新演ずる父親の姿が胸に痛い。問題と真正面から向き合わず、常に目を背け続け育児放棄。あげくの果てに娘を実家に《捨てる》。ことなかれ主義の行き着く先。
父親はそれを「仕方のないこと」だと思っているに違いない。だが鏡写しのようにその姿を見せつけられた私たちには、本当にそれが「仕方のないこと」だったのかという疑問が芽生えてしまう。
発達障害を抱えた子どもたちへの社会的支援がうんたらかんたらというゴタクを吹き飛ばしてしまうほどの、主演の大沢一菜のナチュラルすぎる演技。彼女の出ている場面はまるでドキュメンタリー映像みたいだった。
この作品の最大の難点は、オバケたちを出演させてしまったことだと思う。
発達障害に幻覚症状が生じることはめったになく、誤解を招きはしないかと心配である。
ひとつの家族の在り方
大沢一菜さんが、
あみ子が、
あまりにもインパクトが強くって…
お父さんは、 “後添えさん > 子どもたち” なのね。
まぁ、実際にあるからなー、
周りにこのパターン。
あみ子のような個性のある子どもではなかったし、
何かやらかしたわけでもないのに、リアルに父親出ていったからなー。
ということで、ストーリー云々や、
何かのメッセージを受け取ることはなかったです。
こういう、ひとつの家族の在り方を観た感じ。
内容に関しては、そこまで感動も受け取るものもなかったですが、
配役も含めて、子役たちが本当に素晴らしかった。
大沢さんは、もちろんだけど、
お兄ちゃんの奥村さんも良かったなー。
お兄ちゃんだけは、なんやかんやあっても、ずーっとあみ子の味方だよね。
ベランダのオバケをやっつけに来たシーンは、少し泣けた。
心のトランシーバーで繫がっていたのかな。
憧れの のり君も良かったし、
個人的には、隣の席の坊主頭の子のキャラクターがリアルでね、微笑ましい。
観終わって思ったことは、
最終的に、あみ子には、新しい環境で強く生きて欲しい。としか…
嫌な思い出
私にはあみ子、兄ちゃん、お父さん、お母さん、ノリ君、各々の気持ちが理解できます。あみ子程に重症ではありませんが、あみ子のような人物が身近に居たからです。私の場合は親の立場ではありませんでしたが、最終的にはお父さんと似た様な選択を取りました。その選択に後悔はありません。逆にそんな選択肢があったことを知らず、1人悩み続けてきた莫大な時間を後悔しています。今はようやく自分の人生を創造できているんだなと思えます。
一方、私自身もあみ子同様、目に映る外の世界を理解するのに苦労するタイプでもありました。そんな私には最初、お父さんは健気に映りました。けれど、他のレビューを見ているとどうやらその認識は見直さないといけないのかなとも思うようになってきました。これはドライブマイカーのテーマでもありましたが、「見たくないものを見ない。それに対して向き合わない。」という行為は、場合によって命取りとなるからです。お父さんを肯定する一方、余裕が生まれれば見たくないモノと向き合う瞬間も作らないといけないのかなとも思うようになってきました。あみ子の様な人と積極的に付き合きあおうとは二度と思いません。しかし、社会活動する上では避けられない場面もあります。付きっきりはしませんが、あの坊主頭の同級生の様に一瞬でもいいから損得抜きのコミュニケーション出来るようになりたい、それが出来る勇気が欲しいと思うばかりでした。それができるようになった時、自分の目に映る世界はまた変わるのかなとも思いました。
それにしても嫌な思い出を回想する羽目になり、珍しく映画を見るのが嫌になりました。それが映画の果たす役割でもあるんですけどね。次は娯楽作が観たいです。
どこか覚えのある風景
演技未経験とは思えない存在感
広島に住む小学五年生の田中あみ子は「変わり者」だがお父さんとお義母さん、お兄ちゃんと暮らしていた。臨月になっていたお義母さんのおなかが破水し病院に向かうが死産してしまう。あみ子は死んだ弟の墓を作ってお義母さんを喜ばせようとして「サプライズ」を用意したが、逆にショックを与えてしまって家族がバラバラになるほどの出来事を起こしてしまった。
『むらさきのスカートの女』で161回直木賞を受賞した今村夏子が処女作『あたらしい娘』(のちに『こちらあみ子』に改題)を初監督の森井勇佑氏がメガホンを取った。主役のあみこ子を演じたのはオーディション330人から選ばれた新人大沢一菜さんが、スクリーンいっぱいにその存在感を解き放っていた。一番強烈だったのがあみ子の兄が予想外の変化で、なぜああなったのか気になるところでした。
全115件中、61~80件目を表示