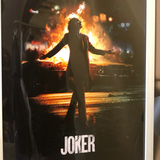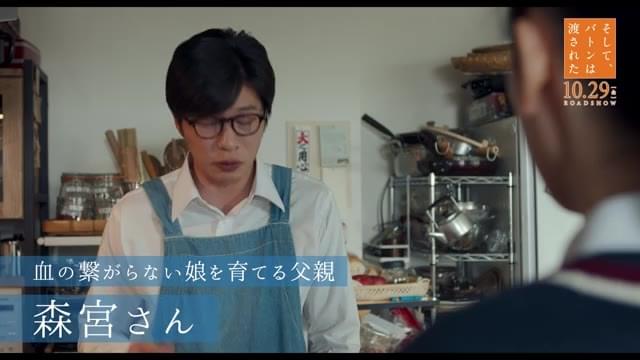そして、バトンは渡されたのレビュー・感想・評価
全563件中、241~260件目を表示
家族モノに涙腺が弱いので・・・
これは賛否分かれるのでしょうね。
構成の仕掛けは割と早くにそういうことなんだろうなと気づいてしまいましたが、ミステリーではないのでわかる人には早い段階でわかってしまっても良いのでしょう。
出てくる人みーんな良い人過ぎる!
そこも含めて私はずっと泣いちゃってました。
中盤の卒業式のシーンからもう勝手に感極まってましたね。
・・・ネタバレ避けると何も書けない作品ですね。
ストーリーの甘さと、ややお涙頂戴風に作り上げているので、そこが引っかかっちゃうと厳しいのかもしれませんが、私は素直にわんわん泣いていました。
萩原みのりさんの使い方が少し残念。終盤何か絡んでくるのかなぁと思ってたけど何もありませんでしたね。勿体ない!!
映画の終盤、『いいタイトルだなぁ』と、つくづく思いながら観た
前知識、全くなし。
他の映画と、どっちを観ようか……と迷って、座ったシート。
なにが起こるのか……?
突拍子もないストーリー展開と、いまいち納得できないキャラクター。
しばらく、なかなかはいりこめなかったけど、映画が始まって約1時間で納得。すごく、とっても。
(だまされた。
最近、タイムラインということばが流行りですけど………。
ど真ん中の球をどんどん投げられていたのに、全く気づかず三振しまくっていた感じ)
前知識なしで映画館で観てこそ出逢えた、『良い映画』。
家族の物語は、ロードムービーなんだなあと思った。
(大好きな、瀬尾まいこさんの小説が原作でしょ!本当に忘れてた!)
そして、石原さとみさんは天使だったんだな。と、今、思う。
泣いてしまう。
好きな人に薦める映画。
総合的に!
脚本の妙
優しい世界の話だった。
なんとなくこんな感じかなー?という大まかな想像通りだったけど、"ママ"については完全に想像とは違った。
みぃちゃん=優子かな?というのは早い段階で感じたけど、名前が違うから「?」と思ったらそういうことか💡
俳優が石原さとみだったので、その色眼鏡があったのかもしれないけど、完全に銭ゲバだと思っていたママはまさかの子ゲバ。
他人の子どもをあそこまで愛せるとか本当にすごい。
そして3人のパパ達もなんてできた人たちばかりなのか…。
特に市村正親。懐広すぎでしょ。
優しい世界の話だった。
"笑っていればハッピーなことが起こる"
本当にそうだと良いな。
そしてバトンは渡された
とてもいい映画で、エンドロール皆さん席を立ちませんでした。めいちゃんの合唱コンクールのシーンは自身の思いでと重なりうるっとなりました。生徒は生徒の立ち位置、親は保護者の立ち位置で、それぞれに感情移入できる作品と思います。子供がお母さんを思う気持ち、所々グッと来て涙しました。周りもすすり泣く音聞こえて、見終えた後、なんだかほっこり優しい気持ちになりました。
優しい心になれる映画です
自分も頑張らねばと思わせてくれた映画
ウルッとはくるけど、かなり無理あり
親の都合で4回名字(苗字?)が変わったのと、永野芽郁が彼女だったのが、ポイントなんだろうけど、親の都合で名字が変わったのは2回だけ。それに、自分のこどもを、名前と関係ないあだ名で呼ぶのはやっぱり不自然すぎる。
あと、そんな都合よく病気になるんかなぁというのも、なくはない。
でもまあ、石原さとみと永野芽郁が良かったので、観て損はなかったかな。
特報の書店員絶賛編で、「2時間泣き通しの映画は初めてです」とコメントしてる店員がいたけど、この映画(に限らず)の冒頭から最後までずっと泣いてたのなら、病院に行った方が良い。
笑顔でいたら、ラッキーがやってくる
良作ではあるけれど
泣けると大絶賛の嵐ですが、違和感ありです。
俳優陣は好演しています。全体として上品にまとめられていると思います。でも、良い人ばかり出てくる、そういうストーリーにみんな癒されたいのでしょうか。
もちろん、人間関係の醜さばかり見せることがリアルとも限りませんが、この映画はリアルとは程遠い、ファンタジーを見せる映画になっています。
優子がよそ見をしながら(客席を見ながら)ピアノを弾くシーンはまるでダメ。
プロのピアニストが表現の一つとして目をつぶって演奏したり、上を見たりということはありますが、そのようなプロでさえ鍵盤からそんなに長く目を離すことはありません。ましてや、優子は練習でつっかえつっかえだったので、鍵盤から目を離さずガチガチに演奏するはずです。監督以下、演出の人たちは何をやってたのでしょうか?ピアノ弾いたことがある人は一人もいなかったのでしょうか?ファンタジーだとしても演出があまりにもいい加減です。
全体に話は淡々と進み、事態が深刻になるようなところはほとんどありません(貧乏な時代はありましたが)。伏線も静かに回収される感じで、そんなに驚きは無いです。いい人たちに囲まれて良かったね、で終わってしまい、あまりに淡泊な気がします。
良い映画だと思う人がいることは不思議ではないですが、みんながそんなに大絶賛するほどの映画とは思えません。号泣するという点に関しては、やや理解の外です。
演技は良かったが、リカさんに感情移入できない
結論、血のつながりは重要ではないということを言いたいのは分かった。それはテーマとしてはわかる。
しかしリカには全く共感ができないし、腹立たしくなるほどだった。
結局のところ、子どもを産めない身体だけど、子どもが欲しかった。しかしそれは自分の生きがいの道具としての意味合いが強く、高級な衣服は買うのにお米はない、に象徴されるように心から子どもを思っての選択ではない。常に自分自身を優先してのこと。
本当の愛情なら、どちらを(高級な服orお米)子どものために選択すべきかはわかるはずなのに。
自分(リカ)の存在意義を見出すために優子の母になったということだし、実の父親からしたら、手紙も渡されず、ありえないと思った。訴訟ですよこんなの。
だって、最初に言ってましたもんね、目的のためなら手段を選ばない、って。
たしかに夢おいびとで、面倒な父親だったかもしれないけど、愛情はあって、娘もあれだけ手紙をだすほど父親に会いたがってたのに、リカにむりやり引き剥がされたも同然。ありえないです。
とにかく実父と優子は本当に可哀想、被害者です。
わたしも子どもがいる身ですが、こんなことになる前に手紙返信こない時点で疑い、即帰国しますけどね。
それができない後ろめたさでも、あったのかと勘ぐってしまうレベルで実父もなぞ。
あと病気だとしてもほんとに優子を愛してるなら、ポッと出の男じゃなくて、実父に連絡しなさいよ。
田中圭がもし変質者だったらどうするの? みんないい人だからいいけど、母としての責任感がまるでない。
また母を失ったらかわいそうだから病気なのを隠したまま消える?え、そんなのいつか知るに決まってるし、母ならなにより、死に際娘に会いたいに決まってます。
リカがいなければ、たしかにみんな巡り会わなかったかもしれないけど、そんなの後付けの綺麗事です。
みんなよく納得するなあ。実父がアル中で、ブラジルで子ども作っちゃったくらいの設定にしないと、いろいろむくわれないです。
よかった点は時系列の演出(ここでみぃちゃんとゆうこが同一人物だと気づいたので)と、永野芽郁の瑞々しさ、彼氏役が懲りずに高校教師と付き合ってる設定、ピアノ(あれは惚れる)、市村さんの財力と包容力くらいですかね。
魂のバトン。
【嘘っぽくて作り物感が満載なのに、役者の演技によって泣かされる映画】
◎鑑賞時は原作未読
〜映画の第一印象〜
ずるい、ずるいぞ、ずるすぎるぞ、この映画。感想を一言に集約すると、「ずるい」に尽きる。映画は矛盾点や違和感のある脚本なのに、役者たちの演技力がそれらをカバーしているからタチが悪い。まるで演技の暴力。そして、この映画に泣かされた自分が悔しい。映画館にこだまする誰かの啜り泣く音。泣かせにくるシーンの数々。涙、涙、涙。泣いてないシーンはどこ?と思うレベルで泣かせにくる。本当にずるい。これほどまでにキャスト陣の演技力に支えられている映画は少ないかもしれない。
〜泣くポイントは人それぞれ〜
上映中に啜り泣く音が聞こえてくるのだが、「えー、なぜここで泣く?」というシーンで泣いていて逆に笑ってしまった。すみません。自分がどこに感情移入し、他人がどこで感情移入するのかを知ることができるのも映画館の醍醐味だなと思った次第です。人と人は同じ映画を見ていても解釈は千差万別なのだと思わされますな。
〜考察〜
①親切な父親たちに共通すること、そして梨花
周囲の人の愛を精一杯受けて育った優子。映画を見た人の中には、こんなに親切な人々ばかりは都合が良すぎると語る人もいる。たしかにそういった一面があることは否定しきれない。現実は厳しい。本当の親子でもないのに、この映画に出てくる人物たちのように子供のために尽くせるか?と問われるとYESと答えられる人は少ないかもしれない。けれど、この映画に出てくる2人目の父親である「泉ケ原さん」、3人目の父親である「森宮さん」。彼らに共通することが一つある。それは余裕だ。金銭的余裕や心の余裕。それがあるからこそ、血のつながらない娘である優子のことを大切に思ってあげられたのではないかと。ある意味で、梨花の人を見る目だけは良かったのかもしれない。
②血の繋がった家族(早瀬君と母親)だから喧嘩できるのか、血の繋がらない親子(森宮さんと優子)だから喧嘩ができないのか。
この映画では、2つの家族を対比的に描くシーンがいくつかある。そして、早瀬君は森宮さん親子の血のつながらない関係は、お互いを尊重し合えるから羨ましいという。しかし、血の繋がった親子でもお互いを尊重することが大事なのではと思ってしまう。
親子の繋がりは血が繋がっているとか、血が繋がっていないとかじゃないと切実に思う。
③リアル感を描けているかどうか
この映画を見た時に、優子の周りにいる人々の親切心にはリアル感がないという意見がある。たしかに、現実は厳しく、血の繋がらない人のためにここまで奮闘できる人は少ないだろう。けれど、リアル感とは何なのか?映画に求めるリアル感とは、実際のところ鑑賞者がリアルだと思う感覚、つまり現実を押し付けているだけなのではないか?と私は思ってしまうのだ。かのアインシュタインが「常識とは20歳までに身につけた偏見である」と言っているが、世界のどこかには科学でも説明のつかない、自分の常識では測れない出来事が確かにある。そして、私は映画とはある意味で自分の常識の外を体験できるツールだと思うのである。と、話が少し脱線した…
映画に話を戻すと、確かに優子を取り巻く人物たちはリアル感に欠けているかもしれない。しかし、ここまでの考えを振り返って、見方を変えてみると、この映画の登場人物たちは、単に鑑賞者である我々が求めるリアル感からは逸脱した存在(常識外)なだけと考えることもできるということだ。
そして、自分に疑問を投げかけてみる。本当にこのような人たちは存在しないのか?と。
もし映画に登場する親切な人々が実際に世の中に存在していると思えれば、世の中は案外捨てたものではないなという見方もできる気がしてくる。このように、自分の常識に疑問を抱いたり、自分のリアル感に問いかける経験ができるのはやはり映画の醍醐味なのだろう。そこから、自分の常識を上書きするなり、リアル感を更新するのもアリかもしれない。
仮に、映画を通した個人的な考えの変化が集団に伝播したら、鑑賞者たちが語るリアル感に欠けるという意見すら、稀な意見になるかもしれない。
④拭えない気持ち悪さのようなもの
つらつら述べたが、上記の見方はこの映画を温かい目で見ようとすればの話だ。個人的にはやはりこの映画を肯定的に捉えることは難しい。
大人たちのエゴによって明るく振る舞うことを身につけたみぃたん(優子)。彼女は母親である梨花から辛い時こそ笑顔でいることが美徳であるかのように教えられる。そして、笑顔でいることを美徳として捉え、常に笑顔を振る舞う。果たして、同級生から虐げられていてもヘラヘラする様は賞賛に値することなのだろうか。「辛い時こそ笑顔でいること」は、ある意味で「呪い」だと捉えることもできるが、この映画ではそういった黒い面には焦点を当てず、お涙頂戴な話に仕立て上げている。そのことに対して、やはり拭えない気持ち悪さのようなものを感じる。やはり母親(梨花)の歪な愛と複雑な家庭環境の中で成長した優子が、梨花と再開して彼女を許すシーンは必要だったのではないだろうか。それをせずに、梨花を殺すことで涙を誘ったこの映画はやはり罪深いと考えざるを得ない。
〜違和感〜
・父親としての森宮さん
森宮さんは終始、父親に徹しようとする。枕詞には「父親として〜」と常に森宮さんにとっての父親であろうとし続ける。本人曰く、東大を出てから生きる意味を見失いかけていた時に、梨花と出会って生きる目的を見つけたと言っていたが、、、
結婚式直前に娘の存在を知るとか、結婚詐欺もいいところだろうに…
・手のひらを返す同級生
最初の方で、優子は高校の同級生とうまく交友関係を築けていなかった描写がある。しかし、優子の身の上話を聞いた途端、優子のことを疎ましく思っていた同級生が手のひらを返したかのように良い人化するのは下せない。その過程は描ききれないのかもしれないが、人は変化する時はするが、そこを軽んじると陳腐なものになってしまう。このように、ストーリー全体に対する細かな部分の配慮がこの映画には足りないと感じてしまう。良い部分はあるものの、涙という情への訴えが悪い部分を曇らせているため、割と高評価なのかもしれない。
〜この脚本では観客の涙は誘えても、本屋大賞は受賞できないだろう〜
この映画の場合は演出よりも、むしろ脚本の方に問題があると考える。今作の脚本の橋下氏は59歳らしい。人は年齢ではないが、描かれる世界にはどうしてもその人が育った世代観というものは出てきてしまうものである。ちなみに、この橋本氏だが、映画『いぬやしき』の脚本も書いているとか。自分史上最高につまらなかった映画だ。『そして、バトンは渡された』の原作の内容も改変するし、この人が脚本を書く映画は見るのをやめようかな(※改変が悪だとは思わない。映画にしかできない見せ方もあるから)。橋本氏は、話題性のある作品に参加させてもらって、そこそこ話題を呼び、そこそこの脚本が書けるから起用されているという感じか。BEST of BESTの芸術家というより、あくまで商業作家なんだなと。
酷評してるみたいになってしまったな…
うーん。橋本氏に対して何か思うところがあるわけではない。この方の脚本は原作を尊重する以上に、映画としてどう見せるかという点を考えているとは思う。が、仮に原作以上のものを映画にしたいと思うとき、やはり実力が問われるということが言いたいだけだ。この脚本では原作の軸である「優子の芯の強さ」が描ききれていない。それは田中梨花という人物を殺したことに由来する。彼は田中梨花を殺すとともに、原作のメッセージをも殺してしまった。つまり、『そして、バトンは渡された』の映画化における改変は脚本家として失格ではと思った次第。これでは結局、酷評したいみたいになってしまった…ohh
◎映画の残念な点
〜バトンについて〜
・この映画の描き方だと「バトン≒優子」になってしまっているんだよな。これはこれでシンプルで分かりやすい。伏線回収としてはこういう見せ方もあると思う。しかし、原作ではバトンは優子であり、森宮さんからの愛とか、思いやりとか、ピアノとか、より抽象的なものとして描かれていたような…その辺をうまく表現できていないのがなぁ、残念。
〜この映画の見せ方〜
・結婚はゴールであり、始まりであるが、幸せの形としてそこをゴールのように描いた点が、女の幸せは結婚であるという穿った見方に繋がりかねない。この物語の本質は結婚ではなく、親子の絆や愛とかにあると思うのだが…皆さんはどう思いますか?
〜この映画を一言であらわすと〜
【田中梨花(石原さとみ)という人物を中心に振り回される人々の群像劇】になってしまっているのが残念で仕方がない。
◎映画の中で良かった点
〜ロッシーニが聴きたくなる映画〜
「2人でロッシーニになろう」は最高のプロポーズなのでは?
〜劇中に出てくる食べ物が飯テロすぎる件〜
餃子のパリパリ感といい、ご飯が進みそうな回鍋肉などはどれも実際に食べたくなるほど美味しそうだった。自分も美味しいご飯を作れる人になりたいと思いました。切実に…
〜映画からのインスピレーション〜
・最後に、この映画を通して自分の意識は何か変化したか?自分の中で何かを変えようと思っているか?
まずは、自分が優子の周囲の人々のようになれるような「余裕」を持つこと。いや、ちょっと待てよ。余裕は持つものなのか?余裕を持つというより、余裕を纏うといった表現が適切な気がする。余裕という服を身に纏い、「余裕のある自分」が自然体でいられる状態が一つの理想かもしれない。このように考えたのは、他人に対して親切になれる社会が仮に存在するならば、個人個人の「余裕」が鍵となると感じたからである。
〜映画館で見るべきか〜
映画館における音響、映像設備を使いこなせているかというと微妙。迫力とは無縁の映画。洋画に比べて邦画が低予算であること、そもそも映画のジャンルがアクションものではないからな。そのため、映画館の音響や映像美を体験すべく、映画館で『そして、バトンは渡された』を見るべきかと問われると見る必要はない気がする。
では、「家で見るか?」と問われると、最初の方が間伸びしてしまい、ここまで泣かされることもなかっただろう。隣の人とか寝かけていたし…結局、映画館で見たが故に、泣かされるというね。
〜泣いたシーン〜
①母目線の卒業式のシーン
▶︎カメラワークと音楽が迫り来るところ
②森宮さんが父親としてバージンロードを歩くことを勧められるシーン
▶︎友人は父親3人であるけば良いのではと言っていて確かにと思った(笑)
家族の形は十人十色
小説で大好きなストーリーの映画化だったので、楽しみに鑑賞しました。
小説以上に感動して泣きました。
石原さとみさん演じる母親は、自由でふらっと娘を置いていなくなってしまうという強引でお金使っちゃう性格ではあるけど、ラスト30分の自分の病気を隠し通してまで、どんな時も娘のことを第一に考えていたことに心を打たれました。
また、「泣いてちゃダメ!笑っていれば幸せが舞い込んでくるんだよ」っていうセリフによく親に言われていたことだと思い出しながら泣いちゃいました。
実の父親が海外へ仕事で行ってしまい、複雑な思いを抱えながら日本に残る様子を見て、自分の家族も、父が単身赴任だったこともあり、重ねて観ていました。
離れて会えなくても家族は家族。たとえ実の父親が再婚して、子供もいるとなっても会えば温かく迎えてくれるシーンに、家族の形は十人十色で形が変わっても、いつまでも家族でいられるんだと思い、ジーンときました。
血はつながっていなくても、お互いのことを思いやって過ごせていけたら、立派な家族だと思わせてくれた今年一番の作品でした。
二段落ちとは
全563件中、241~260件目を表示