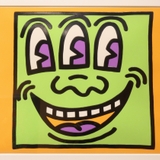シン・仮面ライダーのレビュー・感想・評価
全647件中、421~440件目を表示
大人の仮面ライダー映画!
鑑賞して感じたのがタイトルの通りです。
CGが安っぽかったり(大作洋画に比べて)しても、面白ければなんでもいいです。
シン・仮面ライダーはどうしてもこれ以上の感想がなく、まあまあ面白いという感じでした。
しかし、キャストは豪華でキャラクターに個性があり、ラストは本当に良かったと思います‼️
充分期待を超えている!
期待してなかったけど面白かった!
子供部屋おじさんの世界
リアルタイムでTVシリーズを観ていた、ライダーごっこ世代の感想。
以下、がっかりした点。
まず、冒頭のカーチェイスからのショッカー戦闘員とのバトル。
最近の「大人向け」作品定番のショック表現かもしれないが、王道のヒーロー物にスプラッターは不要。血しぶき浴びる仮面ライダーなど、アマゾン1人でじゅうぶん。似たような(後味悪い)表現として、「エヴァンゲリオン」旧劇場版の主人公の自慰行為なんかがあったが、どういう意図があるんでしょうか。わからん!快
ライダーと怪人のデザイン。「仮面ライダー THE FIRST」の洗練されたデザインには遠く及ばず、全体的にダサかっこ悪く、統一感がない印象。ライダー2人のマスクとスーツは、TVシリーズをほぼ忠実にヨレっと再現したものの、アニメっぽいベルトとバイクがミスマッチ。昆虫型の怪人は硬質のメカ的マスクだが、コウモリオーグは豚っぽい特殊メイク、サソリオーグは顔半分を布で覆っただけで、「快傑ズバット」の殺し屋そっくり(石ノ森作品へのオマージュ?)。
致命的なのは、主人公の本郷猛が、「シン・ウルトラマン」同様、何を考えているかわからない、気弱そうで影の薄いキャラなこと。周囲に流されるまま、機械的に戦っているようにしかみえない。何かを守りたい強い意思とか、情熱とかを持たないヒーローは情けない。ルリ子に「ヒーローは赤」と言われ、マフラー巻かれたらヒーロー完成?
敵組織の目的もよくわからない。怪人達は、それぞれ勝手な思惑で悪事を企て、実行前に殲滅。そういえば、「魔界転生」で、天草四郎に復活させられた死人達も、幕府転覆など関係なく、みんな勝手に行動してましたね。世界征服じゃなく、絶望した人間を改造して好き勝手にやらせるのが、本作のショッカーの企みなんでしょうか。
プラーナやらハビタット世界やら、本筋にあまり絡まない設定が邪魔。解説に要するセリフの量と時間がもったいない。その分、ドラマに厚みを持たせてほしかった。
アジトに戻ったら、政府機関の男達がいて、共闘契約即締結。
コウモリオーグが飛んだら、サイクロンも謎変形で飛ぶ。
一文字隼人は、ルリ子の謎パワーで瞬時に洗脳から解放(この能力使えば、怪人倒さなくてもよさそう。「星雲仮面マシンマン」のカタルシスウェーブ?これもオマージュ?)。
新サイクロンは、政府機関が調達(絶対、ショッカーとつながってる)。
ご都合主義の嵐。なんだ。やっぱり、子ども向け作品だったんじゃないか。
ラストシーンは原作漫画の設定を踏襲していて、ちょっと良い感じだったけど、ここに至るまでの人物描写ができていないので、感動にはほど遠かった。登場怪人を減らしてでも、人物の内面を丁寧に描かないとダメだと思う。庵野監督は、「仮面ライダー」という作品や造形が好きなだけで、人間には興味がないのかなと思える。特撮だけじゃなく、昭和の作品は、人間臭いから面白いと思っているので、庵野監督の趣味の作品世界は、自分が観たいものとはだいぶ違う。昔の作品を徹底的に再現するより、むしろ、昔の作品をリマスター、再編集したほうが、伝わるものが多いのではないかな。
人物描写の浅さは、「シン・ゴジラ」「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダー」3作品に共通している。庵野監督は、どれも同じような手法で映像化しているけど、「シン・ゴジラ」以外は残念な印象しかない。ではなぜ、「シン・ゴジラ」にあれほど感動したのだろう(自分の場合です)。おそらく、観る側が震災の記憶等を重ね合わせ、薄い人間ドラマを脳内で補完したからではないかと思う。今となっては、「シン・ゴジラ」の評価も変わってくる。
「シン・エヴァンゲリオン」の終盤、夢と現実の境界のない世界で、主人公のシンジと父親が、特撮セットの中で戦うシーンがある。これが種明かしで、「シン」シリーズの本質なんじゃないかと思っている。
「今日は、庵野くんの子供部屋で、昔懐かしいおもちゃを引っ張り出して、『かっこいいねぇ』って眺めて、みんなで遊びました」
こんな感じ。ただ、それだけだったんじゃないかと。
本作を見終わって、そんな風に感じてます。
古き良きライダーと豪華俳優
スイカみたいなショッカー隊員!
深い映画
実は人物の描写がとてつもなく細かくて深い映画だと思います。
一回目の観賞時何を言ってるのか聞き取れなかったセリフがあって、それは蜂オーグに対して叫んでたシーンですね。「蜂オーグ!」って叫びます。
あの時本郷は蜂オーグとの戦闘もあってヘルメットの力で殺傷に躊躇いが少ない状態、とても興奮もしてる状況。
だけどそのあと少し震えながら静かな声で「覚悟」と絞り出すあのシーン、あれこそヒーローが誕生したシーン。真に仮面ライダーになったシーン、本郷の人間性がオーグメントであることに打ち勝ったシーン。ルリ子が本郷に希望を感じたシーン。
ルリ子はそんな本郷を目の当たりにしたからこそ後で胸借りたんだなってのがすごくよく分かるシーン。本当に素晴らしい。
本郷はその大変さ過酷さを思いを体感したからこそ一文字が理性保っていることの凄さが分かったのでしょうし、おそらく友達ではなく同士であり、だからこそ戦いたくなかったのだろうなと思います。
この映画は宮崎駿監督の作るアニメに似てる気がします。
映画としての熱さがあまり伝わってこなかった
良かったところ。
浜辺美波 ◎(はなまる)
好きな女優さんですし、予告編でもいい感じだったので期待してましたが、
本当に良かった。画面が締まります。途中で眠たくなりましたが彼女のお陰で寝ずに済みました。私にとっては彼女の存在感で何とかなった感じです。
キャラ的にも、あんな人が身近にいたら「惚れてしまうやろ~」です。
透明感のある美女のボブはチートだと思いました。ある意味ロンギヌスの槍です。
見た目、改めて「綾波っか!」って思いました。
斎藤工 ○
カッコいいとかでは留まらない、ホントいい男。彼も画面の締まる俳優さんです。
所作や至る所から色気が出てきてて、間違いの無い俳優さんです。
柄本佑 ○
親父さん、弟さんもいいですが、彼の少しポップな感じが好きです。
仮面つけているときの演技(声)が良かった。
構図○
やっぱり庵野監督、決まっていてカッコいい画のオンパレードでしたが、
それ以外、脚本、演出、編集は、『なんだろ~』って感じでした。
怪人の造形○
蜘蛛と蜂、かっこ良かった。特に蜂は良くできてた。
前半の特撮、実写アクションは悪くはなかったですが、後半になるにつれシンドくなりました。特にCGはシンドかったです。
中途半端なCGならいっその事もっと少なくして、物語を重厚にして話で魅せて欲しかったでしょうか。昭和の仮面ライダーのテイストだけ頂いて、シンがつく仮面ライダーとして、シン・ゴジラのような、違うアプローチをして欲しかったです。
これをオマージュというのでしょうか?
1号ライダーの悲哀を現す為だと思うのですが、演技が抑えられすぎていて、池松壮亮さんが何か活きていない感じがしてました。
彼にとどまらず役者が余り活きていない作品という感じでした。
PG-12映画ですが、その理由が少しグロいシーン以外は私には解らなかったので、いっその事それをやめて戦隊モノが好きな子供にも観れるようにしてあげればいいのでは、と思いました。
もしくは興行的には厳しくなるでしょうが、R-15やR-18まであげて、もっとグロくやるか。
旧劇場版のエヴァの戦略自衛隊のネルフ本部強襲のように、人間の怖さ、殺伐感を表現できた監督なので制限を少なくすると、どうされるのだろうと思いました。
長澤まさみと森山未來は、無駄遣いでは?とも感じました。
あと、サイクロン号の音が変形すると2気筒から4気筒に変わるのが良かったです。
特に迫ってはこないショッカー
自分の仮面ライダー原体験は「ブラック」で、いわゆる「平成」「令和」ライダーもちょいちょいつまみ食い。
1号2号あたりは知識としてはそれなりにあるものの、さすがに細かい小ネタとかは分からないです。
そんな立場から見た本作ですが…
すっげぇ微妙……
昭和レトロなノリと、監督のお約束といえる厨二臭い専門用語羅列がとにかく食い合わせ悪い。
ダサくいきたいの?オサレに行きたいの?非常にどっちつかず。
時代が明示されない上に、一般大衆の日常が出てくるシーンも皆無なので、世界設定がよく分からないのも難。ショッカーがどういう組織で、世界の中でどういう立ち位置なのかもなんだかよく分からない。そこが弱いから、必然的に仮面ライダーが戦う理由も弱くなる。だから戦いにも感情移入出来ず、勝ったとしてもカタルシスもない。
それでもアクションがよく出来てればまだ見た目的なカタルシスは得られるはずが、そのアクションがまた致命的なまでにひどい。
プロのスーツアクターを使ってないから生身アクションは全く迫力ないし、CGの質は壊滅的なデキ。本当にシンゴジ撮った人なのか疑ってしまうほど。樋口監督が偉大だったのか…?
血飛沫描写のある仮面ライダー、ならアマゾンズの方が本格的で、世界観もしっかりしてますしね…
一応、話がポンポン進むのでテンポは良かったのと、クモオーグ・ハチオーグのデザインやキャラはなかなかだったり、なんだかんだ嫌いじゃないポイントもあるにはありますが…
んー、ちょっとやっぱり、個人的には受け入れられませんでした。
賛否両論分かれる名作
新・浜辺美波
冒頭30分と、ラスト30分は良かった。
等身大実写ヒーロー作品の壁
子供の頃に観た仮面ライダーに
庵野監督はどんなシン解釈を与えてくれるのか?
本作もシンウルトラマンと同様、
従来のご都合主義的な“変身”に
ロジカルな世界観を加えてリアリティを与えたり
迫力を追求したアニメのような激しい演出、
俳優陣の繊細とコミカルの両極に振り切った演技、
実に見所は多彩であった。
ただ仮面ライダーという作品は
これまでも幾度となく大人向け作品へと
アップデートの試みがなされて来た。
その全ての作品を観ている訳では無いが
この文脈の中で、
果たして庵野監督がどれほどの
シンを生み出せたのかは疑問である。
また今回は全体的に等身大実写ヒーロー作品の限界が
見え隠れしたような印象を覚えてしまった。
個人的には願わくば
次回作は第二次世界大戦のような
近代史にトライして頂いて
まだ観ぬ、シン国産戦争映画を生み出して欲しい。
或いはシン•ナウシカか。。。
俺のとは違う、、
マニア向け、ライト層は注意
全647件中、421~440件目を表示