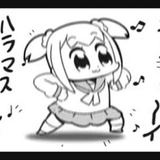シン・仮面ライダーのレビュー・感想・評価
全912件中、681~700件目を表示
控えに言って最高でした!
ぜんぜん期待薄で……むしろ公開が近づく度に、外すんじゃないか!!「キューティーハニー」の二の舞なのでは…!!とおもっていましたが…。ライダーはそんなに大ファンではありませんでしたが、ぜんぜん期待以上でした!!ほんとに外すと思ってましたが、予想外れ!いゃあぁああ良かった!!面白かった!!
本郷たけしも、一文字もいいけど、緑川ルリ子はさらによかったです。一郎もよかった!
ここまで昭和ライダーのテイストを守りつつ、面白く出来たのはさすがです!あと3回は必ず観ます!
浜辺美波のプロモビデオ
あくまで、私の感想ね。
私には主演の彼に魅力が無かった。素人かと思うような演技に、棒読みに近い感情のこもってない台詞で、途中から冷めてしまった。こういう演出だったのだろうか?。素人さんかと思ったら、いろんな賞をもらってるのね。逆にそっちに驚いた。あまりにも大根演技にしか見えん。しかもイメージ合わない。内容も、近年の仮面ライダーを意識しすぎたようなフレンドリーな敵に、ド派手な仮面。今ひとつノレなかった。藤岡弘リアタイ世代の私の作品評価は2です。
ではなぜに評価3.5?
まず・・・浜辺美波が魅力大爆発してるからプラス1しとく。言わせてもらえば、(監督の好みだったのか)ほぼ浜辺美波のプロモーション作品と言えるほどの出演シーンの多さ&セリフ多い&アップ多様・・・しかも可愛く魅力的に。そして(ほぼ)最後まで出ずっぱり。これだけ顰めっ面が可愛い女優さんも珍しいのでは?。
んでもって、脇役が良すぎたから、プラス0.5。
ライダースーツがめっちゃ似合いすぎな柄本兄貴。予告で見てすでに『おっ!似合うな』と思っていたが、本編観てもやはり似合いすぎてた。こっちが主演で良かった気がする。で、何しに出てきたのか意味不明の(シン・ウルトラマンの功労者)長澤まさみ。あんな扱いでいいのか?。大活躍の西野七瀬。庵野作品常連で今回は出演シーン多めの竹野内豊に加えて、同じくシーン多めのウルトラマン斎藤工などなど。
仮面ライダー大好き庵野監督の、インディーズ的なマスターベーション作品。それが私の感想でした。付いて行くには、今回はちとハードル高いぞ。
仮面ライダー、私は2号派。
ゲストビジットの回で観てきた!
エリア的に西野七瀬さんでラッキーすぎた。顔小さすぎるし、可愛すぎた。時間はめっちゃ短かったけど、眼福すぎ。
仮面ライダーには全く触れてきてない人生だったけど、シン・ウルトラマンを見て、予想以上に良かったのでシン・仮面ライダーにも期待して観てみることに。
全体的に割と面白く見れた、バイクのシーンとか迫力あって特撮見てるな〜ってワクワクがあった。けどなんか物足りない感が残ったかな。なんでかはっきり分からないんだけど、仮面ライダーの1号がなんかパッとしない感じ?戦うことに最初抵抗あったくせに、そんなすぐに自分を犠牲にしてまで戦えるもんかね?っていう。
ショッカーが全面的に悪者だと思ってたから序盤混乱。仮面ライダーもショッカー??なのか。予備知識なしの自分にはちょっと難しかった。
あと、聞いてない豪華キャストね。サソリオーグでまずびっくりしたし、エンドクレジットで、え?いた??っていうビックネームがゴロゴロいてびっくりした。キャスト確かめるためにもう一回見たい。笑
これが仮面ライダーか!って興奮があったし、面白く見たけど、どっちかというと私はシン・ウルトラマンの方が好きだったかな〜。(シン・ゴジラはいまだに見れてない)
浜辺美波が可愛いだけ
とにかく浜辺美波が可愛いだけ
個人的に一番大事な戦闘シーンは
戦闘員との戦闘はワンパン ぐしゃだけ
怪人との戦闘は蜘蛛オーグを除き全部酷い出来
ラストの蝶オーグ戦ですら薄暗い場面で発勁で吹っ飛ぶ→起き上がって立ち向かう→発勁で吹っ飛ぶ→数回繰り返した後唐突に弱まって隙が出来て倒せると言った具合
ストーリーは藤岡弘が演技していた方ではなく石ノ森章太郎が描いていた漫画の方を読んでいる前提でトントン拍子で説明無しで進む
総評として金掛けた同人作品みたいなイメージ
個人的に告知ムービーでテンション激上がりだった為にこの上なく残念で仕方が無い おそらく今後庵野作品は二、三週間置いてから評価確認してから観に行くか検討するようにする
日本男児のDNA
まずは面白かったです。
世代的にドンピシャですが、子供のころ観ていたテレビ版より石ノ森章太郎愛を感じますね。シンウルトラマンが普通に楽しめはしたものの、ゆうてそれほどでもなかったので、あんまり期待していなかったのですが、これはなかなか面白かったな。
日本人の男の子のDNAには仮面ライダーカッコいいっていうのは組み込まれてるんだと思います笑
それと何といっても祐と池ちゃんはやっぱり上手い俳優ですよね。二人そろってからはグッと引き込まれました。ウルトラマンとかゴジラはあれっきりっぽいけど、これに関しては2号主役のバージョンも観たいな笑
最近MCUをフェーズ順で見返しているんですが、マーベルも面白いけど俺はやっぱりこっちですね~。
これは、何に対するリスペクトかで全てが変わる。
一緒に観に行った50代の妻でさえ、「これは意見がわかれるわね?」と呟いた作品です。
私は観覧し始めて、少ししてから「あ、石ノ森漫画版の構図だ」と理解してから一気に楽になりました。
緑川ゆり子を誘拐した車を先回りするサイクロン号をはじめ、ショッカーライダーにサイクロン号で囲まれるところなど、様々箇所で漫画版の構図が使われていいます。
漫画版は一回たりとも変身ポーズはありません。
更には第二の皮膚としてライダースーツを認識しているし、サイクロン号がなければ、変身できないのもそうです。
(フェイスクラッシャーから血を吐くのは、仮面ライダー THE First以降のお約束演出?)
ラストシーンのダブルライダーの会話は、2巻のセリフそのもの。
とは言え、随所昭和初期のTVそのものを彷彿させる演出も。(当時は全体的に画面が暗かった)
スーツが堅いから足が伸びきらないとか、「本人」が演じているとか………
TV版・本郷猛をリスペクトする人たちは受け入れるのが難しい作品だと思います。
しかし庵野監督の作品は、また何か仕出かすのでは?と観るまで安心できない……
ところで安田顕さんは何処にいた??
とてもよかった
怪人が拳銃で撃たれて死ぬ。怪人がライダー以外に全く無敵ではなく、一般人が拳銃を使えば倒すことができることに悲哀を感じて、ゾクゾクする。すごくいい。
ショッカーがアホっぽい。そもそも人の幸福など他人が決めることなどできないという、根本が分かっていない。まったく余計なお世話で、バカが力を持つとひどいことになる見本のようだ。真面目に解釈しようとするとこんなふうに思うのだけど、実際製作する場合、敵の基本理念などどう設定するのが面白いのか、そっちの立場で考えると難しい。他にどうすればいいかすぐには思いつかない。
柄本佑がイケメン役でキメキメで面白い。ジャニーズとかイケメン役者を使わない決断がかっこいい。
途中トンネルで戦う場面が暗すぎてよく見えない。改造人間は死ぬと泡になるのだが、服も消えるのは意味が分からない。
(追記)
撮影密着ドキュメンタリーを見てもう一度見る。密着では苦労していたアクションシーンは初めの方だ。カメレオン男までずっと面白いのに、ショッカーの基地に行くトンネルのバッタオーグ集団戦からチョウオーグ戦がとてもつまらない。アクションは長ければ長いほどダメではなかろうか。絵面もつまらない。ダムとか工場とか線路とかの方がいい。
戦ってる最中にどの怪人もよくしゃべる。改めて一文字が素晴らしい。
アクションと緑川ルリコがよか!
話は、イマイチやけど。浜辺美波や西野七瀬、長澤まさみがよかよね。一文字隼人もいいやん。
石ノ森章太郎の原作に忠実かな。13人の仮面ライダーもいたしね。森山未來は、仮面ライダーV3みたいやな。シモン真人の歌がいい。そして竹野内豊が、立花とうべえで、斎藤工が滝なんやね。
全てのバイク乗りに
エヴァもゴジラもウルトラマンも、
庵野秀明の新解釈は本当にグッとくる。
オリジナルのいい所を都合よく上手に拾い
自身が1番熱いと思う所に気持ちを加える。
勘違いし寂しい感想を書かれる方がいますが
雰囲気はかつての空気を味わいつつも、
全く新しい、現代の解釈のもとでリメイクされた
新しい解釈の物語として、楽しむべき作品。
バイク乗りだった父からのメッセージとか
ヘルメットと共に、風を感じながら走ろうとか
本来のモデルであるバッタから着想する
力強いジャンプやキックとか、
進撃ばりに想いを込めたマフラーとか…
オリジナルよりも熱い手心で、より一層
本作品の良い所を膨らませた良い品だと
僕は感じました。
(1号2号は世代では無かったからよかったのかも)
ちょっとだけ知ってる人や知らない人の方が
楽しめるのかも知れませんね。
オリジナルは、あくまでリスペクトの範囲内で。
ぜひスタッフロールの最後まで(あっという間ですが)
味わって欲しい。
昭和のオジサン方、全員集合ですよ!
"シン•ウルトラマン"のオリジナルからの逸脱ぶりにガッカリした経験から、今回ほぼ々期待してませんでした。ところがドッコイ素晴らしい出来に脱帽です!
まずライダー•サイクロン号•ショッカー等の造形のカッコイイこと!それらが当時には無かったVFXで縦横無尽に暴れまくります。そこに重なるライダーサウンド、もうたまりません!コレは現役視聴世代だから堪能できる至福の時間でした。「平成ライダー世代とはこちとら根っこが違うんだぁ!」と言わんばかりに全細胞で反応してしまいました。
話のテンポも良く、次々と現れるショッカー怪人に興奮が止まりませんでした。ラスボスとの決着に多少"?"を感じましたが、もうそんな些細な事は問題にもなりません。
エンドロールに流れるライダー名曲メドレーを聴きながら、目一杯の多幸感に満たされました。
石ノ森章太郎版の実写化
世界観の角度
平成ライダーほどの自由が無い
子供の頃はウルトラマン派で、平成ライダーも詳しくは無いけど、初代仮面ライダーのリメイクだから縛りが多くて、自由がないのは、やむなし。
リメイクであっても原作をうまくオマージュできたのがか、シンゴジラ、シンウルトラマンだとすると、流石にネタ切れというか、ある意味一番オリジナルに近く
いろいろなSF考証を追加しても、一から世界観の構築ができる平成ライダーほどの自由があるわけでなし、この時代に世界征服を目指さない悪の秘密結社の最終目的ってあまり上手くいっていない気がした
浜辺美波は、見事な演技で、作品のシンを、作っていた。
女怪人はどちらもファンなのだけど、どちらも役に合っていない気がする、過去作のキューティーハニー(今なら間違いなく、シンキューティハニーというタイトルだろう)に、比べるとも一つだし、もっと言うと怪人の数減らしても良かったと思う
本当にこれは申し訳ないのだけど、主役がマジカルラブリーに見えてしまって、集中出来なかった
庵野ワールドの役者さんがたくさん出たり、ロボット刑事Kとか、MAGIの筐体等、くすぐるネタ満載で楽しめたけど、庵野さんにはもっと時間とお金を与えて欲しいし、
自分の作ったモノに縛られず自由にやって欲しい。とりあえず次作も見に行きます
仮面ライダーのフルコーラス聞けたのは良かった
ここが限界なのかなと
シン仮面ライダー楽しめましたが、一抹よ居心地の悪さは拭いきれませんでした。懐古的にあえて出来の悪いVFX使っている?それで知識なしで観る若い人に言い訳になるのでしょうか。暗い戦闘シーン然り。製作側の予算問題は十二分あるだろうことは推して知るべしではありますが、それを観る側が忖度して、でもよくやった、と拍手することなのでしょうか。これは庵野秀明という希代の人物に対し充分な支援を行えなかった、あるいはしなかったのかはわかりませんが。
大筋も未だに人類補完計画を完遂させようとしてるのかと。庵野秀明バースは確立するだろうけど、いつまでもセルフオマージュの域を脱することができないのかな。思えば、シン・ゴジラがおもしろかったのは岡本喜八ベースだったからこそなのかなと。
あ、そこを残すんだ?
私、仮面ライダーは放映開始当初に見てた年代なんですね。幼稚園でよく仮面ライダーごっこしてましたっけ。怪人の改造手術シーンとか、茶の間で見てると子供心にちょっとイケない気分で親の手前気恥ずかしかったりして、自分のエロ感覚の萌芽はここにあったと思ったり思わなかったり。
そんな私にとっては、平成以降のライダーはやっぱちょっと、いやかなり違う。それはそれでいいけど、仮面ライダーといったらやはり初期ライダーのあの、怪奇マンガ由来のエログロと、ソフビ人形売りつけ対象向け特撮TV番組の格好良さと荒唐無稽さとダサさがなければ、と思ってしまうのです。
で、この時代に仮面ライダーを映画にするとなったら、あのエログロと格好良さと荒唐無稽さとダサさをどんな塩梅でブレンドして辻褄の合う世界観を作って大人も見られるエンターテイメントとして仕上げるのかというのがキモであり、観客としての興味でもあったわけです。
ところがギッチョン。
あ、そこはそう説明するんだ?
ダサ要素、そのダサさのほうを残しちゃったんだ!?みたいな。
自分の好みにしっくりくるような塩梅ではありませんでした。
本郷と一文字が初めて出会って交戦する時のチャチな映像など、どうしてわざわざチャチに作るのか、残念ながら私にはその意図がわかりません。
でも昔の仮面ライダーへのオマージュはもちろんちょこちょこあって、本郷が脚を怪我したことで一文字が仮面ライダーになるところなんか、おおっ!そうきたか!って感じ。ダブルライダーvsニセライダーとかもワクワクしますね。
あとは、ツンデレ姫緑川ルリ子の抒情パートも良かったです。ブレンド具合が好みじゃないな~と若干斜に構えて見ていた私も、遺言シーンでは涙してしまいました。
それに一文字隼人が一文字隼人らしく描かれていたのも仮面ライダーと手を結ぶ2人の名が立花と滝であったことも良かった。
あ、一番スリリングで怖かったのは冒頭のオートバイで2台のトラック(ダンプだったっけ?忘れた)から逃げるシーンでした。
最後は懐かしの主題歌で締め。
菊池俊輔大先生の音楽は半世紀経っても素晴らしいです。
※本郷の『優秀で正義感があるけどコミュ障で故に就職に失敗』な設定に笑いつつ納得。
藤岡版の学生のくせにオヤジ臭く説教臭い堅物なんて、今の時代に現実感無さ過ぎるもんね。
※私はかつて蜂女のエロさに衝撃を受けた幼女だったので、ヤンデレ風味のヒロミちゃんは可愛いとは思ったけどピンとはきませんでした。
「シン」シリーズのレベル低下が気掛かり
「シン・ゴジラ」「シン・ウルトラマン」に続く「シン」シリーズ3作目である。前の2作は庵野秀明が「自分ならこう作りたい」という意欲を感じさせるものであったので、今作にもかなり期待して見に行ったのだが、残念ながら完全に期待外れであった。ギャグ映画なのかとも思ったが、どうもそうではないらしい。
リアリティへのこだわりという面で考えると、「シン・ゴジラ」を 100 とした場合、「シン・ウルトラマン」は 60 くらいに低下していたのが残念で気になっていたのだが、今作は 20 もないのではないかと思わされた。世界観の話ばかりでなく、登場人物の人生観やモチベーションなどがまるで掴めないのである。
ある日目覚めたら突然超人的な能力が身に付いていたという話は、古典的には「フランケンシュタインの怪人」からあるもので、フランケンシュタイン博士が良く吟味もせずに犯罪者の頭脳を移植してしまったために人殺しの怪物を生んでしまった訳であるが、本郷の内面や価値観などを観客に示すことが非常に不十分にしかできておらず、ダース・ベイダーのようにダークサイドに落ちないという保証は何もなかった。
ヒロイン緑川との関係も極めて作り物めいたヴァーチャルなもので、これだけの関係性で彼女を命懸けで守ろうとするものだろうかという疑念が最初から最後まで払えなかった。彼女の存在性もよく分からず、ファイナルファンタジー7のエアリスのように、製作側の都合に従って行動しているだけのようにしか感じられなかった。
敵の目的もまた不明で、何が良くてそんな野望を持つのかが全く分からなかった。現存する人類の全てから肉体を奪って精神だけの存在にしたところで、どんな世界が待っているというのか?少なくとも新たな生命が生まれる可能性はゼロになるだろうが、自分の全存在をかけてまでやることかという鼻白む思いを持て余した。
敵は虫をモチーフにして改造された人間ばかりだが、それぞれ持ち味を生かし切っているとは思えなかった。特に、透明になれるマントを羽織ったカマキリ怪人は、何故わざわざそのマントを脱いで戦うのかがわからなかった。また、本郷を倒せばいいのであれば、マスクを他人に預けている時が絶好のチャンスであったであろうに、何故わざわざ見逃すのかが分からなかった。長澤まさみのサソリ怪人は、わざわざやっつけられるために登場したとしか思えず、登場シーンもほぼ一瞬だったので、完全にギャグとしか思えなかった。
役者は、まず本郷役の池松壮亮が完全にミスキャストだった。終始表情が変わらず、新田真剣佑でも出て来たのかと思った。何より話し声が常に囁くようで、敵と対面しても同じなのには頭を抱えたくなった。緑川役の浜辺はいくらかマシだったが、もっと彼女の魅力を全開にするような脚本に出来ただろうにと、非常に残念だった。竹野内豊が「シン・ゴジラ」から3作連続で政府関係者役だったのは良いとしても、斎藤工まで出て来たのはどうだったのかと疑問だった。彼がウルトラマンになってしまえば、解決は早まるはずだろうと思うと笑いをこらえるのが難しかった。
音楽は 50 年前のオリジナルを尊重していたが、ゴジラやウルトラマンと違って時代遅れ感が半端なかった。ショッカーの手下がやられる時の出血ばかりが強調されていたが、そこにこだわるよりは話のリアリティにもっと力を注いで欲しかった。この作品の映画化を聞いたときに感じた不安がほぼ的中してしまったような感じで、「シン」シリーズの今後が不安になってしまった。
(映像4+脚本2+役者3+音楽2+演出3)×4= 56 点。
緑川ルリ子の"ツンデレ"設定は、庵野監督の確信犯的な趣味
「シン・仮面ライダー (IMAX)」。
『シン・仮面ライダー』(2023)は、『シン・ゴジラ』(2016)、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』(2021)、『シン・ウルトラマン』(2022)から続く、アラ還(アラウンド還暦)の夢を次々と叶える、庵野秀明監督の「シン」シリーズで括られる話題作。どんな実力のあるクリエイターが望んでも手が届かない、日本映像史の伝説キャラクターの映画化は、庵野監督だけが持つカリスマ性に引き寄せられる社会現象でもある。
すでに「シン・ジャパン・ヒーロー・ユニバース」(https://sjhu.jp/)というクロスマーケティング的な枠組みが始動しているが、映画としてのユニバース作品が登場するのかしないのか、それも庵野氏の掌のうちにある。
『シン・仮面ライダー』は、一度見では消化できないほど観念的な情報がギュッと詰め込まれているという点において、庵野監督らしい仕上がりになっている。日本語字幕がないと、マスクの下で喋る重要なキーワードが一度では判別しづらい。2度3度と見る愉しみのある作品になっている。
アスペクトはシネスコ画角なので、IMAXで観る必要はない。入場者特典のポスターが欲しければ別だが、画質・音質を求めるならドルビーシネマだろう。
本作を特徴づけているのは冒頭のスクリーンに投影される「映倫/PG12」(12歳未満の年少者の観覧には、親または保護者の助言・指導を必要)のマークである。オープニングの戦闘シーンで仮面ライダーはショッカー下級戦闘員に対して尋常ではない血しぶきをあげるほど、殺人を展開する。これは"For Adults"といっていい。
とはいっても、原体験としての”仮面ライダー”は、庵野監督にとっても子供時代のものだ。あえてこういった演出になるのは、今なお脈々と続いている子供番組仕様と一線を画す必要があったから。子供が見てはいけないのではなく、決して子供騙しではないホンモノを目指している。
だから『シン・仮面ライダー』は、必殺技の名前を一切発しない。石ノ森章太郎先生が主題歌に込めた、"ライダーキック"も"ライダージャンプ"の掛け声はない。一方で、"変身! トォー"もない寂しさ。1号、2号それぞれの変身の決めポーズは歌舞伎の見得のように残している。
もうひとつは贅沢すぎる豪華俳優陣。主人公で仮面ライダー1号/バッタオーグとなる本郷猛を演じるのは、池松壮亮。作家性の高い監督作品に人気の中堅俳優だ。ヒロインの緑川ルリ子は浜辺美波。言わずと知れたメジャー俳優だ。中盤から仲間となる仮面ライダー2号は柄本佑。
とくに長澤まさみの"サソリオーグ"は、仮面ライダーではなく政府機関に呆気なく制圧されてしまう。登場シーンが一瞬すぎて、"長澤まさみって出てたっけ?"となるのは必至。ストーリー上もサソリ毒の伏線だけのためにある。
"オーグ"とは"AUGMENT(オーグメント)で、"本作における改造人間のこと。"コウモリオーグ"(手塚とおる)は原作シリーズにおける"蝙蝠男"にあたる。周知の通り"仮面ライダー"は人間とバッタの合成改造人間であるが、本作では"バッタオーグ"となる。
大森南朋は声だけで"クモオーグ"を演じ、声だけという意味では、"ロボット刑事K"(石ノ森章太郎の漫画作品)を彷彿とさせる、"外世界観測用自立型人工知能ケイ”を演じる松坂桃李もいる。ちなみに松坂桃李は歴代ライダーではなく、侍戦隊シンケンジャーのシンケンレッド。
本田奏多が演じたのは"カマキリカメレオンオーグ(KKオーグ)"だが、"ハチオーグ(ヒロミ)"の西野七瀬以外は、いずれも顔が一部または全部隠れている。本田奏多は、仮面ライダー2号(柄本佑)のライダーチョップでマスクを破壊されて顔が見えるものの、緑のペインティングで認識は不可能という有様。有名俳優の使い捨てには予算の余裕度がうかがえる。
"カマキリカメレオンオーグ"は、3体(人間+カマキリ+カメレオン)合成オーグメントで、死神グループが開発したとされているので、これで死神博士(イカデビル)やゲルショッカーのエピソードにつながる続編への可能性を残す。
本作は仮面ライダーTVシリーズの前半と、石ノ森章太郎の原作漫画のダークヒーローエピソードをベースに、庵野秀明の人類解釈の総集編になっている。見れば見るほどエヴァンゲリオンとも酷似している部分が多いが、それはむしろ庵野監督自身が仮面ライダーを原体験としてエヴァに昇華させたともいえる。
人類にとっての現世と心の世界ハビタットワールドの概念が出てくる。
ショッカーに洗脳された人々が取り込まれる「ハビタット(システム)」という言葉は、現存する国際NGOのHabitatと同名で、「誰もがきちんとした場所で暮らせる世界」を本作では精神世界レベルまで拡大解釈している。
生物の生命力の源を"プラーナ"と呼び、あらゆる生物における魂のようなもの。プラーナを圧縮して増幅することで改造人間のオーグメンテーションを支える。一方で、物質的な肉体を捨てて、プラーナを"ハビタットワールド"に転送して幸福を得られるというのが緑川イチローの考え方だ。
洗脳されたショッカーの信者を解き放つことを"パリハライズ"という。人工子宮生まれの生体電算機と自らを表現するヒロインの緑川ルリ子(浜辺美波)が、"パリハライズ"を可能とするプログラムを作り出し、兄でありショッカーの幹部である緑川イチロー(森山未來)を救い出そうとするエンディングへ向かう。
50年前の仮面ライダーを見たことのない世代には、場面転換が唐突すぎると感じるかもしれない。いきなり崖の上にライダーが現れたり、敵の先回りをしたり、これこそが仮面ライダーの様式美なのである。30分番組の省エネ手法だが、それだけでただ美しい。
序盤シーンで山小屋が時限爆弾で破壊された直後に小屋内にあったサイクロン号にすぐに乗れるのは、仮面ライダーの様式美そのものである。
ただし敵が崖から落ちて爆発して終わるという安易な手法は使っていない。本作ではライダーキックの美しいシルエットを徹底的に見せる。
倒された敵は泡となって消える。ショッカー関係者は情報漏えい対策として融解されるという設定。これには子供心にひどく怖かったドクダリアンが人を食べて服だけを残すシーンを思い出した。
原作の「13人のライダー」のネタから、大量発生相変異型バッタオーグ(ショッカーライダー)がクライマックスで出てくる。元タイトルの"13人"から本郷猛(仮面ライダー1号)と一文字隼人(仮面ライダー2号)を外した11人がショッカーライダーで、劇中では緑川イチローの両側に並ぶ(左に6人、右に5人)。
エンディングで、プラーナとして魂だけとなった本郷猛と、体を共有しながら新"1号+2号"となって新サイクロン号で疾走して終わるのは、石ノ森章太郎の漫画と同じ帰結である。そもそもショッカーの本体である大ボスの人工知能のアイや、その"外世界観測用自立型人工知能ケイ”は倒されていない。
TVシリーズで仮面ライダーをアシストした"おやっさん"こと、"立花藤兵衛"がいないなぁと思ったら、最後の最後に一文字隼人に「名前を名乗らない人間は信じない」と言われて、竹野内豊が「立花」と答える。原作には執事の「立花」も出てくるので名前を同じにしただけかもしれない。斎藤工は「滝」。滝は同じく原作に登場したFBI捜査官・滝和也を彷彿とさせる。
そのシーンでは、"コブラオーグ"の登場もコメントされており、『シン・仮面ライダー2』を作れる余地を残した。
最後に2度見、3度見で楽しいシーンをいくつか。
やっぱりヒロイン緑川ルリ子の"ツンデレ"設定は、庵野秀明監督の確信犯的な趣味。浜田美波の起用は綾波レイ似に尽きる。コウモリオーグシーンではルリ子似のコピー人間がたくさん出てきたりもする。エヴァのマリやアスカのように、ルリ子が本郷猛を「信用しない」と突き放したかと思ったら、着替えのシーンでは「私から離れるな」と甘える。悲しみにくれる女性に「肩を貸して」なんて言われるのは作家の願望そのもの。
ハチオーグ/ヒロミ(西野七瀬)の口癖は"あらら"だが、様々な"あらら"を指折り数えてみると、あらら✕8回。
オープニングで仮面ライダーが初登場するシーン。ルリ子が這って逃げる瞬間、一匹のクモが彼女のブーツに取り付くところに注目。これが次の山小屋のシーンにつながる。
その山小屋で、本郷猛が改造人間となった自分に驚愕するカット。洗面台でグローブ、そしてヘルメットを外して、自分の変容に驚いた本郷猛が慌ててヘルメットを被りなおすとき、すでにグローブをはめている。オヤオヤ。
クライマックスで11人のショッカーライダーに追いかけられるシーンは、いくつも登場するサイクロン号の数が合わない。そのために自走するサイクロン号の設定があり、スペアがあると想像することにする。
(2023/3/17/TOHOシネマズ日比谷/Screen4/F-16/シネスコ)
(2023/3/18/丸の内TOEI/Screen1/K-12/シネスコ)
オリジナルは見てないけど、納得感のあるお話で良かった
やー、良かったです。
平成ライダーはだいたい子どもと一緒に見てますが、昭和ライダーのテレビシリーズはちゃんと見たことがなく、往年のファンの方々がどう受け止められるのか気になるところですが、私は好きでした。
キャストも豪華で、しかもすごく合ってた!
冒頭いきなり血しぶきがバンバン飛んでて、
グロはそこまで得意ではないので、全編この調子だったらどうしようかと思いましたが、
その後はそれ程でもなかったので良かったです(笑)
PG12なだけあって、お客さんは9割が大人の男性でした。
実はこれまで庵野監督作品をちゃんと観たことがなかったのですが、
(「エヴァが難解な上に未回収」という話を聞いていて、何となく食わず嫌いで…(苦笑))
仮面ライダー愛や、オリジナルに対するリスペクトが感じられて、好印象でした。
パンフで監督が語られている、
「自分個人がやりたい事ではなく、一人でも多くの方に喜ばれ、共鳴される可能性が高い描写を意識して選択する」
というお話にとても共感できました。
特に、昔から愛されている作品を創る上で、この視点はほんとに持ってて欲しい(願望)
(その点で、余談ではありますが、この映画を観た後に家族の中で湧き出てきた話題が
「ほんと『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』創り直して欲しい…」でした(ー ー;))
結末も、賛否あるかもしれませんが、
必然性やキャラクターの一貫性が感じられたので、私は納得感があり気持ち良かったです。
「初期のテレビ版仮面ライダーのビジュアルをキープして庵野作品特有の映像と設定の羅列で構築された作品」
冒頭から惜しげなく展開する追跡とアクションが小気味良くて掴まれるが、すぐに説明と設定の羅列が入るところは、この手の作品の宿命なのかと思ってしまうのが痛い。
全体的に初代仮面ライダーの1話からダブルライダー編を再構成してライダーや怪人達のビジュアルは、オリジナルを上手く現代に沿う形でクリンナップしてデザインと造形がされておりこの部分は、庵野作品特有の味も添加されており、いい意味で、ダサカッコイイ塩梅だと思う。
ショッカーやキャラクターの設定は、当然だがオリジナルから比較すると細かく現代風にアップデートされており、本郷猛の設定をコミ障の無職にするのには、苦笑だがここも現代的かな
(正義の味方やドラゴン(カンフー使いの方よ)とゆう職業がないのを、大人なると気付かされる😢)
脚本を担当したウルトラマンもそうだが、どうしても複数の怪人と闘うエピソードの羅列になってしまう部分や映画としてのルック(映像)は予算のこともあるのかも知れませんが、クオリティも統一性もバラツキが、ありDVカメラ特有のノッペリとした絵や照明や特撮部分を担当する安いCGも目につくが、全体的にはテンポが良くて結構楽しく観れると思う。
ホントに気になる点は多々あるが、『トップをねらえ』や『ふしぎの海のナディア』あたりのアニメ時代から同じ内容を焼き直して繰り返していること自体は、多くの映像作家も行っているので、正直気にならないが、極端な構図や設定などの説明台詞を早口で提示する辺りは一考してほしい。
公開前の予告編の寡黙ぶりと本編の饒舌さにかなり違和感あるのと、台詞をガシガシ削ってもライターに熱狂する観客には想像力や考察力があると思って欲しい。
近年の多くの作品が同じ事してるが、YouTubeの○ソ考察やファスト映画解説の氾濫する時にこそ、一度説明台詞を思い切って削るとかする事で、新たな流れを構築する事のできる作家だと思うので。
そういえば、コメディタッチだった庵野版キューティーハニーも予算などが、もう少しあったらこちらに近い出来栄えになったのかな。
全912件中、681~700件目を表示