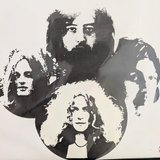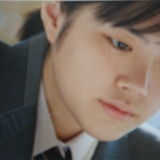王の願い ハングルの始まりのレビュー・感想・評価
全25件中、1~20件目を表示
ハングル成立の謎をリバースエンジニアリング的発想と歴史推理で解き明かす面白さ
朝鮮語の表音文字であるハングル(訓民正音)が誕生したのは15世紀半ば、当時の国王である世宗大王の功績だという。同じ漢字文化圏である日本の表音文字・ひらがなの確立は8世紀末から9世紀頃なので、ずいぶん遅い気もする。朝鮮独自の文字がそれまでできなかった一因は、映画でも描かれているように、上流階級層だけが特権として漢字を学び、知識を庶民に開放しないことで既得権益を守りたがったからだ。
世宗による独自文字の作成にどんな人材が貢献したのかは不明らしいが、製作や脚本で十数年キャリアを築き、本作で監督デビューしたチョ・チョルヒョンは、世宗が当時賎民階級であった仏僧のシンミ和尚に「国のために世を良くした尊者」との称号を贈ったという史実に着目。サンスクリット語や中国語など多くの言語に通じたシンミ和尚がプロジェクトリーダー的な役割を担ったのではないかと推理し、ストーリーを組み立てた。
国民が誰でも使える平易な文字を作りたいと願う心優しさと、重臣たちの反対や抵抗にも屈しない強い意志を併せ持つ世宗役にソン・ガンホ。権力にこびることなく、王の理想に共感して文字作りに尽力するシンミ和尚役にパク・ヘイル。「殺人の追憶」で刑事役と殺人犯役で対決した二人が、本作では文字作りという目的のために協力する役どころで再共演している点も感慨深い。
すべての発音をなるべく少ない文字数で表そうと試行錯誤する過程の描写も知的好奇心をくすぐる。文字の制作過程の記録なども当然残っていないだろうから、ここはおそらく完成形のハングルの構成要素を分解していき、たとえば口の形を表すパーツを定めるまでにはこんなやり取りがあったはずだ、と創作していったのだろう。機械を分解して仕組みや製造方法を学ぶリバースエンジニアリングの手法に近い作業があっただろうと感じた。
なお映画ではハングルが完成するまでしか描かれないが、その後は使用が弾圧された時期などもあり、すぐに普及したわけではなく、義務教育で必修科目になったのは日韓併合時代の20世紀初頭だという。そう聞くと、ハングルが国民に行き渡ってからたかだか百年ほどで、ハングルをベースにした韓流ポップカルチャー(映画、ドラマ、音楽など)が国際的に躍進している現状は率直にすごいなと思う。
「パラサイト 半地下の家族」のソン・ガンホが、独自の文字創生のため...
「パラサイト 半地下の家族」のソン・ガンホが、独自の文字創生のため命を懸けた世宗大王を演じる歴史劇。「殺人の追憶」でソン・ガンホと共演したパク・ヘイルが何カ国もの言語に精通する和尚シンミ役を演じる。朝鮮第4代国王・世宗の時代。朝鮮には自国語を書き表す文字が存在せず、特権として上流階級層だけが中国の漢字を学び使用していた。この状況をもどかしく思っていた世宗は、誰でも容易に学べ、書くことができる朝鮮独自の文字を作ることを決意する。世宗は低い身分ながら何カ国もの言語に詳しい和尚シンミとその弟子たちを呼び寄せ、文字作りへの協力を仰いだ。最下層の僧侶と手を取り合い、庶民に文字を与えようとしている王の行動に臣下たちが激しく反発する中、世宗大王とシンミは新たな文字作りに突き進んでいく。監督は「王の運命 歴史を変えた八日間」の脚本を手がけ、本作が監督デビュー作となるチョ・チョルヒョン。
王の願い ハングルの始まり
2019/韓国
配給:ハーク
民のために文字を作ろうとする王の覚悟
ソン・ガンホ主演なので期待しました。
デジタル化が進む世界中に問いかけています。
ハングルの誕生がテーマの映画
(原題) 나랏말싸미
主要な箇所以外で色々と考えてしまった
王様とお坊さんが、互いのことを深く理解し合って、ハングルを作ったって話なの。
反発しながらも、だんだんとリスペクトし合うようになってくのがいいなあと思って観たよ。
で、思ったのは「韓国のことを本当に知らないな」ってところ。
王様は世宗大王っぽいんだけど、知らないしね。
儒教があんなに威張ってて、仏教が形見の狭い思いをしてたってのも知らなかった。
「いま韓国は仏教どうなってるんだろう」と思ったけど、それも知らないね。
さすがに少しは勉強しようと思ったな。
あとは、王様は、あんまりお坊さんに報いてあげられないんだよね。
お寺は作ってあげたけど、手柄はみんな儒者にあげてしまって。
そこを含めて「理解し合った」ことになってるけど、なかなかしんどいね。
僧侶たちがすごくいい
朝鮮では独自文字が出来たのが遅い
朝鮮国王・世宗の時代、自国語を書く文字が存在せず、上流階級だけが中国の漢字を学び使用していた。しかし、中国の漢字だけでは書くのが難しいため、世宗は誰でも容易に学べ、書くことができる朝鮮独自の文字を作ることにした。世宗は何カ国もの言語に詳しい和尚のシンミたちに文字作りへの協力を仰いだ。最下層の僧侶と手を取り合い、庶民に文字を与えようとしている王の行動に臣下たちが激しく反発する中、世宗王とシンミは新たな文字作りを行っていったという話。
朝鮮語は日本語と文法が似てるので、中国語とは言葉の並びが違って漢字で書くには難しいのはよくわかる。
そんな中、ハングル文字は1443年に作られたらしいから、日本のひらがなが出来た800年ごろに比べるとえらく遅いなと思った。
当時は儒教の影響か、仏教に携わる僧侶が賤しい身分だった事に驚いた。
パラサイトのクソオヤジ役が国王なんだけど、あの印象が強すぎて品の無い国王に見えて仕方なかった。
「ソン・ガンホにハズレ無し」だが・・・・
ハングルは、日本語と語順が同じであること以外は知らないので、文字の創製のシーンは全く分からなかったが、隣国の歴史の勉強になったのは良かった。
漢字を読み書きし専有することで、民衆を支配する特権階級。
かつては仏教が国を支配していたが(そして国を滅ぼした)、この時代は儒者が支配し、仏教は貶められ、大衆の中で生きていたこと。
今も昔も、中国の顔色をうかがって生きている隣国の事情が、浮かび上がってくる。
ハングル文字の創製なかりせば、文化まで支配されていたかもしれない。
ハリウッド映画や韓国映画は、俳優の演技は上手いものの、過剰な演出で、中身のない感動の押し売りをしてくる印象があって、好きではない。
とはいえ、ソン・ガンホは素晴らしい。
王なのだから、もう少し強圧的な演技でしかるべきだと思うが、本作でも“苦悩する王”を好演していた。
ただし、ソン・ガンホが良くても、ソン・ガンホの出る映画が良作とは限らない。映画「パラサイト」がその典型だ。
この映画も、ウィキペディアによると、世宗が仏教を保護しようとしたというのは、史実に反するらしい。
全くの作り話なのだ。となると、作品としては評価できない。
知的な映画
この流れは
中国に配慮しないといけない時代
本作の舞台は世宗大王の時代の朝鮮。「世宗大王 星を追う者たち」という映画では天体観測器や暦を作って、中国からの圧力に怯えた臣下の反感を買う流れだったが、本作では独自の文字を作ろうとして臣下の反感を買う。中国に怯える臣下に気をつかって大変だったんだね、世宗は。
ハングルについては子音と母音の組み合わせでできているということ、そしてその読み方について一通りの知識はあった。でもそんな程度でも十分に楽しめた。音に合わせて文字を考えていく過程、様々な形を書き出し候補とする中、あーこれになっていくのねとか、そこに棒を加えることで文字が成立した!とかの楽しみは味わえた。
文字を作ろうと努力する困難だけでなく、王と僧、王と后、弟子の僧と侍女といった人間関係もうまく描けていて全体としての印象は悪くない。ただし、終わり方はあっさりしているので大きな感動とはならなかったのは残念。文字は作るだけでなく普及させないと意味がない。その困難さについてもう少し説明があっても良かった気がする。
軋轢と因縁
いつ誰が作ったのか
文明国の名折れですよ。
全25件中、1~20件目を表示