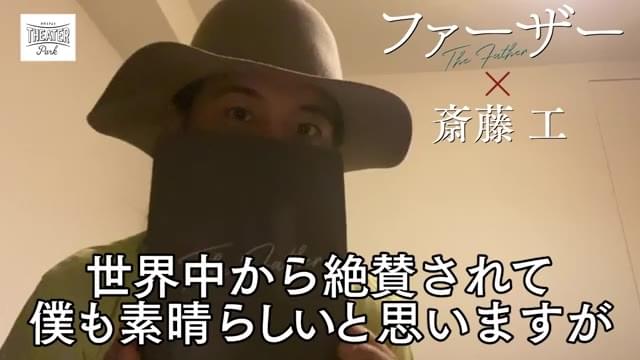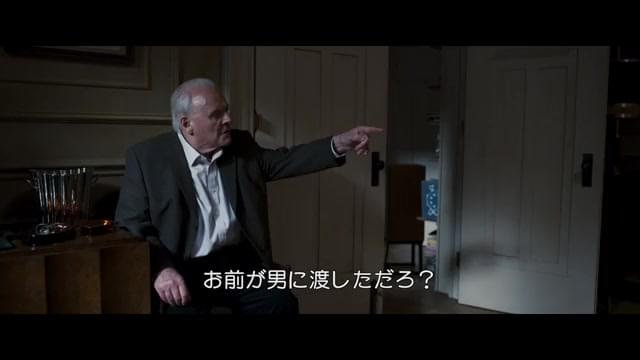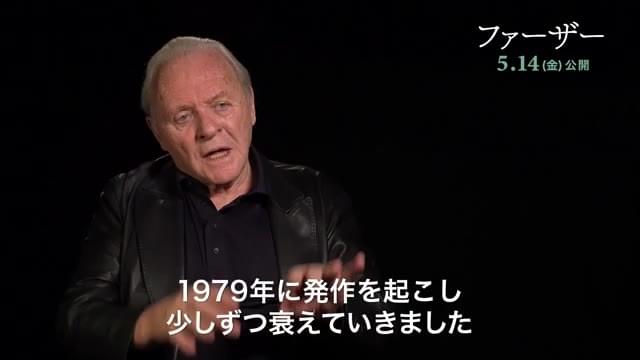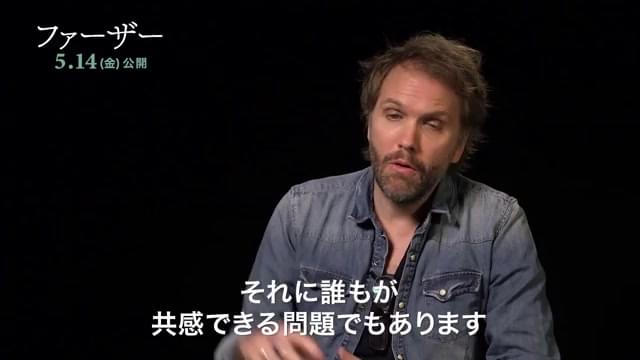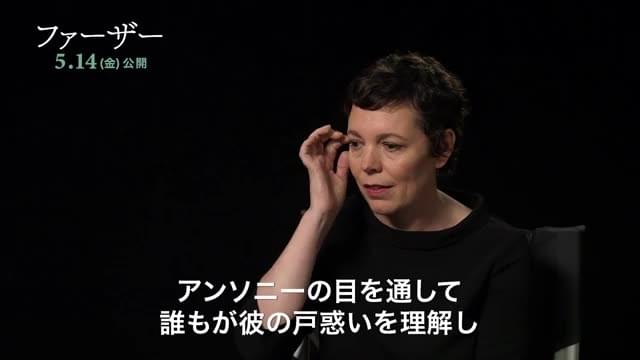ファーザーのレビュー・感想・評価
全346件中、41~60件目を表示
恐ろしく、救いがない
今までに作られてそうだったから
なんと繊細で残酷か
■自分が認知症になるとは?
男性は5人に1人、女性はなんと2人に1人、寿命が尽きる最後の5年間で認知症に罹かります。
人生を最後まで見通す時、これだけ多くの人が認知症になる事実を踏まえると、「自分は認知症になるかも」という想定は不可避です。
しかし、本当に認知症になることが不幸なのでしょうか?
病気の知識はあったとしても、認知症になった自分は一体どう感じ何を考えるのか良くわかりません。
■新しい視点で認知症の日常を描く
『ファーザー』は、認知症の日常を新しい視点で描く映画ですが、特に認知症に罹った人が見ている世界を教えてくれます。
ある日、アンソニー・ホプキンス演じるアンソニーは、娘のアンから新しい恋人とパリで暮らすと告げられます。ところが、自宅のフラット(アパートメント)には、アンと結婚して10年になるという見知らぬ男が現れます。実際にアンは、ロンドンに恋人と暮らしています。
この辻褄があわない状況に、われわれ観客は混乱しますが、ようやくそれはアンソニーが見ている世界だと理解が至ります。
アンは、父の日常生活をサポートしてもらうため介護人を手配しますが、アンソニーは癇癪を起こしトラブルになります。
アンは、アンソニーを引き取って3人で暮らし始めますが、アンソニーはそこを自分のフラットだと勘違いします。
別の日には、亡くなった娘が生きていると言って周りを困惑させます。
こうして認知症は、日増しに進行していきます。
そして最後は、施設に入所したことも、自分の名前もわからなくなります。
■認知症の人が見ている世界
アンソニー・ホプキンスが演じる認知症状の描写は、われわれに認知症のリアルを伝えます。
ざっと取り上げるだけでも・・、アンから直前に聞いた予定を忘れる「短期記憶の低下」、自分の経歴を勘違いする「エピソード記憶の低下」、今いる場所や時間が混乱する「見当識障害」、介護人に対する「暴言」、時計を盗まれたと勘違いする「物盗られ妄想」、同じ体験を二度する「幻想」、といった典型的な症状が次々と現れます。
そして、認知症状が悪化していく様子は、ドキュメンタリーともいってもよいものです。
ただそれだけでなく、この映画は認知症の「心の世界」に迫っています。
この映画は、第三者視点・客観的視点を徹底して貫いています。そのなかで、次々と起こる出来事の矛盾を通じて、認知症のアンソニーが見ている世界を描くことに成功しています。
しかし、アンソニーが抱く混乱や不安、諦めなどの本人の心境には立ち入りません。
故障したCDプレイヤーが、アリア「耳に残るは君の歌声」を繰返し再生する場面は、アンソニー自身が抱えている底知れぬ不安を感じさせます。
■認知症には2人の患者がいる
もう一つ、この映画の特徴は、やはり客観的視点から「世話する人」と「世話される人」という二つの立場を描き分けているところです。
認知症には2人の患者がいるといわれます。アンソニー本人の苦しみはもちろんですが、日常的に世話をするアンの悩みや悲しみはそれに匹敵するものです。
認知症の進行で、周りの人は日常で起こりえない様々な場面に遭遇します。介護に伴う労働はもちろんですが、例えば、記憶障害は家族の記憶にもかかわるものも多く、必要以上に傷つくことがあります。アンもアンソニーの言葉に傷ついていました。
しかし、この映画では、アンの苦しみを必要以上に描いていません。その代わり、アンを取り巻く人々がその都度登場し、感情を表します。
アンの恋人や見知らぬ男は、アンソニーに対する怒りを露わにし、介護人は戸惑います。そして、アンは悲しみ、涙します。
心情を分担させて描くことで、「世話する人」の苦悩を浮き彫りにしています。
このように認知症という現実を、この映画は極めて繊細に描きます。
それゆえ、認知症の残酷さが、われわれに突き刺さります。
あなたはアンソニーよ
これほど釘付けにさせられるとは思わなかった。
登場人物は6人。
人と人との間に広がる世界に引き込まれて、ある時はやり場のない悲しみに、ある時は主人公と共に混乱する気持ちを体感しながら進むストーリー。
おそらくストーリー中の時系列は、すでに主人公が施設に入ったところから始めっており、さまざまな断片化された記憶と現実を結びつけながら話は進んでいっているのだと思われる。
人間の現実を突きつけられる一方で、作品としての深さを思う存分に味わわされる。
アンソニーホプキンスの演技と脚本、グレーな絵が合間って、なんという映画だ。
どうとらえたらよいのか
認知症の方の見え方をそのまま見ているようだと理解できても楽しめるものでもなく、ラストに向けて真実を推理しながら視聴。だからといって面白いのかと問われれば「う~ん?!」という感じ。おじいちゃんが可哀想で、もうちょっと寄り添った言い方をしてあげてと思いながらみてしまった。
意外に凝った構成が良い
混同
恐れ
その心許なさ
ロンドンで一人暮らしをする老人アンソニーをアンソニー・ホプキンスが、オリヴィア・コールマンがその娘を演じる。
薄れゆく記憶、住み慣れた家を離れ、1人施設で生きる事の心許なさ、侘しさ、孤独感…。嗚咽する姿に胸が詰まる。
BS松竹東急を録画にて鑑賞 (吹替版)
事実と妄想 主人公の体験を追体験しているような感覚
本がいい。演技がいい。
気持ちを共有する事で解る、認知症という難病
何が何だかわからない辛さ
認知症目線で、介護される側の気持ちを体験できる。
介護が大変であることは当然知られているけれど、認知症の人自身の混乱や辛さをここまで感じたのは初めてだった。何が何だかわからないということが、どれだけ辛いか。誰にも理解されず、違和感を感じながら生きること…
とても手厚い介護をしてくれるところだから、娘はかなり頑張って高額な施設を選んだんだろうなと思った。
娘も日々を捧げて尽くしても、なかなか届かない気持ちも辛い。
誰も悪くなくて、ただ辛い最中にいることが苦しい。
もし家族や自分がなったらどうしたらいいか、つい考えることも逃げてしまうけど、考えておいた方がいいよなあと思ったり…
将来、認知症が治る病になったら、どれだけ多くの人が救われるだろうか。どうか、開発されたらいいなと願ってしまう。
そして、最後のシーンで『ママに会いたい』という顔が、父親ではなく、子どものような顔になっているところにゾクゾクさせられた。さすが名優、という言葉では足りないくらい、すごいお芝居だった。
完璧
記憶の構成、危うさ、そして音楽の美しさ
他のレビューでも指摘されているけれど、認知症の患者の眼に、毎日がどう映っているのかが、ミステリーのトリックのようにほんの少しのヒントを含みながら危うくつなげられていく。
でも、人間の記憶ってほんとうはこんなふうにあったかどうかわからない思い込みで事実の隙間を埋めて成り立っているのかも、ね。
監督兼原作者のゼレールは、自分のオリジナルの舞台脚本を、わざわざアンソニー・ホプキンスに当て書きをし直して映画に仕上げたのだそうだけれど、当のホプキンスは自分の父親を真似て演じ、そのためとても「楽だった」そう。なんとも言えないオチがついた。
音楽が素晴らしい。まだ理性を保っているうちは、アンソニー(役名もこれ)はパーセルの『アーサー王』のやうな、なかなかに通っぽいオペラばかり聴いている。
でも次第に、それぞれの事実をつなぐ記憶が途切れてくると、いつの間にか音楽はミニマル・ミュージックのような、静かに抑えたピアノの響きだけになっていく。
作曲はルドヴィコ・エイナウディ。微かな音が、あちこちから湧いてくる記憶の糸のように繊細に響くピアノ。それからデゥィド・メンケ。病院(施設?)の現実をあらわすかのような冷たい、硬質な響きの音。
2人とも名前は初めて知ったけれどかなりのアルバムが配信されている。聴くのが楽しみ。
他人事ではない
全346件中、41~60件目を表示