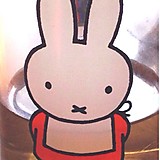親愛なる同志たちへのレビュー・感想・評価
全51件中、1~20件目を表示
コサックの軍服
国家という大きな共同体と家族という最小単位の共同体が、一人の女性の中で衝突する。市政委員会のメンバーである主人公は、体制側の人間だ。イデオロギー的にも共産主義の正しさを心底信じている。一方、その娘は、工場に勤めており、ストライキに参加し体制を批判する側となる。ストは大きな暴動に発展し、軍が鎮圧に乗り出すと、安否のわからなくなった娘の行方を追って主人公は奔走する。
軍が市民を殺すという事態を、体制側は隠ぺいしようとする。しかし、娘がそれに巻き込まれた主人公は、何を信じればいいのか揺らいでいく。娘を想う気持ちと国家を信じたい気持ちの狭間で主人公は葛藤し続ける
主人公と娘の他、主人公の父も重要な存在として描かれる。彼は、コサック兵の軍服を大切に保管している。コサック兵はかつてロシアの支配に対抗した軍事勢力だが、この作品の舞台はコサックがかつて活躍した土地でもある。そんな父の存在によって国家と娘の対立軸に、歴史の経糸が折り重なり、分厚い物語に仕上がっている。改めて、ロシアとはどんな国なのかを知るために、見てほしい作品だ。
モノクロームを通じて身の震えが伝わってくる
なんとも痛烈なタイトルである。60年代、ソ連の南部にある街で起こった労働者たちの大規模なストライキが、無差別銃撃事件へと発展していく過程をモノクロームで描いた作品だ。興味深いのは、ストライキの参加者が主人公というわけではなく、むしろこの混乱をどう収めるか頭を悩ませる”市政委員の女性”にスポットを当てていること。党への忠誠を誓う彼女の瞳を通じて、フルシチョフ政権が派遣する軍やKGBの暗躍、人が逃げ惑い命を落としていく凄惨な状況が浮き彫りになる。そして彼女自身も一人娘の行方を探して街を彷徨い続けーーー。徐々に不安と絶望に覆われていく主演女優の演技に言葉を失う一作だ。この事件から60年が経つが、時代は何も変わっておらず、「力で抑える」「恐怖で治める」ことがもたらす悲劇はいまだ無くならない。現在TVやネットを通じて伝えられるウクライナの凄惨な光景もまた延長線上にあるものではないかと意識させられた。
Satantangonian Throwback
This Russian black-and-white tale of a political massacre in the 1960's feels relevant in the age of shutdowns and surveillance identification; not to mention the event takes place only a few hours drive from Mariupol. Disgruntled factory workers meet their demise when the KGB steps in, and a socialist-loyal official finds herself at the brunt of the disappearing act. Slow but terrifying.
示唆に富みすぎる作品
この映画を観るまで「ノヴォチェルカスク虐殺事件」なんて知りませんでした。
そして、冒頭のセリフから現実社会、政治、経済との対比で次々と考えさせられて頭が疲れました。マジでこんなに考えたのは久しぶりです。映画を観た後に事実経過を調べましたが、この映画の通りでした。モノクロ映像と相まって実にリアルに制作したのだと改めて感心しました。
・「共産主義で物価が上がるのはあり得ない」:常に需要と供給がバランスする建前ですからね。必要なものを必要なだけ。ですが、経済失政(意味不明なデノミ)で激烈なスタグフレーションとなりました。ノヴォチェルカスクは貧しい地域で元受刑者が多く住む町で、賃金は上がらない(どころか下げられる方向)、物価は上がっていくというところから始まります。
・共産党は「無謬性」で成り立っています。党の指導に間違いはない。もし問題があるのなら、それは現場の問題である。そう、理不尽です。でも、現代社会でもそうあるべきだ、そうなっているという前提で物事が進んでないですか?過失に厳しくしすぎていませんか?そして、それがさらなる歪みを生産している現実。今も昔も強度の違いはあれ同じです。
・上意下達の弊害。党本部の指導が絶対です。権限委譲なんてありません。群衆がデモで不満を訴えても町の委員会にはなんの回答も出せません。中枢から幹部がやってきますが彼らは教条主義者です。却って火に油を注ぐだけです。なお、このデモの解決にミコヤン第一副首相が当たっていたことにびっくりしました。党本部は事件に重大性を感じていたのだと理解できます。
・回顧は手軽な現実逃避。主人公リューダは共産党員で町の委員会の幹部で組織に思想に忠実でしたが、物価上昇等からスターリン時代を良い時代だった、スターリンに戻ってきて欲しいと何度か繰り返しますがそんなことにはなりえません。昔を懐かしむ、良い時代だったと回顧するのは現実逃避なんだなあと気づきました。しかし、スターリン時代が良かった、という感覚は私には理解出来ません。ホロドモール、ロシア内には知られてなかったでしょうか。
・軍とKGBの関係が面白い。というか、こんな状態で軍人になろうなんてよく思うよなあ・・・。
・ノヴォチェルカスクってウクライナの隣なんですね。アゾフ海で云々のセリフもありました。
・親の子に対する思いは時代、体制関係ないよね。当たり前ですが。
他にもいろいろとありましたが、このタイミングでドキュメンタリータッチでの上映には感謝します。是非、映画館で。
全体主義国家の恐ろしさが良く分かる映画
収容所群島等が暴露された現在では希薄な印象
1 時代背景
ソ連は1928年から経済5か年計画を開始し驚異的な成長を遂げるのだが、1950年代後半になると停滞し始める。「フルシチョフが呼号した”社会主義的生産様式の優位”は1960年代には失われ、経済の分野で、アメリカ合衆国に追いつき、これを追い越すことは夢物語になってしま」ったことから、その後、経済に代わり軍備拡張による対外的膨張政策に転じていく(猪木正道『共産主義の系譜』)。その帰結が異常な核開発競争である。
本作は、経済的な停滞が生活の悪化をもたらしてきた1962年、現在のロシア・ウクライナ国境に近いノヴォチェルカスクで発生した工場労働者のデモに対し、軍や秘密警察KGBが弾圧を加えた事件を描いている。
2 ソ連からロシアに続く人命軽視と情報統制体質
映画では、冒頭で共産党員の規律の乱れ、計画経済の限界と生活苦、党員の特権的待遇を簡単にスケッチし、その後、工場労働者に対する軍やKGBの銃殺事件を通じてソ連共産党の人命軽視と情報統制の体質を批判している。
それがそのまま現代ロシアへの批判に見えてしまうのは、いまだに人命軽視と情報統制の独裁国家であるロシアの実体が、ウクライナ侵略戦争を通じて明らかになったからだろう。もちろん監督はそれを狙っているはずだ。
3 収容所群島等が暴露された現在では希薄な印象
本作はソ連共産党の地方党員を主人公とし、単に弾圧の被害ばかりでなく、その根本的な原因である共産党独裁と党官僚の腐敗を効果的に描いている。
とはいえ世界はすでにホロドモールや第二次大戦中のドイツ兵、日本兵のシベリア虜囚を、収容所群島の悲惨やプラハの春の弾圧を見てしまった。1962年には本作の事件の半年後にソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』が発表され、統制国家ソ連の実態はやがて次々に暴露されていくのである。
その視点からは、本作の描いた事件ははっきり言って取るに足りないという印象を免れない。映画の感想が希薄なものにならざるを得ない所以である。
これはすごい傑作ではないか?
長らく映画館に行けてない。見逃した作品も数多い中、たまたまタイミングよくケーブルで鑑賞できた注目作。スタンダードサイズのようだったけどほんとかな。
1962年のソ連で起こった国家的犯罪を背景に、党員としての理想と母親としての愛憎に引き裂かれる女。その姿を通して描く、ロシア人が負ってきた不遇と不屈の魂。いやー、主演の女優さんがいいですねー。コンチャロフスキーの奥さんだとか。実に綺麗に撮れてるし芝居がうまい。会議での発表を前にパニックになるあたり、そして終盤のクルマでの帰路、ウオッカをあおりながら歌う革命歌のシーン。白眉です。
少々説明不足なところがあって、何で?ってなるところもあるけれど、あのKGB。いい人もいるのさってことで流していいのかな。それとあの会議はどうなったんだ?
とまれ、悲愴な歴史を生きてきた人々に幸あれと願わずにいられない。ことに独裁者プーチンを戴く現今にあってはなおのこと。
靴下の穴から真実を覗く
裏口
ロシア国民への逆説的な警告映画
スターリン後のフルシチョフの時代、ソ連南部で起きた大規模なストライキの銃撃による鎮圧を題材にしている。
その場に居合わせた共産党の幹部である主人公リューダの苦悩を描いているが、彼女の「スターリン時代の方が良かった」というフレーズが、一番印象に残っています。スターリン時代は弾圧がすさまじく、皆YESMAN・YESWOMANであり、ストライキなど起こせなかったからです。YESMAN・YESWOMANの方が、何も考えなくてもよく、ある意味、楽です。
今のプーチン時代のロシア人に、逆説的に警告を鳴らしているように感じます。
一方、日本を振り返ってみると、国民のほとんどがYESMAN・YESWOMANになり、日中戦争・太平洋戦争へ突き進んでいった歴史があります。ロシア人だけでなく、日本人への警告でもあります。
また、現在、この映画のような国々が、日本の近くにあるのも気がかりです。
青い鳥はいつも傍に。
1962年ソ連:ノヴォチェルカスクで起こった虐殺事件。
ストライキ中の労働者へ軍(KGB?言及せず)が銃を発砲。
死者、重傷者あり。参加者は全て投獄され。目撃者には「秘密をばらすと厳罰に処す」との書面にサインを強要。国をあげて隠蔽した(90年代まで発覚せず)。
主人公は当局「市政委員会」で課長を務める母親。娘がストライキに参加しており投獄されると知ってもなお「反逆者には厳罰をのぞむ」との姿勢を崩さない。しかし行方不明の娘を病院、死体安置所、墓場と探すうち「共産主義以外何を信じたらいい」とか、スターリンを賞賛していた考えが揺らぎ、国への不信感が沸き上がる。
必死に探した娘は死んだと思い、うちのめされて帰宅するとそこに娘が……。
本作は、ノヴォチェルカスク残虐事件そのものに言及したい訳ではないと思った。
母親は「娘は髪を三つ編みにして青いリボンをつけている」と繰り返します。
「青いリボン」
お話の骨組みはまるで「青い鳥」
必死に探した青い鳥は近くにいた。
このお話の教訓は「理想ばかりを追い求めていないで現実を見なさい」です。
監督のコンチャロフスキーもロシア国民に向けて「親愛なる同志たちよ、ロシアの現実を見ろ」と言いたいのでしょう。
「親愛なる同志たちへ」のタイトルは劇中で母親が当局に出せなかった手紙の冒頭ですが、この映画こそが監督からロシア国への手紙なのだと思いました。
また「青い鳥」の母親は「子供に対する愛こそ一番の喜びである」と言っていたと思います。
本作のラストで、娘を抱きしめる母にも重なる言葉です。
タイトルなし(ネタバレ)
観たのは数か月前。映画公開と前後してロシアのウクライナ侵攻がはじまり、あらすじを書いたあたりでレビューがストップしていました。
さて、コンチャロフスキー監督は、同じく監督のニキータ・ミハルコフの兄で、ソ連時代から監督をし、後、米国でもエンタテインメント系の作品も多く撮っていますが、半数ぐらいは日本では劇場未公開ではないかしらん。
監督作品が劇場公開されるのはいつ以来のことかしらん。
2014年製作の『白夜と配達人』は東京国際映画祭で鑑賞しましたが。
1962年、フルシチョフ政権下のソ連南西部ノボチェルカッスクで党役員として活躍するリューダ(ユリア・ヴィソツカヤ)。
実生活では、コサック兵として闘った経験のある父と、機関車工場で働く18歳の娘スヴェッカとの3人暮らし。
町の党委員としては上級の地位にあるのだが、独り身ゆえに疼く心は押さえきれず、同じく党役員と不倫関係にある。
リューダを悩ましているのは、スターリン政権からフルシチョフ政権に代わっての物価高騰と食糧不足。
しかし、それとても党地方組織委員という立場からすれば、希少な食料はわけなく手に入る。
それよりも、娘スヴェッカの行動だ。
若気の至りといえばそれまでだが、政府に楯突くような素振りが感じられる。
そんな中、スヴェッカが働く機関車工場でストライキが勃発する。
社会主義国家の中でストライキとは俄かに信じがたいリューダだったが、物価高騰と食糧不足に加えて、経営陣からの一方的な賃下げ。
スヴェッカはストライキに参加し、他の労働者たちの熱に浮かされて、過激な行動に出るのではないか・・・
リューダも含めて、党幹部が集まった目の前に、労働者のひとりから石礫が投げ込まれ、それが合図であるかのように、銃声が鳴り響く・・・
といったところからはじまる物語は、数年前のマイク・リー監督『ピータールー マンチェスターの悲劇』を思い出すが、国家が国民に銃を向ける映画といえば『天国の門』もそうですね。
で、市民へ向けての発砲、国からの弾圧は映画の中盤、どちらかといえば前半に近いところに位置している。
この発砲銃撃事件までの演出は、共産党地方都市幹部のリューダの日常を描いていくわけですが、狭い部屋での鏡の多用など、普通に撮れば平板になるところを多層的にみせている演出。
冒頭の不倫シーンはヒッチコック『サイコ』をちらりと思い出しました。
そして、発砲銃撃事件となるのですが、混乱の描写を対立法・体位法という、哀しみ大きシーンとは反対の陽気な音楽。
事件近くの美容室で、無音で飛ぶ銃弾に女店主が被弾するシーンでは、ラジオから陽気な音楽が流れている・・・
おお、久しぶりにこの手の演出を観ましたぞ。
黒澤明や小津安二郎も使っていたので、60年代ぐらいまでは割とよく見た演出方法なのですが、ここ最近はとんと観なくなりました。
この混乱の中、娘スヴェッカは行方不明となり、リューダが探す物語が後半となります。
この後半は、近作では『アイダよ何処へ』を思い出しましたが、古くはフレッド・ジンネマン監督『山河遥かなり』も思い出しました。
後者を思い出したのは、リューダを手助けする党幹部の男性が登場することも影響しているかもしれません。
ただ、この男性が登場することで、ややドラマがメロウな方向に流れてしまったのは残念。
探索当初は娘の生存を信じていたリューダですが、次第に娘の死を確信するに至る。
そして、彼女が着けていたリボン(だかの小物)を手掛かりに、娘が埋葬されたと言われる墓にたどり着く・・・
このあたりはかなりのメロウ描写なのですが、監督の想いは最終盤にありました。
死んだと思われていた娘であったが、実は生きていた。
そして、母娘が並んで呟く「この国は、きっと良くなる」という言葉。
これはコンチャロフスキー監督の祖国ロシアへの郷愁と希望と祈りのようなものが込められています。
過去の暴行に目を背けることなく、そんな歴史も受けとめた上で国を信じたい、という願い。
老境のコンチャロフスキー監督に今回のウクライナ侵攻はどのように映っているのでしょうか。
そのことも含めて、今年いちばん心に感じるものの多い映画でした。
現在のロシアで制作する限界か
旧ソ連・フルシチョフ時代に起こり、長く隠蔽されていた労働者弾圧事件を題材にしているということで、国家の横暴や市民への抑圧といった負の側面を、現在のロシアにおいてどのように描いているのか、関心を持って観た。
まず、デモを起こした労働者側ではなく、それに対応する当局者側を主人公にしたのは面白い。デモに参加して行方不明となった娘を探すうちに、国家の恐ろしい姿を知る、というのがメインストーリーだが、もっと主人公と娘の葛藤を真ん中に据えてもよかった。
その代わり、主人公と元コサックの父の関わりが描かれ、意味深だが、よくわからないまま。(反革命?)
発砲の主はKGBであることが示唆されるが、はっきりとは描かれない。主人公を手助けするKGBが、どうもうさんくさい。とってつけたようなエピローグは、現在のロシアで制作する限界を感じさせる。
モノクロスタンダードの画面は、50年代、60年代のヨーロッパ映画を思い起こさせて好ましいが、どうしても現実のウクライナ情勢と重ね合わせて、暗い気持ちにはなってしまう。
【”自国の民に銃口を向ける国に未来はない。”1962年、旧ソ連で起きた「ノボチェルカッスク事件」を描いた作品。暗澹たる気持ちになるのは、この事件が30年の間、徹底的に隠蔽されていた事実である。】
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・全体主義且つ独裁国家は何時かは滅びる事を、今作を観て再確認した。
・今作で、物価高騰や、賃金カットによりストライキを行った、国営工場の労働者たる民衆に銃口を向け、虐殺したのはKGB(カー・ゲー・ベー)となっている。
- 現在のロシアを統べる愚かしき男がKGB出身である事は、周知の事実である。-
・熱心な共産党員で、ノボチェルカッスクの市政委員であるリューダの娘が、ストライキに参加し行方不明になるシーン。
- キツイ女、リューダが、旧ソ連の最高幹部たちを前に”反逆者には制裁を!”と会議で叫んだあと、彼女の娘は行方不明になる。
彼女の国家への忠誠心と葛藤しながら、愛する娘を必死に探す姿。アイロニカルであるが、リューダの姿は心に響く。-
・今作は、徹底的に共産主義の理想と、厳しき現実の隔たりを炙り出している。
・虐殺が行われた数日後に、党の意向で町で祭が行われるシーンも、実に監督の意図を上手く反映している。
<全体主義の危うさ、情報統制国家の恐ろしさを克明に描いた作品。現況下の状況を鑑みると、人間とは過去から学ばない生き物である事が良く分かる。
今作では1962年、旧ソ連で起きた「ノボチェルカッスク事件」を描いているが、2022年の現代、旧ソ連を継いだ国が行っている事・・。
それにしても、今作はアンドレイ・コンチャロフスキー監督だからこそ、制作出来たのであろうか・・。(ラストの描き方などで、当局の検閲を逃れたのでは・・、と私は思った。)
今作で描かれた事には背筋が寒くなるが、観る側に大切なことを訴えかける力を持った作品である。>
<2022年5月22日 刈谷日劇にて鑑賞>
自らの信条に裏切られることの辛さ
フルシチョフ時代に起こった、社会主義体制ではないことにされている労働争議をもとにした映画だが、しばらく忘れていた冷戦期のソ連社会のイメージが色々蘇った。地元の共産党役員で配給も特別扱いされる主人公の目を通して共産党組織の官僚主義や矛盾も明らかにされる。実際に映画のような、あるいはそれ以上の悲劇はあっただろうが、自分の信じた共産主義に裏切られていく主人公の思いに、もっと普遍的な人間の業を感じる。スターリン時代より自由化したフルシチョフ体制下で起きた値上げや賃下げ、ストというのも、歴史の皮肉である。スターリン時代を懐かしむ気持ちも、主人公の立場に立てば分かる。コサックの話まで入れたのはストーリーとして出来過ぎの感もあるが、十分に見応えある作品である。
全51件中、1~20件目を表示