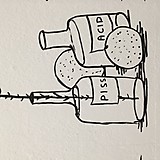ザ・バンド かつて僕らは兄弟だったのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
寂しさが残る作品でした
ザ・バンドの誕生から解散までを描いたドキュメンタリー作品。
劇場で観ようと思ってたら、すぐ終わっちゃって。
そしたらすぐプライムに上がってきて驚きました。
バンドはカントリーとブルーズが混ざったような音で、大好きなバンドなんです。
あの「Last Waltz」を撮ったスコセッシが、製作総指揮としてクレジットされてるのも憎いですね。
それにしてもこれ観ると、改めてボブデュランとの絆の深さがわかります。
青春時代とも言えるビッグピンク期など、こうしてフィルムで観れるのは嬉しいものですね。
中でも「The Weigh」の誕生した話がとても興味深かったし、皆話す顔がキラキラしていた。
でも幸せな時間は永遠ではなく、アルコールとドラッグで段々と歯車が狂ってくるんです。
ロビーとメンバーの間に徐々に溝ができてくる頃ですね。
こうなって来るともうどうしようも無かったのでしょう。
あとこの作品、ロビーロバートソンの自伝を元に作られているので、どうしてもバンドに対して俯瞰に描かれてい無いように感じてしまいます。
これはしょうがないんでしょうけど、観ていて少し引っ掛かりがあるんですよね。
そうして迎えたウインターランドでのライブ。いわゆる「Last Waltz」です。
この時の皆んなの思い出がじわじわと胸にきて、映画だけど終わらないでほしいとさえ思うようになっていましたよ。
この、大切な何かが消えていくような終盤のまとめ方は良かったです。
偉大なバンドである再認識と、どうにかならなかったのという寂しさが残る作品でした。
バイオグラフィでたどるザ・バンド再入門の快感、メンバー間の不和と死
ザ・バンドの奇妙で懐かしい音楽を長らく聴いてきたくせに、彼らのバイオグラフィにはとんと無知だった小生に、本作は彼らの音楽に再入門させてくれる楽しみと、メンバーの多くが鬼籍に入ってしまった寂しさを感じさせるものだった。
1)映画の主な内容
十代の頃のロビー・ロバートソンとリヴォン・ヘルムとの出会いから、ロニー・ホーキンスのバックバンド・ホークスの結成、ロニーの音楽を乗り越えてしまう向上心、ボブ・ディランとの偶然の出会いとヨーロッパ・ツアーでのフォーク・ファンのブーイングとの闘い、そしてファースト・アルバムがロック界に与えた静かで深い衝撃と成功、やがて訪れるアルコールやドラッグ中毒と金銭トラブルによるメンバー間の亀裂、ディラン、エリック・クラプトン、ニール・ヤング、ヴァン・モリソン、ジョニ・ミッチェルらビッグネームを招いた集大成のコンサートと解散、その後のメンバー間の不和、そして5人中3人までの死…それらをリーダーのロビーが丁寧に淡々と語り、それを彼の奥さんや周囲にいた人々が補足していく。
2)ザ・バンドの音楽の影響力
バンドとその音楽について、メンバーと周辺の人々の証言が多くを語っている。
ディランは自らのフォーク・ファンとの戦いに参加し、騎士団のように守ってくれたバンドに感謝する。
ロビーは自分の作った「ザ・ウェイト」を聞いたディランが、賞賛の表情を浮かべたことを嬉しそうに回想する。
「4%パントマイム」で共演した、あの気難し屋のヴァン・モリソンが率直にラスト・ワルツを祝福していること、ファースト・アルバムを聴いたブルース・スプリングスティーンは「これは革命だ」と感じたこと、クラプトンにいたっては「リズムギターでもいいからバンドのメンバーに加えて欲しい」と頼みに行ったこと等々、証言すべてが実に興味深い。
そのサウンドはライ・クーダーらの音楽とともにルーツ・ミュージックの流れを形成し、今やアメリカーナと呼ばれることも本作で初めて知った。マーチン・スコセッシ等の証言には、バンドの音楽にアメリカ文学、スタインベックやメルヴィルとの共通性を見出す意見もあって面白い。
願わくば彼らの音楽性について、専門家がさらに突っ込んだ解説をしてくれれば、音楽映画としてより立体的になったろうにと惜しまれる。
3)メンバー間の亀裂と解散後の不和について
ロビーや奥さんの証言によれば、ドラッグ中毒で不安定な心理状態に陥ったリヴォンは、主要曲の著作権を独占していることに対する嫉妬からロビーを攻撃し始めたという。
しかし、アルコールやドラッグの中毒にならなかったのはロビーだけで、彼が毎朝10時から作曲をしている間、他のメンバーは寝ていた。彼らはアレンジを手伝ったが、著作権は作曲したロビーのもので、それは動かせないということが、周辺の人々から語られる。
他方、手元にあるリヴォン・ヘルムとリック・ダンコのインタビューを見ると、ロビーは次のように批判されている。
リック「(メンバーとの共作がなくなっていったのは)ロビー・ロバートソンのエゴだ。もしもロビーがバンドに戻りたかったら、車輪を回すスポークの1本にならなければいけない」
リヴォン「2枚目の後、俺らに大金が提示され、巡業に出るようになって、バンドを取り巻く環境が変わっていった。同時に発見したことは、レコードを見てみると、どの曲の作者もJ・R・ロバートソンになっているじゃないか(笑い)」
リック「それは本当じゃないんだ」
リヴォン「そんなことが起こって、ザ・バンドはおかしくなっていった。同じ舞台に立つことは二度とないだろう」
このインタビューは1976年の解散後、18年を経た1994年のもの。この直前にザ・バンドはロックの殿堂入りするが、リヴォンはインタビューの発言通り、ロビーを嫌ってその式典への出席を拒否したのだった。
メンバー間の紛争の真実がどこにあるのか、我々には知りようがない。しかし、リヴォンらの主張が「著作権はロビーにはない」ではなく、「著作権はロビーだけのものではない」というものであることに加え、解散後の再結成盤やソロ・アルバムを聴く限り、ロビー以外のものは印象が希薄である。それを踏まえるなら、ロビーがバンドの骨格であり続けたことは間違いない。
最後にリヴォンの死の床(2012年)にはロビーが駆け付け、臨終を看取ったらしい。もはや意識不明だったというが、ここで彼らが和解したと信じ、亡くなったメンバーたちの冥福を祈りたい。
ロックが商業化される前の話なんだが・・・
「ラストワルツ」は随分と前に観ていた。有楽町のスバル座という、今はすでに閉館してしまった映画館でだ。エンドロールが終わって館内が明るくなるまで動けなかったことを鮮明に覚えている。仕方のないことだけれどロビー・ロバートソンの創った映画なのだ。自伝映画みたいなものだから、想像だけれど過去を脚色していることは紛れもないだろう。カッコ悪くは作らない誰だってすることだ。この映画を観る少し前にグレートフルデッドのドキュメンタリーを見てしまっていたので比較してしまった。時代もほぼ同じ、ディランのバックをやったバンドでもあった。しかしながら、バンドとしてのスケールが余りにも違い過ぎていて、ロビー・ロバートソンが可哀そうになってしまった。それは人としてのジェリー・ガルシア(グレートフルデッド・リーダー)の大きさの凄さだった。バンドスタッフ全部をひとまとめにできる統率力はサウンド・ウォールを作り上げたことで立証されてしまっている。半端なヤクザプロモーターなど傍にも寄れぬそのパワーはこの時代の最先端を走っていた。チライブチケットの販売にいたるまですべてを彼らが仕切ってしまっていたのだから・・・・そして、なによりも誰に阿ることもなく(観客も含めて)自分たちの気に入った音楽しか演らなかった。ロビー・ロバートソンは苦しんだと思う。レコード会社にプロモーター・・・そして何よりもディランに阿なくてはならなかったろうに・・・・ひどく疲れ果てて出来上がった曲が「ラストワルツ」だったんじゃないのかな。したがって名曲となったんだ。
ディランは余りにも難解すぎたんだ。
「ラスト・ワルツ」知ってたから観た。疲れた。
伝説のバンド。何故か「ローリングストーン」だかの「偉大なアーティスト」歴代50位だから観た。
ニール・ヤングとの「HELPLESS」だかが記憶から離れない。
ただ結果はあまりよく知らないバンドだけあって、ツウ好みで難解で疲れた。
難解というか、誰でも知ってるヒット曲が無いし、ポピュラーではないから平板なドキュメンタリー。
ボブ・ディランがたかだか珍妙な歌詞程度でノーベル賞受賞者になったことに義憤を感じるワイにはアウト。
ビートルズやストーンズとジャンルが違うから比べてはいけないのだけども、ポピュラーな代表曲一曲くらい欲しい。
ジャンルは全く違えど「21世紀の精神分裂病」のキング・クリムゾンや、ピンクフロイドの方が突き抜けていて上。
あくまで「ド」シロウトの個人的な感想です。悪意はありません。
こんばんは。ガースです。
ボブ・ディランとのツアーがそれほどブーイングの嵐だったとは驚き!いやはや、そのディランのバックバンドとして有名になったとしか知らない程度の中途半端なロックファンのkossyです。ラストワルツは見たことあった・・・という程度。まぁ「アイ・シャル・ビー・リリースト」は名曲だと思ってます。
チャック・ベリーの映像まで出してくるとは、かなりロックの歴史そのものまで描いてましたね。そしてロバートソンの複雑な幼少期やカナダでの活躍など、自伝ならではの詳細な内容にお腹一杯。ジョージ・ハリソンの映像が嬉しかった。
監督は珍しくマーティン・スコセッシではないんですね。ロビー・ロバートソン、ブルース・スプリングスティーンの次に露出していたのに。とにかく、『ラスト・ワルツ』をまた見たくなってきました。
The Bandの曲、歌、サウンドは永遠に不滅!
洋楽を聴き始めた頃にLast Waltzの解散コンサート。その頃はBob Dylanのバックバンドぐらいの認識だったが、数年後に南十字星やMusic from Big Pinkを聴いて、その素晴らしさに感嘆し、すっかりファンになった。そのうちにR.マニュエルの訃報に接し…
この映画の原題にあるとおり、あくまでR.ロバートソンの伝記であり、彼から見たThe Bandの姿をさらしたものなので、批判があるのは当然。R.ダンコ、L.ヘルムも亡くなり、G.ハドソンの発言がない中で、一体どうなの?という気も正直ある。
しかしながら、R.ホーキンスのバックバンドでL.ヘルムと知り合ってからのバンドの歴史を、様々なエピソードや貴重な映像で解きほぐしてくれるこのような作品が観られたことに、本当に感謝したい。
Big Pinkでの共同生活で曲を生み出していく奇跡のような日々、その後のR.ロバートソン以外のメンバーのドラッグ、交通事故などにより、バンドが崩壊し、最後の輝きの舞台としてLast Waltzがあったことなど、これまで語られてきたことではあるが、映像作品として観て実感し、深く感動した。
R.ロバートソンとL.ヘルムは亡くなるまで仲違いしたままだったようだが、この映画の最初と最後にL.ヘルムのリードヴォーカル曲を持ってきたあたりは、作り手のL.ヘルムに対する敬意を感じた。できればR.マニュエルのことをもう少し触れてほしかったかな…
映画の中の発言にあったが、「Beatlesに匹敵するアメリカのバンドはThe Bandだけ」ということをしみじみ感じる。この映画を契機に、より多くの人達にThe Bandを聴いてもらいたい。The Bandの曲、歌、サウンドは永遠に不滅です!
バンド=スタインベック
『かっては兄弟だった。でも、もう兄弟ではない。お互いに付き合いをなくしてしまった。戦争の後で。』
とロビーロバートソンは歌っている。https://www.youtube.com/watch?v=VT407NtOWac
実は、この曲を聞いて、涙が出た。十六年以上も続いたThe Band が事故、麻薬中毒、著作権の争いなどにより、こんな形で、兄弟が死んでしまったのは残念だ。でも、兄弟という言葉を使うなら、もっと助け合うことができなかったのか? いろいろな形の兄弟がいるけど?
でも、この作品は、生きているロビーが作ったもので、ガースのコメントも一言しか入っていなかったと思う。(忘れた)まだガースは生きてるよ。あとの、バンドメンバーは死んでしまっているから、死人に口無しでなんとでも言えるだろう。と言うより、ロビーも生きていく上に、何かを見つけ出したいと思うと思う。ましてや、BLMの動きで、カナダの6Nations (ネイティブ カナダの居住地)の血統をもつロビーにとって、何か話せることもあるだろう。それに、彼は話上手で論理的に聞き手に理解させるように説明できる才能もある。麻薬も少し使っていたようだが(?)、リチャードやレボンたちほと、中毒にならなかったんだろう。
なんて、批判的に考えるのは、私の思考過程で、、、
ところで、このロビーのThe Band のドキュメンタリーがいままでに、観た数々のアーティストのドキュメンタリーの中で一番気に入った。その理由は、単に私はThe Band が大好きだったから。でも、この映画に答えが出ている。ジミーと言う人が(Jimmy V.)がインタビューで、『一つ一つの曲が、ちょっとスタインベック( John Steinbeck)の小説のようだと。そして、DustBowl アメリカのアメリカのイメージのを私に与える』と。このダストボールという言葉は、砂吹雪、砂埃でせっかく作った作物をダメにされ、それでも、また来年も作付けするというアメリカの泥臭いイメージだと思う。納得。私の好きな米国作家はスタインベック、それに、米国(カナダ)音楽はThe Band,オールマンブラザーズバンドだ。
1968年の『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』というでデビューLPを持っていて、「ザ・ウェイト」が好きだった。
The Band Music From Big Pink [Full Album] コピペで聞いて。
そして、私は個人的に1970年の3作目の『ステージ・フライト』まで聞いていた。このバンドは南部の音やブルースやバッハ調で、他のバンドと違った音を出している。レボン(ドラマー)の 歌声が好きで、1960年ごろでドラマーがリードボーカルだと言うのも珍しかったように思う。ロビーは作曲家のイメージが強く、バンド個人個人のことより、歌と曲が好きだった。レボン(ドラマー)の自分の音楽に対する信念は価値がある。マスコミや流行にとらわれない自分の音楽を持ってるから好きだ。個人的に彼の南部のアクセントはちょっと気になるが)娘曰く、わざと南部のアクセントを残していると。自分に誇りをもっている人だからだと思う。
ロビーは映画でも言われているが、ビジョンのある人で、先が見られ、いつもなにか新しいことを求め、行動に移している人。カナダの若手監督を育てるため、このダニエル・ロアー監督を選んだのも彼。それに、マーティン・スコセッシ監督の映画、『レイジング ブル』『アイリッシュ マン』も彼が曲作りをしている。自分が何かできるかを探っているから、人との付き合いを大事にしている。この映画はトロント映画祭(TIFF ティフ)のオープニングの映画に選ばれている。その舞台には6Nations (カナダの インデアンの居住地ーアメリカにもいる)に対する感謝のコメントを忘れないし、自分の息子の作品の宣伝もする。如才の無い人。
https://www.youtube.com/watch?v=ph1GU1qQ1zQ
これに日本の人も出ている。この世界は一つのアイデアが好き。
個人的にはレボン(ドラマー)タイプが好き、音楽バカで、自分の音楽を追求して、ガサツで、馬鹿笑いをするし、、、時々、呆れられるような人が。
ロビーに対して、反論しているわけではないが、(実際のところ私は何が事実か知らない)この映画の監督、プロヂューサーに感謝しているし、ロビーの話術も尊敬している。こんな素晴らしいThe Band のドキュメンタリーが見られたわけだから。
"THE BAND: The Authorized Video Biography" - (1995)
これにはロビーがほとんど出ていない。レボン中心のインタビューが中心だ。
https://www.youtube.com/watch?v=3V2OqxgeD9Y
これはトレーラーだが、レボン映画もある。
Ain't in it for My Health Official Trailer #1 (2013) - Levon Helm Movie HD
この映画を観てから何度も何度もバンドを聞き返した。
https://www.youtube.com/watch?v=iyVSy9DYq9Y
https://www.youtube.com/watch?v=5dReaQWER2k 歌詞がいい!ボブディランとリック ダンゴ作曲
そのすべてが宝物だった
これはロビー・ロバートソンの自伝をもとに作られたザ・バンドのドキュメンタリー。ロビーが生まれてからザ・バンドが解散するまでのロビーのアンソロジーと言ったほうが良いかも。
少年期、ロニー・ホーキンスとのホークス時代、ディランとのツアー、ビッグピンクでの生活、ザ・バンドの始動からラストワルツまで。信者の自分にとってはそのすべてが宝物だった。
彼らをリスペクトするマーティン・スコセッシ、ロン・ハワードなどの巨匠たちが製作総指揮に名をつらねた。この作品に関わりたかったんだろうねぇ。
エリック・クラプトンやブルース・スプリングスティーンの激アツなコメントに落涙。彼らの音楽人生に大きな影響を与えた巨大な存在だった。
ちなみに自分が3曲選ぶとしたら迷わず
・The Weight
・The Night They Drove Old Dixie Down
・Don’t Do It
The Band:
Robbie Robertson
Levon Helm
Rick Danko
Richard Manuel
Garth Hudson
彼からの目線
これ、リヴォン・ヘルムが生きていたら、本作を観たら、ロビーの自伝を読んでいたら、どうなっていただろう、温厚そうなガース・ハドソンは健在、他メンバーは今は亡き、そんな状況だからこそ、この映画を作る事が出来たのであろう。
ロビー・ロバートソンが独走状態でのバンド内部の亀裂は「ラスト・ワルツ」でも描かれ「ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち」で、少しだけ彼らのドキュメント映画を観た気分にもなれたり、ロビーの元奥さん登場が偉そうにも、策士でもある印象のロビー・ロバートソンの正しさ、マジメさ、ワンマンにも思える行動など、複雑になる思いも、正直に観れない自分。
ガース・ハドソンのインタビューをカットしたことに監督の意図が分からず、ロビーの独壇場、何か悪意を感じてしまうが、ザ・バンドの素晴らしさは十分に描かれている、からこそ、正当に五人を描いたモノを観たい欲求に駆られる。
かってThe Bandの音楽があった
かつての兄弟は今の兄弟にあらず
邦題の通り、「かつて」兄弟だった頃は観ていてもとても仲が良くて愛に満ち溢れていて素晴らしかった。
まあ、バンドというものはずっと仲良くやっていくのはとても難しいのだろうけれど、案の定、当時の世相と相まってヘロイン問題がつきまとう。
薬物の怖さを思い知るための映画じゃないんだろうけど恐ろしく感じた。
そしてよくあるお金の配分の問題も。
全てロビーの目線で語られているので、本当のことはどうなのか、当時のことを全く知らない世代の私にはわからない。
しかし、かつての兄弟は今の兄弟にあらず、ということだ。
違う目線で語れば違う物語になるのではないかなとは予想はつく。
ロビーの奥さんは若い時はキュートでマダムになってからもとても上品。ビッグ.・ピンクでの暮らしも、マリブでの暮らしも楽しそうで、子どもの表情が豊かで可愛くて和んだ。
音楽的にはとてもシンプルでストレートでぬるい感じ。このぬるい感じは家族愛や兄弟愛の温もりから生まれた曲だなと感じる。
反抗、反逆、孤独からの音楽ではない。
このストレートさが、ザ・バンドたる所以なのかな。
バンドにザ・バンドという名前をつけるとは。
そのまんまな感じが、ボブ・ディラン様が仰ったのだから仕方ない(笑)
彼らこそまさにザ・バンドだ。
ロビー・ロバートソンのギターは最高!ということは強く言いたい!が、...
邦題、よくないよ。
原題が、
「Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band」
であることに早く気づくべきだった。
「Robbie Robertson and the Band」であって、
「 the Band」ではないのです。
邦題、大事なとこ削っちゃって!
ということで、この作品は
ロビー・ロバートソンによる
ロビー・ロバートソンのための
かつて偉大なバンド在籍時の
思い出話ムービーです。
バンドメンバーそれぞれの背景、心情から
なぜ、解散に至ったのか?だと期待してたのに。
ドキュメンタリーとも言えませんな、残念ながら。
なるほど。
作品のベースはロビー・ロバートソンの本なのか。
広告宣伝用ムービーという名前も授けましょう。
めちゃくちゃガッカリしました。
ホントに。
ロバートソン・.ホークス・ディランの繋がり&綾を見られる!
「Testimony/ザ・バンドよりの青春」のドキュメンタリー映画、というよりも、ロビー・ロバートソンの青春を、お宝映像で見られる!映画といってよいでしょう。
前半の早熟なロバートソンが、ホークスに加わる時代の、ロカビリー全盛期の映像は、見所のひとつ。
同時代に聞いていた、ディランのヨーロッパツアーでの、ブーイングのステージも、生々しく太々しいのも、必見。(あの時代に、確かに、これならば、確実にブーイングだ!)
と、見ているうちにやってくる「ラスト・ワルツ」のステージ映像からは、なんと!悲しいステージだったんだと、教えられます。
全編、生々しいストーリーを見ることができる、最高の記録映画です。
ロバートソンが撮りためた(保管していた)映像があったからこそ、できあがった逸品!(感謝)。
全23件中、1~20件目を表示