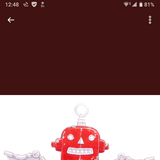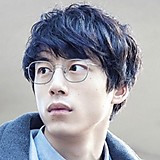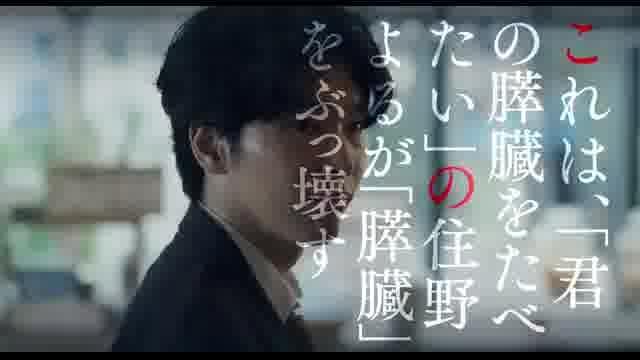青くて痛くて脆いのレビュー・感想・評価
全286件中、101~120件目を表示
期待以上でした......ガッカリ度が。
途中何度か眠くなりました、、、
ストーリーもどんでん返し的な宣伝だけど全く。そのままだし、杉咲花ちゃんはいつも同じ芝居だし、
後輩の子が芝居めっちゃ棒!!!!そっちにしか意識いかなかった。下手くそすぎて(これが何かのミスリードか?!)とか勘ぐったのは恥ずかしい、、
てか個人情報ばら撒いてるのは普通に犯罪だし、逆に謝るってなに?
意味わかんなすぎて見なかった事にしたい、、
久しぶりの映画だったのにめちゃくちゃガッカリした、、
俺は好き。
こころが痛くなりせつない
自分自身の学生時代の気持ちや、社会人になり30代になった現在の心をぐさぐさえぐられるようだった。
心の壁を超えて行動した時、何かが変わるんだよね。きちんと思いを伝えていれば、あの時こうしていれば…それが楓にはできなかった。そして勝手に自分は外されたと思いこみ、恋愛が複雑に絡み合う。
秋吉は天然で意外なほどさっぱりな性格。それの伏線はオープニングで貼られていた。
2人の非対称な性格が歪みだした。見ていて悲しくなってきた。見てて心がぎゅっとなった。
2人で言い合うシーンは見てられないわ。
小説も買って読んでみよう。
吉沢亮と杉咲花の絡み合う視線が青くてイイ
めんどくさい。
気持ち悪い男
すごく主人公の行動、心情がわかってしまう
これはとても恥ずかしいことだけど吉沢亮さん演じる田端の心情が重なる部分が
多々あって、これほど心情がわかる主人公は初めてだった。
ここまで人のせいにして自分を守り人を妬んでしまうものなのかと呆れてしまう人も
いるかもしれないけど、ボクは同じような心情に落ちいり、ふさぎ込んでしまうし
裏切られたと錯覚してしまうし
ありもしない人にとってはきもちわるいであろう理想を空想することもある。
だから後半の柄本佑さん演じる脇坂の言葉はとても痛くやさしくしみました。
多くの人にとっては気持ち悪いどうでもいい映画かもしれないけど
ボクは見て自分をありありと理解できて出会えてよかった映画になりました。
タイトル通りでした。
衝撃作であり、自分の心に寄り添う映画でもある
衝撃作だった。原作者が住野よるだし、予告見るとキミスイみたいな大切な人亡くす話系なのかなと思ってたけど…良い意味でどんどん私たちの思い描いていた予想を裏切ったり超えてったり、人によっては拍子抜けした人もいるんじゃやいかって感じで…一筋縄じゃいかない展開がどんどん出てくる話だった…。
どうしても映画の予告や本編を見ると、これまでに観てきたあの映画ぽいなだとか、あの監督ぽいなとか、あの作品のオマージュ的な要素入れてるなだとか過去の作品と重ねて同じような箇所を照らし合わせて見てしまいがちだけど、これは照らし合わそうにも、雰囲気は重ねられても展開や各人の人物像がどんどんズレたり予想外の動きを見せたりで、こうなったらこの流れになり作品として収まってくんだろうなという一種の安心感から逸脱してく、終始そわそわする気持ち悪い気持ち良さがありました。そこが私にとってのこの映画の魅力のひとつであり、見れば見るほどどっぷりハマっていったポイントとなりました。
予告もそうだし、公式サイトや各映画雑誌やアプリに記載されてるストーリーの書き方がまず巧妙で…(私の想像力の乏しさもあるけど)そこから想像して勝手にこれまでの映画や漫画、ドラマで見てきたストーリーの寄せ集めで自分の脳内で作り上げたものが当てにならない世界だった。主人公を軸にして、「仲良くしていた女の子」「一緒にサークルを立ち上げる」「彼女がこの世界から消えてしまう」「立ち上げたサークルは多くの学生・社会人の手により悪い方向へ変えられる」「そのサークルを壊す事が正義」というキーワードがあり話が進んでいく中で、何が良くて何が悪者なのか、勝手に自分の脳で作ってしまう固定概念というものがこの作品を面白くしていた。結局見てる私達は、主人公の思いや考え方も、その周囲の人間たちの気持ちも、分かった風で都合の良い展開を考えてしまっていたんだなぁと。(ここはMIU404最終回の菅田のラストシーンの一言を思い出した)
下手にこの作品がどういう映画か言うと変にネタバレになるからあれですが、とにかく主人公の思いや気持ち、人物像が物語の核となっていて…根暗や陰湿と受ける人もいるんだろうけど私は共感ばかりだった。自分も人も傷付けたくないから不用意に人に近付きたくない、そんな人間がいざ心から信用できる人や人間性を好きと思える人に出逢ってしまった時はとても素敵な事だし毎日が潤うんだけど…そんな幸せな日々は相手や自分きっかけで脆く崩れ去ってしまう時があるから…。自分の理想と少しずつズレていく事の恐怖とか…。この作品はその辺(だけではないが)が丁寧に淡々と、かといってエンタメ性も忘れずに、でも新しい空気感で描いてて脱帽でした。
吉沢亮、リバーズ・エッジもそうだけど、彼がこの役を演じてくれて本当に良かったと思えた。こういう役がハマり過ぎて他のキャスティングが考えられないハマり役だった。
杉咲花、岡山天音、清水尋也、森七菜など…絶妙なキャスティング兼私得過ぎる俳優陣も大満足でした。
ネタバレにはならないけど、私の崇拝している楳図かずおの「14歳」を思い出したな、見終わってみて。全然違うんだけど、この作品は社会や人間関係の構造や青年期の葛藤や黒い歴史だとかそれだけを描いてるんじゃなくて…人1人の心情を巧みに描いてる作品なんだと思いました。
始まりから終わりまで目が離せなかった、凄く好きな映画です。
いつの時代も「青くて痛くて脆い」
原作は未読です。
映画館内はほとんど10代、20代の方ばかりです。私のような年代はタイトルを見て恥ずかしくて入れなかったのでしょう。
私が大学生だったのは1970年代です。私の大学にも「モアイ」と同じように「世界は変えられる」と叫んでいたサークルがありました。「カクマル」とか「ニッキョウ・ミンセイ」とかいう名前でした。他の大学にも「チュウカク」とか「ニホンセキグン」などの同じようなサークルがいっぱいありました。
時代背景が異なるので、目的や行動は異なりますが、「モアイ」も「カクマル」も「ニッキョウ・ミンセイ」も、みんな「青くて痛くて脆い」サークルです。理念だけ立派で、やっていることは妄想・自己満足・ナンパ・対立・分裂・離散、全く変わりません。
目的どおり「世界を変えた」とはとても思えないでしょう。
私の出身大学には「カクマル」や「ニッキョウ・ミンセイ」と同時の1970年代に「マイコン研究会」というサークルもありました。ここからは現在のIT時代を構築する一翼を担った人材を輩出しています。「世界は変えられる」と思って活動していたかはわかりませんが、結局、世界を変えてしまいました。
「青くて痛くて脆い」若者が世界を変えることだってあるのです。
作者は「青くて痛くて脆い」でもかまわないから「何かしよう」と言いたくて、この作品を作ったのだと解釈しております。
浮きまくる杉咲花さんの演技が素晴らしい。あんな女子学生、1970年代にもいましたね。最近のことですが、私の勤務先の採用面接でもいました。
是非、60代、70代の人に見てもらいたい映画です。
ただし、終わり方は甘い! 最後の2分は不要です。若者向けに迎合してはいけません。これが減点で星4つです。
原作はどうなっているのか、こんど確認してみます。
多分、評価の分かれる作品だと思います。高く評価する人は何でも良いから「青くて痛くて脆い」経験のある方、低く評価する人はそのような経験のない方だと思います。
思いもしなかったマイノリティーの青春映画
題名通り若さ故の青さが痛々しい
杉咲花さんは本当に可愛いらしかった。
この世から居なくなる前は。
この役を上手く演じてました。
最初の脇目もふらず理想に近づこうと走っていた時の
舞台で発声しているような高く良く通る声と
ラストシーンでのあのやり取りのシーンでは声の出し方が違ってました。
秋好さんは世界平和という理念は変わっていなくても、
モアイにどんどんメンバーが増えて、
共同で運営していくにあたり、
少しずつスレていってしまったんですかね。
対して楓くんは、いつまでも少年のようで青いまま。
こうゆう話、現実にも良くあって、
傍らで見ているだけで、痛いなあと。
何かを作ろうと志を一緒にする仲間達で、
仲間割れとか喧嘩とか。
心のすれ違いで。
ラストの二人の真正面からのぶつかり合いは、
見ていて疲れる程、生々しかった。
いやあ、あの演技をするのも相当にエネルギーを使うんだろうなと思います。
痛みも喜びも分けあえるものだから
理想論なんか語っちゃって「さぶッ」と、
冷ややに薄ら笑いを浮かべる自分がいる。
でも語るべき理想すらない自分に気付き
薄ら笑いが凍りつく。
敬語で喋るのは相手を傷つけないため...
なんかじゃない。
自分のこころを覗かれたくないから。
本当は自分が傷つきたくないから。
自分ひとりが銃を投げ捨てても
戦争は終わらない。
むしろ丸腰になったところに銃弾が飛んできて
結局のところ傷つくのは自分自身だ。
わたしたちは本物の銃は持ってないけど
わたしたちは言葉の銃を持っている。
興味本位で、たぶん興味すらもない
およそ関わりもない安全圏で
傍観を決め込むヒトたちによって
無慈悲な言葉は投げつけられる...
SNSが普及するにしたがい
それが顕著になってしまった。悲しいことに...
言葉が怖くなって、言葉に絶望し
言葉を手放したとしても
今の自分はこれまでの言葉が積み重なって
今の自分が出来ているはずだ。
だとしたら、
再び手にする言葉が、希望を託す言葉が
未来を決定づけるはずだ。
そうやって摩擦から発した温みある言葉を胸に
わたしたちは少なからず傷つきながら前進するのだ。
顔を見合わせない、直に体温を感じないSNSでは
言葉の真意を測るためにリテラシーを酷使して
辟易するかもしれないけれど
面と向かって言いにくい本音だったり
日頃は照れ臭さいことだったりと
言葉にできない言葉を発信するには
もってこいなツールだと思うので
“要領・用法”をまもり配慮をもって
正しくお使いください。
同じネット民、同じ映画ファンである
わたしの願いです。
杉咲花さんとか松本穂香さんとかが演じる
明け透けのない性格のヒトって
一見なんにも悩みがないように見えて
実はいちばん傷付いきやすい性分なんですよね。
本心をさらけだすことをせず
傷付きも傷付けることも避けて
慎ましく平坦な生き方を望んでもいいのだけど
彼女たちはそうとはせず
たとえ傷付き、傷付けようとも
喜びも悲しみも等しく受け入れて
起伏のある生き方を選んでしまった。
誰かに何かを言われても
そうして手にしたものが
なにものにも代えがたい財産だと
彼女たちは知っているから...
「こころが痛い」→〈主観〉と
「言動、行動がイタい」→〈客観〉の違いはあるけれど
これからの社会で大事なことは多様性を認める寛容さと
お互いの適切な距離感を推し測り
寄り添う姿勢なのだと思いました。
言葉を届けるために。言葉を受けとるために...
ネットでも。現実でも。
異常者
内容は説教くさくて嫌いだけど、作品の作りとしては良かったので☆4内容をちゃんと受け止められるなら☆5とかだろうか。
反面教師とか警鐘とか教訓として受け止められるならこの作品の意義は大いにある。
現代っぽい話ではあり、タイムリーというか時代を反映してた。「異常者」とのタイトルにしてみたけど、彼のような人間が今後増えていくのだろうと思う。
現代病と言ってもいい。
だが、その処方箋はおそらくない。
俺も含め、この病に冒されてはいないとは断言できない。彼程症状が顕著に現われてこないだけなのかもしれない。彼自身、自分が異常者などと露程も思ってないだろう。締め括りに使われる「ちゃんと傷つけ」って言葉さえ、身勝手な思考だとも考えないだろう。
それがキッカケにはなり得るのだろうけど。
彼は常に受け身が多かったように思う。
その意見を受け入れた自分を無視するかのようだ。
他人に委ねたり依存するのは責任回避ではない。自分の意思を他人に委ねたという責任が発生する。
「自分は間違ってない」と思いたいが故の防衛本能だろうか…終盤のマウントし具合は不様だった。
その行為自体は昔からあるものではあるけれど、その内容だったり、単語が辛辣だ。
自分を優位に見せる為の選択は、理論的は会話ではなく、相手をいかに傷つけられるかに終始する。
相手の間違いを諭すでもなく、誤解を解こうとするわけでもない。直向きに刺し続ける。
…そこまでして守りたいものって何だろう?
そして、その行為を背負いきれず後悔する。
他人を否定し自分の足場が固まって、今度は許してほしいと相手に懇願する。
それがラストの台詞なのだ。
「お前いい加減にしろ」と胸糞悪くなる。
吉沢氏を観たくて行ったのだけれど、そんな胸糞悪くなる主人公に徹し、好演してた。
杉咲さんもそうだけど、なんか日本人の芝居が次世代に差し掛かってきてるのかとも思う。
なんか…形がなくなってきたかのように思う。
今の若者にこそ見てもらいたい作品にも思うので、同世代にしっかりとアピールできる人材がいた事に感謝したい。
初めは復讐劇かと思って見てたのだけど、どおにもそおではなくて…だけど彼自身は明確な敵意を剥き出しにしてる。中盤に差し掛かかり、その敵意に見合うだけの原因がないと感じてからは、一体何を見せられてるのだろうと、暫く居心地が悪い。
途中どちらかが嘘をついてはいてサスペンス風にもなるのだがあんま盛り上がらない。
物語の核はそこではなく、彼の内情だからだ。
厄介なのは、その敵意が燻って熟成し、こねくり回された挙句に発露するとこだ。そして、彼に不利な事が起こらない限り発動しないとこだ。一体、お前ら何をその身に住まわせてんだと、怒鳴りちらしたくなる。
でも、多分ならこおいう人間は増え続ける。その土壌がこの国にはあると思ってる。
個を大切にするのは結構な事だけど、優先順位と度合いは誰かが説かないとと思う。
家庭の在り方とか、教育の在り方とか…人格形成の過程における不自由さは結構大事なんではなかろうか…行き過ぎた自己肯定論の弊害にも感じる。
1番怖いのは
「彼は別に悪くないじゃん、しょうがなくない?」と言っちゃう人間が相当数いるんじゃないかと思えちゃう事だ。
サイコ野郎が主人公のホラー映画に等しいと思われる。現代が反映されてるようにも思うので尚更恐ろしい。
良い意味で裏切られた
タイトルから恋愛が中心のモノかと
思ったら、恋愛要素は薄めでした。
終盤の教室での二人の掛け合いは
ちょっと必見です。
自分が言い争いをしているような気分に
なりました。
杉咲花は上手いですね。
何か引き込まれます。
最後は結ばれるのかな?
でもほぼ触れられず。
久しぶりにズドーンときた
ヒロインうざすぎwwwざまあwww
とにかくヒロインが痛くてうざくてキモい。自分は本当に理想論ばかり語るヒロインが生理的に気持ち悪かった。ストーリー内容も、「何故かクソうざいヒロインが死んで、元々主人公とヒロインが作ったサークルが乗っ取られて飲みサーになったから潰す」っていう、本当にどうでもよすぎる内容でクソつまらないし、ヒロインが出るたびに吐き気がして、最初の1時間は本当に苦痛で何度も途中で帰ろうと思いました。
ただ後半に、ヒロインが死んだというのが主人公の嘘で、ストーリー内容が、「ヒロインに彼氏ができ、ヒロインに裏切られた(と思い込んでる)卑屈で陰キャラな主人公が、ヒロインを逆恨みして、ヒロインが楽しそうに運営してる陽キャラサークルを潰す」という内容だと判明し、見事サークルの闇を暴いてサークルをぶっ潰しざまあみろと言わんばかりにヒロインに暴言をぶつけた時は、ヒロインと陽キャラが嫌いな私は、最高のカタルシスを得られましたね。
主人公だけが陰キャラで嫌なやつ、他の登場人物は陽キャラで良いやつ。その中で嫉妬心と被害妄想の力で孤軍奮闘し勝利した主人公は最高に気持ち悪くてかっこよかった。
あと吉沢亮まじイケメン好き。ヒロインの人誰だか知らないけど吉沢亮と釣り合ってないからwお前の方が気持ち悪いわwww
全286件中、101~120件目を表示