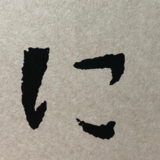ルース・エドガーのレビュー・感想・評価
全57件中、1~20件目を表示
不穏で、いい意味で人を不安にさせる
学校で一番の優等生は、実は恐るべき存在ではないか? そんな疑念が雪だるま式に膨れ上がるミステリーだが、ミステリーを解き明かすことが重要な作品ではない。むしろ疑念は大きなるばかりで、すべては見た目とは違うという普遍的な真実と、それによって右往左往する大人たちの姿があぶり出されていく。タイトルロールの優等生ルース・エドガーについても、一体どんな人物なのかを明確に提示してくれたりはしない。少なくとも、劇中の親たちが思うような子供でもないし、先生が抱いた疑いも的中していたとはいい難い。ただ、押し付けられたイメージに抗う子供の底知れない複雑さに、観客として狼狽えるしかないのである。もちろんこの映画の背景には人種や差別の問題が横たわっているが、われわれが、普段いかに物を本質を見ることなく、都合のいいものを拾い集めて生きているかを突きつけられて、いい意味で不安になる映画だと思う。不安になれてよかった。
バランスとアンバランスの均衡
アメリカという国は、一部の優秀な人間がその他の愚民を率いる教育方針だ。有能な者はどんどん引き上げ、ついてこれない者は次々切り捨てられる。
アメリカという国は、個人レベルから、自分の利益のためならばそれ以外がどうなってもいいと考える。自分が、自分たちが全てを得ようとする。
アメリカという国は、人種のるつぼだ。差別も根強い。差別への反発として抵抗意識も強い。
アメリカが抱える問題点や、アメリカ人らしい思考を巧妙に組み込んで、笑えるくらいにおぞましく恐ろしい脚本は関心するしかない。
ある意味で、アメリカという国を表現したらこうなりましたのような作品だ。
メチャクチャ面白いというわけではないので絶賛はできないけれど、当事者のアメリカ人ではないからこそ関心を持って観られる作品だったのではないかと思う。
アメリカ人にとっては普通の日常で、何が面白いのかわからないだろうから。
つまり、この作品に潜む不気味さがアメリカ人にとっては不気味に感じないということだ。
チラッと映る、アフリカ系だけのチアの面々が「私たちは出来る」と掛け声をかけながら練習に励むシーンなどは、更に凝縮された「濃縮アメリカ」のようで、面白くもあり気味悪くもある。
物語のバランスに対して、アフリカ系だけのチアというのは実にアンバランスだ。このバランスとアンバランスで均衡が取れているところが気味悪さの理由だろう。
なんともチグハグなのである。
日本映画と欧米映画の根本的なちがい・・
それでも子どもをしばるもの
元の名前をどうしても母親が発音できず
名付けた新しい名前はルース。
光という意味だ。
ここに象徴される親子の関係性。
名前を変えさせられ、デニスという魚を投げつけた子どもから、セラピーを経て品行方正の学校が誇るルースへ。
頭が良いからこそ求められる子どもになろうと
もがき続けてきた少年。
母は小児科医、父も地位の高い士業という
意識の高い育ての両親だ。
そこに生まれた歪み。そのあらわれを指摘した
女教師ハリエットに復讐しようとするのは、息ができないほどがんじがらめになっている状況への怨みでもあるはず。自分に期待する母と、ハリエットという女教師、
どちらも型を押し付けることに変わり無いからだ。
ボヤ騒ぎの後、家で、クリスマスプレゼントの隠し場所のを知っていつも驚いたふりをしてきた遠く告白するシーン。 ハグしながら、あなたには未来がある、何にだってなれる、絶対に。という母親の言葉はまたルースを縛るものに聞こえる。
自分をかたにはめ、しばるものは誰なのか。
自分か周りか。それは何なのか。
自己満足なのか愛なのか。
「自分ありのままでいればいい」と言う母の言葉が
空虚でもあり重くもある。
親と養子縁組が多いアメリカでなくても、
親として身につまされるものだと思った。
ピンとこない
オクタビア・スペンサーがいつもの明るく楽しい黒人おばちゃんじゃないのは新鮮だったけど、ウィルソン先生のルースへの疑惑の真意が読み取れなかった。精神疾患の姉妹を持つ自分と未来明るい秀才のルースを比べて嫉妬した?ルースの両親たちも不自然。花火の件最初は隠しておいて、一番ダメなタイミングでヒステリックに叫びながら詰問、しかも相手の言葉を遮ったりして。毒親そのものだけど、そういう意図はなさそうだから映画の雑音にしかならない。あとステファニーが結局なんの役割をしてたのかホントに分からなかった。私の頭が悪いんだろうか?とも思わないでもないけど、全編に流れる思わせぶりな空気感が腹立ったので、この映画の作りが悪いということで矛を収めます。
解釈が難しかったけれど
結論のハッキリしてない物語はだいたい自力では理解できないけれど、今回はうっすら理解したような気がしました。アメリカという国で生きるには箱に入らないといけない。ルースは女性教師はもちろん養父母からも優等生のとされる重荷に抵抗して、女性教師への行動となるわけですが。最後に女性教師から言われる、この国で生きるためには箱に入るしかない、光はわずかしか届かないなどの言葉を聞きます。そして、ルースは自分が改めて恵まれていること、今与えられている恵まれた箱に収まるのが得策だと思ったのでしょう。レールを逸れていわゆる黒人の道に都落ちしますか??それはしたくない!だったら養父母の信頼を取り戻し、もとの道に。ちょっとしんどいけど、それっきゃないんだなって感じのラストに思えました。
小さな事が大きな事になる不安
これだけわかってればいい。
「アフリカの黒人が養子としてアメリカ人の夫婦と住み、学校でも家でも模範となるような生活を送っているのだが、ロッカーに怪しい花火を保管していたことから周りが疑問を持ち始める。」 以上
あとは駆け引き・心理戦とでも言えばいいのかな。親・教師等と少しずつズレを感じ、今までと同じコミュニケーションができなくなる流れ。
自分だったら溜め込んでないで普通に聞いちゃうけどなぁ。「違法な花火持ってるって聞いたんだけど、お前のものなのか?」てね。本当だとしてもドラッグや銃ほど重みを感じないので軽く聞けると思うんだけどな。。。
優秀だから将来いい人生を送れる可能性が高い、台無しにしてはいけない…と周りが慎重すぎるよ。社会に出たら色々と揉まれるから成績優秀=成功するわけではないので。
話題が小さい。
しかし、人生を充実させたい人・既に充実してる人にとっては、些細なことでも周りに与える影響で、もし大きな出来事に発展したら...と不安が生まれるだろう。私の場合、特に仕事してる時なんか些細なことでも気になったりするから「どれだけ影響を及ぼす展開になるのかな」そう思って観てました。
映画ではマイナスに進む流れですが、プラスになることも世の中は多いと信じたい。出会う人との相性、置かれている立場...個人的には主人公より、全裸になり仕事に影響を及ぼす黒人親子の方がわかりやすかった。もちろん他にも話題はありますが、全体的に静かに進む展開なので退屈だったというのが本音。シリアスな話だしナレーションあった方がわかりやすかったかな。
最後は何だかストレス発散に走ってるだけに思え、問題解決には見えなかったけど「それが人生」てことなんですかね。
成功してる人は闇を抱えてるもの。そういうことなのかな…
サイコサスペンス系?
とても重く、深い、観る価値ある作品!
アフリカからアメリカ人白人夫婦の養子になったルース。学校では勉強もスポーツもでき、人気もの。先生の信頼も厚く、誰の目から見ても優等生で親にとっても自慢の息子。
ただ、教師のウィルソンはある課題の内容からルースの内に秘めた危険性を感じ取る。
ウィルソンが課題の文章からそう思うことも少し疑問だし、ロッカーの中を勝手に見たり、他の生徒を皆の前で見下すような発言をしたりと教師としてどうなんだろう。
ルースも褒められるのは嬉しいだろうが、悪いことをした友達を引き合いにだされたり、みんなの前でそれを言われても確かに嫌だろう。贔屓されることなく、下げずまれるのも辛いが、贔屓されるのはされる側の辛い思いもあるだろう。期待に応えなければならないというプレッシャーもあるだろうし。
色々と事件は起きるが、それの真相ははっきりと明かされない。でもおそらくルースが関わっているのだろうと思う。「俺はいい子なんかじゃない」と訴えたかったんだろうな。
人の心の中や考えてることまではなかなかわからないもの。周りの評価、自分の感覚だけで人を決めつけてはいけない、と思い知らされた。
疑惑の青年なのか?
僕にはルースが徹頭徹尾、序盤から終盤まで有能な学生にしか思えない。ある事件によって被害者と加害者に別れた双方の友人を(本来なら双方を救うのが不可能な状況で)救おうと、奮闘する青年にしか思えない。確かに、彼はいくつもの策略を用いたが、あくまでそれは友人を救うためであり、事件自体を表面化させ双方の友人を必要以上の窮地に陥れたのは、かの教師である。ルースが友人を救うために彼女に代償を払わせたのはむしろ当然であり、そこに邪悪さはない。
あえてルースの失点を挙げるなら、若気の至りゆえか、無能で視野の狭い教師をオチョクリすぎ、差別のそもそもの元凶、型に嵌めようと単純に物事を固定する社会の愚かさを、すべてその愚かな教師に(本来なら彼女は彼女で正当性があると底では気づきながらも)委託させすぎたのかと感じた。
自由と可能性という名の不自由と閉塞感。
深すぎて言葉にできず...
ルース、討論のように正々堂々とたたかって!
こんな強烈で、人を引き付けるのストーリーの映画を観たことがない。聴衆者がまぎれもなくこのストーリーに引き込まれていき、参加できる映画で、主に学校と家庭だけの会話で視聴者に質問、問題点を投げかける。
BLMのデモの動きの中、白人が作ったシステムをかえ、他民族にも合わせたシステムを作ろ
うとする運動が活発化している米国の現実に、ちょうどマッチする作品になっている。
エリトリアの戦争地域で少年時代を過ごし、米国バージニアのアーリントンのキャリアのある裕福な白人家庭にもらわれたルーズ。(ケビンKelvin Harrison Jr.)治療したが、まだPTSD symptomsが癒えないルースなのかも。統合失調症的な要素をもつ性格、二重人格、人を笑顔で操れる高校生。美しい笑いの中に何か秘めている事実がある。その笑いが時々、無理に作っている笑いのように見える。
ルースの正直さが見えないから両親は何が本当か探そうとするが、母親のエゴを通して過保護的にもなる。母親を学校まで送らせて、多分彼がウイルソン先生の教室に仕掛けた花火の惨事をみせるなどという企みを図る。奔走したり、疑ったりする母親を見ているのも辛い。
高校生のルースが大人を操っているようの演技していて、何が本当なのか、誰がしたのかわからなくなっている。その中で、他の映画ではこういう疑問はなかったが、この映画の場合は黒人の作った映画だと思え、どんな人かと思い、映画を観終わってから調べたら、ルースのように監督はアフリカのナイジェリアから10歳ぐらいに米国に来て優秀な経歴を持つ黒人だとわかった。
アーリントンのノバ高校では南部連合の旗(the first flag of the Confederate States of America)が降ろされていくのがウィルソン先生の教室の窓から見える。バージニア州でも米国社会の変化の影響が出てきていて、人種差別の象徴の旗は公立の組織からなくしているのも監督の裁量だろう。
白人の友達が黒人の同級生をBlack Blackというがルースに対してはルースだという。ルースは受け入れるが、他の黒人はうけいれられないという差別。こういう差別はよく聞く。監督もルースのように言われてきたのかもしれない。
ウィルソン先生の教室の飾りは彼女の性格や思想を反映している。シーザスチャベス、オバマ、マザーテレサ、キング牧師の写真が貼ってあるし、世界地図はアフリカが中心に見える。私個人の教室も半分は私の哲学が現れているホスターでもう半分は生徒のためのポスターが貼ってある。
ウイルソン先生とルースの思想の戦いが圧巻。これに焦点を絞って書こう。
黒人同士は黒人に厳しい。家庭の躾もそうだが、ルースが夜、ジョギングをしているが、黒人家庭だったら、特に息子には親は夜、暗い中ジョギングをするなというと思う。肌の色が夜と合わさって、夜、動く犯罪人と間違われて殺される可能性があるから。
ルースは白人の家族に育っているから、親からこういうことを言われていないという意味でも『自由』スピリットで育っている。
両親が『Our Black Son 』といって息子を守らなければならないと言ってるのは過保護で、現実の問題点から逃げようとしている。彼のエリトリアで生きた頃の精神問題PTSDを治療したと言ってるが、戦火で、子供心に人にうまく頼って生きるための策略を心得てきていることに疑問点を感じていない。
ここでなにかおかしいと感じているウィルソン先生の第六感は正しい。なにかきな臭いものを感じている。私も先生なので、このウィルソン先生の第六感や生徒がなにを書く(描く)かにより、深層をみることができるのがわかる。
黒人のなかの世代や背景の違う二人の黒人(ルースと歴史のウィルソン先生)黒人のなかにある根強い問題を追及する映画になっている。
社会の有能な黒人は評価され認められる。でも、一般の黒人は人間一人の価値よりまとめてblack Black (ルースの白人の友達がいうように)という見方を社会からされるようだ。
これを『公民権運動』でやっと自由を勝ち取ったが、まだまだ白人が作ったシステムの中で生きている黒人(例えば、ウィルソン先生)にはbest/perfect にならなければ社会から認められないと考えてる思想がある。だからアメリカ生まれじゃない黒人の生徒(ルース)にもパーフェクトを望むし、黒人の代表、完全である良い見本という期待感がある。ルースの友達ディシャンは先生のいうパーフエクト候補ではないからアスリーのスカラーシップも落してしまう(ルースのような生徒はどこもかしこも奨学金をくれるし、彼の家庭はそんなものはいらない。でも、ディシャンにはこれが唯一だったかもしれない)。はっきりいって、優秀でありリーダーになりそうな黒人は箱の中に入れて育てたい。ここから外れるものの面倒はみない。これが、ウィルソン先生の思想。自分の妹に対しても。
しかし、ルースはエリトリアの戦争地域から今の両親に救われて、アメリカの『自由』をやっと満喫していて、学業、スポーツ、討論などでも自分の力を試していて、自分のなかでベストを尽くすことを学んでいる。でも、学校の期待も背負っている生徒。彼は自分のことを米国社会(特に奴隷制度の名残の黒人社会)がみているステレオタイプの枠に自分を入れられないし、ウィルソン先生のいうパーフェクトを望む黒人の世界のエリートの思想にも足をいれない。『黒人であることは十分じゃない!』とルースにウィルソン先生は感じさせる。
ルースは人間として、自分の人生の戦いに挑んでいるが、ウィルソン先生は黒人としての戦いをルースに望んでいる。
黒人のなかでベストになるには完全でなければならないというウィルソン先生の思想とは相容れない二つの見解の戦いである。
最後のシーンでルースは母親に『もう一度やり直せるチャンスがある。』というが、ウィルソン先生は? ルースよ、卑怯な行動を取らず正々堂々と戦ってほしい。
名作中の名作
今、アメリカでは、黒人の差別は黒人の過剰反応だという新しい価値観が広がっている。気にしすぎなのかもしれないし、そうじゃないのかもしれない。
黒人でも、名誉黒人みたいや扱いをされる人もいる。
肌の色だけがテーマではない。
戦争、偏見と自由、理解と束縛、愛と不信…
人種、親子、夫婦、友達、教師と生徒、上司と部下…
社会と個人…
現代社会の問題をルース・エドガーを通して描写している。
単純に、ルースが幸せになる事を願う者と、ルースを利用して社会的地位を得ようとする者の駆け引き、それ以外にも様々な視点で観れる作品だ。
一人でも多くの人が、この作品を観る事で、今後の社会は変化していくのではないだろうか。
高校生は必見の作品だ。
ラベリングの悲劇
事前知識を仕込む余裕がなかったのだが、元が戯曲と聞けば納得するつくりではある。学校と家庭。狭い世界。
タイトルロールであるルース・エドガーは優等生である。しかも彼は紛争が激しい国、アフリカはエリトリアからやってきた。彼は「特別たること」「完璧たること」を期待される運命にある。
対峙する教師オクタヴィア・スペンサーには彼女なりの強固な信念があり、ままならぬ家族がおり、恐らく想像の及ばぬ過去の抑圧がある。それが彼女を走らせてしまう。
とにかく常に互いが噛み合わない。思いが伝わらないというディスコミュニケーションの連鎖が続く。無意識のラベリングの強固さを感じる。
理想の息子、信頼の厚い少年。ケルヴィン・ハリソン・Jrの貼り付いたような笑顔。優等生的な言葉、笑顔。表情があるようでない。
彼は自分の立場をよく知っていて、なおかつ他の境遇に敏感である。彼の時折見せる激しさを、結局誰も受け止めてはくれない。
物語全体が徹底的にディスコミュ二ケーションに彩られている。ナオミ・ワッツは結局息子を「信じていない」。ティム・ロスは常にどこか腰が引けている(客観視という意味では良いのだが、介入を避ける向きがある)。オクタヴィア・スペンサーは「ルース・エドガー」に巨大なものを見すぎている。それは正しいとも言えるが、だがしかしそれは本質なのか?
どうすれば曝け出せるのか?曝け出せないことこそが大いなる問題なのだ。曝け出したら何もかもを失うかもしれない。ルース・エドガーは安定しているように見せかけて、非常に危険な綱渡りを強いられているのだ。
ラストのルースの表情に、やはりこの先にある陰を感じるのは私だけだろうか?
全57件中、1~20件目を表示