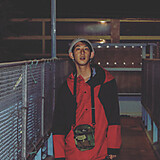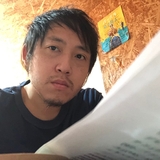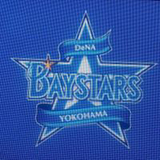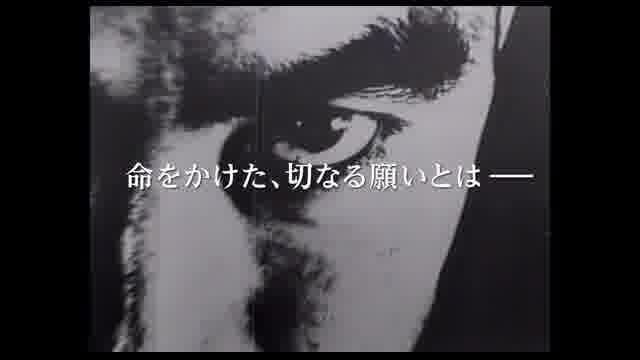三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実のレビュー・感想・評価
全213件中、121~140件目を表示
圧倒的熱量
今たかが18歳しか生きてない私にとってここまで政治に熱く語れる人がいたなんて信じられませんでした。
今現代、酔っ払って政治家に文句を散らす人などは見かけますが正々堂々と相手に敬意を表して語り合う姿は現在では見られないものだと素直に思ってしまいした。
今現代、私たちの中にも政治へ無関心、放棄した人は多くいたと思います。私も国民としてやっぱり政治への関心や理解を深め、一意見を出せるものになれるようにならねばと焦る作品でもありました。私は三島先生を尊敬しています。政治思想とかそうゆう話ではなく一人の作家として一人の表現者として尊敬しております。私もこれからを生きて表現することを選んだ人間なのでこの熱量を今!受け取れたことに感謝と敬意を示します。
芥正彦は負けたのか?
当時三島は44歳であった…
もう50年以上前、正確にいうなら1969年5月にあった「イベント」の記録ですよ。
ビデオで撮影していたら、とっくに消えていたかもしれない映像資料をよくぞTBSは映画にしたものだ。
本編を見る分には、三島はメモの類を一切見ないで東大生と討論しているのだ。
アタマよすぎ!! 旧制学習院高等科で恩賜の銀時計をもらい、東京帝大法学部を出て大蔵省に入った頭脳的優秀性が理解できます。
それはともかく、今こんな芸当ができる44歳の人っているだろうか?
自分以外すべて敵という中で、討論できる人。
お笑い芸人なんかだといるだろうけど、彼らに形而上学的言辞を操りながら、相手を説き伏せるようなことはできんでしょう。
かといって、学者や文学者にもそんなことはできまい。京大出の本作にも出ている平野啓一郎あたりなら可能だろうけど、彼にマッチョ的な道化の仮面をかぶったうえで、そんなことはできない。
かつて、日本にこんな人間がいた。
かつて、日本でこんな議論を仕掛ける若者がいた。
その事実の記録が存在することを知るだけでも、この映画を見る価値がある。
鑑賞した劇場は、中高年から老人がほとんどだったが、若い人ほど見てほしいね、。
「知らないからいいや」とスルーするには勿体ない!!
三島由紀夫?東大全共闘?「知らないからいいや」とスルーされそうなドキュメンタリー映画ではあるが、その考えでスルーしてしまっては絶対に勿体ない作品である。
仮に知識が全くなくても「言葉」のもつ圧倒的な力、熱量というものを感じずにはいられない作品となっている。
左翼思想と右翼思想が対立してるだけという次元のレベルではなくて、人間の持つ思想の根源や存在する意味、自と他の関係性を1960年代後半をリアルタイムに生きている若い世代と、戦争というものが当時の日本国民の脳裏に植え付けた国の運命と自分の運命が共同体であるという思想が敗戦によって「無」とされてしまった日本人との決して交わらないジェネレーションギャップによる物の考え方は理解し合えるかというと難しいし、人によっては自分の思想・主張こそが「正しいもの」と部分のフィルターを通してでしか考えられないために、制圧や暴力という良からぬ方向に傾いていまい、その様な意見のぶつけ合いは、平行線でしかない。
今回の討論会が互いが自分の意見ばかりを主張して、相手の発言を全く受け付けないようなものだったとすれば、暴力事件に発展していたのかもしれない。
しかし、三島も東大全共闘の面々も互いの意見を受け入れて、その中で分解していくスタイルは物事の考えた方が違う者も理解し合えるという希望をもったものではあるが、討論会から50年経った今、残念ながら希望は希望のままに現実には近づいていない。
この討論会は全部理解するのは、正直難しい部分もある。数々の芸術的文学作品を生み出してきた男と東京大学の天才達の発する言葉の数々や引用元は実際にこのドキュメンタリーに登場する人物たちもすべてを理解できている人は少なく、ある程度の憶測をするしかない部分も含まれている。
確実に言えることは、令和の今を生きている人たちにとっても、突き刺さるほどの刺激を与えてくれる討論会であると言えるだろう。
ドキュメンタリーの枠では全然収まっていない、ある種のエンターテイメントとも言える作品であろう。個人的に、こんなに刺激を受けた討論会というのは初めて観た。
当時、この討論会の様子を映像として残していたのは、TBSのみで長い間行方不明状態とされていたために、この討論会を映像で観るというのは、不可能に近かったのだが、TBSが2019年にフィルムを発掘!!
ウェブ上やニュース番組等で3,4分のものを小出しにしてきてはいたが、ここまでの長い映像を観られるということ自体も非常に貴重な体験ができる映画と言ってもいいだろう
セレモニーとしての物足りなさも⁉️
潔く圧倒する姿勢。
素直にただ圧倒された。三島由紀夫のカリスマ性に。
ユーモアを交えた発言と学生との対話を愉しむ姿勢に。
観ておいて良かった、知っておいて良かった、こんなご時世にこそ観ておいて
篤になるドキュメンタリー映画だった。私は三島由紀夫が生きた世代ではない
ので、彼のことは作品と自決したこと以外はほとんど知らなかった。とにかく
その発言の言葉遣いの美しさが心に残った。自分を論破しようと息巻く学生を
相手に、きちんと礼節を以て話を聞き、応える。時に笑いが起こり、まさかの
和んだ風景が幾度も映し出される。内容はかなり難解な言葉の応酬で、なんで
そこまで事物に拘る必要があるんだ?と思うくらい、しつこく繰り返されるの
だが、全共闘の論客・芥正彦氏とのやりとりが筆舌もの。ご存命の三人が当時
を振り返り解説をしてくれるが、この芥氏だけは今でも目力が強くかなり怖い。
議論の内容よりも、討論とはこういうもの。こう来たらこう返す。相手の顔を
見て、真直ぐに、自分の言葉で。という姿勢が潔く心地よい。三島を論破する
ことが目的の学生たちは時に侮蔑を交えた発言もするが、三島は平静にかわす。
この繰り返し。どんな高度な知性もやはり彼には叶わないよと思わせてくれる。
遺されたフィルムによるドキュメンタリーを、元東大全共闘、元楯の会、現場
にいた人、親交のあった人、そして三人の文化人が解説していく構成が非常に
観やすく纏まっているので、観た人それぞれに想いを張り巡らすことができる。
私はこの三島由紀夫の言葉をもっと聞いていたかった。今彼が生きていたなら、
顔を見せない誹謗中傷や罵詈雑言に、どんなユーモアで返してくれただろうか。
三島由紀夫は知らない
言葉の重み
なんで三島も全共闘の学生も、こんなに分かりにくく面倒くさい言い回しするんだか。
哲学思想にかぶれた、難解な言葉が頭がいいことだと思ってるのか?
逆に人に理解される気があるのか?
馬鹿じゃないのか?
みたいな「?」が多く浮かびつつも、真剣さ、熱量は伝わってきました。
右と左の主義が異なる三島と全共闘ではあるが、しょせん手法や信奉対象(三島は天皇や国体・日本人文化、全共闘の学生は個人や学生の立場に未来、という差があった気はします)の違いでしかない。
ナショナリズム(反米愛国心、というより子どもの「攘夷」ごっこ)が底通しているというところで、互いに認め合う姿は、どこか滑稽さを伴いつつ、暑苦しいが清々しかったです。
テレビや雑誌カメラを意識した、(いい意味で)プロレス的な見世物だったのかもしれません。
また、このころは、まだ政治に関して、政治家も作家も学生も「言葉」を大事にしていたように感じました。
言葉を伝えようとし、言葉が通じるかを試し、言葉の力を信じようとしていて、言葉は重く価値があった。
(だからといって分かりにくい言い回しは困りますが)
翻って、今の令和の時代、国民は政治に興味がなく、政治家もマスコミも、発する言葉が軽い。
すぐに発言を訂正し、無かったことにし、文書は改竄して、約束を破る。
三島のように自決しろとは言わない。
ただ、大人として、一人の人間として、発した言葉に責任をもって欲しいと思うのでありました。
ところで、三島の自決後の左翼は、あさま山荘・日本赤軍など、過激な活動で社会から敵視され、敗北し、自壊していったわけだが…
今も生き延びているかつての全共闘の人々は、学生運動とは何だったのか、そして革命とは何がしたかったのか、ちゃんと人生で「総括」してるのかな?
かつてのことを思い出しながら熱く語る70代の方が、作中で数人映っていましたが、この話題になると目が宙を舞い、「それなりに意義はあった」的に語っていました。
革命を目指してたくせに、教員や公務員になって家庭を作り、老後を迎えたその姿に、今や自己正当化の卑怯さが垣間見えるなぁ…
結局、今、言葉を軽くした責任の一端は、学生運動をしてた連中が責任を取らなかったことにもあるんじゃないかな。
などと思ってしまったのは、私がこの時代を直接は知らない、若い世代だからなんでしょうかねぇ。
言葉の意味はよく分からんがとにかくすごい自信だ
「高次元」という言葉がピッタリと言っていいほど彼らから飛び出す言語の理解は困難だ。しかしながら、その言葉と一緒に運ばれてくる熱量を我々は確信的に感じることが出来、結果この作品は時代を超えた普遍的なものになっているのでは無いだろうか。
観客はこの「vs」の結果をどう受け取っただろう?表面的には互角、いや芥のカリスマ的存在感により、むしろ全共闘が優勢に感じる者も少なく無いだろう。
しかし、解説陣複数による「全共闘は自身の人生の中の<あの季節>をどう総括しているのだろう?」という共通の疑問に対する現在の彼らの答えっぷり。そこにヒントがあると思う。三島と対峙していたあの時の熱に溢れていた面影を感じることは出来なかったのだ。
一方で三島が説く「美学」。日本人であるという運命に身を任せるしかないことを肯定し、その中心にいる「天皇」は概念でしかない。自信が戦争に行けなかったことへのコンプレックスのようなものから由来してると推察する者も少なくないこの「美学」は、何かに運命を支配されることへの渇望と、運命を導く者を待望してるわけだが、ここでこの作品を観たものが、絶対的に抱くであろう「今のこの状況、三島はどう思うだろう。いや、この時点で今の日本の状況、三島はわかってたかも…」という感情の先に、憂いてしまう自身が悲しい。。
ドキュメンタリーであるが三島を始め出演者達はその時代を代表するこの上無い演者だ。彼らの熱量を確認できたことに心から感謝したい。
改正健康増進法により全ての施設内でタバコが吸えなくなった2020/4/1に記す!笑
三島由紀夫は最高のプロレスラー
もっと早く公開しなかったわけを知りたい 亡くなったのはほんとうに残念 朝まで生テレビで、野坂昭如や大島渚と討論してほしかった。
私は全共闘世代とは一回りちょっと齢下です。1969年は小学校低学年。三島由紀夫が自決したとき、両親が豊饒の海シリーズを慌てて買っていた記憶がある。子供ながらそうゆう両親の行動が嫌いだったのでなぜか覚えている。そして、三島のセクシャリティについて話しているのも聴いてしまった(誤解だったらしい)。軍服姿はとにかく嫌だった。マッチョも生理的に嫌いだった。学校生活も今思えば付け焼き刃的な民主主義の匂いにあふれていた。当時小学生の私はその後も三島について何の知識をもたないまま、ずっと生理的に嫌っていた。だから大人たちがその死を悼む気持ちも理解しようともしなかった。それが、このドキュメンタリー映画をみて、人間三島由紀夫に対してものすごく親愛の念を感じた。瀬戸内寂聴97歳(わー、エッチな人って長生きだわ)が言う、「優しいひと、ユーモアにあふれた人」。そうそのとお~り(財津一郎のあれで)。まっすぐな人。オレより頭がいいのは、まぁ、しょうがない。学習院高校主席。天皇陛下から銀時計。東大から大蔵省へ。その後、作家活動。1925年生まれ。終戦時、弱冠二十歳。当時、三島の世代(同じかそれよりもっと若い人たち)には特攻隊に志願して散っていった人が沢山いたはずだ。映画でいうと、市川雷蔵の「ある殺し屋」に代表されるトラウマがダブる。
全共闘を含めてあのころの学生運動のことはよくわからない。真実は定まらず、理解するのは無理だと思っている。その世代のひとたちの言うことを聞くとますますわからなくなる。我々の世代はつかこうへいの「初級革命講座飛龍伝」とか、「戦争で死ねなかったお父さんのために」とか、おちょくった芝居や小説を通してしかその雰囲気を感じられなかったためもあろう。頭のいい人たちが当時の学生たちをアジテーションしただけなのか?ほかの国の民主化革命と比較されるが、僕らの世代は当事者でないので、本当によくわからない。
盾の会と全共闘のひとの供述も同じ割合で上手に話をつないでいて、非常にわかりやすかった。1000人対一人の決闘。討論を楽しむ余裕があるのが素敵だと思った。撃たない西部劇みたい。しかし、たばこの量が半端ない。やっぱ、緊張しているのだろう。でも、声も上ずらず、マイクを持つ手も震えず、みんなサムライだった。赤子を抱えた芥正彦という人はほんとうに個性的ですごいと思った。作戦か?子供はずるいが、子供が泣きもしないのはさすが。血筋を感じた。そのアナーキーな信念を70まで突き通しているのがすごくかっこよかった。寺山修二との演劇雑誌を読みたいと思った。ショートピースをあの短時間で二人で計6箱あけたと言っていたが、ほんとにみんなモクモクふかしてたな。
木村修さんの後日談で三島が木村さんに「盾の会」に入らないかと電話で言われて、話を遠回しに答えたが、三島がそれを察知し、周りに誰かいるかと聞いて、木村さんが、「実は彼女のアパートにいるんです。」といったら、変わってくれといいい、木村さんの彼女(現・奥さん)と三島がはなし、木村さんを愛しているかと訊き、奥さんが「愛していると答えた」という話は、単なるおのろけではなく、三島が木村さんを好んだからで、でも愛する人がいるなら、自決する自分と一緒ににはできないと三島が確かめたのではないかな~と思った。三島、優しいもん。
亡くなったのはほんとうに残念。朝まで生テレビで、野坂昭如や大島渚と討論してほしかった。
日本の学生運動が反動で終わったとしたら、政権が佐藤内閣で敵としては柔らかかったのではないか?田中角栄の政権だったらもっと火が付いたかもしれない。日本の政権が幕末から明治維新の系譜から脱却できないのはいい面もあると思うが、首相はすくなくとも学習院よりも上の大学出がいいな。ナレーションが 東出昌大 だった。 まさに東大にはさまれた名前で、やな感じだった。東出昌大は落語ディーバーだけでいい。
楽しい討論空間
記録映像を見ながら、三島由紀夫が実に楽しそうだと思っていたら、関係者もそのように証言していた。
興味の方向性が似ているのに同調は出来ない相手で、しかも知識量が同等で討論好きな人間との討論は、有意義であり充実感がある。興味の方向性が違えば話ははずまない。同調できる相手とは議論になりにくい。知識量が違うと議論が続かない。討論好きな人間でなければ何時間も付き合ってくれない。
つまり、有意義であり充実感がある討論、すなわち「楽しい」討論が出来る相手は稀有と言えるのだが、それが何人も居たあの場は、三島にとって幸せな空間であったに違いない。
と、書いていて気付いたけど、あれを見た後だと文章が硬めになっちゃうね。
あの季節を通り抜けたのはいいけれど、で、どうなったんだ。
それぞれの思惑通りにこの場所が設定され討論が始まってそして今この国はあの頃と比べて良くなったんだろうか?観念が先行する中でゲバルトが幅を利かせて暴力を肯定し言葉を弄んでいたあの頃。あやふやで猥褻な国「日本」。両者の共通の敵はこの国そのものだったし、この
討論で見出せたのはそんな戯言だけだったのだろうか?右も左もなく三島は1000人の学生を説得しようとしたが、自らの命を絶つ為の言い訳に少しだけ役立てたに過ぎなかった。全共闘の猛者たちはタテカンを燃やしあやふやで猥褻な日本の歯車に組み込まれることに抵抗せず、世界人にもならず三島ほどの優れたパフォーマに嫉妬するだけの人間にしかなれなかったことを悔いているかのようだ。しかし、言葉の大切さを痛感せずにはいられない。他者・天皇・熱情これを理解するためには言葉が必要なのだ。真剣に悩む人たちが観る映画だし、ひょろりと世の中を渡って行けると信じている人たちは見ない方が良い。いずれにしてもブレぬ方が身のためだからだ。
言葉の重み
言葉に力がある
自決までもが府に落ちる貴重な記録だった
1969年5月、東京大学駒場キャンパス。三島由紀夫と東大全共闘との討論会の超貴重なドキュメンタリー。
まさに百聞は一見に如かず、三島を知るためのピースが一つ、いや、けっこう埋まった気がした。彼の考えを彼自身の言葉で語った。翌年11月の三島事件/自決が府に落ちた。
武闘派といわれた東大全共闘と三島・楯の会の接点をも模索した。そう、彼らは対極にあるわけではなかった。はなから三島を見下した全共闘側は幼なく、まともな『討論』にならなかったのが残念ではある。
三島のオーラは凄かった。あの時代にあってスーパスターだった。ユーモアたっぷりの語り口で駒場の900番教室全体を魅了した。
個人的に気になったのは、このあと泡のように消えていった全共闘の面々のことだ。どのように熱を覚まして社会復帰したのだろうか?
全213件中、121~140件目を表示