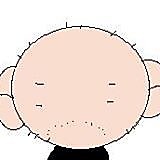三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実のレビュー・感想・評価
全213件中、41~60件目を表示
三島由紀夫の優しさは伝わりました
天才作家がこれほどまでに誠実で優しい人物だとは思わなかった。
しかしながら、ただただ芥というプライドが肥大した高慢ちきな人物が不愉快すぎる。
70過ぎた老人になっても、ただの芸術家気取りの偏屈な人物。
この人物が無駄すぎて、低評価。
6歳で安田講堂事件をテレビで見て、いつか自分も、とぼんやり思った変な子でした
三島は、天皇という一神教を信じ、全共闘が社会主義革命という一神教を信じていると受け止め、一神教信者というメンタリティーにおいて共闘できると信じ込み、アメリカ的価値の堕落という共通の敵と戦おうと勧誘に出向いた、という事なのでしょうか。
東大生と三島の抽象概念のキャッチボール、すごいね、頭いいとはこういう事なんだろうね、などと感心しながら見ていましたが、同時に、ただ言葉の粉飾にすぎないような気もして、本質を見極める力とは別物のような気がしないでもなかった。だから、巷のおばあちゃんなんかが、ぼそりと言う真実に打ちのめされたりすることがあるような。
三島は、割腹自殺という形で一神教に殉じた。しかし、全共闘は果たして本当に一神教信者だったのか。もともと多神教だったのか、あるいは改宗したのか。ただ、あの時代において、まじめに、かつ愚かに、そして熱く対峙する姿は、一回りほど下の私にとって限りなくまぶしい輝きを放つものでした。
全共闘は何を残したのか
1960年代後半の学生運動全盛期の時代背景が分かる映画!
ドキュメンタリーの前半で、当時の時代背景を説明してくれます。東大全共闘を始めとして、日本各地で、学生運動が起こっていた様子が伝わり、今の日本では考えられない様子だと思いました。
その中で三島由紀夫が、東大駒場キャンパスの討論会に出るという、当時の貴重な映像も見ることができるドキュメンタリーです。正直、三島由紀夫や東大の学生が議論で話す内容は、難しい内容も多く、ついていけない部分もありました。それでも、三島由紀夫の思想の一端が分かる映画だと思います。戦後の日本の歴史の中で、その時代を知る意味でも、時代背景や三島由紀夫の思想の一端を知ることができる映画だと思いました。
あの東大駒場キャンパスの討論会の会場の「熱量」は確かにすごかったと感じましたし、「言霊」の力を信じようとして、討論に臨んだ様子が映画から伝わりました。
熱と敬意と言葉と。 その頃のことを全く知らない世代で、自分達が何か...
熱と敬意と言葉と。
その頃のことを全く知らない世代で、自分達が何か行動を起こしたとして世間や政治や何かを変えることなんて出来やしないと思っているし、そもそもそんな真剣に世界のことも自分のことも考えていないと思っている。そんな私からするとこうも変革に向かって突き進んでいこうとする情熱は羨ましいとすら思う。
三島の本もほぼ読んだことないし、断片的にしか知らなかったけど、なんか一気に実在したんだ、という存在感をリアルに感じられた。
ちょっと前までは本当にこんな一人間が何かを思っていたとしても変化は起こせないと思っていたけど、最近はSNSがきっかけで少しずつでも声が届いたりするシーンも見たりする。案外まだこの時代も捨てたものじゃないのかも、まだ真剣に世の中を変えようと考えてくれる人がいて力もあるのかも。そしてその動きの根底には熱と敬意と言葉があって、それってこの全く知らない時代と共通しているんだと知った。
分かり合えなくても、頭ごなしに否定するんじゃなくてまずは熱と敬意と言葉でもって対話して知ろうとする。知ってもらおうとする。そばにいる人との関係においても、大切なことを学んだ。
右と左の二元論で語れるほどに、人の思想は単純なものではないのだ
私は、本作に描かれているような学生運動については聞きかじった程度の知識しかない平成生まれの若造であり、三島由紀夫という男については自衛隊施設を占拠したのちに切腹してこの世を去った文豪であるという程度の知識しかない人間であります。
そんなほとんど無知な私が本作を観た感想としては、「興味深かった」です。
内容が内容だけに「面白かったか?」と問われれば微妙なところですが、少なくとも「興味深く」最後まで飽きずに観ることができました。
冒頭の過激な左派学生運動の描写の後に、右派の三島由紀夫が東京大学にて討論を行う流れになったことで「大丈夫か?殺されるんじゃないか?」と心配になります。しかしながら実際に討論が開始されてみれば意外や意外、三島の発言に会場から笑いが起こったり学生の発言で三島が笑ったり、三島のタバコに学生が火をつけてあげるようなシーンもあって、当初感じていた危機感は次第に薄れていきました。
難しい単語は字幕で注釈が入ったり、当時実際に現場に居合わせた人たちへのインタビュー映像を途中で挟み込むことで、当時の学生運動について知識が乏しい私のような人間にもある程度は理解できる構成にしてくれたのも、本当にありがたかったですね。
・・・・・・・・・・
1969年5月に東京大学駒場キャンパス900番教室で行われた作家三島由紀夫と東大全共闘との討論会を当時の実際の映像や参加者へのインタビューを通じて映し出し、三島由紀夫という男の生きざまを描いたドキュメンタリー。「伝説の討論会」とも呼ばれる討論を現在に蘇らせる。
・・・・・・・・・
個人的に本作で感動したのは「学生運動に参加した学生のその後」を描いているところですね。
当時の学生運動について色々調べたことはありますが、例えば連合赤軍のあさま山荘事件とか2002年に逮捕された重信房子みたいな「一線を越えてしまった過激派のその後」みたいなのは結構見掛けるんですけど「学生運動の一般参加者」に関してはその後の情報があまり見掛けない気がします。もちろんしっかり探せばあるんでしょうけど、センセーショナルに描かれるような話題ではない印象です。しかし本作では三島由紀夫との討論を主催した東大全共闘のメンバーがインタビューに参加しています。全共闘が「敗北」した後にどう考え、どう生きたかをしっかり描いているんですよね。三島由紀夫が主役として扱われている映画でこう言うのも変ですけど、全共闘のメンバーたちも、本作においては紛れもなく主役であったように感じます。
また、本編で描かれている討論の様子にも感動しました。
「右と左」というと対極的な存在で対立していると思われがちですが、冒頭の三島由紀夫の「諸君の熱情は信じます」という言葉で、お互いに認めるところは認めているのだと感じられますし、討論しているうちにお互いに共通認識があることもわかってきたりして、ただただ「論破してやろう」「打ち負かしてやろう」という攻撃的な討論ではなく、実に建設的で愛に溢れた討論であったと感じます。
また、三島の発言の端々から「文学の人間」って感じの美しい表現が飛び出してくるのも感動しました。相手の言葉を受けて意見を返すのが討論ですので、あの場の発言はほとんどが即興で出てきた言葉だと思うんですけど、まるで小説を読んでいるかのような詩的な表現が三島の口から出てくるんですよ。思わず「うわぁすげぇ」と声を出すほどに感心させられました。言葉を使って人の心を動かし続けてきた三島由紀夫という人物の凄さを見せつけられるような場面でした。
平成生まれの自分から見るとまるで異世界のようですが、これが日本に実際に起こった出来事であり、当時の若者たちが自らの青春を投げうって行った「革命」なんですよね。本当に興味深い映画でした。オススメです!!
三島由紀夫こと、平岡公威は、面白い奴だ‼️❓
三島由紀夫のカリスマ性に脱帽
三島かっこいい
熱量と敬意と言葉と…
凄まじい熱量、言葉の応酬、そして三島は学生にきちんと一言一言、敬意を払っている。敵対する千人を前に、向き合い、決して馬鹿にせず、ユーモアを交えながら、認めるものは認めながらも、意見を戦わせる。はっきり言って哲学的、レベルが高過ぎてついていけないが。現代を見たら、三島は何を語るだろう。
本作では三島を一人の等身大として描いているのに好感が持てた。政治的...
本作では三島を一人の等身大として描いているのに好感が持てた。政治的な主張は感じられず、三島を批判するわけでも、過度な肯定感で味付けするわけでもなく、共に生きた人たちから見てどのように映ったのかをいろんなライトで照らし合わせていく。
俺が好意を抱いたところは三島は一人の人間として1000人以上の学生と対峙したところにある。決してねじ伏せるわけでも、説教にし来たわけでもなく、学生と話したいからきたのが男らしいと思った。と同時に意外だったのが、あの安田講堂内では哲学を題材にした三島と学生の討論が行われていたというところにある。
これは憶測にすぎないけれど、もしかしたら学生側は東大の先生とこういう難題の話をしたかったのかもしれない。しかし東大の先生の頭脳より学生側が上回ったからこそ話を聞いてもらえなかったのかもしれない。まともに話ができないからこそ、こういう議題に飢えていたのかな、と鑑賞しながら思った。
学生側の鋭い質問にも三島はたじろぎもせず答える所がこの人のすごいところなんだな。
三島はテレーズ・デスケルウ の小説を引用し、亭主を毒殺した妻は夫の目の中に不安を見たかったからと説く。それを反体制側の人間が大衆の目の中に不安を見たかったからに違いないと語っていたところが好きだし、全共闘は知性主義の東大を壊したという点で評価してたのも興味深い。
後半では三島の天皇論にも言及しており、三島は天皇を日本社会の救済概念・日本の文化伝統が集約されるもの、すなわち無意識的エネルギーの源泉として捉えている。天皇というものを現実を積極的に批判する根拠として読み返して天皇を代表とする日本文化が戦後社会の堕落に対して批判としての力を持つ。もし現実を批判するなら君たちは天皇の名においてやらなければならない、という考えは学生側が意表を突かれて笑ってしまったというエピソードも好きだった。
もしかしたら三島は初代ゴジラのように戦後の日本に喝を入れたかったのだろうと思う。
理解不能な言葉の応酬にただ引き込まれていく
すばらしい記録
大変勉強になった。昔聞いた話の忘れてたことやわからなかったことが少し埋まった感じ。レスペクトということをなにより感じた。学生側はみんな目が輝き、まじめに何か吸収しようという意気込み感じる、三島由紀夫は非常に真摯誠実自分より若い学生自分とは違う思想、前提の若者たちを尊重し楽しみユーモアたっぷりに巧みに話す。三島のユーモアにどっとウケる会場、同じ場を共有し敵味方なく好きなことを言い批判され批判し笑い殴る殴れと挑発あっでも殴らないよ。民青に牛耳らレテいた駒場キャンパスここの建物、教室でのこの時間は、物資的にも精神的にもまさに解放区であったかのよう。解放区において、カメラもあり、東大全共闘の特に壇上の面々はそれなりにおしゃれしてカッコよく写ろうとしていたのかな。学生の時から前歯かけていた小阪修平氏の天皇というキーワード切り出し取り込みよかった。小阪氏もう他界されていたとは(四方田犬彦氏のFacebook記事で知る、、ちなみにこの記事がとてもよい、映画の理解を助ける)平野啓一郎氏の冷静な三島分析も世代の狭間の自分にとってわかりやすく助毛になる洞察。三島文学は訳もわからず中学生のとき魅了された、このような存在は右も左もない。今、世界に、日本に、広い地平を見える事象はあまりに利己的であまりに狭量だ。
親切設計
暴力権
不器用な天才
原作の本が実家にあったので、本は20数年前に読んだことがあります。本を読んでもその熱気が伝わってきましたが、映像で観た方がその当時の空気感が良く伝わってきました。
日本の作家の中で私が一番好きでハマったのが、三島由紀夫です。まずは、文体の美しさ。文体から目に浮かぶ情景。私は、太宰でも川端でもなく、三島です。
本作を鑑賞して一番感じた事は、三島は1945年8月15日で、生きる意味を見失っていたのではないかということです。第二次世界大戦中は、身体共にまともな男であれば戦争に行き、まともでなければ戦争に行けません。三島は後者であり、非日本男子という烙印を国から押された訳です。この『美しくお国の為に死ねなかった』という虚無感が、後の三島文学、例えば金閣寺に投影されていると思います。身体を鍛え上げたのも、若い肉体のまま美しく死ぬ為だったのかもしれません。三島の最期を知っているからかもしれませんが、画面に映し出された三島から現世に蹴りをつけた様な清々しさを感じてしまいました。
三島を観ていて私は「ゆきゆきて神軍」の奥崎を思い出してしまいました。三島と奥崎は、全く異なる主義主張、思想ですが、戦争によって狂わされてしまった人間という意味では同じなのではないかと。いや、ほとんどの日本人が戦争によって実は戦後も狂っていたのではないか?という恐ろしいことを想像してしまいました。
意外にも討論は和気藹々としていて、三島も余裕綽々な感じがしました。討論というよりもリラックスした語り合いに近い感じです。最近のレベルの低い国会で自民党議員や官僚を見ていたからか、レベルの違いに二度びっくり。三島も東大全共闘も思想の違いはあれど、お互いにお互いを敬っているのでは?と思えたほどです。いや、本当、今の親米の自民党連中や竹中平蔵氏を見たら、三島は何て言うのでしょうか。
『政治の時代』と言われるほどに、世界中で価値観の転換が起きた時代だからこそ、自由に能動的に生きた人も多かったのでしょうね。若者も生意気で血気盛んで勢いがありますしね。日本が、大きな経済成長を遂げたのが分かった気がします。
三島の『永すぎた春』の中に『幸せというのは、どうしてこんなに不安なのだろう』という台詞がありますが、私はこんな不安定な三島、狂気な三島が好きなのだろうと思います。
タイトルなし(ネタバレ)
本年最後のレビューは、劇場で観たのになかなか纏まらずレビューがまだだったこの作品。
特別、三島由紀夫さんに思い入れがあるわけでもないですし、僕みたいな無知な人間に理解出来るか不安に思いながら観に行ってきました。
結果…滅茶苦茶良かったです。
三島由紀夫さんと芥さんの対話など100%理解出来たとはとても言えませんが、その熱量、彼等の主義主張がその一部でも知れたのは自分にとって大変為になったと思います。
僕も学生運動を直に知っているわけではありませんし、予備知識もあまり無い状態での鑑賞でしたが、解説が入るので分かり易く、半世紀前の日本の姿、日本での左派もその発生した動機も反アメリカ=愛国が根底にあった事に今更ながら気付けたのは大きな収穫でしたし、当時学生運動に励まれていた方々のその後がほんの少しではありますが知る事が出来、長年の疑問が氷解した感じです。
三島由紀夫さんの“天皇”という考え方には大いに賛同出来ますし、三島由紀夫さんのカリスマ性、器の大きさ…きっと僕も身近にいたら、感化されていた事は間違いないくらい魅力的な方ですね。これは是非、自分よりももっと若い世代、10代や20代の方に観て欲しい作品です。
三島由紀夫さんが現在も存命でしたら、今の日本を見てどう思ったでしょうね?
三島由紀夫さんが全共闘を説得しようとしていたのは、右や左といった一見正反する主義ですが、そこには共通の敵がいる事が分かっていたからだと思います。
そして実はその敵は今も存在していて、その闘いはまだ終わっておらず、未だ続いているんですね。
(過激派の事ではないですよ)
三島由紀夫さんもとても魅力的でしたが、芥正彦さんも興味深い方ですね。
20歳を幾つか過ぎたくらいで三島由紀夫さんと渡り合える辺りからも頭の良さは分かりますが、70歳を過ぎた今でもギラついた刃のような感じの方ですよね。
学生運動について(敗北に終わったのでは?)のインタビューでは“自分がまだ存在している”との主旨の答えをなされていましたが、主義主張は違いますが、パンクの“Punks Not Dead”に通ずるものがあるように思いました。
まだ終わったわけじゃないという芥さんの気概、凄いですよね。
また、三島由紀夫さんが自決なされた事についてのインタビューでは“良かったじゃないか、彼も本望だろう”というような答えをされていて、一瞬、カチンときたのですが、よくよく考えてみたら、決して三島由紀夫さんの死を嘲笑ったりしているわけではなく、真実を語っていただけなのではないかと思います。
三島由紀夫さんは第二次世界大戦を生き残ってしまった事に負い目を感じているような節があったみたいですし、いつか日本のために命を捧げたかったのではないかと、そして自分の中にある美学に則ったのではないかと、そんなふうに僕には思えました。
ですから、芥さんは“本望ではないか”という意味で、あのように答えらっしゃったのではないでしょうか?
三島由紀夫さんと芥さんの決定的な違いは、三島由紀夫さんが本気で全共闘を説得しようとしており、きちんと意見を聞き、相手を尊重したいたのに対し、芥さんは最初から相手に分かってもらうつもりがなかった事、そして言葉で捻じ伏せようとしていた点のような気がします。
議論を途中で投げ出してしまった点も印象として悪く、あれでは逃げたのと変わらないように見えてしまいますよね。
まだ、書き足りないような気がしますが、これ以上書いても纏まらなさそうなので、このくらいにしておきます。
取り留めのないレビューになってしまい、すみません。
最後にご挨拶を。
皆様、今年一年大変お世話になりました。
皆様のお蔭で、今年もまた素敵な映画に出会える事が出来ました。
自分も含め、多くの方がコロナに振り回された一年だったかと思います。
新作映画の公開が延期されたり、映画に携わる方々には厳しい一年になってしまわれたかと思いますが、そのお蔭で多くの方が映画を愛している事を改めて実感出来たような気がします。
個人的な事ですが、元々本業の仕事が減っているところに加えて、このコロナの影響で仕事が更に激減。
加えて、自分のバイト先のお店に、市街地から通じる道路が1年五ヶ月に渡って終日通行止めになるため、バイト先のお店が閉店の危機に瀕していますし(どう考えても踏切工事で接する道路が1年5ヶ月も終日通行止めっておかしくないですか?)全く先行きが見えない状態に陥っています。
来年、どうなるのか全く分かりませんが、また皆様のレビューを拝読させて頂き、より多くの映画を鑑賞出来る一年になれば良いなと思っています。
今年は暗いニュースが多かったような気がしますが、来年は皆が笑顔で過ごせる年になる事を願っております。
それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。
言葉の力
1969年、東大安田講堂事件と同年、革命への期待と騒乱に満ちた「政治の季節」、三島由紀夫は東大全共闘に招かれ公開討論会をおこなった。
その記録映像が、なんとTBSに残されていた。
本作は、討論会のようすと、当時、その場にいた人を中心に証言を集めて編集したドキュメンタリー映画である。
この映画は、こんなナレーションで幕を閉じる。
「あの日、この900番教室に満ちていたのは、三島由紀夫と千人の東大全共闘の『熱と敬意と言葉』だった」
意外にも討論は、言葉の応酬は激しいものの、全体に落ち着いていて、ときに笑いもあった。この雰囲気を作った三島の包容力とユーモアに、ちょっと驚いた。
三島は決して学生を見下すことはなく、真摯に耳を傾け、そして言葉を紡いだ。
三島は最後、東大生たちにこう言って会場を去る。
「言葉は言葉を呼んで、翼をもってこの部屋の中を飛び回ったんです。この言霊がどっかにどんなふうに残るか知りませんが、私がその言葉を、言霊をとにかくここに残して私は去っていきます」
「そして私は諸君の熱情は信じます。これだけは信じます。ほかのものは一切信じないとしても、これだけは信じるということはわかっていただきたい」
この日、三島に討論を挑んだ学生、「東大全共闘きっての論客」と言われる芥氏は、この討論を振り返って、こう語る。
「言葉が力があった時代の最後だと思う」
梨木香歩の近著「ほんとうのリーダーのみつけかた」にこんな一文があったのを思い出した。
「今の政権の大きな罪の一つは、こうやって、日本語の言葉の力を繰り返し、繰り返し、削いできたことだと思っています。それが知らないうちに、国全体の『大地の力のようなもの』まで削いできた。母語の力が急速に失われてきた。この『大地の力のようなもの』こそ、ほんとうのその国固有の『底力』だと思うのです」
三島と全共闘、単純には「ザ・右翼」と「ザ・左翼」という構図に見えるが、実際には通じる部分が多い。
前述の芥氏は、双方にとっての共通の、そして本当の敵は、「あいまいで猥褻な日本国だ」と言い切った。立場は違えど、どちらも日本を社会を、よりよくしたいと願っていたのだ。
三島の事実上の遺書と言われる小文「果たし得ていない約束」にある、彼の予言めいた言葉。
「私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行つたら『日本』はなくなつてしまうのではないかといふ感を日ましに深くする。日本はなくなつて、その代はりに、無機的な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであらう。それでもいいと思つてゐる人たちと、私は口をきく気にもなれなくなつてゐるのである。」
三島と全共闘の、この討論会が開かれたのは50年以上も前のこと。
しかし、いま、僕たちが生きるこの国、この社会のことを考えさせられた。
全213件中、41~60件目を表示