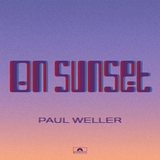ちいさな独裁者のレビュー・感想・評価
全87件中、41~60件目を表示
生き抜くことに必死なあまり…
一つの小さな嘘をごまかすために嘘に嘘を重ね続け、やがてその嘘が膨れ上がってエスカレートし、嘘をついた人間が怪物となっていくという話だった
よくできたフィクションだなぁと思いながら観ていたら実話だった
1945年、第二次世界大戦末期のドイツ
上等兵のヘロルトは、ドイツ軍を脱走
その途中で大尉の服を拾い、大尉になりすます
そして、その嘘を突き通すために人を殺し、その行為はエスカレートしていく
例えば、目の前に警察官の服装を着た人がいて「ちょっと良いですか?」と職務質問されたら、疑う人はいないだろう
主人公のヘロルトは、ただの上等兵なのにもかかわらず、ナチスドイツ軍大尉の制服を拾って着て以来「大尉である」と嘘を突き通し続ける
ヘロルトは、なぜ、嘘を突き通し続けることができたのか
引っ込みがつかなくなったということもあるだろう
しかし、恐らく、実際にナチスの制服を着て上官のフリをしてみたら、周りからチヤホヤされて何でも手に入るし、気分が良かったんじゃないかと思う
そして、二度と元の脱走兵の生活には戻りたくないと思い
気に入らない人間を次から次へと殺すことで周囲に恐怖心を植え付け、 服従させたのではないか
果たして、ヘロルトは嘘をついていることに罪悪感も持たなかったのだろうか
いや、それぐらい、当時のドイツでは、罪悪感よりも生き抜くことに必死だったということだと思う
そこは戦場で、いつ殺されるかわからない状況の中、生き抜くためなら、どんなことだってやってやる
そんな「窮鼠猫を噛む」の状況だったんだろう
だから、この話は恐ろしいのだ
「死ぬ気でやる」人間は、何をしでかすかわからないのだ
そんな恐ろしさにゾッとしてしまう映画だった
意外に残酷ですが実話系ですからね
目をそむけないできちんと観ることによって
歴史と人間のさがに対峙することができます
実話系ですから、評価もくそもありません
戦後、まもなくして英国軍によって
彼とそのとりまきは全て処刑されました
戦争の狂気と人間の性を見せつけられた感じがしました
終戦間近のドイツ軍の上等兵ヘロルトが引き起こした詐欺と謀略の物語。脱走で追われる中、偶然空軍大尉の制服を手に入れた彼は、制服の持ち主に成りすますことに成功します。最初は飢えを凌ぐためのほんのお芝居の積りだったのでしょうが、言葉巧みな彼は規律で鳴らしたドイツ軍の上官たちをいとも簡単に誑かし、いつの間にか大変な権力を握るようになります。この辺りの流れは、詐欺師が人を騙す手口と全く同じなのですが、巷の制服詐欺の話とは違って、人殺しが仕事の軍隊ではたちまち人命に関わります。事実、物語は冗談では片付けられないような深刻な事態に発展して行くのですが、この物語が実話がベースと聞いて本当にビックリ。最初はコメディーのようなノリで観ていたのですが、ホラー映画でもないのに余りの狂気に背筋が凍る思い。「馬子にも衣裳」とは言いますが、見た目だけでこれほど容易に騙されてしまう人間の馬鹿さ加減、そして...一旦権力を持つと悪魔に豹変し得る人の本性に戦慄を覚えずにはいられませんでした。
今まで見た戦争物の中で一番エグく残酷だった。
彼の行為は悪夢ではなく現実である
1945年4月、第二次世界大戦末期のドイツ。
敗戦目前のドイツ軍の若いひとりの兵士(マックス・フーバッヒャー)が、命からがら脱走する。
生き延びた彼がみつけたのは、路傍に置き座られたドイツ軍の車。
後部座席にあった大尉の軍服を見つけた彼は、ヘロルト大尉と身分を詐称し・・・
といったところから始まる物語で、映画において、自分以外の何者かになりすます話は多々あり、概ね佳作・秀作・傑作の部類に入っていたりする。
男性が女性になった『お熱いのがお好き』、その逆『トッツィー』、大統領になっちゃう『デーヴ』など。
なんだけれどこの映画は実話だそうで、「生き延びるために」上等兵が大尉になり、終戦間近の混乱に乗じて、非道ともいえる(というか、非道そのものなのだが)行為に及ぶという話で、まぁ、いっちゃなんだが共感の欠片なんて目覚めない・・・
「・・・」って書いちゃうのだが、これは「・・・」って書かないといけない。
そりゃまぁ、人道的に考えても、収容施設に収監されている脱走兵など、彼の立場と同じ同士を皆殺しにしちゃうなんて言語道断なのだが、生き残るために重ねる嘘によって、そんな言語道断な行為する「当然」「当たり前」「立派な」行為になってしまうことが恐ろしい。
でもでも、恐ろしいけど、「やっちゃうよなぁ・・・」と思わせてしまう状況・・・
それが、戦争。
いや、もう、敵を殺す云々の状況にないわけで。
敵も殺さない奴らを活かして、その上、我々がひもじいので良いのか!!!!!!(って感嘆符、どれだけあれば足りるかわからないぐらいな状況)って、かつての「貴様の身を挺して相手をやっつけてこい、死んで還るな」と、まぁ、ほとんど同じ状況ではありますまいか。
なので、彼のことを笑えないし、畜生にも劣るとも貶せない。
で、そんな、空恐ろしい、えげつない、おぞましい話をハリウッド映画で鍛えた演出で、「これでもか!」とロベルト・シュヴェンケ監督は撮っている。
エンドタイトルのバックには、ヘロルト大尉の特殊部隊が現代に蘇るのだが、これを悪夢と感じられるひとは幸いであるが、これは夢ではなく現(うつつ)に思えて、気が滅入ることしきりでした。
騙されているふり?
演じる
とても面白かった
重いテーマながら画面の美しさ、サウンドの良さ、テンポの軽快さのおかげでのめり込むように見れた
役者がとにかくうまい
撮影中役者も監督もショック状態になることがあったらしいですが、映画ですらあれほど衝撃的なのに実際はどれほど悲惨でショッキングだったことだろう、と思った
サディスティックな笑みといい、次に何を言い出すかわからない感じといい、ときどき幼いような笑顔を見せるかんじといい主演のフーバッヒャー、本当にうまい
ヘロルトは21歳だった、という部分、あの若さであれだけ堂々とやってのけた、というのは素直に驚きというか、いっそ感心すらする
カリスマというか度胸というか、戦時下だからできたのか、それとも彼にもともと備わった気質なのかわからないが…
フライタークやキピンスキーもとても良かった
二人ともほんとうに隊からはぐれたのか脱走したのか定かではないけど、運とタイミングによっては収容所にいれられていたかもしれない、と思いながら見ていた(もちろんヘロルトも)
ヘロルトがくるまでは単なる収容所だったのが、みるみる変わっていくさまがすごい
特にシュッテの妻(ゲルダだっけ?)が冷たい目をして拳銃を取り出したシーンはヘロルトの影響力の凄まじさだけでなく、影響を受けてしまう側の人間の恐ろしさを見た
エンディングで現代ドイツに現れたヘロルトたち、あれゲリラでやったんだろうか、役者なんだろうか…
よく怒られなかったなー
21世紀の街中でも姿勢を崩さずヘロルト隊がヘロルト隊であったのが、なんか役者の凄さを見たというか
女性のフードを後ろからヒョイッととったのが印象に残ったんだけど、あのおちょくるような感じ、なかなかできない…
総合してとても面白かった
テーマもよいし作品としての完成度も高いし多くの人に見てもらいたい
「ヘロルト」という青年の人物描写が嘘くさい。
「ちいさな独裁者」という題名に魅かれてこの作品を観たくなった。本題は、
『THE CAPTAIN』というらしい。戦争作品であるため、目を覆いたくなく残虐性はつきものである。人間の「騙し」と「信用」の脆い部分が上手く描かれている。実際にあった話であるらしいが、どこまでが事実史実であるのか判らない。それほど、首をかしげたくなる作品であった。軍服を纏って偽軍人になる。主人公は、ヘロルトという青年。個人的には、パッとしない印象を受けた。
21歳の青年にしては、かなりの腹の座った指導力の高さに驚かされた。
80人の軍人は、彼の一挙手一投足や発言力にまったく疑いを持たなかったのだろうか。「ハイル!ヒトラー」の掛け声で、みんなが信じてしまう。当時のドイツ軍人の心の状態を考えるだけで、「戦争」という得体のしれない何かに恐ろしさを感じ、日本においても、同じことが起きていたことに「人間の脆さ」を感じずにいられなかった。
現在と過去を考えさせられる実話
人間が作った虚構に
消化できない。
制服と権威になびく小市民
制服を着て信用させるというのは、人間の社会的心理を利用した詐欺ですが、今でも行われています。警察官の制服をきた人が何か言えば、皆従うでしょう。帝銀事件は「白衣」と「腕章」が信用されました。
制服の権威で権力を得た小人はやがて、怪物へと変化していく。
他のレビューアーが指摘されているように、この小国の総理や取り巻きの政治家、高級官僚に通じるものがあります。権力の快感と執着!
やがてトランプやプーチンが英雄に見えてくる……。恐ろしいことですが、現実。
でも本当に怖いのは、権威に追従する部下=われわれ小市民の心理です。残虐なことも「総統が憂いておられる」と言われると、いともたやすく受け入れていく。
我が国でいえば、15年戦争のときには「天皇陛下」の名の下に全てが正当化されていた。
今やそれも過去のことではなく、それは、天皇という言葉への日本人の過剰反応を見てわかります。
エンドロールでトランジットモールに乱入した「ヘロルト即決裁判所」部隊の姿は、正に今ここにある危機の象徴。映画の恐怖ではなく現実の恐怖に目を向けろと監督に言われている気がしました。
我が国の沖縄辺野古基地周辺では、すでにああいった怪物が出現して市民に暴力を奮っているのを直視することが、求められています。
役職者は人格を変える
現代のパワハラにもつながる、笑えないブラックコメディ
終戦間際1945年4月のドイツ。所属部隊から命懸けで逃げたした若い兵士のヘロルトは、逃走中に偶然手に入れたドイツ将校服に着替える。
すると、あれよという間に"威光"を手に入れていく。"自分は大尉だ"、"総統からの特命を受けている"という巧みな言葉を弄し、部下は増え、あらぬ方向へ進んでいく。
なんとこれ。1945年にヴィリー・ヘロルトが引き起こした実際の事件をもとにしている。その怪物っぷりは凄まじく、しまいには収容所の脱走兵の集団処刑を指示する。
笑うに笑えない超ブラックコメディである。原題の"Der Hauptmann"は="大尉"の意味。一介の兵士が"大尉の制服"によって、"偽りの権威"を得る。
権力に屈し、おもねいたり、正しい思考を停止してしまう人間の弱さ。
ドイツの戦争映画といえば、反ナチスが典型だが、本作の場合、ナチがナチを殺す映画なので、変則的ではある。
その"リーダー"は本当に正しいのか。単に"制服"や"肩書き"を身にまとっているだけではないのか。そのリーダーや組織は正常なのか。終戦間際のドイツ軍の混乱と迷走が見えると同時に、"組織に属する人間の盲目的な行動"を揶揄するメッセージが込められている。
ドイツ人のロベルト・シュベンケ監督は、ジョディ・フォスター主演の「フライトプラン」(2005)からハリウッド進出。「ダイバージェント」シリーズなどのメジャーヒットで活躍する監督だが、あえて自国でメッセージ性の高い作品を作った。
"権力"はまた、"お金"にも置き換えられる。近頃、話題になる"パワハラ"もこれの一種にすぎない。あらためて身近な社会でも、似たような事象を考えさせられる。
エンドロールのサービスカットがある。主人公のヘロルトたち即決裁判チームが軍用車で、現代のドイツの街を駆け抜け、ナチスの制服姿で、若者たちの所持品検査をする。
スマホを取り上げたり、映画のプロモーションとはいえ、これは笑っていいものか戸惑う。現代でも人間の行動は何ら変わっていないという、監督の強いメッセージなのだろう。
(2019/2/12/ヒューマントラストシネマ有楽町/シネスコ/字幕:吉川美奈子)
文句なしの傑作
権威とは何か。何によって担保されているのか。当方と同じく気の弱い一般人が畏れる権威や権力が、実は薄氷の上に建っている砂の楼閣かもしれないと思わせる映画である。
兎に角主人公の奸計が凄い。軍隊はヒエラルキーの組織だから上官の権威はほぼ絶対である。最上位の権威はハイル・ヒトラーでおなじみの総統だから、総統の名前を出せば大抵のことは通せる。首相案件という呼び方で国の基本である資料や統計を捻じ曲げる極東の小国にそっくりだ。
権威を証明するものは何かというと、これが意外に難しい。もしかしたら上級将校の軍服だけでも権威を得られるかもしれないというのがこの作品の設定である。必ずしもその人物が何かに優れている必要はない。権威に相応しい威圧的な態度や、横柄な言葉遣いがあれば、権威と認められることがある。
ナチスは役人でできた組織である。役人の基本は昔から自己保身と既得権益への執着だ。それは恐怖心の裏返しでもある。つまり、役人が権威と権力に従うのは恐怖心のためだ。もっと言えば、権威や権力は人々の恐怖心の上にかろうじて支えられているのだ。
主人公はナチスという官僚機構のそんな構造を知ってか知らずか、修羅場をくぐってきた老練な詐欺師のように、軍服ひとつで権威を獲得していく。最初は主人公の嘘がいつバレるかと思いながら観ているが、そのうちにナチスドイツという巨大組織そのものが、ハリボテの巨大な人形のように思えてくる。こんな嘘のかたまりが世界大戦を始めたのかと愕然とする思いだ。そしてそれを支えたのがドイツ人の恐怖であり、保身であり、既得権益への執着であったと考えると、同じことが世界各地で起きていることにも気がつく。現代にナチスがいたらチンピラに過ぎないが、それが虚構に膨れ上がると戦争を起こしてしまう可能性を持っている。人間はどこまでも小さく、そして愚かであることを改めて突きつけられた気がする。
全編にわたって綱渡りを観ているかのような緊迫感があり、目の覚める映像や衝撃的なシーンもふんだんに鏤められている。日本語訳詞の「さらばさらばわが友♪」ではじまるドイツ民謡が歌われるシーンでは、その歌が「わかれ」というタイトルだけに、いろいろな比喩を想像させる。最期の字幕で主人公のモデルとなった実在の人物の年齢を知って心底驚いた。文句なしの傑作である。
愚痴
全87件中、41~60件目を表示