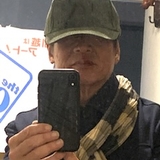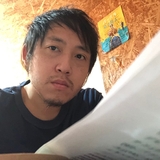峠 最後のサムライのレビュー・感想・評価
全180件中、41~60件目を表示
引くも地獄、進むも地獄であるならば…
期して着々と武装(新式機関砲)は進めてきたとはいえ、戦況から言っても、西軍(官軍)は勝てる相手ではない。さりとて、屈服すれば、かつての盟友であった会津藩を攻めるための先兵として西軍に利用されることは目に見えている―。後ろへ引くも地獄であり、前へ進むも地獄であるとすれば、前へ進むことが武士としての本懐ということだろう。
「武士道とは、死ぬこととみつけたり」とは、このことか。
その潔さが、痛いほどに胸に迫る一本でした。評論子には。
<映画のことば>
今このご時勢のなか、日本男子たる者がことごとく薩摩・長州の勝利者におもねり、争って新時代の側につき。武士(サムライ)の道を忘れ、行うべきことを行わなかったら、後の世はどうなる。
長岡藩すべての藩士が死んでも、人の世というものは続いていく。
後の世の人間に対し武士(サムライ)とはどういうものかを知らしめるためにも、この戦いは、意義がある。
平坦
おつかれさまでした
演技者みんな力が入ってて言いにくいのですがあんぽんたんな映画でした。
河井継之助には先見性がありましたが、時代は幕末、開国派と攘夷派が対立していて、そのあいだにも佐幕やら尊王やら、みんながバラバラにこうすべきだああすべきだと言って譲らず、争っていました。だから継之助もやらざるをえなかった。近代的合理主義を持っているのに時代に翻弄された栗林忠道のような人だと思いました。その立脚点も武士らしい哲理も解りましたし、悲運に朽ち果てるのは不憫でした。
しかし、ぶきっちょすぎる描写とあほなせりふによってむしろコメディでした。
みえを切りすぎです。愁嘆場も設けすぎです。なにやってんだこのひとたちは。へんな描写もいっぱいありました。奥さんと芸者あそびしたり、しみじみオルゴール聴いたり、城を奪還したら村で踊っちゃって、足撃たれたら歌っちゃって、俺を戦場に置いていけと言ったのに屋敷でゆっくりしちゃって・・・ちぐはぐなシーンが、崇高な武士のいきざまをことごとくずっこけに見せてしまっていました。
それをみて、あらためて監督は罪深いものだと思いました。
なぜなら役所広司はじめ演技者全員が渾身の力演だったからです。
黒澤明と仕事していた業界の長老が監督やっていることもあるんでしょうが、みんなにピリッピリに演じさせておきながら、その力みがまったく映画と絡んでこない。ひたすら演技者の空振りが伝わってくる映画でした。おつかれさまでした。
ところで、中盤で政府軍に嘆願書を渡そうとする場面があります。
応対した吉岡秀隆(演)の態度、変じゃなかったですか?わたしは爆笑しました。
吉岡秀隆が演じた岩村精一郎は終始、怒髪天なやつでした。(結ってはいましたが。)
ウィキペディアの岩村精一郎(岩村高俊)にこんなことが書かれています。
『北越戦争時に、山縣有朋が小千谷の新政府軍本営に着いた際、岩村は贅沢な朝食を地元の娘に給仕させており、激怒した山縣は土足のままその膳を蹴り上げたという。長州人の岩村への評価は「キョロマ」であり、木戸孝允も同様の評価をしている。
佐賀県権令としても、ドナルド・キーンの「無能で横柄な岩村の抜擢は、最悪の選択だったと言える」との厳しい評がある。』
(ウィキペディア、岩村高俊より)
なおキョロマとは古い長州の方言で「短気で考えが浅いやつ」だそうです。キョロマでぐぐるとトップにこの岩村精一郎の逸話がでてきます。
継之助の信念を描くためか、嘆願書をしつこく頼む場面が比較的長くとられていますが、そんなキョロマなやつに取り次ぎを粘るのも、なんだかな──でした。
司馬遼太郎の小説のなかでは悲劇のヒーローですが、河井継之助には賛否があります。新潟県民や郷土史家にもアンチがいます。
わたしは、継之助が良いのか良くないのか解りませんが、すくなくとも「短気で考えが浅いやつ」岩村精一郎役を吉岡秀隆が演ったのはかんぜんなミスキャストだと思いました。
吉岡秀隆といえば「短気で考えが浅いやつ」の逆です。少なめに見積もっても100人中80人がそう見るでしょう。笑わせにきてるとしか思えませんでしたし、じっさい笑いました。
また、常在戦場の箴言を知らず錠剤1,000錠だと誤解し、大殿が痛みどめをくれたんだ──いい大殿だなと思いました。きょうび変換が間違っていたとしても誰もそれを指摘しません。意味が通じてしまうからです。錠剤1,000錠でわたし的には完全納得でした。
さて映画は幕末の悲劇をあつかっており、それに対する認識としては、現代の平和は先代のひとびとの苦労のうえに成り立っているゆえに、諧謔的なレビューはきわめて不謹慎です。そんなことは解っています。ただ映画自体はあんぽんたんもいいところでした。
2022 189本目
“最後のサムライ”っていっぱい居るね
原作は司馬遼太郎。名作小説。
監督は小泉堯史。黒澤作品縁のベテランスタッフ。
主演は役所広司。仲代達矢、香川京子、田中泯、井川比佐志らベテラン、松たか子、佐々木蔵之介、吉岡秀隆ら実力派、芳根京子、永山絢斗、AKIRA、東出昌大ら若手…豪華俳優陣。
日本映画の匠が集った時代劇。これぞ格調高い日本映画。
格調高過ぎた…?
司馬遼太郎の原作小説は未読。既読者によると、半分も映像化されておらず、この映画版だけでは本来の『峠』を伝わり切れてないという。
またまた歴史に疎い恥を晒すが、実在の人物である主人公・河井継之助の事も全く知らない。ネット検索して本人の写真画像は見た事あったかもしれないが、ほとんど初めて知ったようなもの。
全くの無知でも勉強になり見応えある作品もあるが、今回ばかりは未読で無知者には敷居が高過ぎた。
長岡藩家老、河井継之助。
徳川慶喜の大政奉還後、東西に分裂し戊辰戦争が勃発した幕末日本に於いて、戦争回避と武装中立を目指す。
が、長岡藩も戦火に呑み込まれ、継之助も闘いの渦中へ…。
幕末の偉人は先見の明を持つ。新しきもの、開かれたものがこの国を発展させる。
それでいて武士としての誇りを失わない。
新しきと古き。美談と悲劇。
両極端の魅力を併せ持ち、その生き様と人物像はカリスマ性ある。
が、作品そのものに継之助のような魅力を感じられなかった。
戦闘シーンもあるものの、展開自体は淡々と平淡。
小泉監督と役所広司が組んだ前作『蜩ノ記』も同様だが、主軸がはっきりとし、ヒューマン・ドラマとして見応えがあった。
本作も継之助の生き様、歴史の悲劇的な逸話、夫婦愛などの魅力ある要素を含んでいるが、う~ん…噛み合っていないと言うか、どれを主軸に置きたいのかぼやけている。
各エピソードも原作小説を要所要所かいつまみ、ただ並べただけにしか感じなかった。よって、テンポも盛り上がりも引き込みもあったもんじゃない。
作品の質は高い。日本映画の匠の技。
が、演出や脚本が今一つ。
“昔ながら”や“古き良き”の精神は欠けがえないが、それが時に作品や日本映画を停滞させる節がある。
作る側や演じる側は本当に作品を理解し臨むのだから、天晴れと思う。
が、時々それが見る側に伝わらない事も…。
作り手の書き込み不足か見る側の理解力不足か、否はどちら側にもあるかもしれないし、無いかもしれない。
何だかそれは皮肉だ。作品に掛けて言うなら、悲劇だ。
未読で無知の自分はここいらで黙るとしよう。
最後に強いて言うなら、
“最後のサムライ”ってあちこちいっぱい居るね。
やはり文庫本「峠」のなかの河井継之助がすべてでした
あの小説を映画にするって、難しいんじゃないのかなあ・・。
知人から、司馬遼太郎の「峠」が上映されると聞いたとき、ふと感じました。
映画は、小説のなかから場面を慎重に選びとり、役所広司と松たか子のすばらしい演技で、凛々しく、美しく、哀しい物語りにまとまっていたと思います。
ただ、小説であれば、たくさんのエピソード、人との出会い(たとえば吉原の小稲、松山藩の山田方谷、福沢諭吉など)が延々と続き、それを読むうちにだんだんと河井継之助という強烈な個性がこちらに染み込んできて、いつしか、継之助の感じ方や判断・行動を「なるほど、そうするのしかないのだろうな」と納得し共感するようになります。
そのような継之助のイメージが映画の前半で観る人のなかに創り出せないと(時間的に無理だと思いますが)、たとえば小千谷談判の場面で、いつもらしからぬ継之助の忍耐、へりくだり、逡巡、最後に痛切な悲壮感をもって諦め、これが激烈な戦争突入へのエネルギーに切り替わるのですが、これは演技だけで表すのは無理で、「・・・こうして戦争になってしまいました」という単なる説明になっていると思います。
ガットリング砲がなにかおもちゃのようにしか見えないとすれば、それはガットリング砲に託した継之助の強い長岡平和希求の気持ちと、入手までの努力がわからないからです。
「峠」はやはり司馬遼太郎の文庫本二冊でじっくり楽しむものだ、という直感は当たったような気がします。
河井継之助の人となり・思想・哲学が語られていない
風雲のなかで独立する!
歴史には無知なのだが、戊辰戦争の旧幕府側のメインキャストとして徳川慶喜、松平容保、伊達慶邦と並んで河井継之助の名前は聞き覚えがある。が、北越戦争の総督だったとは知らなかった。
長岡藩が新政府軍(西軍)と佐幕派(会津藩)との調停役を果たそうとしていたこと、自藩は独立国を目指していたこと、更にはそれらは継之助の強い思いだったことが説明される。
どうやら、継之助にスポットを当てたのは司馬遼太郎が最初のようだ。多分に司馬の創作が含まれているようだが、「峠」によって継之助は広く知られる人物になったらしい。
徳川幕府も、徳川家を敬い奉る大名たちも、尊皇の意識は高い。慶喜の大政奉還を大英断だと解釈している家臣たちにとっては、徳川に逆賊の汚名を着せる薩長の暴挙は許しがたい。
一方、薩長の目的は徳川幕府の掃討だから、調停の余地などない。
佐幕派も義を貫くことだけに固執したわけではなく、家臣や領民の命を守るために戦争回避の努力はしている。映画で描かれた長岡藩の嘆願書だけでなく、会津藩ほかの各藩も天皇への恭順を示して嘆願していたが、新政府軍は受け入れなかった。
武士たちが侍であり続けようとすることで、勝ち目がない戦に突き進まざるを得なくなる悲劇。その時代のうねりの中で長岡藩家老河合継之助という男が、いかに振る舞い、いかに死んでいったか。この破滅の美学を、江戸時代最後の僅か1年間で描く。
自分には、継之助に最後まで付き従った奉公人松蔵(永山絢斗)に、他の侍たちの誰よりも美しさが感じられた。
映画の冒頭に継之助が指揮を執る軍事訓練シーンがある。鉄砲を持った足軽たちが隊列を組んで射撃をするのだが、この様子がなんとも頼りない。狙った演出であれば、だから戦には勝てないのだと印象付ける効果はあったが、そうではないように感じた。エキストラの統率が取れていなかったのだろうと思う。
小泉堯史監督率いる黒澤組スタッフが作り上げた作品という評価を耳にするが、黒澤明は大人数のエキストラを使った場面でこそ画面の端にまで緊張感をもたらす統率力があった。
戦闘場面としては長岡城の攻防戦などが描かれるが、迫力がないとは言わないものの、映画的スケール感をもっと出せなかったものだろうかと、残念に思う。
新政府軍は物量で圧倒したはずだが、それが見えないので長岡藩の善戦ぶりも伝わらない。
小泉監督は一人の侍を淡々と描く力量は高いと思うが、スペクタクルは師匠には遠く及ばない。
ならば、人物描写に重心が置かれているのかと言えば、それほど深掘りされてもいない印象だ。
繰り返すが、私は歴史に無知で河合継之助という人物のことを知らない。
彼がなぜ独立を主張するに至ったかは全く描かれていないし、それに対する長岡の藩論についても触れられていない。
これが、あえて説明するまでもない周知のものなら、自分の無知を恥じるだけだ。
特段の活躍を見せるわけではない幼馴染みの藩士川島(榎木孝明)や藩医良運(佐々木蔵之介)といった仲間を登場させているのに、反対意見の者は出てこない。
北越開戦へのターニングポイントとなる新政府軍監岩村精一郎(吉岡秀隆)との会談の描きかたも軽い。史実として岩村は継之助の嘆願を一蹴したのかもしれないが、岩村には岩村の思想があり、継之助の何かが気にいらなかったのかもしれない。もう少し議論の内容に踏み込めなかったものだろうか。吉岡秀隆をキャスティングしてるのだから。
北越戦争の戦況もよく見えない。継之助の指揮がどのように戦況を左右したのか、沼を渡って城を奪還する作戦くらいしか描かれていない。
どれかひとつでも深掘りしていれば、ドラマに厚みが出ただろう。
この映画は、「河合継之助について予習してからご覧下さい」とか「原作を読んでから劇場へ」という断りを入れるべきだったと思う。
「長い台詞回し」久々に観賞
幕末は面白いなぁ
幕末でよく語られるのは、新撰組や薩長の志士たちの戦いだ。そのら誰に焦点を当てるかに寄って、いろいろな話があるし、どれも面白い。
今回はそんな幕末の雄藩に立ち向かった、小さな藩、長岡藩の話だった。これをみると、戊辰戦争の影に語られなかった当時の武士の生き様、心意気を感じる。
天皇を担ぎ出して、まんまと官軍になり、徳川を賊軍に仕立てた薩長のやり口に反発。長いものに巻かれて寝返る数々の藩の中、自分達の正しいと信じる道をすすむ。方針だけ決めてあとは家老に完全に任せる殿様もあっぱれなら、全てを背負って最後まで突き進む最後の武士の姿は、本当にかっこよかった。松たか子が芸者遊びに連れて行かれて、芸者と一緒に踊るシーンは所作がとても美しかったこと、役所広司が話すセリフに日本の武士の覚悟が詰まっていたこと、仲代達矢の存在感、などなど私にはとてもいい映画だった。
役者はいいが、シナリオはプア
原作は好きだ
10年以上前に原作は読んでとても面白かった。長大な原作の前半は河井継之助が江戸に上京する若い頃の話でとても面白いのだけどそこはばっさりカットで、戊辰戦争からを映画化で、ダイジェストにするより正しい判断だ。
バルカン砲がそれほど威力を発揮していないのも原作通りで、原作で新発田藩にムカついたのもそのままムカつく。
悪くはないけどそれほど感動や興奮はない。
ロングランだそうで
見せ場や山は無い
河井継之助
何を観せられたのか…
恥ずかしながら原作未読なので、この作品だけでは何が何だかよくわからない。サムライ魂は結構だが、全く勝ち目のない戦に突入せざるを得なかったのは何故なのか。無謀な戦争に突入して行った日本軍が好んで使っていた大和魂と大差ないようにすら感じてしまう。そんな義に殉じる「滅びの美学」的価値観のサムライの話なら、別に今更観たくもない。「民の安寧」「自由と権利」などという言葉も空疎に響く。
きっと止むに止まれぬ何か、があった筈。明治維新政府が必ずしも正しいわけではなく、徳川200年の平和な時代など近代史は色んな角度で再評価されている。
これは原作を読まなければ。しかし原作の助けがなければ理解できないようでは、映画作品として成立しているのだろうか…。
画的に好きなシーンがいくつかあったことや、作品の「間」が良かったので3点にしましたが、内容的には…。
新たな日本を誰より見たかった男の最後の悪あがき!!
侍の世が終わりを告げようとする時代。そんな空気感を誰よりも敏感に感じ、新たな日本の夜明けを見据えていた河井継之助。
そんなの継之助視点から描く、激変の日本。
西洋文化を柔軟に受け入れてきた男が、その想いとは裏腹に、自分の侍としての立場が邪魔をする。誰よりも新たな日本の姿を見たかった男が、それが叶わぬ方向に向かっていってしまうもどかしさと、葛藤をじわじわと描いた人間ドラマ。
そのため、侍のチャンバラ映画だと思って観ると失敗する作品だ。
日本を代表する新旧役者陣の緊迫感のある掛け合いという点においては、十分に見応えはあるのだが、チャンバラがないというのも合わせて、全体的に地味な画が続くため、エンターテイメントとしての見応えは全くない。
若い世代の心を打つような要素は皆無であるし、こういった時代劇でありながらチャンバラの少ないドラマ重視作品を好む層というのがいなくなっているのが現状。
そんな需要の変化が、皮肉なことにタイトル同様、最後に向かっているような気がしてならない……。
映画としての構成は破綻しているため、歴史好きという人が辛うじて楽しめるか……といったところだ。
全180件中、41~60件目を表示