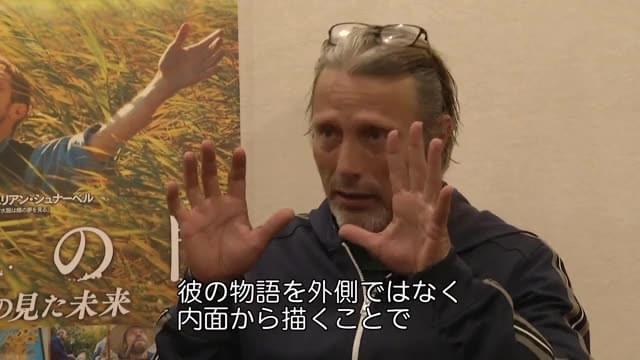永遠の門 ゴッホの見た未来のレビュー・感想・評価
全118件中、41~60件目を表示
この画家を呼ぶのに天才という言葉は果たしてふさわしいものなのか。そんな想いが頭に浮かびました。心の内側が伝わってくる作品です。
この作品の前に、ゴッホをテーマにした他の作品(※)を観たのですが、
ゴッホの人物像が余り描かれていないような気がしました。
この作品ではどうかな、と気になって鑑賞です。
( ※「ゴッホとヘレーネの森」 )
この作品の中では
人間的な面が充分に描かれていたと思います。
悩みこだわり
自信にあふれたかと思えば
自信を失い、取り戻し
心を病んで
最後は…
この作品で
ゴッホの全てが理解できたとは言えませんが
彼の 「作品を産み出す力の源」 が
何となく分かった (ような)
そんな気がします。
自分の描く世界 それが
世の中の求めるものとは違う そうと知りつつ
描きたいものを描く
ただひたすらに描く
…
それしかできない作家だったのかもしれません。
☆ 余談です
弟の存在
時に兄のようにさえ見えました。
ゴッホの精神的支えだったのでしょうか。
彼がいてくれたことが救いです
ゴッホを演じた俳優さん
自画像から抜け出してきたかのようでした。 すごい似てる…
ゴッホを扱った映画
このところ多く作られているようですが その中で
「ゴッホ 最期の手紙」
この作品もすごく観たくなりました。 ( 油彩画がアニメーションする作品 )
どうしようか思案中です。
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
美しかった。
何にフォーカスしているのか
耳はどうなった?
今までゴッホ関係の映画では『炎の人ゴッホ』(1956)、『ゴッホ最期の手紙』(2017)くらいしか観てませんが、ともかく生前には評価されずに死後になって絵が評価されるようになった画家としか認識してません。そして耳を自分で切ったという狂気、「ひまわり」がバブル期に約60億円で売却された事実。
なんだか最後には耳が元通りになってたような気がして、再生するんか~?などと感じてしまった。ちょっと時系列もわからなかったのが残念。その中でもマッツ・ミケルセン演ずる聖職者とのやりとりで概要がわかり、ゴッホの心の中を垣間見た感じがした。
最期には撃たれたにもかかわらず、少年たちが罪に問われるとして黙ったまま死を迎えることになる優しさに驚いた。定説では自殺。しかし、銃の暴発によって誤射されたとする説も有力になっているという。
身体から湧き上がるゴッホの心情、共感
何かを描く際のゴッホの心情や信念に共感覚え、思いを共感し会える友人関係や、傍観者の冷たい視線浴びせられた切ない心境に痛感、胸に突き刺さった
ピアノの躍動感溢れるBGM背景に、身体全身で湧き上がる感情を想いのまま表現していて、アカデミー賞にノミネートされたウィレム・デフォーの演技に圧倒された
銃弾を受けた日まで絵を描いていた
ストーリーは
1880年代パリ。
若い画家たちがカフェで、いかにして絵を売って生活していくかで画商と交渉をしている。ゴーギャンは作家たちが絵を描くことよりも、売ることに汲々としていることに腹を立てる。自分は自由を求めてマダガスカルに行くつもりでいる。友人のフィンセント ゴッホには、ほかの画家たちとつるんでいるのを止めて、南の温かいところに行って絵を描くように勧める。彼の言葉に従って、ゴッホは南フランスに移り住むことにする。
底の抜けた靴、穴の開いて指が見える靴下、身なりかまわずゴッホは、田舎の景色のなかに身を浸し、風景を写し取る。陽光を浴び、風景を描き続ける。しかし教養の無い田舎の百姓たちにとって画家の姿は異質で、異様だ。田舎の子供たちは画家をからかい、写生する画家を妨害する。怒ったゴッホは子供たちを怖がらせたことで、警察によって精神病院に強制入院させられる。呼び出しを受けて、パリから飛んでやってきた弟のテオに、フィンセントは、じつはこのごろ幻覚が起きて、見えないものが見えたりするんだ、と告白する。しかしパリで画商をしているテオは、忙しくフィンセントにずっと付き添ってやることなどできない。送金の約束だけして彼は兄に、あまり悩まずに見えるものを描き続けるように励まして、自分はパリに帰る。
やがて、ゴーギャンがマダガスカルから、パリに帰って来た。ゴッホはゴーギャンと一緒に住んで、互いに活力を得て、画業に集中する。しかし強い個性を持った男同士の共同生活には、すぐに無理が生じて、ゴーギャンは出ていく。ゴッホは、ゴーギャンに謝罪の意味で、片耳を切り落とす。再び彼は精神病院に入院させられる。
しばらくして、病院長から呼び出され、どうして醜い絵ばかり描くのか、と彼は問われる。ゴッホは自分は神から才能を与えられた。自分にしか見えないものを人々に見せたい、という。彼は退院を許されて、再びマダムジヌーを世話になり宿屋に戻って絵を描き続ける。しかし田舎の地元では、頭のおかしい画家ゴッホを嫌う人が多かった。ワインを浴びるほど飲み、人と関わろうとせず、孤立しているゴッホは、ある夜二人の若者のトラブルに巻き込まれて、腹部を銃で撃たれ、その傷がもとで亡くなる。弟テオがパリから駆け付けた時、彼は息を引き取った。’
というおはなし。
ゴッホのような目を持てたらどんなに良いだろう。果てしない広がりを持った世界で、感性を思い切り自由に羽ばたかせながら生きることができるだろうか。
「ひまわり」を描くゴッホの目には、水々しいひまわりのつぼみが、やがて朝露とともに広がり、強い太陽に射すくめられた末についにしぼんでいく、そのすべての過程が見えていたのだろうか。「アルルの女」を描いているゴッホの目には、ジヌー夫人の強靭な精神に裏付けられた穏やかな人柄と、彼に対する同情、憐憫、母心、包容力、死ぬまで世話を焼いてくれた友情までが見えていたのだろうか。「ガシェット医師」を描くゴッホには、ドクターの自信と誇りをもった、でもユーモアとウィットに富む田舎紳士のほがらかさや人の善さが見えていたのだろうか。
ゴッホは精神医学的にいえば、精神病質に生まれて精神分裂症を発症した患者、社会学的に言えば、全く生活能力が無く、生活のすべてを弟テオの送金に頼っていた上、社交で人と関わることも出来なかった反社会的で、人格障害をもった人間だ。
しかし彼ほど切実に自分の見た物を描こうとして真摯に生を生きた画家はいない。人には見えない永遠の命を描いて人々に見せたい。自分は一生表現者として描くことが自分の使命だと信じて描き、その決意は死ぬまでゆるぎなかった。
映画でゴッホを演じたウィルム デフォーは、この映画でベネチア国際映画賞で主演男優賞を受賞した。アカデミー賞主演男優賞の候補にあげられたが、「ボヘミアン ラプソデイ―」でプリンスのフレデリック マーキュリーを演じたラミ マレックに賞を持っていかれた。ボヘミアン ラプソデイ―を切っ掛けに、プリンスが再び大爆発的な脚光を浴び、ヒットチャートを記録して大ブームを引き起こしたので仕方がない。第91回2019アカデミー賞会場でもプリンスの、71歳で依然としてかっこいいブライアン メイと、69歳のロジャーテイラーがパフォーマンスのトップを飾るなどして、2019アカデミー賞は、プリンスで始まってプリンスで終わった。プリンスの電子音に比べると、フィンセント ゴッホの世界は何と繊細で孤独の世界だろうか。
監督ジュリアン シュナベールは画家でもある。監督した作品には「潜水服は蝶の夢を見る」(2007)と、「夜になる前に」(2000)などがある。
彼は、「ゴッホの伝記はすでにたくさんの監督によって製作されているが、ゴッホの目では世界がどう見えていたのか、という視点で映画を作りたかったのだ」と言っている。
映画は、ゴッホのモノローグで語られ、彼の目線で見たものが映されている。彼の目がカメラになると人との会話では、ハンドカメラで相手がズームアップされる。カンバスを背負って穀倉地帯や森や丘を歩き回る時は、カメラがずっと下がって大写しになる。ハンドカメラが接写と遠近を繰り返すカメラワークは、ゴッホの主観を接写で、客観を遠くで捉えることで表している。これで酔う人が出たそうだ。
ゴッホが南フランスの穀倉地帯や森や丘を歩きまわる。広々とした自然の中で風に吹かれ、光に身をまかせ、永遠を感じる。陽の上がるのを待ち太陽を全身に感じて心を解放させる、そうして描いてきた風景が、精神病院で療養するごとに、徐々にぼやけてくる。風景の半分がよく見えない。徐々に蝕まれていくゴッホの精神が、ぼやける映像によって事実になっていく。彼は見た物を描く。ぼやけていても見ればそこに真実がある。そうやって彼は最後に銃弾を受ける日まで絵を描いていた。
映画のシーンで、ゴーギャンがジヌー夫人を座らせてデッサンを描いている。そこにゴッホが帰って来る。するとやわらゴッホはカンバスを立て、いきなりオイルでものすごいスピードで描き出す。ジヌー夫人はさっさと去っていくがモデルが居なくなってもゴッホは記憶をもとに描き続ける。そんなふうに油絵を完成させてしまうゴッホを見ながら、ゴーギャンーは、「描くのが速すぎるよ。どうしてゆっくり描けないの。」と言い、さらに「君の絵は塗って、塗って、重ねて塗って、まるで彫刻をつくるみたいだ。」とあきれる。二人の天才画家の会話が興味深い。
1853年に牧師の子供として生まれ、1890年に37歳で若くして亡くなったゴッホは、2000点以上の作品を残したという。2017年に彼のデッサン帳が新たに見つかった。
宿屋でシェイクスピアの「リチャード3世」を読んでいたゴッホに、ジヌー夫人が、「そんなに本が好きなら本をあげるわ。でも何も書いてない本なのよ。」と言って分厚い本をゴッホに渡すところで、この映画が始まる。ゴッホはそれをデッサン帳にして持ち歩く。彼によって描きためられたこのデッサン帳が、彼が精神病院から退院したときに他の病院記録などと一緒に放置され、ずっとあとになって21世紀を生きる人々の手に渡る、そんなシーンで映画が終わる。ゴッホは永遠だ、とでもいうように。ミステリーが好きだと、映画の中でゴッホに言わせている。そんなミステリーっぽい終わり方がしゃれている。
とても印象深い映画だ。
ごめんね
全然響いてこなかった。0.5点はパリ在住のメイクの薮内綾さんをロールで見つけたから。
ゴッホについては何度か展覧会も行き人生も少しは知っていたつもり。評価されるのを待たず38歳で苦難のうちに早世した半ば狂った(失礼)画家の生き急いだ感覚、果たしてデフォーでどうなの?好きな俳優で演技しまくっているのは見ればわかるだけに起用に納得いかない。
パリ、アルル、有名俳優を起用した画家の人生についての物語。いくらでも見せられるものがあるのに、なぜもう少しでもため息が出るほど美しい映像を見せてくれないのか。ポスターの美しい写真に騙された。
最後、2016年にスケッチブックが見つかった、って字幕で説明。TVドキュメンタリーのつもりなのか。
#105 なるべく後ろの席で
観てください。映画の日でめちゃ混みで1列めで観たから顔がドアップなシーンが多くて辛かったです。
ゴッホの死因とか弟に養ってもらってたとか知らないことが多かったのでそれは良かった。
さらにセリフがゆっくりで綺麗な話が多いのでドアップの字幕を観なくても楽しめる部分は良かったかも。
絵を堪能したい方はともかく後ろの席で❣️
気持ち悪くなる揺れ
始まりから画面が揺れ続ける。
ゴッホの視線?を意識しているのか。しかし人間は走っていても、脳で認識する外部の映像は揺れない。揺れないように脳で調整している。外部を認識するために。
必要以上の揺れ演出が私には受け入れられなかった。
だいぶ今までのゴッホの生い立ちと違った解釈をしているようで、これを史実と解釈するのは違うだろう。監督の解釈?なのだろう。
ただ画面から南仏の明るい陽光を感じることは出来なかった。
また、画面半分下がボケているのも何を意味するのかわからなかった。眼鏡をかけてはいないがゴッホは眼病を患っていたのか。
デフォーは歳が違うがゴッホが描く自画像のようで適役なのだろう。
神と自分を重ねるのはいただけないが、最後まで世間に受け入れられなかった“天賦の才“を持つ人の悲しい半生をこの監督の解釈で描いた映画。
“僕に見えるものをみんなに見せてあげる”- V・f・Gogh
映画が始まってからずっと頭に浮かんでいたのは「何故人間は絵を描くのだろう」ということ。「人間」はともかく何故ゴッホは描くのだろう、何故あの様な絵を描くのだろうということに映画は迫っていく。それと、私の子供の頃から時々頭を掠めていた「果たして人は同じ光景を見ているのだろうか。共通幻想として見えていると思いたがっているだけではないのか」という疑問が思い出されてくる(個人的に)。
asylumでのマッツ・マケルセン扮する神父とゴッホとの間に交わされる会話の豊潤さは凄い、しみじみと余韻が残る名シーンだ。ウィリアム・デフォー好演。受ける、マッツ・マケルセンも見事。自分の目に写る世界の、自然の真実・力を彼独自の絵で後世に残すことだけを考えて描き続けた1画家の物語。「本当の花の方が一般人には美しいかも知れない。でもそれはいつか枯れてしまう。でも僕の描いた絵の中の花はいつまでも色褪せない。じゃあ、私も描いてもらおうかしら。若さを残して貰らうために。もっと若くもかけるよ。それはフェはじゃないわ」…
視界
よく寝れた。
ゴッホの事は良く知らない。絵画に興味がある訳でもないし、ルネッサンスとかも単語を知ってる程度だ。
なので…全く良くわからない。
この映画の脈絡についていける人ならば面白いのであろう。この映画を観ただけでは、天才と狂人は紙一重って事くらいしか分からない。
まぁ、だいたいからして独自の世界観があるからこその芸術家なわけで…それを解説したり、共有したりなど出来るわけがない。
彼は言う
「僕の世界を皆んなに見せてあげる」
もう唯我独尊まっしぐらだ。
うつらうつらしながら観てたから良く分からなかったのかと思ったのだけど、そうでもなかった。
ある日、ゴッホは少年に撃たれる。
それが故に命を落とすわけなのだけど…。
映画としても突然だった。
この事件は結構認知度が高いのだろうか?
なんらかの確執があるようなのだけれど、全く説明不足で訳がわからない。
おそらくなら全編そんな感じの編集で、時代は飛ぶは、ネタも飛んでいくのだろう…。
面白いなぁと思えたのは、作品のモチーフが随所に登場するところかな。
それとゴッホの黄色と言われるように、作品中に様々な黄色が登場する。
その描写は素敵だった。
模写と言えばいいのだろうか?贋作は的外れなような気がする。ゴッホが残した絵画たちも目に楽しかった。
後はまあ…ゴッホの視界なのだろうけど、時折画面の下がボケる。
ちょっと傲慢かなぁと考える。
他人が見てるものがどんなものかなんて、その人にしか分からない。
「こんな風に見えるんだ」と話しを聞いても全てを共有できるわけもない。
ましてや、天才なのか狂人なのか「見てる世界が他の人と違う」と宣う芸術家だ。
そんな人物の視界を模倣したところで何になると言うのだろう。
生前は認められる事のなかったゴッホ。
死人に口無しとはよく言ったもので、どんな解釈でどんな虚像を作り上げられても反論の1つも出来はしない。
デフォーを観たくて行ったのだけど、結構な予備知識がないと、そのデフォーさえも観れない作品だった。
ゴッホ好きしか見ちゃダメ
天才を理解するのは凡人には難しい。
ゴッホ
ゴッホを名前しか知らない人にはgood!
画家のほんの一瞬
小説で言えば、純文学的な
最初の15分位、退屈で、失敗したかな?と後悔しかけました。
途中からは、ゴッホの報われないけど、ただひたむきに、中から涌き出る物を信じて描き続けた一生、弟テオだけが理解者だった、知るとなおさら、ゴッホの絵の黄色が、心に迫ります。
ストーリーはあるような、ないような。退屈でしたが、ゴッホ役ウィレムデフォーの演技、南フランスの農村の黄金色を堪能しました。
皆さんが書かれてるカメラ酔いは、私は大丈夫でしたが、ゴッホ視点とは言えあそこまでグワグワ振り回す必要はあるのか?とは思いました。
ゴッホ展
現在開催中のゴッホ展にいきゴッホの人生に興味を持ち、この映画を観てみた。
恥ずかしながらウィレム・デフォーの出演作を2、3作しか観ておらず、しかしそれが却って良かったのか、鑑賞中彼の演じるゴッホがまるで本物のゴッホのように錯覚してしまった。ゴッホは37歳で亡くなるので30代を演じているのだろうがデフォーの顔のシワや年老いた表情は不自然ではなく、ゴッホの苦悩を自然に表現していた。
ウィレム・デフォーの映画といっても過言ではないが一見の価値はある。
少々残念だったのはフレームをボカした映像で、自分が思うゴッホの目線とは違っていたこと。
全118件中、41~60件目を表示