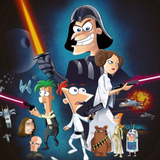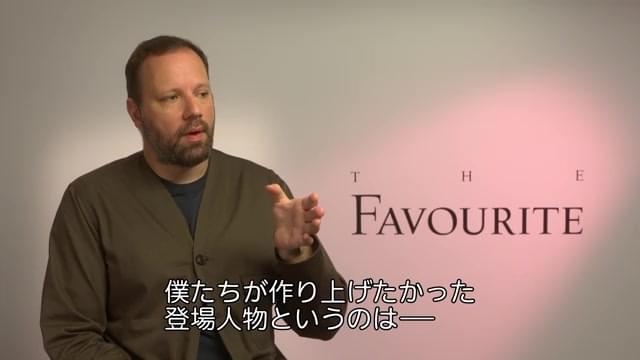女王陛下のお気に入りのレビュー・感想・評価
全293件中、241~260件目を表示
嗅覚
最初の章の、例の「泥」から、自分には 視覚と同じかそれ以上に嗅覚/臭覚をつつかれた作品でした。
えええと、表現が下品かもしれませんが女王陛下が着飾っていいもん食べててもなんだかシーツの下から臭ってきそうな、あの重ねたドレスの内側の布から糖のにおい?や生傷の血のにおいがしてきそうな… そんなところを果敢に攻めてたのかエマったら。。。
部屋のなかも荘厳なんだけどウサギやアヒルの動物臭がしてきそうとか、蔵書のにおい、下女たちの醜悪なにおい、男たちの化粧、その下のたるんだ身体からわいて出てそうな刺激臭、宮廷の裏通路の閉塞した臭気? 瘴気? ローソクやタイマツからの酸化した油のにおい、などなど。。。
こういう映画はなかなかなくて、大昔にみたピーター・グリーナウェイの「コックと泥棒、その妻と愛人」でもそんな感じしたの思い出しました、、うーんでも今回は腐敗臭めいたのはなかったからやっぱりちょっとちがうかな。。
嗅覚は 強烈に記憶に残りそうな印象があって、それぞれに何かの意味やメッセージを孕んでるんじゃないかとか、そういうとこで楽しめました。
それにしてもエマ・ストーン、自分的にはあの人、とても派手な顔立ちにもかかわらずこざっぱりして見えるんですよね、冷水で洗顔したての顔とか・ 「ラ・ラ・ランド」では感じなかったのにな、、
あ! 「マーヴェリック」のときのジョディ・フォスターと似てる、そいえばヘアスタイルが似てましたね。
ノブレス オブリージュ
まず…映画の感想からはズレますが…
今日も上映中、2人の携帯が鳴った。
…ふう。
気を取り直して。
セリフや名称(特に人物の呼び方が複数ある)をちゃんと聞き、展開されている行為や表情の意味をしっかり追っていかないと部分的に見失ってしまうかも知れないが、ストーリーの大筋は比較的シンプル。
かと言って、全てが説明されている訳でもなく、解釈は観客に委ねられている部分も多い。
一筋縄ではいかんな、というのが率直な印象の映画。
でも、観て良かった。
まず、美術や衣装が素晴らしい。これ見るだけでも価値がある。
そして、それを効果的に見せるカメラ。また、広角レンズで捉えた映像はただでさえ情報量が多いのに加えて、カットを割らずにカメラを180度横に振って別々のシーンが1カットに構成されていたりするので、まるでかぶりつきの席で舞台を観ている感覚にも似ている。
ほぼすべての登場人物は自分のエゴのために行動し、そのぶつかり合い・足の引っ張り合いが、時にコミカルに、時に皮肉たっぷりに描かれる。
しかし、そうして手に入れた地位にも、やはり責任と同時に苦しみや憎しみ、自分を利用しようとする敵や味方が存在するという「堂々巡り」。
目指した場所、手に入れた場所、そこに本当に幸せはあるのか。
序盤はエマ・ストーン演ずる主人公アビゲイルの下剋上を応援していた我々観客も、後半では苦々しく彼女を見守るようになり、最後はキャストの全員が哀れにさえ見えてくるという、なかなか悲痛な映画なのだが、もしアビゲイルを彼女以外の女優が演じていたら、さらに陰湿な感じになってしまったかも。そういう意味でこのキャスティングは正解だった気がする。
そして女王役のオリヴィア・コールマンの名演。インタビューの姿と比べると特にその凄さがわかる。
観賞後、
「世界の全ては女性が動かしているのです。」
そんな気にさせられる映画。
だって、ここに出てくる男達のだらしなさ・軽薄さときたら…
追記:
女王が鎧のような物を着けるシーン(これは何のシーンだったんでしょう?)で流れるパイプオルガンの曲って、『カリオストロの城』でクラリスと伯爵の結婚式で流れる曲ですよね?
勝ちは負けで,負けは勝ち
サラにとっては,アビゲイルに「自分は勝った」と思わせておくことが勝利だったのではないか?
*
女王からの愛を失い,王宮から追い出されたサラ。
女王に手紙をしたためる。
だがアビゲイルは,女王が読む前に手紙を抜き取る。
そこには女王への愛と「忠実なサラより」という言葉が綴られていた。
手紙を女王に見せず、焼き捨てたアビゲイル。
「サラが国庫から横領していた」と女王に告げる。(横領の真偽は定かではない。)
女王はサラ夫婦の国外追放を決定。サラの邸宅に使いを送る。
(【2/23追記】女王はアビゲイルに対しサラの横領を認めなかったにもかかわらず、政治家たちの前でアビゲイルの讒言を根拠にサラの国外追放を決定する。これは女王の保身のためか?サラを自由にしてやるためか?はたまた、横領を知っていたか、自分がサラに金を渡していたか?)
窓から追放使節の一団が到着したのを眺め「手紙の返事が来た」とつぶやくサラ。
明らかに,やってきたのは手紙ではない。だがサラに驚きの表情はない。
まるで自分が追放されることを予期していたかのように。
まるで,女王の愛を取り戻すための手紙を送れば,アビゲイルがそれを盗み見て,自分を徹底的に排除しようとするであろうことを予測していたかのように。
サラの手紙を見たアビゲイルが、讒言によって自分を追放しようとするであろうことが予想されたのであれば、サラの手紙の真の宛先はアビゲイルであり、追放こそがアビゲイルからの返信なのだ。
ではサラは、国外追放されることによって何を得るのだろう。
それは「アビゲイルに勝たせること」(勝ったと思わせておくこと)である。
アビゲイルはサラに勝って女王の寵愛を得た。サラが再び、アビゲイルの競争相手になろうとすれば、アビゲイルは自分が得た地位をより堅固に守ろうとするだろう。自分が守ろうとしているものが、自分にとってどんな利益をもたらすかもよく考えずに。
自分にとって利益にならないものであっても、それを他者が奪おうとすると、なぜかそれを奪われたくないと感じ、競い、相手を蹴落とそうとする。しばしば人間に見られるこの習性をサラは利用したのだ。
こうしてアビゲイルは女王との親密な関係を守り抜く。サラに勝ち、自分は女王を手中に収めたのだ、と勝利した気になる。だが長い目で見れば、それは敗北である。なぜならば、女王に対して偽りの献身を続けなければなないからだ。愛してもいない女王に対し、愛情表現をし続けなければならないからだ。そのことに気づきつつあるアビゲイルは涙を流し、女王もまた、自分に言いよる者たちの愛情が嘘か真かを見極めることに疲れた表情を呈する。
ただ勝利だけを手にした(と思いたい)のはサラも同じである。彼女も政治的な地位を失い、国を追われて、実利のない勝利だけを手にする。
アン女王、アビゲイル、サラ、三者三様に、それを獲得した瞬間は興奮こそすれど、時間が経ってみれば中身がなく虚しいと気づく勝利だけを得て物語は終わる。
愛を偽ること。本当の愛情。これはヨルゴス・ランティモス監督が前々作『ロブスター』で設定した構図でもある。
主人公は愛することを強制される環境では真実の愛を見つけられず、動物に変えられないため止むを得ず愛しているフリをする。
だが恋愛禁止のレジスタンスのもとに逃げ込んだ途端、真実の愛を見つける。
女王を愛する者は女王の要求とは逆のことをする。女王を愛していない者が女王の要求通りのことをする。その内外のギャップに,女王は苦しむのである。
このような「逆張り」を,ランティモス監督は今作でも見せたかったのだろう。
*
アビゲイルが手紙を盗み見るだろうことを,サラは予期していた。なぜそう言えるのだろうか。
それは,はじめ女王に対し憎しみの込もったメッセージを送ろうとしていたサラが,逆にご機嫌をとるような手紙を送ったからだ。
女王にとってのサラの価値は,ご機嫌とりではなく,厳しい言葉をかけることができることにある。女王を叱咤し,発破をかけ,高いレベルに引き上げようとする点にある。それがサラの"正直者"としての魅力である。(女王に対しては皆ご機嫌を取ろうとするので,女王を不快にさせる言葉を発することのできる者は正直だと思いがちだが,実際にはそうではない。「正直者」というサラのキャラクターも,半分は本当,半分はサラが自分自身に課した設定なのかもしれない。)
だとするならば,まさに憎しみこそサラが女王に伝えるべき言葉ではないのか。率直に憎しみを伝え,彼女の魅力をアピールすべきではないのか。ご機嫌とりの言葉をかける人物なら,アビゲイルで十分ではないか。
ご機嫌とりの言葉をかけたとしても,女王に対し,サラは自分を魅力的に見せることはできないのである。
それゆえ,サラがご機嫌とりの言葉を手紙に記すとすれば,それはアンに読ませるためではなかった,ということになる。
だがアビゲイルは,ご機嫌とりの言葉こそアン女王にかけるべきだと思っている。アビゲイルには女王がサラを愛する所以がよくわからないのだとすれば,サラが手紙に記した愛の言葉は,サラが女王への愛情を取り戻そうとしているように思えただろう。それゆえ,アビゲイルの目にはサラが脅威に見えるのである。
*
はじめサラは,女王に手紙を書くにあたって「あなたの眼を串刺しにすることを長い間夢見ていた」と書き記す。これはサラの本心だったのかもしれない。
だが仮にアビゲイルが手紙を盗み見るとしよう。サラの本心=女王への憎しみー実際には愛情も入り混じった「愛憎」とも呼ぶべきものなのだがーをアビゲイルが知ったとしたら,サラが女王の元を離れ,自由になれたのは,サラの勝利である。(もちろん,女王に取り入ることによる政治的・経済的なメリットは大きいのだが,その見返りとして,女王によって拘束されなければならない)
もしも「女王から離れること」が勝利だとしたら,アビゲイルは自分が今女王のそばにいることが敗北なのだと気づいてしまう。確かにアビゲイルは女王のそばにいることによって,最初のうちはたくさんの見返りを得るだろう。失ったレディの地位を回復し,豪奢な生活を送る。
だがやがて倦怠期が訪れるだろう。愛してもいない女王への愛を偽り続けることに疲れるだろう。ラストシーン,アビゲイルの感情を失ったかのような表情は,すでにその始まりを感じさせる。愛情を偽ったまま奉仕し続けることへの絶望感。
「感情を偽って奉仕し続けたくない」「早めに女王の元を離れよう」とアビゲイルに早々に気づかれては,サラは困るのだ。女王の寵愛を得てサラに勝利したという余韻に浸らせておき,気づいたら拘束され感情の自由を失っていた。そのような状況にアビゲイルを陥れることが,サラにとっての1つの勝利である。
もちろん,サラは政治的な地位を失った。そのため,全面的な勝利はあり得ない。サラはアビゲイルを鎖に繋いだことで,アビゲイルに勝利したと言えるし,アビゲイルは女王のお気に入りの地位からサラを蹴落としたことでサラに勝利したとも言える。
女王は,命じたことをなんでもやってもらえるがゆえに,サラのように反抗的な態度も取れる人物を好むかもしれない。誰もが女王に取り入ろうとしてなんでも進んでやってくれるがゆえに,本心から自分に献身してくれる人物を見つけようとする。その表れとして,あえてしばしば自分の意図に反して厳しく接する人物をそばに置く。だが,結局は自分の言うことを聞いてほしい。自分の望みを叶えて欲しい時に本心から奉仕してくれる人物が欲しいのであって,望みを叶えて欲しい時に厳しいことを言われるのも嫌だし,望みを叶えて欲しくない時に何かをされても嫌だ。
女王は,サラがしてくれないことをしてくれるアビゲイルを重用するけれども,アビゲイルはアビゲイルでただのイエス(ウー)マンである。して欲しいことをしてくれるけど,本心からではない。
いずれサラを呼び戻したり,サラのような性格の人物を登用するようになるのだろうか。それともすでにサラのような人物を経験したうえでアビゲイルを選んだことをわかっているから,しばらくはアビゲイルでいようと思えるのだろうか。
アビゲイルの才能は,上昇することにあった。サラとの勝負のさなかに発揮されるものであった。何かを獲得する時に発揮されるものであって,それを獲得したあと,勝利したあと,登りきったあとは虚しくなるだけであった。
その点については,サラの方がうまい。サラは勝負開始以前の,女王の寵愛を確保した頂点において,その地位を維持し,政治的手腕を発揮する治世者であった。
*
どことなく『ファントム・スレッド』で感じたような逃げ道のなさがフラッシュバックする。
同じ出世と転落の物語である『バリー・リンドン』もまた,豪華で優雅だが,下品さと汚濁をふんだんに盛り込んでいた。
3大女優が最高!
終わりは始まり?戻る
ダーティーなワードセンスとメイン女優3人の演技で見せる傑作ブラック・コメディ。ある意味ted。
傑作ブラックコメディでありました!
クズっぷりを発揮してる登場人物しかいない。
騙し合い、落とし合い、マウントの取り合い……人間の醜い部分が凝縮されてるのに、どこか滑稽で不思議と笑えてしまう。
それもダーティーなワードセンスとメイン女優3人の演技力ゆえでしょう。
ストーリー全体の進行より、セリフのやり取りひとつひとつが楽しい。
見た目は上品なのに汚い言葉を使いまくり。
地位、階級、上下関係……と絶妙にズレた会話にニヤニヤしちゃう。
舞台美術もドレスもめちゃくちゃ綺麗なのに、同時にどれもが滑稽に見えてしまう面白さ。
真面目な空気が漂いながらも、ある意味で『ted』に近い楽しみ方ができてしまいます。
メイン3人の演技はどんでもないレベル。
エマ・ストーンは特徴のある顔なのに、作品ごとに別人に見えるのがすごいです。
今作はバードマンでの役に似てるけど、またどこか違う。
一見エマ・ストーンが主役のようだけど、主演がオリヴィア・コールマン(アン女王)となってるのも面白い。それを踏まえると見方が変わるかも。
物語の早い段階に”銃”が登場するのが効いてる気がします。
一撃で人を殺せる道具が出てくることで作中に緊張感を与えてる。
壮絶の女性の戦いを経てのエンディングがとんでもない!
なんじゃ、あの終わり方は!最高じゃないですかー。
さらにスタッフロールでエルトン・ジョンが流れるのが……スタッフを含めこの映画に関わってるすべてが皮肉たっぷりだなぁ;
緊張感、脱力感、カメラワーク、セリフ、演技、乾いた空気……ハマる人はドハマリすると思います。
アン女王のどうしようもない様子の演技は見事でした。
『ヴィクトリア女王 最後の秘密』でのジュディ・デンチ演じる気品溢れる女王セットで見て比較するのもオススメです。
時代は違うといえど、舞台美術の違いとかも面白い。
ドロドロとした蹴落とし合いをカラッと笑える話に仕立て上げた絶妙さ。大満足!
見たあとに予告編を見直すと、表面だけを切り取ってて、うまくできてますなぁ。
実際はもっとしょーもない会話ばかり笑
そのギャップの面白さ!
I have spoken! 英国のドロドロっぷりにハマる!
2019年度アカデミー賞に軒並みノミネートしている本作。納得の怪作でした。今まで余り英国王室に思い入れとかなかったのですが、本作を観て色々検索すると本当にドロドロしてるよなぁっと思います。アン女王以外でもドロドロした話がてんこ盛り。で、多分なんですけど、本作の監督ヨルゴス・ランティモスもギリシャ人ですしイギリスには余り思い入れは無さそうで、イギリス王室の醜聞を渇いたタッチで描いています。うーん、面白かった。
あのカメラを定点視点で固定して見せるのって面白い撮り方ですよね。最近でいうとVRで動画見るとあんな感じの視点になるので上手い事取り入れてるなぁっと思いました。なんというか自分もその場にいて見てる感じになるんですよね。
レイチェル・ワイズ、エマ・ストーンの演技が素晴らしいのは勿論の事、アン女王を演じたオリヴィア・コールマンのインパクトったら!実際のアン女王も頭使うより体動かす方が好きな人物だったみたいで、歳を取ってからはブランデー好きが祟って肥満や痛風で苦しんだようなのですが、オリヴィア・コールマンはそんなアン女王を見事に体現してましたね。もう本人そのもの!そして、ニコラス・ホルトが楽しそうでした。
長年アン女王の右腕として政治も取り仕切っていたサラに比べ、結局アビゲイルの目標って貴族に帰り咲く所までだったんですよね。で、貴族になったらなったで、サラも追い落としちゃった後は何処となく退屈そうで。アン女王の方はサラを切っちゃったんで自分で悩まなくっちゃいけないようになってて。字が読めないような体調でも虫メガネ使って苦労してて。んー、誰も幸せになってないんじゃ!?
色々検索するとアン女王はサラを追放した四年後には亡くなってるみたいなんですよね。で、アビゲイルもそれと共に宮廷を去ってるようです。片やサラは84歳まで長生きしてて。確かに映画の中でも、サラは最後には何ともいえぬスッキリとした表情してましたし、人生何が良いのかわからないもんだよなぁっとしみじみ思いました。
三つ巴
エマ・ストーン
この物語には出口も終わりも無い
久しぶりに見た普遍性のあるテーマの映画。感動無し、涙無し、驚き無しだが、見るべき映画だってことは確実に言える、まぁ、人それぞれですけど。
アビゲイルの成り上がり物語から垣間見えるのは、権威権力者の「お気に入り」が国策にまで影響し、時に権力者に変わって決定さえ行っていること。
「梅毒の兵士に抱かれる時に、道徳的であった事を後悔したくない」アビゲイルは、道徳を捨てて媚び始めます。女王のお気に入りとなり政策にも影響する事が出来る立場に立っても、彼女にはその気が無い。ただ、再び落ちぶれたく無い一心。ここが皮肉。
一方のサラは媚びない。愛してるからこそ正直なのだと言うが、女王には思いが届かず、最後はアビゲイルの策略の果てに、国外追放の身まで落ちる不幸。
権力者の孤独。故に求める「お気に入り」。お気に入りになるために媚びる者の醜さ。志無く媚びる事の愚かさ、引き起こされる悲劇。
映画のラストは、媚びる事を忘れたお気に入りに、媚びる事を命じながら、出口の無い苦痛の迷路でひと時の快楽に恍惚する女王と、これまた出口の無い屈従の迷路に囚われた事を知ったアビゲイルの姿を映し出して終わる。オチも決着も無いラストシーンの意味するのは、「この構図は18世紀の英国だけの物語りに非ず」と言っている。世界中の至るところ、あらゆる時代、あらゆる階層で、この物語りは繰り広げられている。
そう言いたいのだと思う次第。
俺も今日から、帰ったら女房に媚びます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
オリビア・コールマンのオスカー受賞記念追記(2/28)
「The favorite」には、designated winning horse=勝ち馬になると見なされる、のニュアンスがある。映画を観る限り、このタイトルは「女王の第一側近そのもの」を指している様です。アビゲイルとサラの椅子取りゲームは、「プライドをかなぐり捨てた卑屈さと策略」と「純粋な社会的欲求」を対比させながら、滑稽さを強調することで、見るものをゲンナリさせてくれます。王室の描写は不敬です、笑っちゃうほどに。
女王の元から追い出されたサラは後悔と、尚も持ち続ける社会的欲求から、女王に本心を理解してもらうための手紙をしたためます。最初は「辛辣な本音」の文章。何度も書き直すうちに内容は徐々に変化し、最終的にはアビゲイル流に遜ります。自分を殺して卑屈になることも厭わない姿勢ですが、手紙は女王に届きません。警戒したアビゲイルが検閲していることなど、「卑しい人間」には縁が無かったであろうサラには想像できなかったでしょう。増税を主張して来た場面でも、「べき論」にのみ思考を支配され、「現実」に1分の理解も示そうとしないサラの頑固さと、宰相としての浅さが故の悲劇。
そもそも、その手紙を女王に届ける気などサラサラ持ち合わせないアビゲイルは、雑に封蠟を剥し、目を通し、燃やしてしまいます。自分こそが「designated winning horse」になったことを確信した瞬間ですが、それは同時に、「遜ったウソで手に入れた地位を守るために、屈従の迷路に囚われてしまった瞬間」でもあり。それを思い知らされるのは、少し後の事ですが、まさに後の祭り。
女王には届かなかった手紙。待ち続けた女王から下された処分は国外追放。社会的欲求は粉々にされましたが、おそらく、思い残すことなど無く、国を去るサラ夫妻。晴れ晴れとした表情は「卑屈に生きなければならないレース」に身を投じずに済んだこと。レースから「解放」された実感からなのだと思う。
時に5歳、ある時は60歳。あらゆる年代の「女」としての人格が、一人の人物に同居している女王アン。情緒は一定せず、時に依存心丸出しの幼女になり、時に権威を前面に押し出した女帝として振る舞い。とどのつまり、女王アンの心の安寧には、アビゲイルとサラの両者が必要なはずなのだが、サラを切ってしまうと言う失敗は、いつか苦痛となってアンに戻ってくる、だろうに。
この面倒くさくてしょうがない、幼いメンタルの女帝を演じきったオリビア・コールマンに拍手。オスカーに値する演技だった…いや、獲ったんだから値してたんですね!
確かに普遍的なヤダみ
下品
煌びやか
今年度アカデミー賞最多ノミネートの今作といったところでかなり多くの人が観ていた。制作会社の「フォックスサーチライト」は個人的に一番好きな制作会社なので普通に期待していた。
物語としては18世紀のイングランド王室を舞台に女王と彼女に仕える2人の女性の入り乱れる愛憎を描いていた。
煌びやかな衣装やセット、今作出ている俳優陣の高い演技力によってスッとすぐに物語に溶け込むことができた。また、アビゲイル(エマストーン)とサラ(レイチェルウイズ)両者ともに物語を見ることができ何回でも楽しめると個人的に思う。
エマストーンは「アメイジングスパイダーマン」などで清純派ヒロインをかなりしているイメージがあるが、個人的にだが今作のように嫌な女を演じることが上手い役者だと確信した。だが、俳優陣で一番よかったのはアン女王を演じたオリビアコールマンである。彼女は他の作品をみたときには大柄なイメージはなかったのだが、今作はかなり大柄であり、弱々しい一面を見せながらも、横暴な所もあり、役作りを徹底的しているなと思った。
ストーリーについてだが、8パートほどに分かれており、小説でも読んでいるように軽々と進んでいった。今作を語る上で絶対に外すことができないのはラストシーンであるが、3人の悲壮感や虚しさ、女王とアビゲイルとうさぎのあわさった画面を含めて丸く終わるよりも、結局誰も得しなかったや、この世にハッピーエンドなことなどないと強調されたり、女王の存在感がたっぷりと味わえたのでよかったと思う。
今年のアカデミー賞は「ローマ」、「グリーンブック」のどちらかと考えていたので今作を観てますます作品賞が楽しみになってきた。衣装やセット、役者をみるだけでも楽しいので是非みなさんのお気に入りにして下さい。
何だかんだ分からない
ブリティッシュの腹黒さ
もともとレイチェル・ワイズではなくケイト・ウィンスレットにオファーが来ていたという本作。確かにこの役では、ややミスキャスト感がしなくもない。
アン女王の権力を利用した愛憎劇にフォーカスした作品だが、実際はアンとサラの政治的価値観の違いによる決裂が大きいだろう。アンは和平推進派に傾き、サラは戦争推進派だったので王国を巻き込んだ政治的奔走をもう少し入れ込めば、作品として厚みが出たのでは。
予算を抑えるため、ほとんどが王宮内の出来事で、2時間引っ張るのは正直観客はしんどいだろう。ただ塗れ場シーンが割と出てくるので、何とか持つか、という感じか。装飾、衣装、美術は素晴らしく見る価値はある。
アカデミー賞10ノミネートだが、
主演か助演、美術賞、衣装賞の3部門くらいにとどまるだろう。このスケール感、クオリティで作品賞、監督賞はとって欲しくない。
音楽も不気味感を煽るのはいいが、少し間延びしすぎる感がある。9部門をとった割にはやや期待はずれかもしれない。
17回妊娠して誰一人成人になれなかったのだから、気が狂う気持ちも分かる。
3女優の競演が強烈
女は怖い
最後のオーバーラップ…怖
全293件中、241~260件目を表示