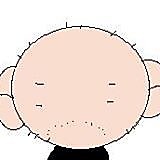バンクシーを盗んだ男のレビュー・感想・評価
全10件を表示
【”ストリートアートは売り物ではない!”2007年、バンクシーはベツレヘムの巨大な分離壁に6つの壁画を描いた意味。誤解により切り取られ売られた「ロバと兵士」のその後の行方から考えさせられる事を記す。】
ー 覆面アーティスト・バンクシーの作品から見えて来る現代社会の光と闇に迫るドキュメンタリー。-
■2007年、バンクシーはパレスチナ・ヨルダン川西岸地区にあるベツレヘムの巨大な分離壁に6つの壁画を描いた。キリスト生誕の地に観光客を誘致する前衛的なプロジェクトだったが、描かれた1枚の絵「ロバと兵士」が地元住民の怒りを買ってしまう。
◆感想
・今作が発するメッセージは数多い。
何故、バンクシーはベツレヘムの巨大な分離壁に6つの壁画を描いたのか。
そして、彼は壁画が切り取らた後に、彼の有名な「Love is in the Air」を再び壁に書き、好意的にパレスチナの民から捉えられる。
ー 「Girl with Balloon」も同じである。-
・今作で、シニカルなのは切り取られた壁画「ロバと兵士」(ロバは愚鈍の意味があり、パレスチナ人に誤解された。)のその後の過程である。
数々の国で”美術品”として、買い取られながらも、徐々に値段が下がり、今では売りも似にならずに、何処にあるか分からないという。
<イスラエル、パレスチナ紛争が激化し、先が見えない現在。ベツレヘムの巨大な分離壁は今、どうなっているかも気になりながら鑑賞した、知的好奇心をくすぐられるドキュメンタリー作品である。
重ねて書くが、”ストリートアートは売り物ではない!”。バンクシーは難民問題、反戦、反資本主義、反消費主義といった社会的メッセージを持たせ、敢えてストリートアートとして、身を隠しつつ絵を書いているからである。>
芸術の力
イスラエル🇮🇱にとっては治安を守る壁、パレスチナ🇵🇸にとっては分断の壁、そんな目的の為に造られたベツレヘムの分離壁。2007年にロンドンの団体が世界の注目を集める為に14人のアーティストに絵を描かせた。アーティストにとっては最高のキャンバス。アーティストの1人が語る。「私たちの作品を見にきてもらうことでパレスチナ支援になればというのが趣旨,我々があそこに絵を描いたのはあの壁の意味を問いかけたかったから」
別のある女性アーティストは「あの壁に描くことに意味がある。壁は人々を侵害し虐待し冒涜する存在。全くもって残虐で人々を心理的に攻撃してる。彼らはそんな中で生活している」
このプロジェクト、考えついたことがすごい。確かに注目を集める。あのバンクシーのアートが描かれたとなればマスコミは追いかけるし、知らなかった人でさえ、この壁の存在を知るキッカケになる。
映画はバンクシーのアートを壁ごと切り取った持ち主を手伝い、切り取る作業を手伝ったタクシー運転手を追う形のドキュメンタリー。なかなかわからない中東のことも少し知れて、ストリートアートのことも少しわかるし、先に見た「イグジットスルーザギフトショップ」より面白い。
バンクシーの言葉「何世紀も聖地だったベツレヘムにコンクリートの壁が作られた。この巨大なキャンバスに絵を描けば世界最大のアートに変えられる。ただし短命なことが大切」
あるアーティスト、彼はレジェンドだね。まさにそうかも。
なかなか勉強になりました。
強制収容所
イスラエルとパレスチナの間に建設された壁が、まるで過去のユダヤ人強制収容所の様でした。私は勝手にイスラエル建国後直ぐに壁ができたと思っていたのですが、壁ができたのはここ20年弱の事ということを知り驚きました。壁ができるまでは、ユダヤ人とパレスチナ人は共生していたと。
植民地支配は形を変え、あらゆる文化をお金に変えてますよね。一見バンクシーの絵がパレスチナ問題を提議しているかの様に見えますが、この絵がこの地で様々な諍いの元になっていました。
私が今まで見てきたバンクシーに関わる人や好きな人は、欧州や欧米でお金を持っていてそれなりの教養がある人+流行好きな人。彼らはこの地を訪れ、お土産を買っていく。でも、未だにパレスチナは何も変わらないし、貧困や差別はそのまま。
バンクシー本人の意図は分かりませんが、バンクシーを利用して政治的なことをポップカルチャーに変えてお金に変えるのは流石植民地資本主義って感じでした。日本も欧米の植民地ですけど。障害者の感動を「与えます」と言っちゃう24時間TV、開催国に住んでいる住人置き去りでスポーツの感動を「あなたにも」と言っちゃうオリンピックと同じ、金儲けの構造が見えた気がします。
バンクシーを通して語られる「アート論」
“バンクシー”という存在が浮かび上げるもの
アーティストが服従したら、ただの職人
本当に、純粋に、個人的な好みで満点にします。この映画、ドキュメンタリーでは無く「弁論大会」。
イスラエル西岸地区の分離壁に描かれた、現代アートの壁画を軸に、色んな立場の人物が登場し、語り続けます。カメラはイスラエルと欧州、アメリカを往き来します。民族、金、アートと商業主義。語られる内容は多岐に亘り、一々深く、気を抜けば置いてけぼりを喰らうこと必至。
商業主義に毒されていないコレクター。商業主義への抗議から自らのアートを塗り潰してしまったブルー。純粋に保存目的で活動しているボローニャの大学教授。そして、当のアーティスト達。志を持って話をしている人達の言葉は、直ぐに分かるもんなんだ。そうでない者の話の、なんと胡散臭く、ご都合主義であることか。嘘を見抜かせてくれるインタビュアーの才能と、渋いイギーポップの語りに拍手します。
俺は、この作品好きです。とても勉強になる。普遍性のある語りが多いから。
文脈から切り取られた壁画に価値は無い、と言う人達。俺もそう思う。保存が必要だと言う人達。確かに地下鉄の駅のゴミ箱に捨てられるのは忍びないよなぁ。
アーティスト達は、何故キャンバスではなく「そこ」を選んだのか。額縁に入れて保存しなくては腐ってしまう「芸術」に背を向けてストリートに出るのか。
「創造する人」の周りに「創造出来ない人」がビジネス目的で群がる。最大の皮肉は、そこに生活する人達は壁画の意味を理解していない事。求めている事は、壁画が「金」を運んで来てくれる事。誰も彼も。
くそったれな世界を見せてくれる映画の語りが、イギーポップってところにしびれました。
ストリートアートの存在と影響
全10件を表示