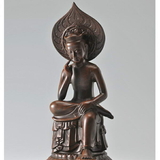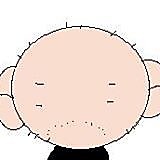洗骨のレビュー・感想・評価
全79件中、1~20件目を表示
未知の文化を知る面白さ
沖縄の離島にこんな風習が残っていることを知らなかった。映画はたくさんの未知の文化を教えてくれる良いモノだと改めて思った。数年経った死者の骨を洗うというのはすごい。ここでは、死んだらそれで人生が終わりではない、死の世界と生の世界が地続きになっている。島の地理に死の世界があるというのが面白い。この島では死が、ここではないどこかではなく、我々が生きている世界の一部なのだ。そう考えると、死が怖いものではなくなる。死んでも自分はこの世界の一部で、どこかで何かをつながっていられるのだ。
それにしてもラストカットがすごい。新しい生と死が向き合うあのカットが、この島の死生観を見事に描写していたと思う。あのカットを観るだけで1800円の価値がある。照屋年之監督は、ただのタレント監督ではない。本当の実力を持った映画作家だ。
命のバトン
今年2月に観た「かなさんどー」がとてもよかったので、同じく照屋年之(ゴリ)監督・脚本の本作をDVDで観賞しました。美しい奥さんに先立たれたダメ親父と残された子供達との不和と和解っていうあらすじは似てますが、作品の雰囲気はかなり違った印象でした。個人的には、「かなさんどー」の登場人物の方が魅力的で、クスッと笑えるシーンもたくさんあって好みでした。洗骨という風習は、今作で初めて知りました。今は、一部の離島を除いてなくなったようですが、なかなか強烈な文化だと思いました。こういう儀式を通じて、否が応でも死を直視し、自分の命が先祖から受け継がれ、子孫へバトンを渡すものであることを肌で感じられるんだなと思いました。
神々しいカメラ
沖縄が好きなので良く旅行をしてますが、洗骨のことは昔読んだ本で知っている程度でした。今まで洗骨をテーマにした映画ってあったのだろうか?
確かに、火葬場で直ぐに骨にするより、4~5年かけて骨になった身内の洗骨の方が、同じ骨でも死者との繋がりが強く感じられると思います。それに、人は生まれ死ぬのだという当たり前のサイクルを身体で理解できるようになるのではないでしょうか。
内地では明治時代でほぼ皆が火葬になったらしいので、日本人の庶民が遺骨を大切する文化は結構最近なんですかね?
チベットでは鳥葬、インドでは水葬、世界では土葬が一般的な場所も多いことから、日本も沖縄も遺体を骨にできる燃料や場所があり、更に綺麗に保管ができる環境・風土があるから、遺骨を大切にする文化が生まれたのだと思いました。火葬だとゾンビという概念も出てこないですね。
奥田瑛二さんの雰囲気が、沖縄出身の義理の叔父に似ていました。個人的に大好きな古謝美佐子さんが出演していて嬉しかった。そして、ゴリの作品をこれからも観たくなりました!
命を繋ぐ
厳かな気持ちになりました。
出産ーンの神々しさ、
頭を垂れて、言いたくなる。
「あかあさん、ありがとう」
この映画の司令塔である信子おばさんの言葉、
「女は命をつなぐんだよ」
「女は命を懸けて子供を産む」
そして本テーマである
「洗骨」
沖縄の離島・粟国島(アグニ島)に残る風習。
葬儀は土葬で、火葬せずに小さい箱に身体を折りたたんで入れる。
4年後に、(風葬と言っていましたが・・・肉が溶けて骨になるまで)
4年待って、
墓(岩場にある壁面の入り口に小石を積み重ねている)を、
今度は、小石を一個、一個取り除くと、棺と言えないほど粗末な、
木箱の蓋を開ける。
衝撃なのは、お骨が、そのエミコ・オカアの頭蓋骨が、
本物にしか見えないんですよ。
黄身色がかった頭蓋骨には頭髪がくっ付いていて、
オトウがその縮れた短い髪の毛を
指の腹で優しく優しく洗い流しのです。
驚くほど小さい頭蓋骨。しゃれこうべ。
考えてみれば娘の優子が臨月近い大きなお腹を抱えて、
フェリーで粟国島に帰ってくる。
父方の妹である信子オバサンに会いたがらず、
ブランコに乗り時間をつぶす。
優子はオバサンに会うのを引き伸ばしている。
理由は優子が一人で出産してシングルマザーになる決心を
しているからです。
お腹の子の父親は分かってはいるが、
“逃げられた“と告げる。
この波乱の幕開けが、伏線で、
洗骨の儀式、
洗骨の場で産気づいて、青空の中、汗まみれの、
家族7人が
立ち会いもとで行われる開放的な出産。
数々見てきたはずの出産シーンの中でも、
えーっ‼️と、思う、なんとも、原始的で、かつ感動的な
出産シーンでした。
「オカア、ありがとう」
「オカア、産んでくれて、ありがとう」
そして、映画は、感動と共に余韻を残し、
ブツリと終わる。
(ここで終わりたいのですが、)
吉本のお笑い芸人であるガレッジセールのゴリさん。
本名の照屋年之の名前で初監督。
日本映画監督協会新人賞に輝いた秀作。
「洗骨」
あゝ、あゝ、あゝ、
沖縄はやはり本土とはまるで違う。
この映画に出てくる2人の子どもたち、
元太8歳)と、小鳥(6歳)
元太がゴリさんで、
ゴリさんが幼い頃経験した洗骨の儀式が、
ベースになってるのかな?
と、勝手に想像したけれど、
いい映画でした。
人生のポイントごとに見たい作品
監督の照屋年之さん
名古屋の中京テレビで『ゴリ夢中』という番組でガレッジセールのゴリさんが出てるんです
観光地でもなんでもない町をぶらついてゴリさんが気になった人やお店などとの触れ合う番組なんです
この番組でゴリさんの優しい人柄が溢れ出ているんです
そして彼の一般の方の話を引き出す能力の高さに驚きました
『鶴瓶の家族に乾杯』に匹敵します
そしてゴリさんの人や物やお店のチョイスがオシャレでセンスがいいのです(私の好みですけどね)
そんな彼の作品ですから当然興味がないわけがない
演者の方々の魅力あふれる個性、度肝を抜くような風習
先祖と私達の生命の繋がり
歳を重ねるとそんなことを無碍にできないのですよ
心に残るいい映画でした
また私の状況が変わったら見てみたい作品です、
笑いと神秘体験と・・・
祖先は私たちそのもの。死は終わりではなかった。そしてこの世に生を受けた者。家族のそれぞれの悩み、抱えている問題が「洗骨」という風習によって一気に噴き出し、さらに収束する絆。初めて見る洗骨の儀式はとても神秘的で、即身仏のような遺体の骨をバラバラにして丁寧に洗っていく光景だ。
新城信綱の妻・恵美子が亡くなって4年。儀式のために長男・剛、長女・優子が帰省するのだが、剛は家族を連れて来ず、優子は未婚のまま臨月を迎えていた。美しい碧い海に囲まれた粟国島の風景は田舎であるも、誰をも受け入れてくれる優しい村だと感じられる。しかし、700人程度の人口の村では噂がすぐに広まる息苦しさもあるのです。
悩みなんて吹っ飛ばしてくれる大声の信子伯母さん(大島蓉子)。彼女が存分に笑わせてくれるし、優子の相手の男(鈴木Q太郎)もいい味出しています。儀式まではまるでよしもと新喜劇の人情ストーリーとも思えるのですが、終盤のシークエンスは生命の神秘を見せてくれるので、得した気分にさえなるのです。命をつなぐのは女よ!と、男のおいらは寂しくもあります・・・ぐすん。
死んだら終わりでは無い
魅せるって難しい
ゴリさんは初監督作品なのかしらと思ったら、過去にも何作か撮ってるのね。その割に時間経過の描写がいまいちだなあが最初の感想になってしまった…。
他の監督さんにはない素材だけれど、演出はたくさん見て勉強したほうが良いと思った。
美しい土地、美しい人々だから、余計にね。
コンビニのおばさんがやたらリアルなのは良かったけれど。
奥田瑛二が、いまは亡き父親にそっくりで、
顔かたちではなく、父もまた母を先に亡くして孤独の中で生きていた人だった。
そこがどうしても重なる。
心配してくれる人が居るって幸せなこと。
心配する人が居るって幸せなこと。
骨が気持ち悪くないギリギリで、美術スタッフさんすごいなと思った。
沖縄の光と影、まだまだあるんだろうな。
ぜひ美しい時間経過を勉強して、もっと美しい作品を見せて欲しいな。
河瀬直美のテーマを、他に描ける人がいた
個人評価:4.1
滝田監督のおくりびとで描かれたテーマを、さらに掘り下げた作品であると感じる。
4年後にある洗骨という風習。残された家族にとって、それは例えではなく死者に再び会い、向き合う儀式。
通常の火葬で灰になれば、死者はその時点から過去の人になってしまうが、この洗骨という風習は、4年間は、まだそこに魂が存在してる死者である事がわかる。そして洗骨によって魂を綺麗し、おくりだす。長男が洗骨前夜に、母親に会う前に髪を切った様に、この島では、まだ母は現世に存在していると感じる。
本作は笑いのテイストも多数盛り込み、観やすく作られているが、この素晴らしいテーマであれば、笑い無しの脚本と演出でも観たいと思う。
河瀬直美が描き続けている風土と魂が、本作にもテーマとしてしっかりと描かれている。
私はゴリが監督という事で、よくある吉本の安易な企画映画として捉えていたが、それは大きな間違いだ。
この作品のテーマを自ら脚本監督した、照屋年之名義という人は、素晴らしい作り手だ。
しかし、何故Q太郎なのだろうか、、そこ、、。
心臓の病にて最愛の妻を亡くした夫と実家に帰って来た息子と娘の行動を沖縄の風習を活かして語る。
自分としては様々な沖縄の風習のTVや映画を観ている(旅行にも何度か行ってる)だけに、前半沖縄の良さは伝わるが淡白。
タイトル通り「洗骨」という風習みたさに映画を観たい人間にとっては少し苦痛。
娘や息子の現在事情、親父の過去を絡ませるのはいいんだけど、今でも長男は実家に戻らなければならないとか、シングルマザーは駄目だとか、「昭和の田舎」みたいな古臭い考えの拘りもちょっと、、、。
また他の方が書いてますが、デリカシーの無さを笑いや面白味にする所も好きにはなれないな。
先骨シーンは良かったですよ。(そうなるだろうな演出が重なり絶賛はしませんが。それぞれ分けて黙って観たかった感あり。)
全体的に伯母:信子役の大島蓉子が居なかったら苦痛でしかならなかったかも💦
しかし、何故Q太郎なのだろうか、、、、。
驚いた
評判が良かったのでレンタルDVDで視聴。
ガレッジセールのゴリが本名の照屋年之名義で、かつて沖縄で行われていたという葬儀の風習「洗骨」を題材に、家族の再生を描いた映画なんだけど、これがビックリするくらい良かった。
昨今は、各所で血縁の“呪い”を題材に、血縁に頼らない擬似家族のあり方を描く作品が流行っている印象なんだけど、そんな流れに逆行するように、本作は血の繋がった家族の再生を暖かい視線で丁寧に描いている。
映画に対して真摯に向き合っていることが伝わってきて好感が持てるし、失礼を承知で言えば、ちゃんと映画になってるとも思った。
初の長編ということもあり、正直拙い部分は多々あるけど、そこはベテラン俳優の奥田瑛二や大島蓉子らキャスト陣の素晴らしい演技でカバー。
小作品ながら、観た人の心に残る秀作になっていると思う。
オススメ。
感動に水を差すようでゴメンナサイ。少々、辛口です。
普通、死者は遠ざけられ隠されるもので、土に埋めたり、火で焼いたりして決別するものですが、風葬でしかも4年後に骨を洗う、というのはちょっとビックリ。
洗骨はかつて沖縄本島を含む多くの島で行われていたようで、しかし1970年頃には、ほとんど行われなくなったようです。照屋監督が、粟国島を舞台に選んだのは、洗骨の風習が最近まで残っていた島、という事なのでしょうか。
では、なぜ、こうした風葬なのか。勝手に想像するに、こんな事ではないでしょうか。
・小さな離島で森林が少ないため、火葬に使えるほど木材が潤沢ではない。
・屈葬のような形で小さな棺桶にすることで、木材の使用を最小限にしている。
・強烈なにおいを避けるため、島の西側をあの世として人里から遠ざけている。
・墓の入口を石組みにすることで通気性を保ち、においがこもらないようにしている。
・大型の肉食動物がいないため、死体が荒らされることはない。
で、4年もたてば腐敗は完全に終わるのでしょう。その時に、洗うことで生きていた時の痕跡(例えば髪とか)をすべて剥ぎ取り、ただの骨にするのです。個人を特定できる諸々を失った骨は、この世との関係を断ち、あの世へと完全に移り住むことができる、と残された者は感じるのかもしれません。儀式とは、区切りです。
映画としては、どうか。死と生を結び付け、命の賛歌として感動的ではあり、重くなり過ぎないようジョークを織り交ぜる意図は分かるのですが、ちょっと吉本流に走りすぎた感があります。そして、「これが答えです」的なエンディングは、かなり頂けない。
そもそも、洗骨は女の仕事、特に長男の嫁の仕事とされ、戦後、女性解放や衛生面の意識向上から、洗骨廃止運動もあったという歴史を知ると(「洗骨 女性」のキーワードで、そんな内容のホームページにたどり着く、と家の奥様に教えてもらいました)、洗骨を感動的に描くことはどうなのか、という気持ちになります。
映画を成立させるために、歴史や文化を一面的かつ都合よく題材にする。実際に洗骨や廃止運動にかかわった人からは、どんな風に見えるのでしょうか。
暗くなりがちなテーマをコミカルに描いた良作
全79件中、1~20件目を表示