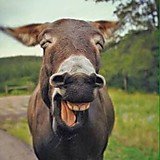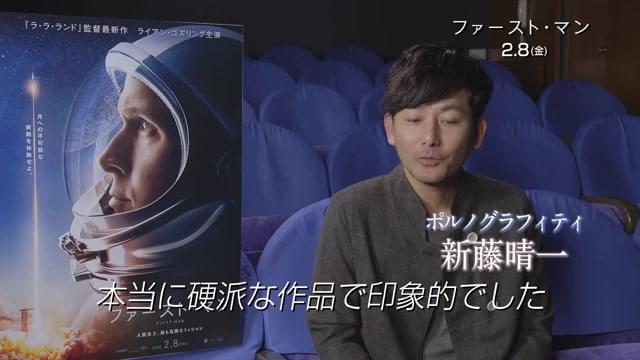ファースト・マンのレビュー・感想・評価
全372件中、61~80件目を表示
デイミアンチャゼル新境地
1960年代を舞台に、実在した最も有名な宇宙飛行士の1人、ニールアームストロングらによる人類初の月面着陸を描いた作品。
「セッション」「ララランド」などの傑作音楽作品を生み出した若き天才デイミアンチャゼルによる伝記作品。
ディミアンチャゼル監督の過去作品とは打って変わって最愛の娘の死や度重なる飛行実験の失敗とそれに伴う友人たちの死などの暗く重い演出でニールアームストロング個人の葛藤や苦悩を描く内容だった。
大学時代からのパートナーだという作曲家のジャスティンハーウィッツの劇伴も作品の雰囲気に合わせ、目立ちすぎず、より一層の重苦しい演出に抜群の組み合わせだった。
ただ静かな作品もあってか、やはり寝てしまった笑。
ララランドの次作ともあって、そういった方向性を期待してしすぎてしまった感もあるが、デイミアンチャゼルの新境地として見れば、今後も期待できると思う。
まーまー。
命を懸ける仕事って
淡々と、偉業に挑む男の姿を見せてくれた。
娘の死から話が始まり、恐らくそれが動機になっている、本人も作中で影響はあると言っている。
個人的な動機はそれだが、国家としては国の威信。
対ソ連の勝たなきゃいけないという。
○
初めは同じ目標に向かう仲間とどちらかというと明るい希望に満ちたお話が続く。
そのうちに一人また一人と仲間が命を落としていくなかで心に微妙な変化が生まれてくる。
家族ともしっくりいかなくなっていく。
結局は奥さんの説得で家族とも絆を確かめ、偉業に挑んでいく。
結果、ファースト・マンにはアームストロングがなるが、そこに至る人々も丁寧に描かれていた。
最初からギクシャクしていたオルドリンとチームを組んで最後のミッションに臨むのはなんとも皮肉な巡り合わせ。
とても丁寧に作られていたと思う。
人類の偉業の裏側の恐怖と勇気!
1970年大阪万博でアポロ12号が持ち帰った月の石を、アメリカ館で何時間も行列して見たのを今でも鮮明に覚えている。確か高校生だった。
本作はその前年1969年のアポロ11号の月面着陸をジェミニ計画から参加したニール・アームストロング船長の目線で克明に描いている。
その当時の宇宙飛行、宇宙遊泳やドッキング、その先にある月面着陸がいかに困難で危険なことだったかを思い出すと、アームストロングの妻や同じ宇宙飛行士仲間たちの葛藤や不安や死の恐怖が画面からひしひしと伝わって来た。
東西冷戦の最中の米ソの宇宙開発競争で米国がいかに無理をして開発を急いでいたか、50年前の記憶が蘇ってきた。
アームストロング船長のジェミニ8号の事故時の異常なまでの沈着冷静な対応ぶりや妻との回線の切断など、開発過程の裏側もよく描かれていると思う。
初めての月面着陸で、月面の状況によっては着陸船の足が月面の砂に深く埋まってしまうのではないかとか、着陸船が転倒したら救出方法はなく100%地球に戻れなくなると言われていた。映画ではそんな場合に備えて米国大統領のメッセージも紹介されていたのが秀逸だった。
ラストの月面着陸の場面は緊張感MAXでハラハラドキドキが止まらなくなった。
人類初の月面着陸という偉業の表面上の華やかさとは真逆のエンディングの隔離室でのアームストロング船長と妻との再開シーンには心が揺さぶられた。
本作は、名作ライトスタッフやアポロ13号とは別テイストのドキュメンタリータッチの素晴らしい映画だと思う。
奥さん役だけが
みんなよく演じていたと思ったが、奥さん役だけがしっくりこなかった。それだけが残念。最近このアポロ関係の映画を良く観た。ソ連には負けられないと勇んで成し遂げた偉業。ベトナム戦争で亡くなる友人達。月上陸を夢見て果てる仲間。多くの犠牲の上に今があるんだな
でも、最後は切ない
静かに戦う男
"喪失"こそがライトスタッフ
こんなにテーマと監督が合致している作品も珍しい。
デミアンチャゼル監督の作品はセッション、ラ・ラ・ランドと過去2作拝見している。彼の描きたいテーマは「自分にとってかけがえの無いものを失った喪失感こそが本人を何者かにさせる」である。
過去2作、共に物語中盤で主人公が自分の理想の為に恋人を捨てる。そしてクライマックス、主人公はなりたかった自分になりエンドロールという流れだ。
私は過去2作の主人公達にどうしても乗れなかった。自分勝手に映ってしまい恋人を失った喪失感を見せられても自業自得だろと思った。
しかし、本作は違う。主人公ニール・アームストロングは不治の病で自分の子供を失う。過去2作では何かを失うか、失わないかの選択権が主人公にあったが本作には無い。また、失うものも恋人、言って終えば他人では無く肉親、かけがえの無い子供である。本作の喪失はニールには避ける術がなく深い。
この物語だけで無く月は死の世界の象徴である。この物語は月に行く=死に触れることと捉えて描いている。
この物語には3回死が出てくる。
パイロット仲間のエリオット・シーとエド・ホワイトそして娘・カレンの3人の死だ。
娘・カレンを失った悲しみを埋めるようにニールは仕事に没頭する。しかし彼の仕事は月に行くこと、つまり死に触れることなのだ。
エリオットとエドの二人は死に触れようとして帰ってこれなかった、死に引き込まれてしまったように映る。
エリオットが搭乗した描写の後のジェミニ8号の座席、エドが搭乗した描写の後のアポロ11号のハッチ、どちらも電気椅子と棺桶にしか見えない。
いやパイロットにはこう見えているのだ。
アメリカ宇宙開発史は栄光の歴史だ。だからそれを描く映画も成功の輝きに満ちている。
だが、本当の宇宙開発はそんな綺麗事で済まされない。宇宙開発は死と隣合わせの挑戦、いや死も業務結果の1つなのだと分らせてくれた。
この作品、とにかく観客に内側を見せる。この映画の中で我々がテレビでロケット発射を見るときの、全体像が写って下から炎を吹き出しながら上昇するあの定番の画が無い。NASAの伝記映画なのに!
じゃあ何を見せるか?ロケットが打ちあがる時、その時パイロットは何を見ているのか、パイロットの目線を徹底して見せてくれた。
そこで描写されたのは成す術が限られた中で拘束され宇宙に打ち上げられる、運が良ければ生きて帰ってこられる極限の環境だった。
ニール・アームストロングのウィキペディアにはジェミニ宇宙船の回転を止めて地球に帰還したとか、幼い娘を病気で亡くしたとか文字で書かれているがそれを実際、彼はどう感じたのか。
彼はずっと娘の亡霊を感じていたし、宇宙船の回転が1秒間に一回以上ってああいう回転になるというのを徹底して観客に見せる。
そして!月の世界も観客に見せる。
NASAの伝記映画でここまできちんと月着陸を描いた映画は無い。凄い、本当に凄い。この映画を見れば月を旅行しているようなものだ。
この月の世界でニールは娘、そして死に触れる。彼は肉体は生きて帰ってこれたのだが、なんか魂は月に置いてきたような気がするのだ。
ラスト、奥さんと窓越しに再開する場面が二人の心がもう繋がれない、俗世に居る奥さんと魂は死の世界に行ってしまったニールのように映る。(史実として後に二人は離婚する)
恐らく普通の映画でニール・アームストロングを語ろうとすると冷静すぎて感情に起伏が無くよく分からない人になってしまう。
しかし本作は避けようの無い喪失と徹底したニール目線、そして月(死)の世界を見せることでニールに深く感情移入出来た。
本作でデミアンチャゼル監督は一皮剥けたと思う。喪失の描き方が一段レベルが上がった。
次はアカデミー賞獲れると思う。
人類で初めて月面に到達した男の伝記映画としてこれ以上無い傑作。素晴らしい作品です。
月面着陸についての懐疑が払拭された(笑)
思えば、名作「カプリコン1」という映画がホントのところ原因だった気がするが、アポロ11号は月へは行けていない!という疑惑は私には根強くあった。
(しかもアームストロング船長の息子という人も疑わしいと言ってる事に反論してない様子に見えた)
何故か。
いろいろな指摘はあるものの
その後まったく月に誰も行ってないから、という理由は大きい。
アポロ11号が月へ行ったのが1969年。
あの頃 人々は、その約30年後の21世紀には月にはアパートが建ってて様々な人が住んでいる事を確信していたし
まして2020年に誰もが月を放ったらかしてまだあの頃と同じように地上から眺めるだけに留めているなんて思ってもいなかったんだから。
2001年には宇宙の旅が実現しており
いろんな惑星からの生き物との交流が実現したり。
なーんて全然ですから。
戦後、我が国は連合国(特にアメリカ)にこっぴどく負けた反省から、もう絶対に戦争はしませんと誓い、戦後教育に於いては日本さえ反省してれば世界は平和なんだくらいのことを植え付けられた(信じられないかもしれないけれど本当)
まさか21世紀になってもまだこんなに揉め続けているとは思っていなかった。
そりゃ宇宙どころじゃないよねえ。
と言ったような理由で私は長らく、アポロ11号は月面着陸してはいないという考えを支持しておりました。はい。
この映画はアームストロング船長の自伝本が原作であるらしいが読んだ事はないし、その存在を知っていたとしても読む気にはならなかったと思う。映画にしていただきありがとうございますといったところだ。
しかし実話だと思えば、亡くした娘の遺品を月の海に落としたのは事実?フィクション?どっちなんだろうか とか
確か、ニクソン大統領から電話が来てやるべき用が出来なかったって事あったよね とか そう言った部分の答え合わせ的なものを求めてしまって
その邪念に映画としての楽しみの邪魔をされるのもよくある事だ。
ここで、まったく関係のない自論を ちょっと宇宙つながりでひとつ。
そもそも人類は
宇宙人というものにロマンを持ちすぎると思う。
宇宙人が地球にやってくる理由
それは侵略以外にありますか?
新大陸として南北アメリカ大陸に移住したのもオーストラリア大陸に入植したのも
侵略そのものだったじゃないの?
何の用事があって はるばる遠くの宇宙の彼方から地球に来ますか?
と身も蓋もないけどそう考えている。
そうなって初めて地球は一致団結できるのかな。
いやいや
ロシアか中国のどっちかがな〜んか裏切りそうに思えてならぬ。
本当の冒険を見るようだ
ニール・アームストロング船長
1969年にアポロ11号で、人類で初めて月に降り立ったニール・アームストロング船長(ライアン・ゴズリング)の物語。
幼い娘を亡くし、NASAに行くことを決意する。
宇宙開発ではすべてソ連に先行されていたアメリカだが、月面着陸で遂に先行した。
このプロジェクトがとてつもないスケールだったことがよくわかる。
ただ、この船長がとても真面目な方で、冗談も言わないタイプなので、ドラマとしては淡々と進む感じ。
もっと長く見たかった
世界的な興奮と熱狂の向こうで
人類史上最高の偉業の一つである月面着陸を、こんなにも物悲しい視点から描いた作品だったことに、ただただ言葉を失ってしまった。しかも、監督・主演は、「ラ・ラ・ランド」の二人である。かのアカデミー賞作品は、アンハッピーなエンディングが賛否両論の評価だったように感じるが、本作は、延々とアンハッピーな空気を纏ったままで終始する。
ライアン・ゴズリング演じるアームストロング船長の視点を中心としたカメラワークが、狭く、息苦しいアポロ11号からの眺めと、宇宙服のフードごしの寂寞とした月面を、観る者に追体験させる。
あの時、彼は、本作のようにノスタルジーに心を奪われたのだろうか。亡き娘の忘れ形見を、眼下のクレーターにそっと葬ったのは実話なのだろうか。月面に偉大なる一歩を記してからの数分間のシーンが、切なすぎてえもいわれぬ感情に襲われた。彼が月面を目指したのは、亡き娘カレンに会うためだったのだ。なぜか、そのように思えてならなかった。
生前の彼を知る人々は、どんな切迫した状況にあっても常に冷静で、富や名声に執着しない、謙虚で、見方によっては全く面白みのない人間だったと語っている。世界的な興奮と熱狂の向こうで、人の営みやいのちの儚さを達観していたのだろうか。ゴズリングのあの物悲しい眼が、本人以上に多くの哀しみを語っていたように感じた。
人類の探求心
宇宙の魅力と恐ろしさの体感。
全372件中、61~80件目を表示