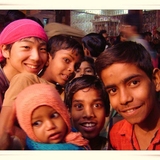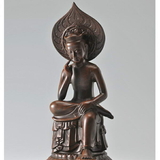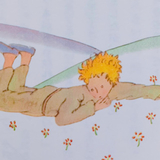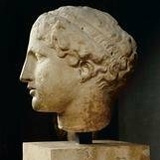日日是好日のレビュー・感想・評価
全274件中、41~60件目を表示
世の中は、あまりにも目に見える変化を求めすぎている。 でも、目には...
世の中は、あまりにも目に見える変化を求めすぎている。
でも、目には見えない変化に気づける人はどれぐらいいるだろうか。
そしてそれは変わらぬものの中にこそ見つかるのだと思う。
意味のないことを継続することに喜びを感じられる強さ。
そしてもっと丁寧に生きていきたいと思った。
悲しみ、寂しさ。それもまた日々是好日なり。
#不器用 #ハートブレイク #変わらぬ日々
茶道
出会ったものを大切にする心
お茶を通して感じる人生
一つ一つの所作の意味は何だろう?
ありそうでなかなかなかった現代劇の茶道映画
映画館では2018年10月15日イオンシネマ石巻で鑑賞
原作未読
「にちにちこれこうじつ」と読むらしい
日日是抗日ではない
都会的で文化的で知的な映画
美しい日本を味あう作品
樹木希林がお茶の先生役
黒木華と多部未華子は従兄弟同士でお茶の生徒役
美人とは云い難い3人がメイン
黒木華の自然な笑顔が可愛くて大好きだ
本当の邦画ファンなら茶道に興味がなくても樹木希林黒木華多部未華子3人のポスターを映画館のロビーで見かけたら観たくなるのが当然でそうじゃないならもぐりだ
色とりどりで艶やかな着物姿の数々に自分の目がハッキリと喜んだ
派手な多部未華子より純和風な黒木華の方が着物がよく似合う
茶道の知識が得られるが自分にとっては実用的じゃない無駄知識だ
自分が通っていた高校にも茶道部があったが当時はお茶とお菓子を食べるだけのお気楽な部活だと羨ましかったが入部する気にはなれなかった
いま思えば少なくとも帰宅部よりはちょいブスたちとワイワイやってた方が楽しかっただろうなと少し後悔している
やりたい仕事がないなら結婚という選択肢がある人は良いよなあ
懐かしい所作
最初から最後まで心地よかった
まずタイトルの入りが実に美しく、とても印象的でした。
冒頭のフェリーニの「道」と、「道(どう)」を引っ掛けてるのも面白い。良い作品の予感がしました。
茶道の美しさと厳しさに触れる、現代の女の子の話。
メインとなる三人の役者で回っているのですが、何だかんだと樹木希林が持っていってます。そして今回は実に可愛らしい。
厳かなイメージの茶道ですがイベント事は別なようで、皆バーゲンに群がる女性達のように賑やか。
それがまたみんな、少女の様な顔をしているんですね。
最初はパッとしなかった黒木華も終盤では実に堂々とした着物姿で、柔らかながらに凛とした佇まいは流石の演技力だった。
私は武道しかちゃんと触れていないのですが、「道」とは生涯を通じ寄り添い修める事と思います。
そしてまさにそれを地でいくよう描いた作品でした。
最初から最後まで、とても心地よかったです。
茶道を習った人なら
本を読んでから観ました。
私は原田マハさんの本を読んでから最近映画を観ました。
このお話は大好きで、「一期一会」の大切さをとてもよく教えてくれるお話です。
お茶の一つ一つの入れ方に主人公は「なぜ?」と意味を聞くシーンがあります、映画ではその一つ一つの細かいお茶の入れ方や作法を細かく話す樹木希林演じる先生が
見ている私も思わず「なぜこんな面倒な淹れ方なのかな」と問いたくなるようなシーンになっており、とっても良かったです。
まるで主人公と一緒に、お茶を習っている気分になります。
ネタバレになりますが、私がこちらのお話を読んで観て思ったのは
考えるより感じろ、ということかと思いました。
日日是好日という言葉はその日をありのままに。
という意味がありますが、まさにその時その日を感じ、ありのままにいること
それがとても大事なことなんだと思わせてれるお話です。
自粛期間中、「やることがない」「つまらない」と思いがちですが
そんなことはなく日々の些細なことに楽しみやその時の幸せがあるということ
とても深くて素敵なお話でした。
樹木希林さんの演技は本当に素晴らしいです。
引き込まれます、本当にお茶をやっている先生みたい。
黒木華ちゃんの演技も、原作の主人公とピッタリだと思います。
綺麗になる黒木華。
お茶の時間
茶道つええ
この映画を見ると、厳格な作法の指導者たる人物は、意外におおらかな性格を持っているものだ──という仮説を容易に信じることができる。
それは、むろん、お茶のことだけではない。
たとえば、わたしたちが、かつて出会ったことのある、柔/剣/弓道の師範だとか、あるいは禅僧だとか、あるいは、商業でも農業でも工業でも、その仕事の技術を極めた達人は、もはや厳しさを通り過ぎて、まるで樹木希林のように朗らかで鷹揚なことが、往往にしてある──ものではないだろうか。
その道のプロや、本物なひとほど、その外観や、性情に、丸みを持っているものではないだろうか。どんな分野でもいいが、そんな古豪に出会ったことはないだろうか?
もちろん性格も教え方も厳しい教官もいるが、あんがい、すごいひとほど爪を隠すことを、わたしたちはけっこう知っている。
本作の樹木希林は、そのことを、思い起こさせる。
ところが、樹木希林は女優であって、お茶の先生ではない。
それを、忘れて見ていた──わけである。
それは演技力ではない。と思う。
樹木希林は「演技」をしているだろうか?
じっさいはどうなのか知らないが、演技をして、それをもって、役に寄せている──とは、思えない。
晩年、印象的だったのは駆込み女~や母の記や万引き家族の樹木希林だが、あれらが演技によるものとは思えない。
なんていうか、それを演技だと言ってしまうなら、あまりにも泰然自若すぎる。
そもそも「そうでない方はそれなりに」で大流行したフジカラーのテレビコマーシャルの岸本加世子とのやりとりでも樹木希林が演技していた──とは思わなかった。
雰囲気に「絶対的な日常」を持っていて、カメラの前で演技しても、それが演技に見えない人だと思う。
その凄みが、この亡くなったのと同年の映画にも余すところなくあらわれていた。
ところで、わたしはお茶のことはぜんぜん知らないが、本作を見ると、お茶の作法を習得することによって、お茶の作法が習得できる──だけではないことがわかる。
つまり典子(黒木華:演)が、そうしたように、人生の岐路で何かの決断をするにあたって、なんの関係もないはずの茶道が、彼女に雄弁な助言を与えていることが、わかる。
また、大切な人の死にたいする悲しみを茶道が癒やすことも、わかる。
だからこそ、それが道と呼ばれるゆえんも納得できる。
20代30代にお茶を習いはじめ、そのことと自分の人生の出来事を、強引に重ね合わせている──わけではない。
ほとんど必然的に、茶道の精神が、人生を扶け、活性化させてきた──と、この原作者は言っているのである。
それが「日日是好日」につながっている。
ただし、父が倒れた──に至る描写はかなりフラグ立たせて、感傷におとしている。
原作未読なので比較できないが、監督のカラーも入っている(と思われる)。
しかし本作にあらわれる、大森立嗣監督のカラー(個人的に大森立嗣監督のカラーだと思われる描出)は、他の同監督の映画よりも、はるかに少なかった。
──のでよかった。
茶の湯を催して、静寂閑雅の境地にはいる・・・。
わたしには風雅のかけらもないが、千利休にいたって大成したその道が武家時代の必修作法だったのは、まぎれもない事実である。
たとえば戦(いくさ)のような場面でさえ、雌雄を決するのに、それ(茶道)が作用したかもしれない。
もっと単純に解釈するなら、作法が乱れるならば、平常心をうしなっていると、自分を顧みるバロメーターになり得る。のが茶道だと思った。
原作は未読で、原作者についても、よく知らないが、映画中「それでもやがて、私みたいな人をフリーライターと呼ぶようになって、あせることはなくなった」というナレーションがあったので、おそらくフリーライターの草創のような人物なのだろう、と思う。原作も読んでみようと思った
なんか浮かばないタイトル
うまい言葉が何も浮かばないけど、
いい映画だと思います。他の人のレビュー読んだら、なるほどなと思いました。緻密に繊細に作り込まれた映画なんですね。
僕は、知識もないし、いいレビューもかけませんが、思い浮かぶことを自分の記録として羅列します。
日本古来の伝統。お茶って千利休からなのかな。調べたら千利休は戦国時代や安土桃山時代の人でしたね。
鶴田真由が劇中で言っているように、昔、電話も何も、無かった時代、一度人と分かれると、次にいつ会えるかわからない、そんな時代では、お茶は一期一会だった。
お茶は四季や日本の行事、伝統も関係しているんですね。
雨の日でも雪の日でも寒い日も暑い日もその四季や自然の音などを感じ、あじわい、たのしむのだ。だから毎日が良い日なんだね。
淡々と映画は進む。急展開やどんでん返しなんてない。ただただ日常があり、ただその中で主人公は、就活、友達の結婚、失恋、父の死があり、彼女の長い年月がお茶とともにあった。12年は長い話だ。
こういう、しみじみした映画もいいです。映画っていろんな映画があり、多様性があるからいいですね。
全274件中、41~60件目を表示