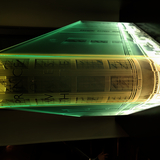博士と狂人のレビュー・感想・評価
全102件中、1~20件目を表示
圧巻のショーン・ペン、贖罪と狂人
事実は小説より奇なり、そんなありきたりな言葉がこれほどしっくりくる物語はそうない。特異な人物像に説得力を持たせたショーン・ペンの演技に見入ってしまった。
ベースとなる事実だけでもインパクトがある。オックスフォード英語辞典(OED)の編纂にあたり用例を公募していたこと。貧困で進学出来なかった身からOEDの編集主幹就任にまで至ったマレー博士や、精神病院の中から大量の的確な用例カードを送り続けたマイナーの学究の徒としての執念。彼らをはじめとした関係者の尽力をもってしても立案から完成まで約70年を要したOEDの情報量など。
そして、辞典編纂の過程と並行して描かれるマイナーの心のドラマはまるで荒海のようだった。南北戦争従軍がきっかけで心を病み、アイルランド人に狙われる妄想から無関係な男性を殺してしまう。入院後のマレー博士との邂逅、未亡人とのやり取りを経ながら、常に狂気と贖罪意識を抱えて揺れ続ける。後半、この二つが重なって強烈に発露し、物語が大きく転回するのだが、マイナーの精神の振れ幅に置いてきぼりを食らわず、心の動きを感じ取りながら観ることが出来た。脚本のよさとショーン・ペンの力量だろう。
贖罪から解放されることの難しさを考えさせられた。そして「博士」と「狂人」とは?
辞典編纂への貢献を考えると、マレー博士から見ればマイナーこそ博士の称号を与えたい存在だっただろう。また、狂人という言葉は精神を病んだマイナーだけを指すのか?別の観点で狂人の呼称に値する人間が他にもいたように思えてならない。
この作品のフライヤーに「博士」と「狂人」を表すアンビグラム(逆さから見ると違う文字に読めるグラフィック)が描かれているのを見て、余計その思いが強くなった。
言葉をもっと大切にしなければ、と諭される思い
コンピュータもデータベースもない19世紀、膨大な用例を集めるのは途方もないマンパワーを要する難事業であったことは容易に想像がつく。メル・ギブソンが演じたマレー博士は単に語学の天才だっただけでなく、広くボランティアを募って用例収集に協力してもらうという、IT時代の分散コンピューティングを先取りしたような独創的な発想の持ち主でもあった。
殺人を犯した“狂人”マイナーを演じたショーン・ペンは、前半は演技過剰に感じたが、マイナーに夫を殺されたイライザ(ナタリー・ドーマーが憎しみから愛情へ揺らぐ心情を好演)と関わるあたりから持ち味を活かせた印象。彼女が子供たちをマイナーと面会させた時の、長女が取った行動には胸を締めつけられた。マイナーによる「言葉の翼があれば世界の果てまで行ける」は名言で、言葉の力と可能性を端的に示している。精神病院の警備員に扮するエディ・マーサンも人間味を感じさせる名脇役だった。
辞書作りを意識しすぎてしまいました...
辞書作りってどうやって完成するんだろう・・全部の言葉の意味を入れるわけでしょ? 大変な作業なんだろうなぁ。それだけの理由でこの映画を観ることにしましたので何の予備知識もありません。
前半は、囚人ショーン・ペン(狂人)と辞書作りに励むメル・ギブソン(博士)がどう繋がっていくのか気にしてただけで特筆することは無し。。。
50分前。生活のため止む無くショーン・ペンに会うナタリー・ドーマー。この辺りから何となく繋がっていく流れではあったけど、基本的に博士と狂人を交互に映す演出のため、これはラストになるまで2大スターは会わないのかな、そんなこと考えていた。
会うようになってからは、何やら単語を言い合ってて楽しそう。目標があると苦痛も楽しみに変わる瞬間に見えた。
「A.B」だけで1冊の分厚い辞書の出来上がり!一体「Z」まで進んだら何冊になるんだ!?
(最後の説明部でわかるけど)
何が気に食わんのか「お偉いさん」達の企み、そしてショーン・ペンの苦悩ぶりなど見所はあるんですが、個人的にはどうやって辞書が完成するのかばかりに気にしてしまい、他の話は退屈になってしまいました。
全体的にはヒューマン系の良き話とは思います。
ショーン・ペンが演じたマイナーの魅力
辞書作りといえば三浦しをん原作の「舟を編む」が思い浮かぶ。本作の中で「舟を編む」のように博士と狂人の二人で用例採集するのかななんてワクワクしてしまったが、そんなお気楽な感じではなくシリアスなドラマ作品だった。
辞書作りとは言葉を伝えることだ。言葉の存在とその意味だ。
何世紀にもわたり使用例を記すことで、言葉の歴史と用法も伝えようとした一大プロジェクトが本作の内容である。
しかしメインとなる物語はショーン・ペン演じるマイナーの過去から現在で、特に未亡人との交流の比率が大きい。
この未亡人との交流を要らないと感じているレビューアーが多いようだが、むしろ非常に重要だ。
先に書いたように辞書作りとは言葉を伝えることだ。しかしその辞書も文字を読めない人間にとっては何の意味もない。
つまりマイナーは、言葉を伝えるということについて一番下から一番上まで助けようとしたのだ。
今の罪だけではなく過去の罪の贖罪としてマイナーが選んだことが、言葉を伝える手伝いだったのである。
統合失調症となり自分がおかしくなっていることを自覚しているマイナーはできる限り全てをかけて言葉を伝える手伝いをしようとした。
彼は間違いを犯したが、その純粋で崇高な魂に応えようとするマレーたちの行動は、人として当然のことのように思えた。
善き人であろうとしたマイナーを見捨ててはそれこそ人でなしなのである。
穏やかなとき半狂乱のとき、かなりギャップのあるキャラクターであったが、名優ショーン・ペンは軽々とこなし、にじみ出る人間性まで表現したように思う。
刑務官のマンシーが作品序盤で同僚を助けてもらったという直接的な理由があるとはいえ、やけにいい人だったのも頷ける。マイナーを見て悪意が芽生えるならば、やはりそれは人でなしだ。
それだけ、ショーン・ペンが演じたマイナーという男は魅力的だったのである。
信念をもって
今まで聞いたことがない言語名がたくさんマレー博士の口から出た時、
お二人が、謎かけのように言葉を掛け合わせていた時、
だけでこの作品を観て良かったと感じました。
言葉については真剣勝負のようなお二人の鬼気迫る想いが伝わって来てそれがマレー夫人の気持ちも納得させたのかと。
未亡人との事は、フィクションだけれど、知らなかった文字を使い気持ちを表せる迄になった過程を通してこの作品のテーマである辞典作りの意義を表すためだと受け取りました。
フレディ、マンシー、チャーチル内務大臣など味方にも恵まれていて良かった。
(一度決めたら)迷いと恐れを捨て信念を持ってやり遂げる。
この上なき勤勉な人生を
私も座右の銘とすべく頑張りたいです。
重厚?暗い?
言葉を綴る終わりなき旅!
OED編纂の実話
友情と愛
アメリカに帰ってからは?
最初は狂人と博士が、どんなふうに繋がるのか不思議だったけど、徐々に繋がってきて楽しくなる。
ただ、狂人の帰国後の様子が分かりづらかったので、終わり方が好ましくないなと…
それと、夫の職場に行って妻がスピーチする時代じゃないし…理解に苦しむシーンも。
だけど、この映画で私が得たものは狂人の言葉…
言葉の翼を持てば世界の果てまで飛べる
私たちの頭の中は空より広い
殺してしまった男の妻が、文盲だと分かったと同時に、狂人が妻に伝えた言葉である。
本当にそうだなぁと感じます。
言葉を大切に、生きて行かねばと感じた映画でした。
英国舟を編む
テーマ曲が良い
・マレー博士は無事に辞書編纂を成し遂げられるのか?
・マイナー氏は罪や病から立ち直れるのか?
という2つの主軸が絡み合うストーリー展開は、新鮮な面白さを感じた。
中盤まではやや退屈ではあるものの地味に丁寧に話が進むのだが、対照的?に、終盤、若干演出が安っぽくなる(例→手を握ると目に光が戻る、看守が院長に反抗する、博士夫人が理事会でよく分からない演説をぶつ)のがちょっと気になった。
最後のシーン、時間の経過を感じさせるような演出はジーンと来た。そこで流れるテーマ曲もメロディアスで大変良いです。
世界最高の辞書(オックスフォード英語大辞典)OEDの誕生秘話。
感動したと言うより、(知識)が多少増える映画でした。
そういう知的好奇心の旺盛なかた向きの映画でした。
まず、OED(オックスフォード英語大辞典)が編纂された目的ですが、
ヴィクトリア王朝時代(1837年〜1901年)の英国はなんと世界の4分の1を支配していたのです。
だから植民地を統治するための指針として「共通の言語」が必要だった訳です。
キャスティングも実力派の渋い俳優揃いです。
違うキャストと別のアプローチならもう少し面白くなったのではとも考えます。
もともとが辞書作り(オックスフォード英語大辞典)を膨大な年月をかけて編纂する・・
はじめから地味なのですが、そこに殺人犯で心を病んだ男マイナー(ショーン・ペン)が、
ボランティアとして協力したことから起こる、横やりと軋轢が最大の見せ場になります。
マイナーの心の闇も19世紀にこんなに複雑な心の男がいたのかと興味深かった。
オックスフォード英語大辞典(OED)は41万語を収録する世界最高峰の辞書です。
大学も出ずに独学で20カ国語を操る男・ジェームズ・マレーをメル・ギブソン。
辞書作りに膨大な資料を送って来る男マイナーが殺人犯でしかも狂人とは?
原作はノンフィクションのベストセラー。
「博士と狂人 世界最高の辞書OEDの誕生秘話」
(サイモン・ウィンチェスター著)
メル・ギブソンはマレー博士の落ち着いた嘘のない重厚な人物像を熱演。
対してショーン・ペンは自分の犯した罪の重さに押し潰され、そしてまた
被害者の妻を愛することで、自らを傷付けてしまう(ここは、ショッキングです)
やはり狂人役がこんなに似合う人は他にいないかも知れません。
オックスフォードの美しい景色や書籍が山積みの部屋。
そして何よりマレー博士亡き後も続けられて70年掛かって完成された(1928年)
「オックスフォード英語大辞典」こそが主役の映画でした。
しかしOEDのどこがそんなに重要で凄いのか?
あまり伝わってこなかった。
ネットの情報は360度に渡って多方向に検索できますね。
その情報を正しく選ぶことこそが難しい。
そう言える現代社会です。
「オックスフォード英語大辞典(OED)」より引用と書けば、
その語彙の情報の正確さにお墨付きが与えられる・・・
そんな価値があるのかも知れません。
・・・辞書は言葉の海を渡る舟・・・
目的はこの映画の《OED》も「舟を編む」の辞書《大渡海》と同じ。
しかし「舟を編む」程の、若く魅力的な人物が生き生き動くような感動には
至らなかったと言うのが本音です。
(私には難しすぎた?!)
過去鑑賞
オックスフォード英語辞典編纂の裏にあった実話。 重厚感があり、今ま...
なんかおもしろくなかった、
オックスフォード英語辞典誕生秘話
19世紀、オックスフォード英語辞典誕生秘話。オックスフォードならさぞ大学の権威筋が編纂したものと思っていたが独学で言語学をマスターしたジェームズ・マレーが編集主幹というだけでも意外なのに精神を病んだ殺人犯ウィリアム・マイナーが協力というのも驚きでした。もっとも彼はエール大学の医大生だったころアルバイトでウェブスター辞書の改訂版製作に関わっていたので辞書に関して造詣が深かったと思われます。
邦画の「舟を編む」も辞書編纂の話だったが、冒頭の右の定義がユニークで惹きこまれてしまったが本作は英語だし、出典や用例に拘るのであまりピンとこなかった。
何故マレーらが過去に遡って語彙を追っているかというと、1066年のノルマン人によるイングランド征服後1362年までフランス語を公用語にされていた、16世紀の後半になると、さらにラテン語、ギリシア語をはじめ、ヘブライ語、アラビア語などの流入も進んだ。母国語の再定義はまさに英国人のアイデンティを復活させるための偉業だった訳である。
それでも、どこの国でも権威を笠に足を引っ張る輩はいるから編纂作業は順風満帆と言う訳では無いし、スキャンダルが絡んでも不思議はない。
ウィリアム・マイナーの精神錯乱は南北戦争従軍時の今でいうPTSDが原因だから同情の余地はあるものの罪もない人を撃つなんて悩んで当然、看守は嘔吐していたが自身の陰茎を斬り落とすなんて酷いシーンに付き合わされた。
総じて、編纂の背景や苦労はわかったものの感傷的に描き過ぎているし、観ていて愉しい映画ではありませんでした。
「言葉」の重みを見せつけられる2時間
私の好きなYoutubeチャンネルに「ゆる言語学ラジオ」という言語学を取り扱った教養系のチャンネルがあるのですが、そのチャンネル内で「オックスフォード英語大辞典(以下、OED)」の編纂には殺人犯が関わっていたという話が出てきたことがあります。その際に紹介されていたのが本作『博士と狂人』です。
ざっくりですが事前に映画の内容については知っていたため普通に観ることができましたが、これってタイトルだけ見ると『ジキルとハイド』と勘違いしてしまいそうですよね。間違って鑑賞した方もいらっしゃるかもしれません。多分。
本作を鑑賞した感想ですが、非常に面白かったです。「全ての言葉を収録した辞典を作る」という前代未聞の辞書編纂プロジェクトに参加することになったアマチュア言語学者であるマレーと、彼の辞書編纂に協力していた収容所に収監された殺人犯マイナーの、何とも奇妙な友情と情熱の物語。若干説明不足に感じる部分もないわけじゃないけど、それでも十分に楽しめました。私は事前に内容を知った状態で鑑賞したので、事前知識なしで鑑賞した方の感想も聞いていみたいですね。
・・・・・・・・・・
貧しい家庭環境故に学歴は無いものの、卓越した言語の知識を独学で獲得した異端の言語学者であるジェームズ・マレー(メル・ギブソン)は、「全ての英単語を収録する」という前代未聞の辞書「オックスフォード英語大辞典(OED)」の編纂に携わることとなる。膨大な仕事量と不足する人員で先の見えない作業、マレーのアイディアで一般人ボランティアに協力を仰ぐことで人員不足はある程度解消されたように見えたが、言語学者でない協力者から送られてきた単語カードは使えないクオリティのものばかり。そんな中で、クオリティの高い単語カードを大量に送ってくれる協力者が現れる。それが、元アメリカ軍医で戦争のトラウマによって精神病を患い、殺人の罪で投獄されていたウィリアム・チェスター・マイナー(ショーン・ペン)であった。
・・・・・・・・・・
本作を観ていると、エニグマ暗号の解読に成功した天才数学者アラン・チューリングを描いた名作映画『イミテーション・ゲーム』を思い出します。ネタバレになるので詳細は伏せますが、ストーリーにかなり似ていますね。どちらも第一次世界大戦あたりに活躍した実在の人物の偉業を描いた実話を基にした作品ですし、ラストの展開がかなり似ているように見えました。本作を観て楽しめた方は、『イミテーション・ゲーム』もハマると思いますのでオススメです。
本作は、アマチュア言語学者のマレーと元軍医で知的な殺人犯のマイナーの友情物語と観ることもできますし、彼らの偉業を理解できずに圧力を掛けたりプロジェクトから外そうとする権力に対する反逆の物語と観ることもできます。
私はマレーとマイナーの関係性が凄く好きですね。特にマレーが最初にマイナーに会いに行くシーン。最初はマイナーが受刑者だったことを知り驚くマレーでしたが、話をしているうちにお互いの言語への情熱や知識量に関心し、どんどんと心を開いていく。そして最終的には面会時間が終わるまで、ひたすら二人で言語に関するクイズを出し合ったりして大盛り上がり。「言語」という共通の関心があったことで、あっという間に距離が近づいていくのが上手く描写されていました。
そしてラストシーン、マレーは生涯にわたってOED編纂に携わり、その一生を終えたことが描写されます。しかしマイナーに関してはあまり詳細な描写がありません。というのも、精神病の悪化などが原因で故郷のアメリカに送還されたマイナーですが、OEDに大きな貢献をした彼の偉業は周囲の人にはほとんど知られていなかった故に、孤独に寂しく余生を過ごしたとのこと。ラストに若干の哀愁を残して終わる本作の締めは、個人的には結構刺さりましたね。
非常に面白い映画でした。オススメです!!
辞書の編纂は狂人出なければできない
本当にそのとおりだと思う。
あって当たり前の辞書。
最初にどうやって作ったのかなんて想像もしたことがなかった。
最初は学士も持っていない人が編纂人だったこと(独学でどうやってあれだけの知識を身につけたのか、驚愕するしかない)。
編纂に殺人犯が関わっていたこと。
当時でもあり得ないことだったのだろうが、実現した。
現代で同じことが起きる可能性は、ゼロな気がする。
フレデリックにナイスアシスト賞をあげたい。
罪悪感が人を狂わせ、愛が人を救う。
これもこの映画のテーマのひとつだったと感じる。
いろいろあってへこたれてたけど、自分がやるべきことを貫くべきだと、意を新たにした。
生き物としての言葉
青春映画の傑作から不良の象徴に今やオスカー俳優として演技派になったショーン・ペンと娯楽作でアクションスターとしてのイメージが強いメル・ギブソンは監督としてオスカーを手に入れた、そんな二人の初共演作。
互いに80年代から活動しながらも役者としてジャンル違いの相容れない関係性のようで、この二人の共演は個人的に衝撃的な出来事でありながら00年代位?から意外性のある共演は多々あるココ最近!?
にしても地味なテーマと映画としてのLookが一昔前のオスカー狙い的な要素にも思われ、実際の感想も小難しいイメージから物語の展開はテンポ良く分かりやすく進む反面、単純さは否めなくショーン・ペンに話の主軸が傾き過ぎで主人公としてメル・ギブソンの存在が徐々に霞んでしまい、作品全体がテーマから逸れてしまっている気もしてならない??
メル・ギブソンとショーン・ペンの監督としての手腕があるからこそ、本作の監督は残念ながら不甲斐無い。
全102件中、1~20件目を表示