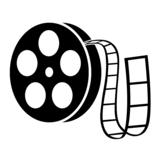20センチュリー・ウーマンのレビュー・感想・評価
全104件中、21~40件目を表示
みんな違って、みんな良い...!?
世代も、嗜好も育った環境も、どこを切り取っても共通点なく、ただただ噛み合うことなく、お決まりの結託もなく、敢えて共通項と言えばとにかくよく話し、それぞれのスタンスで自然体に表現し発信してる女性3人と、それに不器用ながらいつも理想の男として寄り添いたいと思っている男性2人の掛け合いをベースに展開されるお話。
まとめてみたら、ちっとも面白くないとのに、女性×女性、女性×男性、たまに男性×男性、女3人x男2人の組み合わせで紡ぎだされるダイアログや、たまに入るモノローグが、いちいち琴線に触れてくる、極めてドメスティックでエモいけど、90年代の時代の転換という壮大さと自然に交差される現代の鉄板テクニックのお陰なのか⁈…嫌味がかけらもなく、不思議な心地よさにじわじわ浸透して、病みつきに引き込まれていく。。
空気感
「母はいてくれさえすればいい」
・母が営む宿舎というシチュエーションに、いろんな生い立ちと性格の人物を放り込んだときに起きる出来事を、淡々と切り抜いた映画。
・だから次々と事件が巻き起こる。
・各人物像のキャラの濃さも相まって、その事件は予測不可能。
・ドキュメンタリーに限りなく近い。
・脚本の構造どうなってるんだ?
・ノンフィクションは本当におもしろい。
・観ていてなぜこんな個人的な内容の作品が作られるのかと思った。
・今の時代は人間関係の葛藤やどう生きるべきかということが、時代の共通課題になっているのではないか。
・昔は人間関係どころじゃないところもあったのかもしれない。それがジブリの鈴木さんがいうところの貧乏の克服というところだろう。
・個人的な人間関係をつぶさに紐解くと、観ている人には、ところどころ共感できる部分がある
・そこに教えがあり、ヒントがあり、郷愁がある
・そういうものをいまの時代のお客さんは求めているのではないか。価値が宿るのではないか。
・そして、女性主体の映画であることもマーケティング的にも影響が大きいのではないか。
・映画の中の70年代は、男性主体の社会であったのではないかと想像する。
・「いやいや女性たちのクセはすごかったし、すごい影響を受けたんやで」と、監督は当時の女性の力強さも描いている。
・その想いがタイトルに反映してる
・スマホが出ない。音楽はレコード。えりのでかいシャツ。
・女性が求めていることは、快楽ではない。自分が求められているという手がかりがほしい。
・子が母に、自分の面倒を見ることを諦めただろうと問う。母が私のようになってほしくないからだ、その為には他の人の助けが必要だと応える。それに子は、「母がいてくれさえすればいい」と言う。
・この子どもの言葉は、あらゆる子どもにとって共感できる言葉じゃないだろうか。
・めんどくさいから干渉しすぎないでくれともとれるし、あなたじゃないと代わりはいないという、どっちの言葉にもとれるダブルミーニングになっている。
・息子の母に対する複雑な感情を言い当てている。そこがすべての息子・娘が共感できるパンチラインになっている。
現実逃避したい時に観たい映画
レビュー
1970年代の個性的な女性たちの生き方を、現代の個性派女優たちが華麗に演じる。
3人の強い女性
女性の強さを飾らずに描いた作品。
2017年のアカデミー脚本賞にノミネートされた本作。ずっと前から気になっていた作品でしたが、ようやく観ることができました。脚本賞というのはもちろん、脚本家に贈られる賞ですが、監督にも編集者にも贈られてもいいと思います。映画というのは、3度書き換えられると言われています。脚本で、撮影で、編集で。ハリウッドは特に特徴的で、脚本家はプロダクション行こう全く作品に関わらないということも稀ではありません。この作品は、脚本家が監督もするパターンですが、脚本家のマイク・マイルズと監督としてのマイク・マイルズとは別人と考えてもいいと思います。
素晴らしい脚本は、キャラクターが動いている。もちろん、キャラクターは常に動いているのですが、動かされているのではなく、自分から動いているキャラクターというのは作品中でかなり生き生きしています。この作品の優れているところは、3世代の女性キャラクターをステレオタイプではなく、ユニークながらもその世代を象徴するように描けているということです。その3人の女性はジェイミーという少年を中心に描かれます。まず、ドロシー。ジェイミーッの母で戦争を経験し、夫と離婚し女で1つで息子を育て上げてきた強い女性です。息子の幸せを願う母親ですが、「自分よりも幸せに生きてほしい。」という願いが強すぎるが故に少し硬い部分があります。しかし、2人のシェアハウスの住人と、ジェイミーの幼なじみによってその硬さがとれ、少しずつ柔軟になることにより、彼女の人生にも小さな光が降り注ぎます。アビーはドロシーの家で一室を借りる写真家。若い輝きを放つ彼女ですが、その光が強すぎて、時には前が見えず道を外してしまうときもあります。しかし、ジェイミーという年下を気にかけることで大人の女性として落ち着きや責任を感じるように。ジェイミーの幼馴染のジュリーは思春期でなんでも吸収してしまう女の子。ドロシーとアビーの大人の姿を見て、憧れとそこからくる反感から自分とは何かを探していきます。この3世代の女性が失ったもの、まだ持っていない部分をお互いに気付かせ合い、人生とは幸せとは何かを探して行くその好奇心など、とても深い部分に入っていきます。
編集もとてもバランスが良く、咲く日のリズムをうまくつかめているように感じました、リズムと一言で言える言葉ですが、2時間の映画の中でそのリズムを作り上げて行くことはとても難しいものです。そのリズムにより、キャラクターたちの立ち位置、関係性が大きく変化するため、そのリズムを見失うことは、映画を崩すことに一致します。キャラクターを中心とした脚本と編集があってこそのこの作品の良さが最大限出ているのではないでしょうか。キャラクター同士の関係を考慮して、女性という大きなテーマを描いた素晴らしい作品です。
性別の違いを知るのにいい作品
なんかいい映画だった
母の目から見た息子と自分
50代も中盤に差し掛かった母が息子を持て余す。しっかりと地に足のついた男に育って欲しい、そのためには母親の力だけでは足りない。シングルマザーなら、いや母親なら誰もが抱くであろう悩みと、母としての自負と、さしたるドラマのない日常を生きる自分へのもどかしさ。
自分のようになってほしくない。そのセリフを語る彼女は哀しそうだ。しかし、下宿人の子宮癌の経過を気にかけ、消防士を誕生パーティに招び、クラブを見学に行き、自分の好きな音楽とタバコを誰が何と言おうと楽しむ姿は、息子の心に焼き付いている。20年後、肺がんでなくなる、息子にメモを残す力もない、とのモノローグ。母は永遠に息子を思い、やり残したことを後悔し、何者にもなれなかった自分をちっぽけに感じるのだ。母の目から見るとしみじみと共感する映画。
40歳で息子を生み離婚した’24年生まれの女性
カリフォルニア州サンタバーバラ
70年代
ハチワレの猫がいる
途中から出番なくなった。
パンク好きなら面白いのか?
自分が幸せかどうかなんて考えたらうつになる。
失神ゲーム
ここで語られる男とは、女とはには納得。70年代生まれのせいか。
話全般については?女性向映画なのかも。
そもそも母親になるつもりはなかったように感じられる。
結婚も離婚も適当。
70年代はタバコ吸い放題。
年頃の息子と母親ってこんなに話し合うのか、アメリカでは。
年上のお姉さんに色々教えてもらっちゃうとおかしくなっちゃうような気がする。
slutジュリーがヤル理由がなんとも男には聞きたくない本音。
マイクミルズは2度目から
子の心親知らず、母の心子知らず
15歳の多感な少年の気持ちなんて、母親にはわからないだろうね。
セクシャリティーな面も含めて。
年上のお姉さんで子宮頸がんを患ったアビーと、息子ジェイミーの同級生でませてるジュリー。「今の世の中難しいから、息子を気にかけてやって」と頼まれた二人。普通同性の人に頼むと思うんだけど。その辺がちょっと疑問に思いました。年は違えども、母と二人は同じ女性なんだから。
登場人物の過去や生き方が随所に盛り込まれていて。群像劇っぽい面も感じました。
また母が頼んだ二人のいろんな悩みを聞いたり、話をしたり。シェアハウス+息子の同級生という、コミュニティーの一体感がありました。
母親役。最初誰このしわくちゃ(失礼)と思ってよーく見たら。アネット・べニング!。55歳の設定でしたが、こんな感じなのか?と自分の年齢を考えてショックを受けました。仕方ないけどね。
途中息子がスケボーで下り坂を左右に進んでいく所や、息子の運転で母がスケボーに乗る場面が。人生の曲がり方や下り方を表してた気がします。
ま正直、チョッとだらっとした感じは否めないかな。
90分ぐらいで凝縮してもよかったかも。
時代の変化
あまりピンとは来なかったが...
全104件中、21~40件目を表示