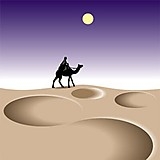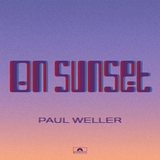わたしは、ダニエル・ブレイクのレビュー・感想・評価
全197件中、161~180件目を表示
明日が見えない。
評価の難しい映画です。ケン・ローチの作品は10本以上見ているけど、これほど希望の見えない映画は作ってこなかった気がします。生きることの全否定、弱いものは黙って朽ちていくしかないのでしょうか。あるのは現実の厳しさだけです。それを伝えたいがために、再びメガホンを握ったとも思えないのですが。
誰が悪い訳でもなく、淡々と仕事をこなした結果の地獄、穿ち過ぎな見方かもしれませんが、有料観覧者からいくらかずつ取って、30年間の基金にするとのこと。そのプロモーションのために作られたとしたら、完璧な出来です。きっとメッセージは、この30年間に誰か革命起こせよ、といったところでしょうか。
生活物資受給所でのシーン
ケイティがあまりにもお腹が空いて、受給所で思わず缶詰を開けて食べるシーン。
そのあと我に返った彼女は自分の惨めさに泣き崩れる。
人の尊厳はどこで傷つくのか、どんな場面で壊れるのか、見せつけられた気がした。「もう我慢ができない!」を発しないと・・・。
私もダニエルのように、いつか心臓病を患うような気がする。
けど、希望は捨てる必要はない。捨てさせようという権利は誰にもないのだ。そしてその希望が人と人をつなぎ、生きる証しになるのだ。
不思議な余韻を是非体験して欲しい。
見終わって30分ほど経つが
まだ頭の中がジンジンと熱い。
驚くほどエンドロールが短かったので
劇場の暗闇の中で余韻に浸る時間もなかった。
込み上げてくる感情はあるが
感動した?訳ではない。
涙もこぼれたが、感涙の涙でもなかった。
ここ最近観た映画の中では
独特な余韻が長く続いている。
けれど、とにかく見てよかった。
劇場が少ないので
電車で1時間かけて観に来た。
その甲斐があった。
人を選ぶ映画だった。
観るタイミングも
一緒に観る人も
選ぶ映画だと思う。
おそらく、観ていて
辛い「100分」になるだろう。
でも、是非観て欲しい。
ほとんどBGMなし。
残酷なまでに淡々と進むその様は
深夜のドキュメンタリー番組を見てるかのよう。
ささやきのようなセリフや
路面を踏みしめる音。
全ての日常の音がくっきりと聞こえて来た。
だからこそBGMなんて、いらなかったのか。
正直、序盤は
ダニエルにも、シングルマザーにも
感情移入できなかった。
そこまで怒ること?
自業自得じゃないの?
そう感じていた。
「役人目線」で物語を見ていた。
だが、物語が進むにつれ
気がつくとダニエル側から
景色を見ている自分がいた。
フードバンクでのシーンでは
ダニエルと一緒に
ケイティを慰めている自分がいた。
ダニエルの落書きのシーンでは
通りすがりのおっちゃんと一緒に
大喝采を送った。
自分の隣にもし
「ダニエル」がいたら?
私自身、家電量販店に勤務している。
パソコンを担当している私は
毎日のように、ITに不慣れな
いろんな「ダニエル」に出会う。
自分のスキルがあれば
彼らを助けられる。
でも業務外になってしまう。
役所で女上司に叱られていた
アンの気持ちが痛いほどわかる。
明日ぐらいは
業務逸脱してみようかな(^^;;
まだ余韻冷めやらぬ今のうちに
上司への言い訳を考えておくか(^-^)v
わたしは、ダニエル・ブレイクだ。
私は、何の為に税金を払っているのだろうか。私は、何故こんなにも怒りが込み上げてきたのだろうか。私は、どうしてこんな社会になるまで、目をつぶり続けたのだろうか。
今、日本でも生活に瀕している沢山の人がいる。彼らを助けない政府、彼らを叩く人達。
「助ける」という行為そのものが嫌悪される社会に、人間が集まる事に、一体何の意味があるのだろうか。
私達は「自己責任」という言葉を、国民同士で振りかざしすぎてはいないだろうか。
勘違いをしたくないのは、この作品が決して生活困窮者である他人の話ではないということ。
「わたしは、わたしたちは、ダニエル・ブレイク」なのだということ。
ケン・ローチが点火した「抗議」の火が、この日私の胸に静かに静かに引火した。
私はダニエル.クレイグと勘違いしそう
ストーリーはイギリスのおじいさんの奮闘記と言う事でわかりやすい。イギリスもユーロ脱退とか底辺には住みにくいんだろうな。階級社会だしな。黒人の兄ちゃん良いやつだな。ただ、題名がダニエルクレイグと被るな。向こうで言えば佐藤さん並みに多いのかな?
語り口は静かだが、強い怒り
役所というところには、法の執行者であることが権力を持つことだと、大きな勘違いをしている者がときどき見受けられる。自分が血税に雇われた身であり、法で定められたことを誠実に実行することが自分の仕事であって、そこには自分の恣意など一切介在させてはならないという、民主国家では自明のことを忘れているものがいる。
映画の冒頭には「医療専門家」なる女性による質問と脅しにもとれる言葉が出てくる。しかも、この「医療専門家」が国から委託された民間企業の人間だというのだから噴飯ものである。
主人公のダンは求職手当と支援手当(日本でいえば雇用保険と生活保護にあたるのだろう)のどちらの支給要件からも漏れてしまっている。おまけにこうした福祉を受けるための手続きに必要なPCを扱う経験もなく、書類の作成もままならない。
働いているときは真面目に納税してきた彼を、病気で働けなくなったときに救い上げることのない福祉制度の矛盾は、議会が解決するかも知れない。しかし、この矛盾を矛盾とも思わない人々は、そう簡単にはこの社会から消えていなくなることはない。
特にハッとするようなカメラワークや編集のテクニックがあるわけではない。しかし、全編を通じてふつふつと湧きあがる憤りが心を揺さぶり続ける。
「マッチ売りの少女」あるいは「一杯のかけそば」、貧困と闘う尊厳の在り方を問う
"パルムドールを受賞したから、いい作品。"という方程式はないが、"やっぱりね、パルムドールを受賞してるんだね。"という会話は成り立つ。そんな映画だ。じんわり泣けてくる。
心臓病で医者から仕事を止められているダニエルは、自身を犠牲にしながらもシングルマザーのケイティと2人の子供の家族を助ける。しかし、そんなダニエルの正義感をよそに、厳しい現実に追い詰められていく。
貧困と社会を描く、この手のタイプは、アンデルセンの「マッチ売りの少女」や「フランダースの犬」、あるいは栗良平の「一杯のかけそば」のような描き方もある。しかしケン・ローチ監督は社会制度そのものに怒りを燃やし、問題提起している。そして人間の尊厳・プライドを主張する社会派ドラマに仕立てた。
おそらく私小説的なアカデミー作品賞の「ムーンライト」より、素直に心を寄せることができるに違いない。
(2017/3/24 /ヒューマントラストシネマ有楽町/シネスコ/字幕:石田泰子)
ケン・ローチの静かな激昂
「映画が声を上げている!」と思った。
あまり前情報を入れずに見に行った映画だったので、ケン・ローチ監督の新作で、ローチ監督らしい社会派のドラマだろうくらいの感覚でいたし、実際に、一人の貧困な男をめぐる物語として映画ははじまっていく。しかし、物語が進めば進むほどに、この映画が社会に対して声を上げて何かを呼び掛けているのを感じてくる。「こんな社会は間違っているだろう!」「こんな制度はおかしいだろう!」「平等や同権の意味は何だ!」と、頭の中で疑問や疑念が渦巻いてくる。そしてそれは、おそらく、どこの国のどんな社会にも通じる、大きな問題に違いないとはたと気づく。人々が、というよりも、国や社会や制度が、ある一定の層の人々に対し、公然と差別をはたらいているようなもの。映画という媒体を飛び越えて、人々の目を覚まさせる、そんな作品だった。
きっと公務員の人たちは悪くないんだよ。彼らも仕事としてしていることで、慈善事業というわけではないから、「温情」とやらを簡単に持ち出すわけには行かないし。だから一人の公務員の女性がダニエルにネット申し込みのやり方を教えてあげようとすると彼女の上司が「前例を作るわけにいかない」といってそれを止めるシーンがある。彼らも、何かおかしいと思いながらも、無力さを感じて仕事をしているはず・・・って、同じように働く社会人として、彼らの気持ちもちょっと分かるような気がしたり。
ダニエルと若いシングルマザーとの交流に、心救われる部分がある。もちろん、彼らの生活に救済はない。それでも、重く考えさせられる題材の中で、彼らのこころの触れ合いを感じて、少しだけ安らぎを感じる。二人の役者も本当に素晴らしかった。
映画だからと言って、ダニエル・ブレイクを安易に救済せずに幕を閉じる。カタルシスも残さずに観客の前から映画自体が立ち去る。残された私たちはますます考えてしまう。この映画を見た夜は、ちょっと眠れなくなった。
貧しさを教わる。
政府は福祉が困窮者に行き渡らないように画策している
去年、川崎市市民ミュージアムで観た、昔の作品の『キャシー・カム・ホーム』と確かに似ている。50年も前の作品なのにお役所の姿勢はは何も変わっていないようですね。 キャシー~は都会を夢見て無計画に田舎から出てきた娘が、都会で知り合った男と所帯を持つが失業し、政府の保護を受けることの困難さを描いていたけど、こんどは心臓発作で仕事を医者に止められている老人が失業給付を申請する話。
今回は主役がお年寄りになったことと、役所での申請がパソコン必須になりつつある事の弊害も加わってます。お年寄りはパソコンが苦手ですからね。電話の対応は機械音声、求職手当の申請に、働けないのに面接の実績と証拠が必要ときた。 この主人公は心臓の病気で医者に仕事を止められているのにですよ。 これは機械が苦手なお年寄りじゃなくてもイライラすると思います。
イギリスでは数年前の福祉改革により、最貧困層にある家庭200万世帯の状況がさらに悪化しているそうです。改革とは名ばかりですね。生活保護などが削減され生活困窮者がさらに困窮しているとの事。またこの映画の中で悪態を突かれていた、使っていない寝室に税金を課すという寝室税は
初めて知りました。福祉の名の下、貧しい人がより貧しくなるのは何故なんでしょうか?なんかおかしいですよね?
それから二人の子供を抱えたシングルマザーも登場します。彼女はお金を稼ぐために禁断の方法に手を染めてしまうのですが、そのきっかけは貧困が原因の子供のイジメなんですね。しかし、その禁断の方法はより子供が差別を受けやすくなるというのに、やもえず落ちていく感じが切なかったですね。
登場人物が不器用すぎる感はありますが、格差社会が急速に進む昨今、この映画を観て多くの人に理不尽さを感じてほしい。
厳しすぎる。
愛の欠落と他人事ではない無責任
よかった
そもそも役所になんか頼ろうとしてもどうせ気分よくならないに決まっているのでなるべく当てにしないことにしていた。しかし、里親活動をするに当たって児童相談所のお世話になったら、とても手厚く面倒をみていただいて、今ではその印象が逆になっている。部門によってきっと違うのだろう。
おじいさんが車椅子の弁護士を頼ったとたん、すんなり事が運びそうになっていたのが、よかったのだが、本来そうあるべきであり、なんとも残念な気持ちになった。
ヒロインがシングルマザーで、生活苦から風俗嬢になってしまうところがあまりに切なかった。リアルな現実なのだろうし、現実にそうして生きている人がいるのだが、本人も触れて欲しくないだろうし、実際ユーザーもいる。問題視しづらい問題だ。市場原理の負の側面だ。
観るのに覚悟が要ります
よそ事ではない・・
Working Class Hero
人が人として人らしく生きる権利
全197件中、161~180件目を表示