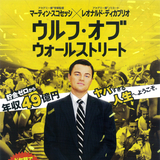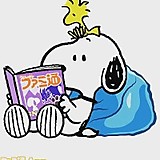沈黙 サイレンスのレビュー・感想・評価
全421件中、361~380件目を表示
役者が、ナーバスになるのも納得・・・
ハリウッドが、日本を舞台にここまで作り上げたら邦画は敵わない。
映画好きとしては、クワイ=ガン・ジン、スパイディ、カイロ・レンを演じた俳優さんだったのと、窪塚さんや浅野さん、尾形さん以外にも・・・
えっ!て感じで、馴染みの日本人役者さんが惜しげも無く出演してるので、難しく考える間もなく物語に入り込めました。
ただ内容的には、胸が詰まる思いと痛さと理不尽の連続でかなり重いですが、その中で、キチジローが何度も何度も懲りず同じことを繰り返す・・・
しつこいくらいに繰り返す・・・・
宣教師ロドリゴが、心痛に見舞われてる時に限って現れる・・・・
役に入り込んでるアンドリューと一発即発にもなるったって、窪塚さんの後日談にも納得の☆4.2
出来れば朝や昼間より夜観て帰るだけにしないと・・・長くキツイ1日になると思います。
思ってたほどには重くない
原作ファンとしては…
ちょっと惜しい作品。
待ちに待った作品だったので尚更。
全体的に原作のシーンを忠実になぞっていき
作品のテーマを分かりやすく表現しているところは、流石スコセッシというところ。
映像はコントラストの高い
フィルム調の映像に仕上がっており、
無駄なBGMが流れず、作品に没入できる。
ただ、原作ファンとしては
如何せんロドリゴが神と対話し葛藤、苦悩するシーンが短すぎるのが惜しい。
転ぶ直前に見つけたフェレイラの手跡、
(幾ら何でも見つけるの早すぎやしないか?)
拷問時の呻きを門番の鼾と勘違いした時の
あっけなさ、そしてラストシーン
棄教に至るまでの葛藤にもっともっと
時間を割いて欲しかった…
えっ!もう諦めるの?感がどうしても拭えません。
ただでさえ長尺の作品なので
興業的に延ばせないのであれば
シーン単位のオミットが必要だったのでは…
原作ファン目線だと辛口になりますね。
女性と見に行く映画ではないが圧倒的迫力のハリウッド映画 必見
この映画は家族や夫婦で見る映画ではない。むしろ一人で人生とは信仰とは何かを考えながら見る映画。人には命より大切な物がある。それが家族であったり、自分の信じるものであったり人それぞれであろう。最初から弱き者をこれでもかと代官がキリシタン達を拷問する。貧しい農民達にとってキリシタン達は信仰が全てであった。自分が何かを捨てなければならない時、彼等にとって最後まですてられないものは信仰であった。神父の祈りに対しても神は沈黙し何も答えない。村のキリシタンは海に建てられた十字架の上で3日生き続け、引き潮の時には賛美歌を歌いそれが村に響く。何か崇高なものを見たような気がする。これはまさしく現代ではあり得ない日本人がなした崇高さである。キチジロウは私のように弱くずるく、汚い人間である。しかし信仰を捨てられない。神父につきまとい神父からも軽蔑されているが、最後には神父から一緒にいてくれてありがとうと言われる。最後に神は沈黙を破る。このシーンではたぶん一人であったら涙が出ていたと思う。涙をこらえるに必死で腹が痙攣するほど動いていた。娯楽はないが確実に感動する映画であり、映画の価値も非常に高い。
弱さと強さはコインの裏表かもしれない
約400年近く前の日本の九州が舞台であるが、単なる信仰を扱う映画としてでなく人間の内面を見つめる映画としてよく出来ている。スコセッシ監督は映像ドラマとしてしっかり作っている。特に誰しも好きではない拷問場面は苦痛を感じるが、これも考えるためのツールとして割り切るしかない。
テーマは宣教者のような高い理想を目指す人間だとしても、やはり逆境のなかでは完全とはなり得ないことを示している。この映画にはヒーローはおらず、登場人物が弱さを持ち同時に強さを持つ。卑怯なやり方で人間の外面をどのように変えようとも変えられないものはある。それが信仰であったり信念だったりする。
日本人俳優はイッセイ尾形の奉行や通訳の浅野忠信はじめ多くの俳優に存在感があった。個人的には窪塚洋介のいい加減なキチジローが共鳴できた。弱さを持ちながら必死に生きている。こういった弱い人間を愛することが出来るのは神しかいないかも知れないが…。静かに人間のあり方を考えることができる至高の映画である。
信仰や疑い、弱さや人間のありようについて深く考えさせられる傑作
原作は遠藤周作の小説。キリスト教が禁じられた江戸時代の初期を描く殉教映画です。洋画にカテゴリーされる作品ですが、日本人俳優が重要な役を演じる邦画ファンも必見の作品。構想から完成までなんと28年も。いくつもの困難を乗り越えて映画化を実現したというマーティン・スコセッシ監督の執念がまるで、「神の試練」のように感じてしまいました。信仰や疑い、弱さや人間のありようについて深く考えさせられる傑作です。
舞台は17世紀、江戸初期の長崎。
冒頭から、幕府によって捕らえられた宣教師たちが雲仙の源泉に連れて行かれて、そこで熱湯を浴びせられるという拷問、処刑シーンが描かれます。いくらそういう映画なんだと予告編で覚悟してきても、やはりあまりにむごすぎて息を飲んでしまいました。ふと気がつくと、そのシーンには、映画に付きものの音楽がついていないのです。そんな沈黙が、余計に戦慄さを感じさせたのかもしれません。
さて、物語はこのあとポルトガルのイエズス会本部に移ります。宣教師であるセバスチャン・ロドリゴ神父(アンドリュー・ガーフィールド)とフランシス・ガルペ神父(アダム・ドライヴァー)は、信じがたい噂を耳にします。それは自分たちの師であり、日本でのキリスト教の布教を使命としていたクリストヴァン・フェレイラ神父(リーアム・ニーソン)が、日本で棄教したという噂でした。尊敬していた師が棄教したことがどうしても信じられず、それを確かめるべくふたりは危険を冒してでも、日本へ渡ることを決意するのです。
ふたりは中国・マカオで日本人の漁師にしてキリシタンであるキチジロー(窪塚洋介)の手引きにより、日本のトモギ村に密入国します。そこで目にしたのは、キリシタンに対する想像を絶する仕打ちや拷問でした。そして村には司祭はおらず、「じいさま」と呼ばれる村長のイチゾウ(笈田ヨシ)だけが洗礼のみを行えるという過酷な環境だったのです。それでも村人たちは、信仰を捨てずに祈り続けていました。ふたりは村人達と交流を交わし、布教活動を行っていきます。
キチジローはかつて弾圧を受け、踏み絵により棄教したのでしたが、その時自分以外の家族は踏み絵を行えず、眼前で処刑されたのだというのです。罪の意識を背負い苦しむキチジローは自分の村である五島列島にも宣教師を招き、布教を広めます。そこでフェレイラの手掛かりも掴み、任務は順調かと思えたのでした。
しかし、キリシタンがトモギ村に潜んでいることを嗅ぎ付けた長崎奉行・井上筑後守が村に訪れ、ふたりの宣教師の身柄を要求したのでした。村人達は必死に匿いましたが、代償としてイチゾウ、キチジロー、そして敬虔な信者であったモキチ(塚本晋也)を含む4人の村人が人質となりました。奉行は踏み絵だけではキリシタンをあぶり出すことは困難と考え、「イエス・キリストの像に唾を吐け」と強要したのです。4人の内キチジローを除く3人は棄教しきれず、処刑されることとなったのです。
自分達を守るために苦しむ信者達を見てロドリゴは苦悩します。「なぜ神は我々にこんなにも苦しい試練を与えながら、沈黙したままなのか―?」と。タイトルの「沈黙」とは、この神の無言のことを指しています。これほど多くの殉教者の血が流れているのに、それをただ見つめているだけの神の存在に、ロドリゴは次第に疑問を抱くようになるのでした。そして、長崎奉行の井上筑後守(イッセー尾形)が語りかける「棄教すれば、信者を助けられる」という言葉に、固い信仰心が揺らいでいくのでした。
信徒には、執拗に弾圧の手を緩めないのに、狡猾な井上はロドリゴには衣食を与えて厚遇します。それは、ロドリゴに棄教を迫るための巧妙な手段でした。井上の直感では、ロドリゴは必ず“転ぶ”(棄教の隠語)ものと察しをつけていたのです。であるなら殺さず生かしておいて、しぶとく残る信徒の切り崩しに利用しようというのが、井上の魂胆でした。
現実主義の通訳(浅野忠信)にも諭され、ロドリゴは、信仰を貫くのか、信徒の命を守るために、信仰を捨てるのかという、聖職者として究極の選択を迫られます。井上が繰り出した奥の手は、棄教したフェレイラ神父にロドリゴを引き合わせることでした。これは、原作でもよく知られた結末です。でも本作では、スコセッシ監督が長い思索の末に見つけたラストシーンを用意していていました。一見蛇足のようなシーンですが、ロドリゴが心から棄教したのかどうか、原作よりも納得できることでしょう。
ところで、洋画としてキリスト教国の側から描かれる本作なのに、井上が憎たらしい悪役として描かれないところには驚かさせられました。
スコセッシ監督は隠れキリシタンへの弾圧について、こう語っていました。“「隠れキリシタンへの拷問は暴力でしたが、西洋からやってきた宣教師も同じように暴力を持ち込んだのではないでしょうか。『これが普遍的な唯一の真実である』とキリスト教を持ち込んだわけです。それに対処するには、彼らの傲慢をひとつずつ崩していくしかないと、日本の為政者は考えたのです。”と述べています。つまり井上の主張にも、日本人として当然の言い分取り入れられていて好感が持てました。
ロドリゴの主張には、「自分たちこそ真理」という信念に傲慢さを感じました。権威的なアプローチで教えを説いたところで、日本で受け入れられるやり方にはならなかったでしょう。彼の信仰には、「厳しく罰する、父なる神」としてのキリスト教の一面が強すぎて、本来の愛と救済の教えから遠ざかっていたのです。
そんなロドリゴに井上は、日本になぜキリスト教がなぜ根付かなかったのか理路整然と語りかけていくのです。そもそもなんで犠牲者を出してまで、自分の信仰を他国に布教する必要があるのかと素朴な疑問をぶつけるのでした。そして日本は仏教国であり仏の慈悲を諄々に説いたのです。
トドメは、フェレイラが語るサビエルによる日本布教の欺瞞。自然崇拝の強い日本人に対して、方便を使ってしまったのです。サビエルは、父なる神とは“大日”なんだと。キリスト教の信仰対象を、古来からわが国にあった太陽信仰に置き換えたのでした。だから日本のキリシタンが崇めていたのは、なんと大日如来だったのです。さぞかしロドリゴもこの言葉に愕然としたことでしょう。
ただ井上の言葉に、頑なにそれを拒絶しようとするロドリゴの気持ちもよく分かります。“自分こそが正しい”と、信じて譲らない頑固な老人と使命感に生きる生硬な青年。でも、彼らが使命を果たすこと、理想を求めることで、たくさんの信徒の命が失われる現実は変わりません。これは民族と宗教が相克し合い、無差別テロを引き起こしている現代にも繋がる、争いがなくならない世界への警句のようでもあると感じました。
わが身ひとりの苦難苦痛であれば、ロドリゴも棄教への迷いを微塵にも抱かず殉教したことでしょう。しかし、自分のせいで多く信徒に苦難がおよび、いままさに目の前で殺されようとしている信徒から、救いの声が発せられたとき、棄教しないという信念は果たして正しいことなのかどうか?
数多くの殉教者を輩出したキリスト教の歴史。それにキリスト教に限らず、信仰の本分からすれば、どんな苦難困難にあったとても棄教はあってはならないことです。しかし、棄教しなければ助けられない眼前の信徒の命という究極の矛楯。選択を迫られて苦悩するロドリゴに対して、同じ信仰を持つものとして涙しました。
こんな状況でも、神は沈黙したのか。そしてロドリゴはどのように変わったのか。熱烈なカトリックの家庭で育ったスコセッシ監督の演出に、ぜひご注目を!
そんな中で、行動に全く筋が通っていない弱き者、キチジロー(窪塚洋介)が救いとなます。ロドリゴをあがめているのに裏切り、神を信じていると言いながら踏み絵を踏むのに、神を畏れ、赦しを求めて何度もロドリコに告解を求めようとする彼の心情が、宗教に縁がない人には分かりづらいづらいのではないでしょうか。
しかし悪人正機説に立てば、彼ほど信仰を求めていた存在なのかのかもしれません。キチジローは『この世の中に、弱き者に生きる場はあるのか』とロドリゴに問います。この作品は、弱きを否定せずに、受け入れることの大切さを描いています。それは、人が人として生きる事の意味を考えることでもあると思うのです。
原作者の遠藤周作も、浄土真宗的なものにイエスを歪曲しているという批評について、エッセー『私にとって神とは』のなかで、日本的宗教意識として肯定しています。キチジローという存在は、煩悩具足の凡夫の象徴であり、浄土真宗の核心を描いた作品でもあるといっても過言ではないでしょう。
さらに本作でうれしいことには、「外国人監督が撮った日本」によくある違和感が、この映画には全くないこと。映画化にあたっては、17世紀の日本をどこまで忠実に再現できるかが大きなポイントでした。ふさわしい場所を求めて、ニュージーランドやカナダなど様々な場所を見て回り、ついに台湾で完璧なロケ地を見つけたといいます。舞台である長崎と、地形や天候が似ていたのが、大きな決め手になったそうです。
台湾での撮影にあたっては、台湾出身のアン・リー監督らの協力を得て、リー監督の『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』のために建造された水槽を活用。司祭たちが海岸の近くを移動するいくつかのシーンを撮影したそうです。
撮影では、京都の時代劇のスタッフも参加したそうです。そこに外国人の見方の加わったところが新鮮で、感銘の深い作品となりました。
スコセッシ監督のルーツは、カトリックの本拠イタリアからの移民の子にあります。昔日本に来たヨーロッパ人宣教師たちの無残な挫折のこの物語には、彼には日本人以上に身近で心に響くものがあるのでしょうね。
演技面では、キリシタンの立場を分かったようなフリをして、冗談など交えて残酷に裁いていく、イッセー尾形の飄々とした演技が素晴らしかったです。また通訳役の浅野忠信が教養と自負心でロドリゴを屈服させようとする演技にも説得力がありました。キチジローになりきった窪塚は、本作で世界に発見されることでしょう。
そしてなによりキリシタンの農民役として拷問や処刑にかかって、ギリギリまで強烈な大波を被りつづけたり、火であぶられたり、逆さに吊され続けた多くの出演陣の健闘をたたえたいと思います。
沈黙
私は、幸福の科学大川隆法総裁を根本仏と信じる信仰者です。この映画を見て宗教の立場から見て、最初は、キリスト教殉教の醍醐味と信仰を貫く信仰者の信仰の高さ純粋性、その反面の目を覆いたくなるような殉教を貫く残虐さを感じました。しかしながら、なぜ今この映画が作られたんだろうと恐ろしさが残りました。この地上では様々な宗教が、政治と時の流れに利用され、その救世主の意図が曲げられ、今では全然違う宗教が出来上がり、宗教戦争に各世界で勃発しています。この映画は、日本人の残虐性が残ってしまいます。あの徳川の時代に、日本にキリスト教を入れなくて正解だったのです。植民地化を目的とした国は、キリスト教牧師を各世界に送り込み、結局はその国を植民地にしていきます。勿論、牧師たちは植民地化が目的と知りません。只々、伝道が目的で思いは純粋なのです。私は、あの時代の徳川幕府の国・民を護るための日本の鎖国政策は間違っていなかったと思います。そうしなければ、今この日本はなかったでしょう。
それから、牧師が迷った時に、胸の内に聞こえてくる主からのメッセセージは、なかなかの真理がありました。この地上では、人間には自由が与えられています。しかし、この地上で何をしてきたのか、どう生きて来たのかあの世で裁かれます。この文明が発展しているこの時代に生きる人間ならば、この地上を幸福にする義務があります。
遠藤周作さんは、キリシタンですので日本で行われた殉教の拷問の酷さを表しいますが、同じ日本人として非常に残念です。なぜ、今この時代に日本人の残虐さの部分だけが残る映画が作られたんでしょうか?日本人の残虐さを世界に広める制作の怖さを感じます。
クリスチャンとして。。
皆さんおっしゃる通り「重い作品」です。
そして、私は心に刺さりました。
今、通ってる教会が九州の教会で韓国から宣教に来られて、教会も出来たばかりで信者さんも少ないとこに通ってます。
日本のクリスチャン人口は全体の2%と言われてます。
韓国やアメリカは恐らく50%以上はクリスチャンではないでしょうか
アメリカの教会も今、いろいろと揺れ動いてまして、事件も絶えません、韓国での教会も信仰なのかショービズなのかわからない状況にも来ております。
エルサレムを聖地とするキリスト教ですが、エルサレム自体もとても不安定な現状です。
クリスチャンだからこそ、そういった背景を感じ取れるので、同じクリスチャンであるスコセッシ監督なら熱望された映画化だと思います。
なぜ、今「沈黙」なのかではなく・・逆にやっと・・満を持して映画化されたんです。
僕自身も教会に通いながら牧師先生(プロテスタントですので神父さんではないです)の話に宗教的疑問を感じることも多々ありますが。。私は福音派(聖書に書いてる事を絶対的に信じる宗派)なのでイエス様の教えや、主の導きに関しては凄く生活に密着してます。 死んだら天国にいけるといった話が沢山出てきますが。。
平和な世の中で生活してるので、やはり「死んだら天国」という思想に関してはいまいち、執着しておらず。
イエス様の導きの元、苦難も恵みも全てを主が与えてくださってるという考えなので・・「私の人生は主のもの」「全てを捧げます」といった信仰生活を送ってます。
もっと、宗教感のお話は深いのですけど。。
そういった背景の元・・鑑賞したので
「踏み絵」のシーンは酷く心が痛かったです。
主が沈黙してるという部分に関しては、私たちクリスチャンにとってよく語られる名作の中にメルギブソン監督の「パッション」というイエスキリストの処刑までのお話を映画化した作品がありますが
そこでも、似たような描写がされます。
クリスチャン的教えとして、「主の大事な独り子」として遣わされたイエス様が処刑されてる間、主はイエス様の処刑を「沈黙」して耐えておられたという解釈があります。
そのため、主はいつも我らと一緒におられます。
そこで・・後半のロドリゴが踏み絵を実行するときに
「神様の声:福音」がします。
主は常に我らと共おられるからこそ、我らの苦しみも主は感じておられる、その苦しみは十分にわかっておられるからこそ、
「私を信じなさい、そして踏みなさい」とおっしゃっておられたのだと思います。
主イエスキリストとの関係性を維持したという描写が・・
皆さんが・・最後の描写はいらなかったんじゃない?だらだらと・・と思ってる部分ですが。。
クリスチャンとしてはとても、あのシーンは重みがあるのです。
私たちは、今でも小さな迫害はあります。
いじめられることは無いですが・・さすがに、受け入れてはもらえません。
同じキリスト教でも沢山の宗派があり、社会問題にもなってしまった残念な宗派もございます。
そのため・・よく勘違いもされますし、「アーメン、ソーメン」などともじられたりもします。
弾圧まではいきませんが、やはり日本にはまだまだそういったキリスト教への反発は根強いです。
そんな中で生活をしてると・・例えば食事の前のお祈り、寝る前のお祈り。。やはり色眼鏡で見られます。
だからこその、最後にロドリゴ牧師が十字架を持って埋葬されたシーンについては・・何度も踏み絵をさせられて、何度もくじかれそうになり・・仏教の思想を押し付けられた人生の中で。。
恐らくロドリゴ牧師は・・棄教したときは30代ぐらいだったのではないでしょうか?
バチカンに帰ることも許されず、宣教師としての目的も果たせずに、ひたすら最後まで生きるだけのための人生を主に捧げたのです。
その長い年月を思うと・・涙なく見れません。。
だからこその、最後のエンドクレジットで立つことも出来ずに
その場で僕は黙想(祈り)をしました。
場内が明るくなるまで・・黙想しました。
そのため、最後に「日本に来られてる宣教師・牧師に捧げる」とメッセージが添えられてました。
ここまでは・・クリスチャンとしての立場で観た感想です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからは。。
映画ファンとしての意見です。
マーティン・スコセッシ監督作品は、一通り見てきました。
そのうえで申し上げますと
個人的には「グッドフェローズ」が一番好きな映画なんですけど
「ウルフオブウォールストリート」がその次に好きな作品。
そして・・そういった部分も見事に塗り替えて
「スコセッシ最高傑作!!」と思いました。
サントラも、あるにはあるのですけど。。
今作、極力・・背景に音楽を置いてないです。
タイトルの「沈黙」をしっかりと根底に置いて・・
音のデザインが秀逸です。
自然の音の使い方がもう・・絶妙で。。
感嘆いたします。
あと・・日本人役者のポテンシャルを余すことなくどころか引き出し方が上手いというか・・こんなに凄いんだ!!日本人!!ってくらいに・・登場人物の演技がどの方も素晴らしすぎます!
まさに、奇跡の映画です。
カメラワークですが。。
1人称視点のカメラワーク恐ろしくリアルで、ロドリゴの視点そのもので「追体験」をさせられましたが・・「見てるしか出来ないジレンマ」がじわじわと・・心に負担をかけていきます。
登場人物のアップも、必要不可欠な感情表現のアップや
光と影を絶妙に取り入れての撮影など。。あらゆるところに芸術性の高さも見て取れました。
時代背景としては1640年なので、前の年にポルトガルからの船を禁止して鎖国が完了した年の翌年にあたり。
3年前には天草四郎が率いての農民一揆が起きてるので。。
江戸幕府としても、もっともキリシタン弾圧が激しい時期だったんだと思いますが。。
その江戸時代の長崎周辺の再現度が半端ないです。。
もう、これを見せられたら・・日本映画の時代劇がなんて酷い作りなんだと思わざるおえない。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
観る人によって感じ方が分かれるのは当然なのですけど。。
どちらかの視点によらないと、痛烈に刺さる作品の成立は難しいとは思うのですが・・どちらの言い分も丁寧に描いてる作品だなとは思いました。
ポップコーン片手にビールでも飲みながら観れる映画ではないですね。
厳粛に真面目に、向き合う覚悟で、そこからすべてを拾う覚悟で挑まないと・・何も伝わりませんし。。
斜に構えてみてしまうと・・うっかり拾い損ねる部分が大いにあります。
また、宗教映画なので・・信仰がなくても観れるのですけど
信仰がないと深いところまでは理解出来ないので意味不明な部分が何か所も出てくるかもしれません。
哲学的な部分も含まれてるので、一言一句に自分なりの解釈や思考を織り交ぜながら鑑賞しないと、下手すると寝るかもしれません。
全体的に、脚本も原作も素晴らしいので、真剣に見ればしっかりと最後まで観れる作品なので。。
万民向けではないかもしれません。
それでも、「人生に残る映画」のひとつになりうる衝撃は与えられる作品としてのパワーは計り知れないですね。
評価不能
エンドロールは秀逸
禁教令による切支丹弾圧という史実。 どの民族にも負の歴史は有るだろ...
"Silence" is an epic historical drama film
"Silence" is directed by ,one of my favourite directors, Martin Scorsese, who is known for directing "Taxi Driver", "Raging Bull", "Goodfellas", and "Hugo" and stars Andrew Garfield (Amazing Spider-Man), Adam Driver(Star Wars Force Awakens), Tadanobu Asano and Liam Neeson(Schindler's List).
I'd been waiting for this film since Martin Scorsese just planned to make this. Although I haven't read the novel by Shuuskaku Endo, which bases this story, I've just studied this era in which Christianity had been banned in Japan and Christians were forced to step on a fumie to make sure that they renounce their faith. Honestly I was not really good at this era in Japanese history class cos the textbook just depicts some particular events really briefly, nevertheless it's full of words that we have to know at least to apprehend that era. Whereas lots of things that I didn't know or remember got absorbed into my brain through this film, even which runs for only 160mins (though as a film, it's a little bit long). I just would like to thank Martin Scorsese for making such a brilliant epic for us. It's really worthwhile watching this but one thing that I want you to know is that this even, in which Japanese people torture Christians, what is more, decapitated them, actually happened about 400years ago. Kinda curious about how Christians feel if they watch the film though.
Hope Silence will win some Oscars this year.
すごかった! 観ればわかると思います!! キチジロー役の窪塚洋介さ...
重いです
全421件中、361~380件目を表示