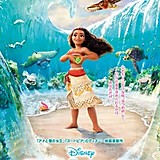沈黙 サイレンスのレビュー・感想・評価
全421件中、341~360件目を表示
大作
マーティンスコセッシありがとう
まず概ね原作通りで安心しました。原作ファン、遠藤周作ファンという人...
まず概ね原作通りで安心しました。原作ファン、遠藤周作ファンという人でも、(著しく過度な期待をしない限りは)ハリウッド映画でよかったと満足できると思います。監督がとても原作を尊重してくれているのが伝わりました。
ただ原作通りな部分が多い分、原作を読んでいないとちょっと分かりにくい映画かもしれません。有名な小説ですが、未読の方はぜひ読まれるといいと思います。
公開前から少し心配だったのが日本人俳優陣だったのですが、こちらもなかなか頑張っておられてよかったです。個人的にキチジロー役はもう少し小汚いおじさん(失礼)のイメージだったので、ちょっとピュアで綺麗すぎてんん?となりましたが、まあ彼が一番むずかしい役だと思いますのでこれも1つのキチジロー像かなと納得です。
命を救うのか魂を救うのか
江戸時代の宣教師の苦悩を描いた作品
冒頭の湯気での全体が見渡せない雰囲気、主人公達の赴く村での霧のシーンなど、得体のしれない不安、掴みどころの無さなど開始そうそうに引き込まれました。
布教、師匠探し、信者からの需要、自分自身の信仰、大いなる覚悟の下、アンドリュウ・ガーフィールドとアダム・ドライバーの二人の試練の日々。話が進むにつれ揺らいでいく姿が全編通して良く描かれていたと思う。
日本俳優陣の演技もとてもよかった。主要人物は英語で台詞を言うのですが、浅野忠信以外はたどたどしかったように思う。
当時の日本に英語を話せる人が何人いたかわからないが、日本訛りの英語それはそれでいい味が出ていたようにも思える。
イッセー尾形の演技でしばしば笑えてしまったが、冷酷な時に見せる表情と緩急はさすがだなと感じた。
塚本監督はかすれ声と表情が正に幸薄い村民感だ出ていたし、芯に強い信仰があるからこそどんな事でも耐えられる、そんな目をしていた。
窪塚洋介の役は本当に難しかったように思う、弱い人間の姿、意地汚さ、苦悩、救い、一番人間らしいが一番成りたくない人間。
全てを演じ切れたようには思えないがそれでも観客の心に強く残ったはず。
以前「殺し屋1」見ていたため、浅野、塚本の新旧演技が比べられてよかった。
金子役のSABU、菅田俊も役人役で出ていたので少し嬉しかった。
スコセッシは「殺し屋1」見てるんじゃないだろうか・・・
現世で救う命と死後、天国で救われる命
宗教の命題、今作は明確な答えを出してくれない、そもそも答えなど無いのかも知れない。
ただそれぞれの信仰は自由だし誰も辞めさせる権利はない、全ては自分次第なのだ。
他人にとやかく言われる筋合いもないし言う必要もない、来る者を拒まず去る者を追わない事が大切なのかと思う。
自分自身あまり宗教とは関わりが有るほうではないが、信仰が有ることで強くなる人もいるし、どうしようもない状況から救われたい、縋りたいという気持ちも解からない訳でもない。
幸か不幸かそんなに追い詰められた状況になった事もないし、縋るほどのモノを持たないがこの作品を見て自分自身に納得のいく生き方ができればそれでいいのではないかと思った。
劇中セリフより
「神は許してくれますか?こんな俺でも」
罪を犯し懺悔すれば許されるのなら悲劇は続く、許さなければ永遠に落ちていく。
自分の行動に責任と納得できる行動をとる事、失敗したなら反省し次に生かすこと、小学校で習うような事を思い出した。
自分に出来るかわからないが、目指す意義はあると思った。
はてしなく重い祈り
熱量
スコセッシ監督が、ずーっとつくりたかった作品。
その熱量が、本当に、細部から、全ての質感やセンスから伝わってくるものになっています。
音のセンスがまた、本当に秀逸です。無駄に音楽をつかいません。
原作を読んでいないので、原作ファンの方の持つ違和感はわかりませんが、信仰があるないに関わらず、また洋画邦画と意識せずに見られる大作です。
162分と長いですが、これは描くのにはそれくらい必要だと納得。
他の方も書かれていますが、【外国から見た日本の描き方】の違和感は感じません。日本人キャストの力もあますところなく出されていると思います。
どちらかと言うと二枚目担当なイメージのある窪塚君が演じる姿は、もう何枚も脱皮したような印象です。(色々経験されて昔とは違うのかな)
信仰と、目の前の信徒を救うこととの矛盾。迷いや苦しみの中、神の福音(声)を求め続け、絶望し、彼が一番拒んでいたことを受け入れるその瞬間に、神の存在を感じる矛盾。
原作を読んでみたいと思いました。
かつて日本においてもこんなにも信仰で苦しんだ人々がいたことー歴史の知識でしか知らなかったことが立体的に、重さと苦しさ、胸の痛みの実感をもって、知る機会になりました。
観るのに受け止める気力が必要ですが、それに値する作品だと感じます。
完全な無音の「沈黙」は映画館でしか体験できない。
ネタバレしないように気をつけたので、薄く書きます。
まだ見てない人のために最初に伝えておくと、この作品はエンドロールですらBGMが流れません。
従って、映画館で売っている食べ物であっても食べたり飲んだりすると異常に響きます。
結論から言うと、本当に見て良かったです。
なぜ映画館で観るべきかというと、
強制的に、耳が痛くなるほどの無音状態を体験できるのは映画館だけだからです。
この映画の大事なポイントは、題名の通り「Silence」
本当のSilenceを体験でき、理解できるのは映画館でだけ。
とあるシーンで完全に無音になります。
その無音が意味するところを、噛みしめる事ができるのは映画館でだけです。
なぜキリスト教が日本に根付かないと思うか、井上筑後守がとある物に例えて言うセリフが、いち日本人として心に残りました。
ぜひ、映画館で見てください。
神は沈黙していない!
誰もが考えること
こころは常に動く
劇中の日本の情景や、鈴虫の音色が、何故か今日は悲しく感じた。
日本の島たるものも少し垣間見た気がする。
田舎は余所者を嫌い、学歴や、見かけ、生まれを特に気にする。
権力や地位たるものは、時に暴走さえもしてしまう。
そもそもなぜ異教を拒んだのか。
また、なぜ、布教を目指したのか。
にっぽんの光には多くの影が潜んでいる。
正直に生きることは裏切られ、嘆くその時、人々は何を真実とするのか。
誰もが、明日に希望を持つ為、生きる為、日々何かしら祈っている。
それは、神であり、現実であり、そして、母だ。
踏み絵や、真っ直ぐな人々が命を落とし、今のこの自由な時代があることを忘れてはいけない。
静けさを動かすものは、人、そして、心でしかないのかもしれない。
映画『沈黙 サイレンス』評
映画『沈黙-サイレンス-』(米2016/マーティン・スコセッシ監督作品)評
-音が探求する真実を映像に求める時観る者は捜索者として君臨する自己証明の有りかを液体の変容過程の中に見出だすのである。その時人は映画が炎という記号が醸す光の存在である宿命を認識するであろう。それがリュミエール兄弟への潔い諦念である事を再認識させるに足るこれは映画の原点を光と影に求めるまさしく探求者の映画である-
深い霧が立ち込める地獄温泉での宣教師の棄教の為の熱湯による苛酷までの拷問作業に従事する幕府方の周囲には霧深さを浸透する湯気の荒々しさまでもが加担する蒸気と大気のあくなき交錯が醸されそれは映画に独特のダイナミズムの発生装置を担わせる。
マーティン・スコセッシ監督はこの膨大に廻したであろうフィルムから元編集マンの実績からも無駄を省いた自己の映画論を宣うべくキリスト教がヤソ教と蔑まれ禁令さえ発する日本の江戸時代との確執の中でまずポルトガル宣教師の強靭なる意志力によって耐え抜く為の力学を五島列島のかくれキリシタンに伝授してゆく。筑紫守の強硬な踏み絵作業に加担しない人間への痛烈なシウチには宗教戦争の過酷さを知る事だろう。
さわさわと騒ぐ虫の音がピークを迎えた途端なりやむ時映画はタイトル『サイレンス』だけが黒画面に描かれる。この時この映画が例えモノクロであっても何等不自由しないとも謂えるほど血の赤さが鮮明さを誇示するのも幾度も踏み絵の対象となるイエスの肉体そのものの静止がまさに沈黙という二字に纏わる事でこの映画が沈黙と深く渡り合う時こそが映画の説話的磁場である筑後守の制度との沈黙の闘争劇として成功している。これはそんな音の探求が映画という視力を得たものの特権を担う観衆自らがこの宣教師に擬え音から派生する映像に於いて真実への捜索者を施行するノエマによる自己証明へのあくなき探求を量る事となる。
それは主題とも関わる記号体系としての液体による変容が映画の進行により様々な形態を示唆するプロセスを歩む時のキリスト教に於けるナチュラリズムの根源を伺わせる。島雨特有の冷徹さに満ちた水の表情はやがて神の沈黙に於ける宗教が切り捨ての被写体と成るときこそかくれキリシタン達の責め苦の材料として十字架に張り付けられ冬の高波に浴びせられ死んでゆく凶器とも謂えるだろう。または宣教師の喉の乾きを癒す為の雨水からそれが人間誰もが流す体内の血肉が拷問の一環として役人がかくれキリシタンの若人の首を撥ね囚人達の罵声と泣き声のカオスからその身体を引きずる時の血の轍が死生観を喪失させる唯物的描写はいかにもユマニストに
徹するスコセッシらしい呆気ないそぶりが潜んでいる。
そして行方不明のフェレイラ神父の回想場面での拷問として逆さ吊した時に耳に開ける傷から自然に漏れる血の色にはキリストのたっ形を倒錯させた拷問形態としてその苛酷さが窺えるのだがこれこそは彼の踏み絵と棄教の原因ともなるまさに人間回帰の原点的な血でありこのキリシタン狩りによる自己犠牲の儀式の終焉としての収束した血でもある。
然しそれは決して最期ではなくスマキにされた女達を舟からふるい落とし海水による溺死へと導く時の凶器の海水そのものが晴天下に行使される時映画はマリア不在の悲劇的クライマックスを向かえる。
スコセッシはこの液体の変容過程からも自らを宗教映画監督とは決して見做さず虚構的空間に於ける唯物史観に則ったイタリアン・ネオ・レアリズモの申し子或は末裔として任ずるこの水にキリストの顔を浮かばせるほど些かシニカルな視点を有しており決して審美観でフィルムを廻してはいない。そこが似た題材を映画に持ち込んだタルコフスキーへのシニカルな一瞥でもあろう。
マーティン・スコセッシ監督はこの雄大な土地を背景とした映画の中で自然が創造したキリスト教の当時の位置をその自然界を司る天・地・水・風そして映画誕生の兄弟リュミエールへ敬意を払うべくラストの宣教師の収まった棺を炎で焼く場面にカメラまでもをその中まで侵入させる時晩年は棄教し検閲等で余生を暮らしていた死んだ彼のその手の中に光る木彫りの十字架のイエスに接近する時この映画の主題体系が実はフランス語リュミエールの意味に自然と繋がるのだ。もうお分かりだろう。それは常に女性名詞(マリアに代表される)である所の「光」の存在であるからに他ならない。
(了)
浅野忠信は色気で人を殺せる
日本は「建前」の社会なのだと思う。
キリシタンへ踏み絵を命じる役人達が「形だけでよい」「指をかすめるだけでもよい」と言うように、それが本当に背教の証明だとは思っていない。百姓達のキリスト教信仰を根絶できるとも考えていない。ただ公に聖画を踏んだという事実が重要なのであり、社会としてキリスト教を禁止する体裁が必要なのである。
井上奉行が背教司祭となったロドリゴに何度も証文を書かせたのも、棄教の事実を公的なものとする建前を求め続けたからであり、しかし一方でキリシタンの残る村を紹介したりしているのだ。
そんな日本社会へ最終的に順応することを選んだロドリゴは、幕府の禁教政策に協力し、日本名を授かり、神の名を遂に口にすることなく死んでいきながらも、最後まで信仰を捨てていなかった。
背教司祭という建前を守り抜き、座棺の中で隠し持っていた十字架のように、心の中でひっそりと神を信じ続けたのだ。
必要に迫られればいつでも踏み絵をし、ロドリゴを裏切ることもした弱く卑しい窪塚洋介も、心の中では常に神を信じ続けていたのかもしれない。他の村人達と違い、形ある信仰の証を欲しがらなかった彼は、最後までロドリゴを追いかけ告悔をし続けた。
社会は心の中まで取り締まることはできない。心を裁けるのは神のみである。
信仰とは何か。ロドリゴは布教の志を捨ててしまったけれども、一方でその答えにたどり着くことができたのだと思う。
・・・なんて、とくにキリスト教とか宗教に詳しいわけでもないが、色々と考えてしまいました。
キリシタン達に降りかかる数々の苦難や拷問のシーンは、本当に観ていて苦しくなるし、ズシンと重たい気持ちが残るものの、どこか希望というか救いも感じられる不思議な鑑賞後感です。
蜩の声による「日本」感醸し出し効果はすごい。
ちょんまげで英語を喋る浅野忠信は至高。
「ラスト・プリースト」なわけで
重厚で厳かな圧倒的な画力。ブラックアウトで始まり、ブラックアウトで終わる。そこには自然音だけが響いている。"神"は一貫して沈黙したままだ。エンドロールの余韻が深い。
カトリック信者であり、キリスト教文学を多く残した遠藤周作だからこそ、生来のクリスチャン(=マーティン・スコセッシ)による映像化は待望といえるかもしれない。ただひたすらにスコセッシの原作への想いが強く迫ってくる。
キチジローは"ユダ"だし、ロドリゴは"イエス"、井上筑後守は"ローマ総督"なわけで、クリスチャンに刺さる内容ながら、一方で宗教的な解釈を持たず、単なる歴史映画として観ることもできる。日本人による日本語で書かれた原作なわけだから、自由な解釈で観てかまわないはず。エンターテイメント性はゼロだが・・・。
「ラストサムライ」(2003)ならぬ、「ラスト・プリースト」である。"日本人って何なのか"をガイコクジン目線で語られるとドキッとする。そんな映画のひとつになる。"大自然"に神を見い出し、"絶対神"ではなく、キリストを自己都合の解釈で消化してしまう日本文化の土壌を客観的に指摘していたりして。
カトリック信者には評価が分かれる原作だが、字幕をカトリック・イエズス会司祭で上智大学文学部教授の川村信三氏に監修依頼しているので、しっかりと考証のバックグラウンドは押さえられている。
ホントは茶化しちゃいけないとは思いつつも、宣教師フェレイラ役のリーアム・ニーソンは"クワイ=ガン・ジン"だし。悩む司祭仲間のアダム・ドライバーは"カイロ・レン"だし。そうなるとフェレイラを"師"と仰ぐ、アンドリュー・ガーフィールドが長髪を後で縛っている姿がユアン・マクレガーに見えてくる(笑)。すみません。
(2017/1/21/TOHOシネマズ日本橋/シネスコ/字幕:松浦美奈/翻訳監修:川村信三)
「観てよかった」と「観て欲しい」の違い
「見てよかった」と「見て欲しい」の違い
マーチンスコセッシ。
名前は知ってる。
昔観た「ケープフィアー」を
おぼろげに覚えてるくらい。
そんな知識の私が観た結果。
この映画は、、、。
「怒り」のレビューでも書いたのだけど
「観てよかった」映画であって
「観て欲しい」映画ではないかな、ということ。
勧めたくない、訳ではない。
胸を張ってお勧めできる映画なのだが
人と、観るタイミングを選ぶ映画。
テーマも重いし
序盤の絵面も重たい。
長い上映時間も相まって
気力と体力に自信があるタイミングで
ぜひ観に行って欲しい。
そんな映画。
間違っても残業明けの
レイトショーなんかは
お勧めできない。
この映画を選んだ理由は
とにかく窪塚洋介が見たかったから。
アイキャンフライしてから
映像の世界からは遠ざかっていたが
はじめて劇場で「GO」を見たときの
あの衝撃は今でも忘れられない。
その窪塚洋介。
・・・。
どうも私の頭の中に
未だにIWGPのキングの
残像が残っているために
狡い、強かなキチジローと
一致せず、そのまま消化不良で
終わってしまった。
普通ならこれで「つまらない」
と、終わってしまうところだが
他の日本人キャストが
なかなかよかった。
やはりイッセー尾形だろう。
怪優が見事に怪演した。
薄ら笑いに甲高い声。
喉が渇いたり
立ち上がるときに発する
「ん、ん、ん」という
お付きのものに甘えるような声。
あんな演技は
彼しかできなかったと思う。
海外の人にどうな風に見えるんだろう。
そんなことばかり気にしながら観ていた。
あと驚いたのが
浅野忠信。
この人の演技って
日本語だとボソボソ
抑揚なく喋ってる感じがして
あんまり好きじゃないんだけど
英語でのセリフを聞いて
こっちの方がしっくりきた。
この人の英語力ってどうなんでしょう?
ネイティブの方、お教えください^_^
それ以外にも贅沢なくらいに
有名、個性派の俳優陣を起用。
160分の映画だったが
その時間ほど長くは感じなかったな。
外国映画によくありがちな
日本の風景の再現力の低さはなく、
不自然にならなかったのも
引き込まれた一因なのかも。
エンドロールも個人的に
すごくよかった。
もしここでタイアップした
どっかの有名アーチストの曲が流れたら
一気に白けてしまうところ。
ただ、自然の音を淡々と流す。
この映画にはこれ以上ない
素晴らしいエンドロールだった。
残念なのは
途中で出てきた
EXILEののAKIRA。
アーチスト、パフォーマーとしては
すごいんだろうけどね。
このいかにも
ねじ込まれた感がある
キャスティングは如何なものか。
結構重要なシーンだっただけに
学芸会のような演技に
場が一気に盛り下がってしまったのが残念。
兎にも角にも
一度マーチンスコセッシの映画を
ちゃんと見てみようと思わせてくれる
そんな映画だった。
PS:
これは偶然だと思うが
予告が終わって本編が始まるときに
2分近い「沈黙」があった。
これはもしや、タイトルに引っ掛けた
イオンシネマの粋な計らい?
・・・な訳ないか。
ちょっと、面白かったので
蛇足。
信仰
やってしまいましたね、
見事な大失敗ですね。
沈黙+スコセッシでかなり期待していたのですけど、殆どマイナス評価ですね。
真面目な話しですが、何を間違えてしまっているのでしょうか?
ちゃんと小説の中身を捉えているのでしょうか? 理解しているつもりなだけなのか? それとも脚本を誰かに丸投げしているのか?
配役も変だし、、、
悪い点を挙げればキリが無いです。真面目な意味でのツッ込みどころ満載です。ホントに遠藤周作を読んでいるのかなぁ?
例えば小説の最も重要な配役であるキチジローです。彼は3人の心を持っていなければならないのに、誰の心も込められていません。込められるべき3人とはキリストでありユダであり、主人公ロドリゴであります。それらを通じて神を感じる事が主題なのです。
神が沈黙の中に於いても主人公の苦しみを分かち合っていると云う事をキチジローを生き鏡として表現しなければならないのに、何にも表現出来ていないです。そしてその神の苦しみはキリストの苦しみであり、またユダの苦しみであると云う事を理解させなければならない。
この映画では単純にキチジローをユダ扱い程度でやめてしまっている。キチジローが何度も踏み絵を踏んでいる事が本当の神のメッセージである事を伝えられていない。
もっとも、窪塚洋介じゃあ、こんな難しい役はこなせないでしょうね。キチジローはみすぼらしく卑しい人間として演技しなければならないのに、トレンディドラマみたいな演技で眼光をギラつかせてちゃ台無しですね。ありきたりの演技で、韓流と間違えているんじゃないでしょうか?
本人はどうやって上手に英語を喋るかに夢中だった感じで、本当は英語の聞き易さなんてどうでも良い事に格好を付けようとするんで、本来果たすべきキチジローの人間表現が全く成り立っていないと云うかブチ壊しなんですね。まあ、本来なら小説を読んだ時点で自分の実力に見合っていない事を早々に悟って、辞退しといた方が良かったんですけど、この人は仕事が来れば何でも食い付くんでしょうか?
次に最悪なのがイッセー尾形です。私はイッセー尾形さんは十指に入る大好きな芸人さんですけど、彼の一人芝居をそのまま映画に乗っけてる様で酷すぎます。元々、映画の演技などとはカテゴリーが違い過ぎるんで、、無理なんです。その上、アフレコの英語が外れまくっています。多分、アフレコ時に英文を読むのがやっとで、自分の舌を見てる余裕が無かったんでしょうけど、誰かちゃんとサポートしてあげて暮れなかったんでしょうかね?
イッセー尾形の井上筑後守の役はキリストを処刑したときのローマ総督を追体験しようとする者だとは、誰も教えてあげていないのでしょうか?
そして、この映画の根本をひっくり返しているのが、神様が喋くりまくる点です。遠藤周作が一番悩んだであろう沈黙をいとも簡単に破って、あれこれ神ツイート三昧です。オマケにイメージ画像付きです。「やってくれるね~!」って感じですね。どうせ神様が喋るのであれば、主人公の声でやるか、キチジローの声でやれば何とかなったんでしょうけど、ありきたりな野太い声でやられてしまって残念でつまらないです。
で、未だあるんです。本当のクライマックスである、逆さ吊りの刑での呻き声のとこですね。小説ではこの呻き声に悩まされる過程が主人公の棄教への最も大事な契機になっているのに、、、、 30秒くらいでサラッと流されちゃいました。「えっ! あれっ? はっ? どうしたの? こんだけ? えっホント? どう云う意味?」って、暫く凍り付きました。「じゃあ、いったい、この映画は何が表現したいんダヨ?」と、「ただのエンターテーメントじゃん!」て感じで情けなくて仕方ありません。
まあ、棄教した後も長ったらしいし、「小説の方はこんなにダラダラしてたっけかな~?」って思い出しながら観てましたけど、、、 要は説明が必要なんですね!!、、いちいち、、本編の映像表現で出来なかったんもんで、、 映画でこんな長いナレーションは私は聞いたことが無いですね。落語の枕話しよりも長い!! 誰もそんなの聞きゃあしないよ!!
エンディングのオチは、まるで学生映画か何かのノリです。こんな事しなくても良いのに、、、 主題が入れ替わってしまっている感じです。
でも、世間の評価は良いみたいですので、興味のある方は観てみましょう。但し、観た後に小説の「沈黙」を読み直すのを忘れないで下さい。この映画と対比する事で、遠藤周作が何を問いかけようとしていたかが理解し易くなるでしょう。そうする事によって、小説「沈黙」の本当の意思が伝わって来ると思います。
違和感あり・・・
内容はさておき当時の役人があんなに外国語に堪能だったでしょうか。また教えてほしいのですが外国語を使うシーンがすべて英語だったように思います。パードレはポルトガル人なのでポルトガル語が全く聞きとれなかったように思いますが。
せっかくいい映画なのに違和感を感じる理由です。
全421件中、341~360件目を表示