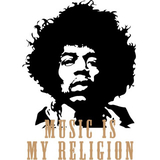たかが世界の終わり(2016)のレビュー・感想・評価
全37件中、1~20件目を表示
何も言えねぇ
あらすじでは魅力が伝わらない系映画。
余命少ないことを告白するために帰ってきたはずなのに、家族が全然言わせてくれない。昔の家にも行かせない。恨みや疑念、冗談で誤魔化したあと、やっぱり愛してる…と仄めかすツンデレ家族。面倒臭すぎて主人公に同情したけど、12年も表面的な付き合いしかしてなかった奴がいきなり現れたら動揺するんかな。あと母や兄の「聞きたくない」ってのが死の予告に対する発言なら、不器用な愛情の発露でもあるのかもしれない。
何も言えないまま映画が終わって少しびっくり、でもずっと観てられるので不思議。私はあと3時間同じことが続いてもぎり観れます。
ちょうど田舎に帰省中。気取った映画ばっか観てんなと姉に怒られ、自分の行く末を予言されているようで妙に沁みました。
フランスの家族はこんなもの??
ネットでの評判やカンヌ映画祭のグランプリ?作品とのことで鑑賞。
見る前の簡単なあらすじ読んで、これ日本人に理解できる内容かな?と少し不安を持ちながら見てみたら、案の定な内容…
正直、ほぼ意味がわからなかった。息子に久々に会うのに化粧やネイルして準備をし、自分が話したいからと明らかに周りはうんざりするのがわかってて、何度も話したネタをいかにも今初めて公表するかのように話す母親の気持ち。
何につけても揚げ足を取るような発言をして周りを苛立たせ、しまいには俺が悪いのか?とブチ切れ始める頭のネジの3本くらいなくなった長男。
どう考えても機能不全家族だろ?こんな話見せられて意味不明、心も暗くさせられ、なんの時間過ごしたんだろ?というのが率直な感想。
長男が殴りかかる寸前で拳がわかるように映っていたが、何度か殴ったことのある傷跡が見れた。ここからきっと普段周りにも暴力振るっているんだろうなというのが推測される。
大体長男は最初見た時、あまりにも帰宅した弟と比べて老けているので親父かと思っていた、兄さんって呼ばれたのでその時点でようやくわかった。
自分にはどうしてグランプリ取れたか理解がし難い内容でした。
強いて言うなら、昔流行った『恋のマイヤヒ』が途中でかかったこと。とても懐かしく思わず替え歌で口ずさんでしまっていた。
疲れた😓
私の世界の終わり
私の世界は終わります
でも、周りの人の世界は続いていき
過去から未来へと継続される流れは、変えたくてもなかなか変わらない
人生の転機をきっかけに話して理解を得たいが
話すことすら難しいそんな家族の関係性で
結局話せずに終わる
話せていたらお互いにもっと理解し労り合う事ができたのかもしれないが
現実は無情でそれを許さない
関係性を描くのに会話にちょっと頼りすぎかな?
って少し思った
キャストは悪いと思えないので脚本がもうちょっとだった感じがする
タイトルは色んな事を想起させて面白かったんだけどな
タイトルなし
フランスの豪華キャストが出演するが、死を告げるために久々に故郷に帰ってきたが母、兄夫婦、妹はいがみ合い、まともな会話ができず、ラスト迄言い出せない。そのもどかしさがあまり特徴的に表現されておらず、いがみ合いだけがうるさく残った。
自分の事ばっかりの家族
すぐに怒りの沸点に到達する兄と妹。
引っ込み思案の兄の奥さん。
同じ話しを何度もする母。
今まで家族に無関心だった主人公。
物語は主人公ルイが自分の死期が近くなり長年会ってない家族に会いにいくが、中々話せずに他愛もない話しや感情のままに怒り狂うケンカに発展したりと死期が話せない。
そりゃそうでしょ。ずっと無関心だったくせにいきなり帰ってきたなら、何かあるだろうと勘繰るのが普通。
喋らせまいと残された家族も必死にもなります。
ルイも優しそうな雰囲気だが、実家のマットで思うのは昔の彼女と自分の事。家族の思い出は?
そんな家族無関心男がいきなり帰ってくるんだから、兄は怒りのボルテージマックスでしょう。
ルイとアントワネーヌのドライブはルイが家に到着前の空港の話しをするけど、アントワーヌには響かず。
今まで家族をほっといて今朝の話しをされても怒りの沸点低いアントワーヌにはグツグツに煮えたぎった怒りをぶちまけるだけ。
その後の家族の前でのアントワーヌの思いの吐露。
そして、色んな壁にぶち当たり1人孤独に死にそうな小鳥。主人公は自分と重ねたのかと思います。
いやぁ、演技合戦がすごいですね。
名優揃いで特にアントワーヌ演じるヴァンサンカッセルはすごかったなぁ。
あんな扱いづらい人にみえますもんね。
全編を通して顔のアップも多く、演者さんの表情、特に目で何かをメッセージを残してるような演技は皆さん素晴らしいですね。
重たい映画で見終わった後にはズーンとなったりしますが一見の価値ありです。
Juste la fin du monde
「愛が終わることに比べたら、たかが世界の終わりなんて」
12年ぶりに帰省をする主人公・ルイ。その帰省は間も無く訪れる自らの「死」を家族へ告げるためでもあり、『僕という存在の幻想を、他者にそして自分に遺していく』ための「旅」でもあった。「作家」という設定を背負ったルイらしい決意だと感じた。
ルイ役のギャスパー・ウリエルがDVDの特典映像のインタビューで語っているように、この映画のテーマは「思っていることをはっきりと伝えない、人間の意思疎通の物語」であるのと同時に、私は「絶え間なく流れる"時間"がもたらす変化」でもあるのだと思う。劇中に登場する鳩時計や、移ろう太陽の光、そして"12年ぶり"の帰省がその象徴だろう。
「人間の意思疎通」に着目してみる。劇中で登場人物によって交わされる言葉は、どこか意味ありげで、ストレートさに欠ける。そういった台詞は、役者陣の陰影ある表情と共に語られ、この映画の持つ雰囲気を最大限に演出するのに一役買ってもいるのだが、やはりルイの12年もの不在の間に、残された家族にもたらされた様々な「変化」によって、より現実味を帯びたものになっているのではないだろうか。淡々と交わされる言葉に抵抗を覚える観客も居るだろうが、この映画が描きたいのは分かりやすい家族像ではなく、監督・グザヴィエ・ドランが語るように、よりリアルな「不完全な人間模様」なのではないだろうか。
次に「絶え間なく流れる"時間"がもたらす変化」に着目してみる。劇中でルイの母・マルティーヌが昔話を楽しそうに話す場面がある。しかしそれを拒むかのように話を遮る長男・アントワーヌと長女・シュザンヌ。加えて死を目前にしたルイのかつての恋人との回想と、昔住んでいた家を訪れたいという台詞が挿入されている。過去を忘れたい子供達と、過去を大切にしたい母。今となっては、お互いの向いている方向が食い違う。幸せだった日々を思い出すことで、現在との違いが明確になるならば、目を背けたくもなるだろう。アントワーヌの妻・カトリーヌは、ルイが家族に無関心だと言う。取り留めのない絵葉書を送るだけで、12年の間に家族に何が起きていたのか知っていたのだろうか。母・マルティーヌはルイに語りかける。「シュザンヌは家を出たいの」「アントワーヌは自由が欲しい」12年もの間、確実に時は流れ、家族にも変化が起きていたのだ。そんな折、ルイは自らの死を伝えに帰省するも、今の家族を目の当たりにしては伝えるに伝えられないのも頷ける。決して「家は救いの港ではない」のだったから。
ラスト20分。一家はデザートのため再び食卓を囲む。ついにルイが口を開き「もう帰らないと」と言う。12年も不在にした挙句、残された家族の気持ちなど知ることもなく突如帰省し、重大なことを伝えにきたルイに拳をあげるアントワーヌ。兄や母にはルイが何のために帰省したのか分かっていたのだろう。次にいつ会えるかわからないから、二言三言では足りないと言うマルティーヌ。全てを察しているからかルイの話を遮るアントワーヌ。皆の横顔が差し込む夕陽で橙に染まる。時計の振り子の音が、残された時間が僅かであることを強調する。カトリーヌの潤んだ瞳は、何を映しているのか。眩しく輝く玄関に一人残されたルイの足元に、一羽の鳥が墜ちる。この鳥がもう「家」に帰ることはないのだ。
時間が流れるのと並行して、様々な要因があって人間の心情も変化する。その「時間」は一体どこに向かって流れるのだろうか。人は生まれながらにして「死」へ向かうと言う。家族にとって愛すべきルイが12年ぶりに帰省して、母や妹はルイと過ごせる時間を止めたいと思ったに違いない。しかし皮肉にも止まることのない時が、きっとあの家には今も流れ続けている。私は、残された者が過ごす時間に想いを馳せる。
家族という舞台
ルイが主役の話、と思って観ていたら、なかなか呑み込みきれない部分も多かったですが、
「次男坊が12年間不在にしていた家族」が舞台の話、として解釈したら、切なく、痛く、愛の溢れた話になりました。
「ルイの不在を哀しみながらも生活していた家族」なら、当の本人ルイは、その舞台を乱す闖入者になる。
ルイの帰郷を張り切って迎え入れる、という役割を演じた母だが、
それまで「家族を支える」という役割を演じていた兄は、弟を素直に迎えられずに反発する。
ルイの存在をほぼ覚えてなかった妹ちゃんは、家族の舞台に巻き込まれた感じかな?
そんなルイが「これからはもっと長文かくよ!」「家においでよ」なんて言い出したから、これまで何十年と兄の役割を演じ続けていた兄は激昂。
弟を追い出すという形で、その舞台から引きずり下ろす。
ラストシーンの時計の音は、終演を告げるベルか。
度々出ていた、終わりを予感させていた兄の言葉は、余命わずかなルイの死や、「ルイが帰れば元の家族にもどる」の、どっちにもとれると感じました。
家族なのに、闖入者になるって辛いなぁ、って気持ちと、そこまでして家族の形を守ろうとしただろう、兄の気持ちを思うと壮絶でした。
「家族」という舞台だと解釈して観てみたら、気持ちを知るにはアップのシーンが頼りで、目が離せなかった。
解釈のひとつとして書き残します。
*
追記
ラストシーン、目に涙を目一杯ためて怒鳴り付けるシーンは、
「こんなにおれは苦労したのに、お前はそんな見え透いた嘘で家族の関心を全部かっさらっていくのか!くやしい!さびしい!」
っていう気持ちにも見えたし、直前の、「わからないから美しく見える」
というセリフから、兄は弟に憧れてる部分がもしかしたらあって、それなのに全うなことを言い出す弟が怖くなったりもしたのかな?と思いました。
どちらにせよ、言葉が足らない兄弟は哀しい。
あと、最近知ったのですが、戯曲バージョンはルイが兄なんですね。設定変えた理由が気になる...
(20181104)
大切なことは言葉にしなきゃいけない
終始家族がイライラしていて、、恐らく家族関係の崩壊・彼の苦悩を描いているのかな?伝えたいことが分かりづらいです。
会話の中で時折垣間見える言葉…本当は家族も彼の伝えたいことを分かっているのか…告げられたくないのか…それさえもうやむやで終わってしまう。。
世界観は悪くないのに・・結局彼は言いたいことも伝えられないまま、観ていて不完全燃焼の残念な感じでした。。
意味が分かれば、本当は深く心に響く作品なのだろうけど…私には難しくて評価しづらいです。
みなさんのレビューを拝見させて頂きましたが、理解力の素晴らしさに感服致します。とても分かりやすく納得させられます。
切ない家族模様
自分の世界が終わる事を告げに12年ぶりに実家に帰ったのに、自己評価が低すぎて卑屈になったお兄ちゃんがとんでもなくめんどくさかったり、大人になってた妹に戸惑ったり…落ち着くはずの実家は都会で1人成功した主人公が帰ることで混沌としてしまう。
最終的に目的は果たせないまま実家を後にする切なさよ!でも主人公は微笑んでる。
それが邦題をつけた理由なのかな。
この混沌は日常であって、むしろそれがこの家族の幸せの確認作業で、主人公は自分の死を告知することは、それを壊すほどの価値はないと思ったのか…。
やるせない映画だったなぁ。
お母さんの真っ青なアイシャドウ・ネイル・リングと薔薇柄のパンツスーツがファッショナブルすぎて、クセが強い!!
あと部屋の壁紙がオールディーズでかわいい。
何度か考えさせられる
家族が壊れるくらいなら、僕の死なんて たかが世界の終わり。
アントワーヌから始まる家族喧嘩と見守るカトリーヌ。ルイからみんなが離れてルイだけの無言の最後の数分がとてつもなく鳥肌がたった。
時計と鳥、伏せる瞼深くかぶるキャップ。
主人公が家を出た理由として、分からなかったけど2回目で過去の同性愛描写があったからそれかなと思った。
他の人の感想読んで、アントワーヌはルイの理由について気付いたから追い出そうとしたのと、ただの苛立ちとかを見つけてどちらかは定かではないけれどルイを分かってたのは他人であるカトリーヌだけだったのかもしれないと最後のアイコンタクトで感じたけどどうなのだろう。
主人公のルイにはセリフがほとんどなく他の登場人物と同様に画面いっぱいの顔が映る。その表情息遣いとか瞳だけに葛藤や諦めが写ってて、その瞳に映る揺れるカーテンとか涙とかが繊細に見えた。そして微笑んで言葉を飲み込む。
リアルな口喧嘩とどぎまぎした空気感に飲み込まれていく。もっと深くしりたくなった。
さすが
「もうすぐ死ぬ」と家族に伝えるために、12年ぶりに帰郷する人気作家のルイ。母のマルティーヌは息子の好きだった料理を用意し、幼い頃に別れた兄を覚えていない妹のシュザンヌは慣れないオシャレをして待っていた。浮足立つ二人と違って、素っ気なく迎える兄のアントワーヌ、彼の妻のカトリーヌはルイとは初対面だ。オードブルにメインと、まるでルイが何かを告白するのを恐れるかのように、ひたすら続く意味のない会話。戸惑いながらも、デザートの頃には打ち明けようと決意するルイ。だが、過熱していく兄の激しい言葉が頂点に達した時、それぞれが隠していた思わぬ感情がほとばしる。ルイは何も言わずに去ってゆく。ラストの鳩時計から鳥が飛びだして去ってゆくルイの足元で死んでしまうさびしいが余韻の残るラストシーン。
雰囲気悪い
ゲイでセレブの青年が里帰りしたら、家族の雰囲気がとても悪い。特にお兄さんは大変な怒りんぼで、ずっと何かと突っかかってくる。本人にもコントロール不能に陥っているようであった。一体なぜあんなに腹を立てているのか、それはゲイのせいなのか、元からああいった性格なのか不明だった。元からの性格だとしたらよく結婚できたものだ。
なぜ雰囲気が悪いのか最後まで分からなかった。特に物語が展開しないまま最後まで行ってしまい退屈だった。見ているこっちもストレスで病気になりそうだった。
見終わってから解説を読んだら主人公がもうすぐ死ぬとあったのだが、映画を見ていて全く気づかなかった。冒頭でなにか語っていたようだがそのことだったのだろうか。考え事をしていて何も頭に入ってこなかった。
睡魔…
衝撃作「マミー」のドラン監督に、レア・セドゥ、ヴァンサン・カッセル、マリオン・コティヤールが出演!!大いに期待して観に行ったが…開始数十分で睡魔に襲われ、気がつけば、話は後半。その後も二度寝し、話も何も分かりませんでした(笑)。ただ、思ったのは、開始時点と何も変わってないなってこと。ずっと家で喋ってただけ。それは辛いよ…。「マミー」はめちゃくちゃ面白かったのに!「アデル」のレアも魅力半減。他の役者も良くは見えなかった。
意外と好きな映画
とても映画通の映画っぽかったので気になり鑑賞。
この映画はとても難しく、なんと感想を言えば良いのか分からないがなんか凄かった。こう言ってしまうとざっくりしているが、まさにこの通りだった。99分という映画としては平均的な長さだが大きな事件が起きる訳ではなく、家族一人一人の心の闇が徐々に見えてくると言ったもの。
他の映画と違うなと感じたのは、結局この闇の部分は最後まで消化しきれず、挙句の果てに家族に死ぬことすら打ち明けられずに終わってしまう所。ここが妙にリアルに感じた。
最後の鳩時計から出てきた本物の小鳥が家の中を飛び回り、最後時計の中に戻ろうとしてその手前で死ぬ描写が主人公と重なって見えた。
やっぱりマザコンだよね
グザヴィエ・ドランって、音楽と映像のセンスがもの凄くあって、お話が創れて映画が撮れて美青年で、しかもゲイなの。
クリエイターとしてもうこれ以上何を望めばいいのかってくらい全部もってるよね。
話の中で主人公が、妹、兄嫁、母親とそれぞれ一対一で話すんだけど、母親が一番気合い入れて描かれてんの。「あ、そういえばドラン、マザコンだった」と思ったね。マザコンはクリエーターにとってプラスなのかな。
解るような解らないような内容で、綺麗な映像と音楽で流れてくいつものグザヴィエ・ドラン品質だと思ったな。そして《私はロランス》を超えてくる作品は、もうないのかなと思った。
最後、お兄ちゃんが「俺が全部悪いのか」っていうところでは、お兄ちゃん可哀想と思った。
才能溢れる人が身の回りにいたら辛いよね。異性は賞賛するかも知れないけど、同性は辛い。
コミュ障家族の悲しみ
最初から最後まですれ違う家族関係を描く映画は、しんどいものではあるのですが、深く考えさせられるため観応えがあります。本作も観応えはあったし、鑑賞後はいろいろ考えることができて面白かったと言えるのですが、鑑賞中はとにかく観心地の悪い作品でした。
その理由は、最初から最後まで演者をアップで撮るという演出にあります。
演じ手と観手の距離がほとんどなくなり、観客は演者の情動をダイレクトに感じさせられてしまう。しかもこの作品は登場人物たちが怒鳴りっぱなしなので、ずっと刺々しい感情を浴びせられる。観ている側としては圧迫されてゆとりがなくなり、息苦しくなりました。
おそらく主人公ルイが体験している感覚はこのようなものなのだと思います。グザビエ・ドランの狙いは、この感覚を観客にも直接体験させたい、といったものかもしれないし、もしそうであるならばそれなりに成功していると感じましたが、やっぱりシンドいので個人的には趣味に合わなかったです。
一方、内容は興味深かったです。この家族はマリオン・コティヤール演じる兄嫁以外、話を聞いたり他者の気持ちを受け止めたりする文化が皆無。兄と妹は腹が立ったら怒りをぶちまけてグチャグチャになるといった不毛なコミュニケーションを繰り返し、母親は先回りしてコントロールを試みる。コミュ障という言葉がありますが、彼らこそ真のコミュ障でしょう。
こんなコミュ障家族の中で育てば、温厚なタイプのルイが何も言わない人になるのは自明です。
母親と妹はルイを迎え入れているのですが、ルイの話を聞かないし、彼の気持ちにも無関心。実際に愛はあるのだと感じますが、そんな愛では窒息するだけ。エンディングでは静かに家から去るルイですが、多分12年前も同じパターンだったのだろうと想像しました。
この作品や葛城事件のようなうまくいかない家族の映画を観るたびに、愛があるだけではダメで、相手を想像する力や気持ちの伝え方など、愛を実現させるスキルも不可欠だな、としみじみ思います。
グザヴィエ・ドランらしさ
前作マザーに見られるアスペクト比1:1のような視覚トリックに近いものは今作にはない。
しかし、人の性格やオーラ、空気感を捉える日常の流れや、交錯する人間関係は、グザヴィエドラン監督の「らしさ」としか言いようがない。
主人公の柔和で全てを受け入れる体制、家族から飛び出たくなる、誰にも見せられない奥底の部分、
兄の自我を前面に出してしまう性格、弟に対する劣等感や嫉妬、自分だけが理解されないという念、
母の開けっぴろげな性格の奥にある愛、包容力、
妹の自由を渇望するのに縛られている感覚
誰もが登場人物の全てに想いを馳せることができる監督の観察眼に魅せられた
感情のぶつかり合い
家族の感情のぶつかり合いが激しく
とても疲れます。悪い意味ではありません。
カメラワークが早く、たぶん短いスパンで撮影、それを編集してるんだと思います。流れがいいですね。元カノと思い出のシーンは意味不明でしたが...
主人公のお兄さん役にイライラするかもしれませんが、たぶん兄は弟が怖かったんだと思います。
ギャスパーのセリフは少ないのですが
あれほどの気持ちを表現するなんて圧巻です。
好みが分かれますが、私は好きです。
なんも言えねぇ。
なんとも言えない嫌な気分になることが多い作品なのだが、
所変われば様々な家族の愛のカタチがあるのだということ
もよく分かる。12年ぶりに帰郷した次男を待つ家族の愛憎。
あ~これこそが我が家だ、と思ったに違いない彼の苦笑い。
嫌な気分というのには二通りあって、まるで我が家を見る
ように思うのと、こんな家族は見たことも味わったことも
ないのに分かれるだろう。自身は前者の方でまぁ今作ほど
酷くはないが、大声で罵り合う父母なんてのは日常茶飯事。
なぜ我が家はよその親みたいに穏やかで物静かな話し方が
できないんだろうと思ったものだった。家族の罵り合いは
喧嘩というより愛憎に近く、本当は愛しているのに素直に
それを表現できないもどかしさが強調されている。次男は
まさに「なんも言えねぇ」状態に置かれる。口を挟む隙も
そもそもの帰郷の理由すらも言い出せない。あ~可哀相(^^;
と思うのだが、彼がジッと見入る聞き入る家族の肖像こそ
彼が家に帰ってきた証。12年も家を空ければ自分はすでに
お客様の立場に置かれ、家族の愚痴や不満やアンタが留守
の間に色々あって私たちは…みたいな告白の渦に巻かれる。
唯一他者目線で長男の嫁を演じたマリオンがいかに外側の
人間かがよく分かる。この家族内での彼女の苦労は計り知
れないが、慈愛の目で兄弟を見守る演技が素晴らしかった。
「なんも言えねぇ」まま、静かに家をあとにする主人公の
表情から、自身の死など「たかが一つの終わり」であって、
家族の愛情は終わらないことの確信が持てたように感じた。
(憎まれ兄役のヴァンサンがお見事!あんな兄貴嫌だけど~)
全37件中、1~20件目を表示