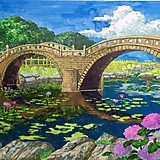タレンタイム 優しい歌のレビュー・感想・評価
全51件中、21~40件目を表示
元の国がレアでどう判断するか難しい…。
今年233本目(合計509本目/今月(2022年8月度)9本目)。
追悼上映ということで急遽決まったようです。
韓国・中国・台湾などを多く扱うシネマートですが、マレーシアは初めてではなかったかな…と思います(タイ、インドは見たことがあります)。
ストーリーは意外にもわかりやすく「タレンタイム」(音楽コンサートのこと。あえて訳せば「talent timeで「才能の時間」が正しい模様)に参加する高校で、各楽器などに選ばれた生徒(学生)たちのコミュニケーションを描く映画、というところになりますでしょうか。
この映画自体、シネマートでは追悼上映で今日ですが、ここにあるように劇場公開日は2017年であるのに、さらに映画自体は2009年であるようです。そのため、学校にはいろいろな方がいるところ(ハンディキャップを持った方など)、そうした方に対する対応が「若干」不親切かな…とは思いつつも、今から13年も前の、それも日本ではない発展途上国のことをいっても仕方がないですし…。
マレーシアは多民族・他宗教の国で、それを前提にするような内容も出ます。むしろこのような国にある一つの高校でチャレンジした(フィクションではありますが)こと、それ自体に見る価値があるのではないか…というところです。
なお、妙に変な方向にいったり、出てはきてもストーリーに一切関係しない人も結構多いです。日本やアメリカなどの映画を見ていればある程度の「相場観」「採点相場観」はつきますが、この映画はあまり…というかほとんど見たことがないマレーシアで、「そういう趣旨になるほうが好まれるんだ」という考え方があるかもしれません。ここはよくわかりません(ちょうど、インド映画で3時間を超えてダンスシーンが当たり前だというように)。
若干、「2022年の人権感覚から考えると危うい」点は感じましたが、もとは2009年の「他国の」映画でリバイバル追悼上映であるということも考えれば、それも鑑みて減点なしにしていますう。
【”大切な貴方、愛しい人よ・・。””幸せと不幸は隣りあわせ。”民族、宗教や身体的障害など多くの壁を、音楽の力で乗り越えて行く多民族国家・マレーシアの若者達の姿が胸を打つ、慈愛と寛容さに溢れた作品。】
■ある高校で音楽コンクール“タレンタイム” が開催される。ピアノが上手な女学生・ムルーは、耳の聞こえないマヘシュと恋に落ちる。
一方、二胡を演奏する優等生・カーホウは、歌もギターも上手なハフィズに成績トップの座を奪われ、わだかまりを感じていた・・。
◆感想<Caution!内容に触れています。&沁みたシーン。>
ー 今作は、若くして亡くなってしまった、ヤスミン・アフマド監督の、多民族国家・マレーシアの抱える現実を描きながらも、人間性肯定感に溢れた慈愛ある作品である。ー
・女学生・ムルーが、マヘシュが耳が聞こえない事を知らずに苛立つシーン。だが、彼女はマヘシュが聾唖者であることを知っても、彼を遠ざけず、逆に親密になって行く姿。
・マヘシュの母が、ムスリムのムルーとの恋を認めない姿に対し、雨の中膝を付きながら、手話で必死に語り掛けるマヘシュの姿。
・二胡の得意なカーホウが、それまで常に学年一位の成績だったのに、病の母の看病をするハフィズに抜かれ、愚かしき父親に叱責される姿。
故に、彼はハフィズとは微妙な関係であったが、タレンタイムの際、ハフィズがギターで演奏している横に椅子を持って来て、伴奏をするシーン。そして、演奏後、抱き合う二人の姿。
<等々、今作は多民族国家・マレーシアの音楽コンクールに臨む若者たちの青春を描いた作品であり、彼らが民族、宗教の違いなどの壁に葛藤しつつ、交流していく様が素晴しき作品である。
全ての民族が、他民族に対し、寛容な姿勢で接すれば、世界の紛争は激減するであろうに‥、と思ってしまった作品でもある。>
パリス・ヒルトンの職業はいったい何なんだ?
『細い目』と連続で観たのですが、民族の多様性はさらに広がりを見せ、北京語、英語、マレー語、タミル語の四か国語に手話も加わっていて、頭が混乱する。中でも、2人で会話するときにタミル語対英語だったりとか、バイリンガルが凄すぎるのです。
群像劇風に描かれる中、中心となっていたのがピアノの弾き語りをするムルー。彼女の一家でさえ、祖母がイギリス人だったり、中国人もいたりと多種多様。どんな繋がりなのかさっぱりわからなかった。スキンヘッドのお父さんは『細い目』のお父さんと同じ。軽めのギャグをかましているのに、それほど笑えない。
学校の先生たちも結構コミカルに描かれていて、屁をこいてばかりの先生や、ゲイじゃないかと驚いて隠れる先生もいるし、楽しい学校だと感じる。人種差別なんて全くないし、宗教色にしてもムスリムの礼拝が描かれている程度。
聴覚障碍者との恋や成績の1、2位を競うカーホウとハフィズがメインとなり、親族の不幸から立ち直りを見せる高校生たちの一面がとても爽やか。それほど泣ける作品でもないかな~などと思っていたら、最後のワンショットでウルっときた。この作品が遺作となってしまったヤスミン・アフマド監督。もっと色んな作品を撮ってもらいたかった・・・
タイトルなし
「重力」としてのゴルトベルクと月の光
マレーシアの世情に疎い自分にとって、ヤスミン監督の作品は、常によく分からない感じがつきまとう。
この作品もストーリーは追えるが、「民族の壁も宗教の壁も越えて」という背景となると、どこまで理解できているのか覚束ない。
また、かなり登場人物が多い。
学校を中心となる「惑星」として、その周りをムルー(マレー系)とハフィズ(マレー系)とマヘシュ(インド系)の3つの家族が、それぞれ「衛星」となって回る。
さらに、カーホウ(中国系)が「彗星」のように加わる。
ただ、メインの話と関係ない“脱線”が多い。それらの「遠心力」によって、話の「軌道」が乱される。
“叔父の死”や“メイド”は、話を分裂させる方向に働くだけだ。
“謎めいた車いすの男”や“教師のオナラ”は、緊張を解くギャグなのかもしれないが(笑)、インパクトが強い「隕石」だ。
結局のところ、全くまとまりのないストーリーを、音楽のもつ強大な「引力」で無理矢理まとめ上げたという印象だ。
「ゴルトベルク変奏曲」のアリアと「月の光」、そしてオリジナル曲の「I Go」と「Angel」という、すべてスローな曲で映画の雰囲気を形作って、それで押し切ってしまう。
“最高傑作”というには物足りない。やはり、まだまだこれからの“夭折”の人だったのだろう。
言葉にできないことの可能性へのまなざし
我々が人と何かを伝え交わす時に、言葉で伝えきれないと感じることがあると思う。
それは適切な言葉が見当たらないという限界かもしれないし、言葉などで全てを掬い上げられないという抑えきれない何かがそこにあるからかもしれない。
どんな理由であっても、この物語の彼ら彼女らは若くしてそのことを皆知っているし、嫌でも知ることとなるプロセスを、家族や友人や先生のような親しい立場の視点からそっと見させてもらっているような映画だと思う。
よくよく考えたら、この物語の彼ら彼女らはなかなかにハードな状況ではないだろうか。
身内を殺されたり、病気で余命残り僅かな母親の最後の願いを汲んで敢えて会いに行かなかったり、突如訪れた最期は看取ったり、恋人と宗教の違いや悲しい過去によって引き裂かれたり、引き裂かれようとしていたり…
特にマレーシアという国がこんなにも多民族国家なのだということを初めて知ったし、日本だと考えられないような民族・宗教の違いによる諍いが身近に普通に存在することにまず驚いてしまった。
それ故に引き起こされるいくつかの悲劇や過去を、当事者たちが新しい時代へとどう乗り越えていくかというのも1つのテーマだったんだろうなと。
話を戻すと、マヘシュとムルーの恋がそのまなざしや控えめに触れようとする手の軌跡や、そういった細やかなもので充分にスクリーンから伝わるだけで胸がいっぱいになるし、ムルーの歌で恋に落ちた瞬間も彼女の想いも溢れているのが解るし、それを遠くからマヘシュとハフィドが聴いてるのが良い。
マヘシュはその気持ちを言葉にはできないけれど、彼女に接する姿から大切に想っていることがよくわかる。
ハフィドは母の看病もしながら、勉強もできて、ギターも歌も上手くて、完璧すぎるから…人の気持ちまで分かりすぎてしまうから、身を引いてしまうところがあるんだろう。彼はこの先1人でもやっていけるとは思うけど、どうかもう少しだけ自分のためだけに生きて欲しいようにも思う。
そして、母を喪った日にタレンタイムに臨んだハフィドの傍らで、カーホウが静かに二胡を弾くシーンで涙腺が崩壊してしまった。
予告にあったあの音楽が、まさかこんな意味を持っていたなんて。
彼は彼でつらい境遇があって、ハフィドを疎ましく思わざるを得ないのもわかる。だからこそ、ハフィドの状況を知って、そっと無言のうちに二胡の調べで寄り添う。まさに言葉ではなし得ないこと。本当の想いがそこに溢れていた。
映画の始まりで、タレンタイムを行う教室の電気が付き、それが消されることで映画の幕が引かれるのも素晴らしい。静かなさじ加減が絶妙な名作。
【細い目】の続編的な世界観でした∧(ё)∧
前回の【細い目】に続き,Yasmin監督作品2作目を魅了しました。【Malaysia】→“多民族国家“であるが故に,民族・習慣・文化等の様々な点で“壁”があり,それを乗り越えるのが如何に大変であるのかを痛感させられた作品でした。自分自身,福音派のクリスチャンでありながら仏教徒の主人と結婚し,それでも偶に夫婦揃って日曜礼拝に行くので同じ様な世界観であるかと思いながら鑑賞したらとんでも無かったので衝撃を受けました!
Malaysiaに於いて【改宗】→“家族&親族との【commune】其の物が崩壊する可能性がある”と言う現実があり,前回魅了した【細い目】の続編的な物語で仕上がっていたのが印象的でした。それでも【音楽】を通して民族の壁を乗り越える生徒達の志は本当に熱かったし,何より大好きなDebussyの作品【月の光】→“BGM”として活用されているのも素敵でした(^-^)♪
多民族国家マレーシアを舞台にした普遍的青春ドラマ
マレー系、インド系、中国系、ヨーロッパ系が混在し、宗教もムスリム、ヒンズーなどが、民族ごとに、ときに民族の中でも異なり、反対に民族を超えて共通することさえある社会。貧富の差や家庭の事情がそれに加わる。
さまざまなオトナの事情があってややこしい事態が生じるなか、シンプルに人が人を好きになること、相手を大切に思う真情が、それらをのりこえる橋となる、のか。
んん、面白くなりそう。
音楽も悪くない。
感情移入できなかったのは、コテコテのギャグや分かり易すぎる演技、人工的に過ぎる状況設定、無理がある人物造形などのせいかな?いろいろな意味で、過剰でした。
ヤスミン・アフマド最後の作品。もちろん彼女にはそんな意識はなかっただろうが、集大成となってしまった作品。
これが最高傑作とされることを一番悔しく思っているのは、彼女かもしれない。
ヤスミン監督の集大成的な作品で万人にオススメ
高校で開催される音楽コンテストのタレンタイムに出場する生徒達の家庭の事情と交流を音楽を交えて描く群像劇。
裕福な家庭の娘と母子家庭で育った聾唖の青年の恋。
重い病気に苦しむ母親を支える秀才と彼を妬む同級生。
しばらく青年が聾唖なのが分からない展開上手い。
随所にある歌と音楽もシンプルに物語を盛り上げてくれる。
裕福な家庭の姉妹の父親が、「細い目」と同じ役者で同じような役柄なのが可笑しい。
ヤスミン監督の集大成的な完成度あるので、誰にでもオススメできる。
残念なのは、上映された画質が、おそらくフイルム撮影映像が今一つの画質でデジタル化された様子で「細い目」と同じ撮影者なのに発色や解像感も悪くて若干のくすんだ状態だった事。
もはや古典。大傑作
評判通りの大傑作でした!
青春群像劇というフォーマットで、わかりやすい感動が味わえるポップさがめちゃめちゃある作品ですが、ヤスミン師匠の代表作らしく、安っぽい感動ではなく、かなり深いところが動かされました。
ヤスミン師匠のガーエーを観ると、優しく包まれるような、受容されるような安らぎを感じます。
それは、登場人物たちが家族に受容されてきたからではないか、と仮説を立てております。家族の愛情描写が多く、主人公たちはそれをベースに試練に立ち向かい、障壁を乗り越えていきます。たとえ別離があっても、愛情を受けてきたから真正面から受け止められる。
つまり、主人公たちは愛情を受けることで、自分の気持ちに正直になる勇気を得て成長します。やがて彼らは愛を与える側になっていくのでしょう。そして愛を受け取った者たちがまた障壁を乗り越えて行く…
ヤスミン師匠が生涯をかけて挑んだことは、この『正の循環』を創り出すことだったのでは、と感じます。
さらに本作はアートという媒体を用いて、オーキッド3部作以上の強度で正の循環を歌い上げていると感じました。
本作は音楽映画でして、音楽や歌詞、さらにダンスが持つ特別な力が伝わってきました。楽曲も良かったし、印象的に用いられるドビュッシーのピアノ曲も心に沁みます。個人的にクライマックス以外で最も好きなのはインド系の女の子のダンスでした。
本作における音楽は、観客に訴えるだけではないです。家族の愛情をベースにして障壁を乗り越えるという、ヤスミンワールドの(そしておそらく現実世界の)方程式を、アートによって超えるシーンが描かれてました。
中華系の二胡弾きカーホウは、親父から虐待チックに育てられており、作品内の描写からは家族の愛情を感じません。なので、カーホウは暗くて嫌な雰囲気をまとっています。
しかし、このカーホウが障壁を超えるのです。そのきっかけは音楽です。カーホウはあるアートを感じ、それに応えて一気に乗り越えて行くのです!その鮮やかさ、軽やかさといったら!
ヤスミン師匠は優しいが強い人です。妥協や誤魔化しを許さない厳しさがあります。つまり純度が高い。
一方、アートもリアルであればあるほど誤魔化しが効かず、純度が高くなる特性があると推察しています。
カーホウは純度の高いアートを感じ、その衝撃で一気に自分に正直になる力を得たのでしょう。それは意志の力というよりも、大いなる力=アートの力が彼を一気に解放させたのでしょう。もちろん、その背景にはカーホウが感じていた他者へのポジティブな芽があったことは間違いないです。
しかし、それを一瞬で現実化する力がアートには備わっていることがまざまざと伝わってくるシーンでした。本当にこころがふるえまくりましたね!本当に凄い!凄いシーンでした!
それからもう一点印象的だったのは、主人公のひとりが弱さを抱えたまま作品が終わっていったことです。
それは、その人物が弱いというよりも、弱さに正直になれた、とも言えるのではないかと感じます。ヤスミンの描く『Strength』の道半ば、という感じも受けます。これもまたリアルで誠実だと感じました。
本作はすでに古典の領域にあると感じます。間違いなく今後本作の評価はさらに高まり、もっと身近な作品となっていくことが予想されます。文芸系映画好きにとってはマストとなっていく映画だと感じました。
この作品をともに観たあなたへ
映画は、遠い南国に暮らすいくつかの家族の描写から始まります。人々の顔だちや、彼らが着るもの、住む家はどれも、この列島に生まれ育った私たちには見馴れないので、すぐに感情移入することが難しかったのではないでしょうか。
ドビュッシーのピアノ曲が静かに流れる冒頭の学校は、ある時期の台湾の映画監督の作品を思い起こさせます。あるいは、ある年代の日本生まれの人々は、大林宣彦の青春ファンタジーを懐かしく思い出したかも知れません。
私は、この作品を撮ったヤスミン・アフマドが、これらの先達の映画を観てきたであろうという推測に疑いを持ちません。マレーシアの一般的な学校に制服があるのかどうか私は存じませんが、映画の中の高校生たちは日本と同じような制服を身に付けています。そしてこの一点がこの映画を学園物語のジャンルへプロファイルし、私たち北東アジアに暮らす者にも馴染のある世界へとぐっと引き寄せるのです。
しかも、賢明な観客であるあなたには、そこで生起している感情の全てが、どこの誰にでも起き得る心の動きだと思えてくるはずです。嫉妬や憤怒など、その中のネガティブなものも含めてです。
私たちの日常には、相手のことを何も知らぬままに、自分の中に生まれてくる感情に突き動かされる言動がたくさんあります。いや、むしろ相手への無知の上に浮かんだ情動こそ、日々の暮らしの中でのエネルギーを生成しているのではないでしょうか。
私たちの社会を構成する信頼や愛だけでなく、誤解というエラーも、全てが人生の出来事に繋がっていくのは、そういうことなのではないでしょうか。
私にとって、2年ぶりの鑑賞となる今回で三度目の鑑賞は、このような思いが再び、いや三度私の中で強くなる経験となりました。
そして今回は、期せずして、ヤスミン作品で3度主演女優を務めた女優、シャリファ・アマニ氏のトークショーが付くという幸運にも恵まれました。
母親を喪ったマレー系の少年ハフィズが早朝のモスクで祈りを捧げるシーンで、彼の前を一羽の小鳥が横切ります。
最初に観たときから、モスクに迷い込んだこの小鳥には、どんな意味があるのか興味がありましたが、アマニ氏の話はその謎に答えるもの以上の感激を私に与えてくれました。
スクリーンに何が映っているのかということは、私たちが映画を観る際にともすると忘れがちな重要問題です。被写体となっている人物の心情を理解し、繋がれた場面間の出来事の連続性を推測するという思考に集中するあまり、私たちは画面に映るものへの意識を失いがちです。
しかしながら、登場人物への理解やストーリーの把握とは、観客の頭の中で起きることであって、スクリーン上に現れているものではありません。
映画を観るとは、フィルムを通して暗闇に浮かぶ影を見ることに他ならないのです。
祈りの場に、しかもたった一人の肉親である、母を亡くした少年が悲しみの祈りを捧げている傍らを、一羽の小鳥が歩くというこの画に、驚きと神の愛を感じるというささやかな幸福。
スクリーンに映る小さな鳥が偶然の所産であることを知っているにせよ、知らないにせよ、その体験の価値に違いなどないのです。アマニ氏のお話を直接聴く機会に恵まれたわたくしは、映画を観るという行為の本来的な意味に、再び立ち還る幸運に恵まれたのです。
また、監督が俳優のミステイクに寛容であり、ときにはそのハプニングを映画にとり込むこともあるという話を聞いて、わたしにはなおさら、この作品に監督の人柄がにじみ出ているのだという思いを強くしました。
他者への無理解と不寛容が日に日に世界中を覆う今日。人々の誤解(ミステイク)が溶けてく先に、信頼と慈愛が満ちてくるこの映画はヤスミン監督そのものなのだと。
そして、この映画はヤスミンやその他のスタッフ、キャスト、そして観客に対する神の恩寵なのです。
人が一本の映画を撮る理由は様々あると思います。それが職業だから。もちろんお金のため。愛する人をスターにしたい。そのどれもが正当な理由であり、そのような目的のために撮られた作品で好きなものもたくさんあります。
ところが、ある作品に、理屈抜きに、どうしようもなく感情を揺さぶられるということは、撮る者の人となりを感じるということから自由にはなれない場合にのみ起きます。
ヤスミン・アフマドの監督作品を、まだこの「タレンタイム」しか観てはいない私が、彼女の人柄について言及することは不適格なのかも知れません。
しかし、アマニ氏の貴重なお話が、このような私の勇み足とも言えるヤスミン・アフマド観に確信を与えてくれたことは確かですし、また、私が青山の小さな映画館の特集上映でヤスミンの他の作品を鑑賞するであろうことも、極めて確かなものであることを述べておきます。
多様な価値観に翻弄される人々を優しく見つめる美しいドラマ
アディバ校長が心血を注ぐ高校の学内イベント”タレンタイム”はオーディションで選考された7人の生徒がしのぎを削る音楽コンクール。選ばれたのはピアノと歌を得意とするロマンティストの女子ムルー、二胡を演奏する優等生カーホウ、ギターの弾き語りで挑む転校生ハフィズら。ムルーはコンクール会場への送迎を担当する無口なイケメン青年マヘシュが気になってしょうがないし、カーホウは転入生ハフィズに学内成績1位の座を奪われて傷つき、ハフィズには脳腫瘍を患う母がいる・・・生徒達が抱える様々な葛藤が宗教の違いや貧富の差と綯い交ぜとなる中、タレンタイム本番の日がやってくる。
多彩な文化が共存するマレーシアという多民族国家が抱える社会問題を背景に様々な想いを抱え苦悩する人々を優しく見つめる作品。登場人物たちの会話ひとつを取っても様々な言語が入り混じり、映像の中にも多様な宗教観が滲んでいて複雑さに眩暈を憶えるほどですが、アディバ校長に密かに思いを寄せる教師がやたらと放つオナラやオーディションに紛れ込んだメガネ男子の奇妙なダンスなどのシュールなギャグがスパイスとなっているし、タレンタイムで披露される楽曲が実にキャッチ―で美しく辛辣なテーマを扱いながらもあくまで軽妙でロマンティック。温かい涙の向こうに静かに訪れる終幕がじんわりと胸に滲みる傑作です。監督はヤスミン・アフマド、残念ながら本作が遺作。ウィキペディアによると自身が最も影響を受けたのがチャップリンということで確かに辛辣な風刺をギャグで彩る作風はそういうことかと膝を打ちました。
すごく好きです
何度でも観たい
全51件中、21~40件目を表示