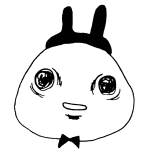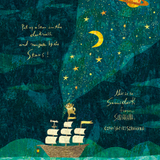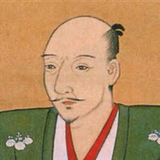オデッセイのレビュー・感想・評価
全763件中、21~40件目を表示
火星に1人取り残されたら?
火星に1人取り残されたという、とんでもない設定の物語。規模がデカすぎて、ちとイメージが湧かなすぎる。
そのせいか、取り残されたのにこんなに明るくお気楽なの⁉︎と感じてしまった。だって助けが来ると言っても最初は4年後とか言っているのに、受け止め方が軽い。
そういう点では、エンタメ要素がかなり強かったのかなと感じる作品でした。皆さんが高評価ながらも、少し物足りなさを感じた点がそこでしょうか。(そもそもあの小さい施設が綺麗に火星で残っているのも不思議)
ただ、火星やら宇宙の映像美は圧巻で、素晴らしかった。最近の映像技術はすごかったです。
挑戦的なエンタテイメントでありながら、新しい環境の中でのサバイバルにおいて科学的思考を学ぶことの重要性を体現
リドリー・スコット 監督による2015年製作(142分/G)のアメリカ映画。
原題:The Martian、配給:20世紀フォックス映画、劇場公開日:2016年2月5日。
未読だが、アンディ・ウィアー「火星の人」が原作。火星にただ1人で取り残された植物学者でもある宇宙飛行士マーク・ワトニー(マット・デイモン)が、科学の力で長期間サバイバルする姿が描かれていて、感動させられた。家族愛的人情もの要素は排除し、シンプルに科学的知識と実行力で生きていく描写、リドリー・スコット演出に、大いなる好意も覚えた。
じゃがいもと栽培研究用微生物は持ち込みだが、燃料ヒドラジンN2H4から水素を分離し、酸素存在下で燃焼させて、水を作り出した。そして、宇宙飛行士の排出物を肥料にして、微生物利用し、じゃがいも栽培に見事に成功。思わず拍手してしまった。送付情報が限定的な中、地球との二進法利用のアルファベットでの交信成功も見事に思えた。
救助に関して、地球の重力を利用して加速させるスイングバイを利用して帰還中の宇宙船を再度火星に向かわせる展開も、面白かった。見ている時は良く分からなかったが、地球が火星に向かって進んでいる時には、万有引力による推進力が相加的に加わるということらしい。「はやぶさ」もこの力を利用して小惑星に辿り着いたとのことで、映画では大発見みたいな扱いだったが、そんな特別のことでは無い様だ。
全体的に、挑戦的なエンタテイメントでありながら、新しい環境の中でのサバイバルにおいて科学的思考を学ぶことの重要性を体現しており、多くの日本の子どもたちに見てもらいたい映画に思えた。
監督リドリー・スコット、製作サイモン・キンバーグ、 リドリー・スコット、 マイケル・シェイファー 、アディッティア・スード、 マーク・ハッファム、原作アンディ・ウィアー、脚本ドリュー・ゴダード、撮影ダリウス・ウォルスキー、美術アーサー・マックス、衣装ジャンティ・イェーツ、編集ピエトロ・スカリア、音楽ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ。
出演
マーク・ワトニーマット・デイモン、メリッサ・ルイスジェシカ・チャステイン、アニー・モントローズクリステン・ウィグ、テディ・サンダースジェフ・ダニエルズ、リック・マルティネスマイケル・ペーニャ、ミッチ・ヘンダーソンショーン・ビーン、ベス・ヨハンセンケイト・マーラ、クリス・ベックセバスチャン・スタン、アレックス・フォーゲルアクセル・ヘニー、ビンセント・カプーアキ、ウェテル・イジョフォー、ドナルド・グローバー、
マッケンジー・デイビス、ベネディクト・ウォン、ニック・モハメッド、チェン・シュー、エディ・コー。
宇宙開発が盛んなこの時期だからこそ作る意味があった作品。
2012年8月6日にNASAの火星探査車「キュリオシティ」が火星に着陸した。
個人的な印象だが、あのころから人々は火星に興味を持ちはじめた印象がある。有人・無人はともかくとして人類がアクセスできる場所としての興味だ。
もちろん、まだ人間が火星にいったことはない。それでもNASAや民間宇宙企業が開発競争を加速しているのを見ていると、近いうちにいけるのではないかという気がしてくる。
そのような状況で本作である。
火星に取り残された植物学者マーク・ワトニーがなんとか生き延びようと、ひとりきりでさまざまな工夫をこらす。そして、彼が生きていることに気づいたNASAは、ワトニーを地球に連れ戻すために知恵をしぼる。
本作では火星という、誰もいったことのない土地で生き延びねばならなくなった人間の孤独なサバイバルと、彼を支える仲間たちの姿が描かれる。
サバイバル術もリアルなような気もする。なにしろ誰も火星にいったことがないので、本当にそういうことが可能なのかわからない。「エイリアン」の描写に現実的な要素は求めないが、本作のように科学的・植物学的な説明がはいる作品についてはリアルなのか、とまずは疑ってかかってしまう。
とはいえ、「2001年宇宙の旅」のほうがリアルに見える、というのは思った。モノリスやスターチャイルドといった、リアルとはかけはなれた要素が登場するにもかかわらず、リアルに感じるのは、キューブリックのすごさなのかもしれない。もしくは小説を担当した、 アーサー・C・クラークの腕前なのか。
製作費150億円。
興行収入920億円。
映画としては成功している。
マット・デイモンやジェシカ・チャスティン、ショーン・ビーンといった有名俳優のおかげもあって、安心して観られる作品だった。
難を言えば、火星に取り残された植物学者がいかに孤独か、といった部分の描写が弱かったと思う。
本作は宇宙開発が盛んになってきたタイミングで作られたサバイバルものではあるが、孤独にさいなまれる人間と、それを助けようとする仲間といった、それこそ宇宙規模の距離も描いてほしかった。
そして、サバイバル映画としてはやや地味な仕上がりになっている。
好きな映画ではあるが、どっちつかずになってしまっている印象ではある。
火星で1人鉄腕DASH
知識とアイデアは絶望を希望に変える
火星探査中のクルーが激しい砂嵐に襲われる。そのクルーの1人、植物学者のマークは嵐による飛来物に巻き込まれ行方不明になる。死亡したと判断され、他のクルーは帰還する選択をとる。しかし奇跡的に彼は生きており結果的に火星に取り残されることになる。マークは4年後にある次の火星探査計画まで生き延びることを決意する。
通信手段がなく自身の生存を伝えることができない中、食料もわずかな極限状況で植物学者としての知識と経験を使い、1個1個問題を解決しながら火星でのサバイバルを開始する。
私が最も印象に残っていることは、
知識と経験はどんな状況であっても自分の武器になり可能性を広げることができるという事です。植物学者としての知識とそれを使うアイデアによって生存不可能と思われた状況に希望を見出していくマークの姿にあきらめないことの大事さを改めて感じました。
個人的には食料問題の解決方法が「火星でそんなことできるのか」と必見です。
求める結果を得るためにはどうすればいいか、事業家として私も日々試行錯誤をしていますが、知識と経験により視野が広くなりできることが増えることを体感しています。知識を得る最も身近で効果的な方法は読書だと考えていて、私も日々読んでいます。
いろんな知識をつけることで人生の見える景色が変わるかもしれませんね。
火星に取り残されても諦めない人
火星わくわくサバイバル生活
もしくは、脱出島火星編。
映画館とレンタル開始直後の2回見ていて、今回が3回目。アマプラで見られるようになってすぐ見た。やはり面白い映画は何度見ても面白い。
地球では火星に取り残された主人公の精神状態を心配する中、本人は超ポジティブに楽しんでるぐらい。
思わず笑っちゃう。
火星で生き残るためにあらゆる方法を模索するわけだが、賢い人ってすごいよ。
一番の問題は飯。
次に助けが来る日を想定して、それまでに餓死しないためにはどれくらい必要なのか。当然非常食だけでは足りない。ならば栽培するしかない。火星で!
一般人には到底できない。
また、それだけでは限界があるから、なんとか地球と通信をしたい。
そんなことどうすればいいのか。それも解決していく。
前半の説得力があるので、後半は結構とんでも展開が続くが、割と突っ込まずに見られるのはさすがの構成。
それにしても、視聴者は地球のやりとりや救助の人たち、そして火星の主人公、全員の動きや心情を見てるから分かるけど、主人公はあくまで地球と通信してる文字でしかやりとりしてない。
そんな状態で、火星から宇宙に飛び出すのって、マジで怖いよな。
人生をもっと面白がろう!
まさに「I will survive 」
観よう観ようと思いつつ、個人的にはSFものは後回しにする傾向があり、やっと今頃鑑賞。
観終えて後悔!? これは名作、何でもっと早く観なかったのか。
リドリー・スコット監督なので、結構重く創られてると思いきや、ユーモアも交えたかなりくだけたシーンも多用されていて、観ていてとにかく心が弾む。そして度々流れる懐かしのディスコソングが、上がったテンションにさらに拍車をかける。
そして、本来は絶望と隣合わせの緊張ピリピリムードを、スーパーポジティブシンキングで吹っ飛ばしたのは実に爽快。登場人物が皆善人だったのも心洗われる。
そして、エンドロールでのまさかの「I will survive 」。この計算し尽くされた外し方、最後の最後まで心つかまれる。
個人的には、本作はリドリー・スコット監督の最高傑作といってもよいと思う。
「まず始めるんだ。問題を1つ解決したら次の問題に取り組む。そうして解決していけば帰れる」この教訓はこころに刻ませていただこう。
絶対に諦めない。ワトニーならそうする。
公開当時に劇場に行き、最近サブスクでも公開されたので改めて鑑賞。やはり素晴らしい作品だ。「火星でジャガイモを育てる映画」というユニークなシーンが独り歩きしている感があるが、この作品の本質はそこではない。
本作の原作は小説だが、その成り立ちはかなり独特だと聞く。というのも、小説本文を全てインターネットに無料公開し、読者からの指摘を受け付け、内容をレビューした上で本文に取り込んで修正していくという、テック業界でいうところのOSS (オープンソースソフトウェア) に近い形態が取られたとのことだ。こうして「開発」されたシナリオは集合知を武器として圧倒的なリアリティと説得力を備えている。
未来の宇宙開発を舞台にしているにもかかわらず、まるで記録映像を見ているかのような現実感は、この映画最大の魅力だろう。そして「火星に1人置き去り」という果てしなく困難な問題に対して、主人公ワトニーは地道に、泥臭く、しかしあくまでもポジティブに立ち向かっていく。現実とはスーパーマンがひとっ飛びで助けに来てくれるなんてことはなく、チームで協力して限られた資源の中で解決させるしかないのだ。(外部の協力者は現れるが、それだって無敵の解決策ではない)
彼の姿を見て「絶望感が足りない」と言う人はいったい何を求めているのか。目の前の課題を解決してゴールに近づくことを諦めない、科学者としての理想がこの映画にはある。「余裕がありすぎる」という意見は… まあ分からんでもない。あとはまあ、派手なアクションシーンはないので、渋い映画ではある。
それでも、もう一度見たいと思っていて、そして見るたびに励まされる映画だと改めて実感。ワトニーの生きざまは人生の手本にしたいぐらいだ。
久しぶりに見直したが、やはりリアル路線SF映画の傑作。 原作の小説...
なんか微妙
最近The Planet Crafterというゲームを始めたのだが、未開拓の荒れ果てた惑星に降りたって人が住める環境にテラフォーマーしよう! 的な作品でこれがまた面白い。面白すぎて連日夜遅くまでやってしまうせいで寝不足気味……
てな訳で、「なんかこんな映画あったよなぁ」と思い出して鑑賞する為にNetflixに登録。
期待大にして観ていたのだが、中盤で退屈になりウトウト……。半分寝てる状態で観ていてよく内容は覚えてない
いやいや、寝てるせいで内容覚えてないから低評価なんてあんまりじゃないか!? と思われるかも知れないけど、マジで面白い映画は2日間寝てなくても目ガンギマリで見入っちゃう自分が寝ちゃうってことはつまりそういう事なのである
とにもかくにも設定は凄くいいのにそれが活かしきれてない。ドクターストーンのように化学お勉強知識無双映画かと言われるとそこまでではないし、極限の漂流サバイバルかと言われるとそんなに緊迫感はない
そもそもマークのメンタルが鬼すぎて(というかそのくらいの鬼メンタルじゃないと火星開拓チームなんかに務められないのかも知れないが。友を見捨てる判断早い奴然り)、全然緊張感がない。火星に1人取り残された絶望感というのが演出的に今ひとつなのだ
いやいや、それこそがこの映画のテーマにおいてもっとも重要なんじゃねーの!? って思いたくなるんだけど、鬼メンタルのマークは普通に何事も無かったかのようにじゃがいも栽培し始める
じゃがいも栽培もそこまで苦なく、一度の失敗があった程度で難なく成功。絶望感ゼロ。
しかも早いうちにNASAと交信できたおかげで1人取り残された感も中盤も早い内に解消されてしまい、どうやって助けるかに物語はシフトしていく。もはや火星に取り残されたサバイバル映画感はこの時点で皆無である
その後のことはなんかもうウトウトでほとんど覚えてないけれど、火星という環境で1人取り残されてサバイバルする映像が観たかったのに肩透かしもいいところで飽きて寝てしまった
もし中盤から後半にかけてその映像がこれでもかと詰まっていたのであれば寝てしまった自分を恨みたいところではあるが、序盤でその面白さを引き出し切れてない時点で微妙な映画である
期待して観たもののアメリカマンセー的なよくあるクソ映画って感じ。中国が見返り求めずに助け舟出すなんてあるわきゃねーだろよ、となった時点でリアリティの欠片も感じずリタイアのきっかけにもなったかな。とにもかくにも残念な映画だった
中国が米国を支援する筋書はファンタジー
感想です
タイトルなし(ネタバレ)
火星に一人取り残されるってこれ以上の絶望ってないと思うんだけどマークのポジティブでユーモアのあるキャラクターのおかげで落ち着いて見ていられる。
精神論や都合のいい奇跡で乗り切るんじゃなくて持てる知識で挑んでいくところが良い。
誰一人見捨てようとせずみんなが全力で助けようとするのが好感が持てるし感動的だった。
マット・デイモンと賢者の芋
全763件中、21~40件目を表示