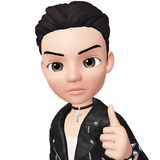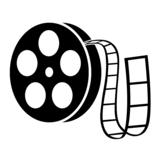ドローン・オブ・ウォーのレビュー・感想・評価
全48件中、1~20件目を表示
善きサマリア人のたとえ
あまり期待せず観たから?
結構面白かった。
ネバダ州のコンテナの中から無人機により爆撃する様子が描かれている。まさにTVゲーム。映像だけ。着弾時の震動も爆音も死体の匂いもない。地上を歩いている一般人をロックオンしてスイッチ押すだけ。軍事スキルは要らない。なぜ軍人にやらせているのか?が謎。
他方、ネバダ州といえばベガス。広大な砂漠。コンテナの外は「ザ・アメリカ」。このギャップが上手く描けていた。
主人公はとても倫理的な人間。病んでゆく。病んでゆくだけのお話です。
もし私が同じ立場であれば、あの主人公のように病むのだろうか?
ゲーセンのコンテナみたいな無人機による爆撃ゲーム。気に病むことなくポチポチとゲームのスイッチを押す。多分、そういう人間の方が圧倒的な多数派だろう。なぜなら「殺した」という感覚が何もないから。
人が倫理を取り戻すために、リアルで人を殺したり殺されたり、したほうが良いのかもしれない・・・と言うと狂人扱いされる。だが、この映画を観て、あなたはどう思うだろう?少し考えてみて欲しい。「殺し」の無い世界。ある世界。どっちが良い世界なのだろう?
主人公はカトリック教徒だ。作中、キリストが張り付けになった十字架が何度も描写される。
どういう意味があるのか?
私なりの答えは多分「善きサマリア人のたとえ」にある(まぁ人によって様々な解釈があることを踏まえて、あえて書く。もちろん違った解釈もあると思います)。
スイッチを押せと言われて、素直にポチっと押して人を殺せる人間。スイッチを押せと言われて、それを受け入れられずに精神を病んでゆく人間。
あなたはどちらを隣人にしたいですか?
現代のアメリカは「スイッチを押せと言われて、素直にポチっと押して人を殺せる人間」が次々に再生産される世界になりつつある。
この映画の中で十字架が繰り返し描写される意味は、こうしたアメリカ社会に対する批判が込められているように思える。
アメリカはキリスト教原理主義国家といっても過言ではない。映画による政権批判も、キリスト教の教え、を軸に行われる。
「倫理を教える」ということはとても難しい。「善きサマリア人のたとえ」も、単に読んだだけでは、それが指し示している意味は真に理解できない。こうして映画を通じた体験が、真の理解をするための助けとなる。
今ここにある戦争
これが、未来の戦争か…?
否! すでにもう、“今ここにある戦争”だ。
だからこうして、映画として描かれる。
ターゲットをロックオンする。
だが、派遣された海外の現地ではない。
米国内。基地内。コンテナの中で。
監視も攻撃もドローンによって。たった発射ボタンを一つ押すだけ。
一日の任務が終われば、普通に帰宅。家族と過ごす。
そして再び任務に就く。
現地で敵兵に狙われたり、命の危険に晒される事などナシ。絶対安全。
だが…
ただドローンによる遠隔操作で映像を見て、標的を無情に攻撃。それこそ本当にゲーム感覚。
そこに感情は無い。
例え現地の一般人が暴力を振るわれても、助けてやる事など出来ない。ただ傍観するだけ。
それが、任務だから。
ただただ無情に、命令通り標的を殺す。
やられる前に、やれ。
死と隣り合わせの戦地で精神をすり減らし、陥る戦争後遺症=PTSD。
それは、絶対安全なこの戦場でも。
一体何と戦っているのか、自分は何をしているのか、任務と現実の境すら分からなくなってくる。
やがてそれは家族関係にも影響を…。
アンドリュー・ニコル×イーサン・ホーク。
その昔、『ガタカ』で近未来の管理社会を痛烈に描いたコンビが、本作ではドローンを使った戦争の実態とそれによって苦しむ兵の姿をリアルに描く。
派手さも無く、どちらかと言うと全体的に静かなタッチ。
PTSDに苦しめられても、兵たちは何かを犠牲に“今ここにある戦争”を続けなければならない。
ゾッと恐ろしい作品でもあった。
平和のために
タイトルなし
期待に反して良かった。現代の遠く自国にいながら、ゲーム感覚のボタン一つで無人飛行機からのミサイル爆撃が行える戦争、それを扱う兵士の苦悩が描かれており引き込まれた。イーサン・ホークの演技が素晴らしい。
こういう終わり方くらいしか救いが無いか。
ドローンを使った戦争を描いた映画。
実際にこういう形で本当に人を殺しているんだろうか?・・と疑いたくなるような話。
もちろん、ストーリーは映画的に面白くするために、CIAの横槍とか少し話を膨らませているところはあると思う。けど、現実の任務はおそらくこの映画で描かれている通りなんだろう。
私は当然戦争には参加したことが無いけれど、それでももし参加することになり人を殺す状況になったとしても、ちゃんと「その相手を殺す意志」を持ってその行為を行いたい。
それは戦争という非日常の中でも、最低限の相手に対する礼儀のように思う。
ドローンを使った人殺しにはそれが無い。これは単なる「殺戮」だと私は思う。ゲームのように、相手の顔すら見ずに簡単に人を殺す。
主人公はパイロットとして現実の戦争に参加していたという設定だったので、PTSDになるくらい悩むことになったわけだけど、戦争に参加したことが無く、人格が少し壊れてる人がこの任務についたら、それこそ歯止めが効かなくなる。
神では無い人間として、規則に背いてまで行った主人公の最後の行動が正しいのかどうかは正直私にはわからないが、この物語の中では主人公の再生のために必要な儀式だったんだろうな。。
もし、戦争してるお互いがこの機械を使う(使える)ようになったらどんな状態になるんだろう・・
色々と考えさせられる良い映画です。
これ以上話しが広がらないよなあ
ずいぶんタイムリーな時期に見てしまった。
ここで軍事評論しても仕方ないので、それはやめとく。
尺は短め。映画として思ったのは、これだとこれ以上話しが広がらないよなあ、ということ。戦争映画におけるドラマもこうして変っていく。
テーマはアメリカンスナイパーに通じるところがありそうで、正義とその裏には闇があり、その闇の中で傷を負っているのは、たとえば兵個人の精神、心である、という。
でも、これ描けば描くほどどつぼにはまるテーマになりそう。そもそも答えを提示できない。答えがあったらもうやってない。またトランプがイランとおっぱじめたし。
ラストの暗示同様に、終わりがない、ていう答えなのかもしれないけど。
恐ろしく虚しい
オペレーション・ルームからゲームのようにアルカイダのテロリストを見つけ、空対地ミサイル“ヘルファイア”を撃ち込むというミッション。毎日、そうしたテロリストのアジトに撃ち込むため、非戦闘員、民間人も巻き添えにすることがあり、世間からも非難の声が上がっている。
ロボットが人間を殺すとか、無人戦闘機が人を殺すとか、戦争の在り方が変化しつつある現在。良心が痛まないとかいう評判もあるが主人公トミー(ホーク)は徐々に心を病んでいくのだ。衛星画面では戦闘員と民間人の違いがわかるほど正確であり、10秒ほどのタイムラグがあるため巻き込んでしまうことも多いのだ。恐ろしい。
ミサイルを撃つこと自体、大量殺戮に繋がるので、スイッチを押す者は心が痛むことがあって当然だし、上官の命令と割り切れば罪の意識もなくなるのであろう。現代の戦争だけではなく、自らが安全な位置にいるミサイルを撃つのはみなそうだ。物語は淡々と描かれるだけにどんどん嫌悪感を募らせる作りになっているが、大きな展開もないため、虚しくなるだけの作品。
マスターアーム・オン!!
FPSのいわゆる「空からの死」のステージが好きなので、妻子や友達もいない私にはぴったりの職場でした。家族持ちの主人公の苦悩というのは早くも前半から描かれ、ぶっちゃけますと取って付けた感じだと思います。同僚の女性も、高い給料をもらって文句を言うのは止めて欲しいです。日本では銃撃で死んでいる一般人はいませんが、国が率先して若者から徹底的なな搾取を行い、食べ物が小さくなる悪徳商売が横行しており、自分さえ良ければ良い・今だけ儲かれば良いという考え方が主流になってしまった為、本作を観てドローンを使った戦争が…PTSDが…とか言っても所詮現実から目をそらすだけの綺麗事に過ぎないと思います。ジャンルは違いますが、「ウルフ・オブ・ウォールストリート」のように平気でできる人間を高揚感のある演出で描かないと、異常性も伝わらないと思います。
21世紀の戦争の形。
じわりじわりと
終始、大きな起伏があるわけでもないのに、じわりじわりと主人公の心が蝕まれていくのがわかる。戦闘機のパイロットとして再び空を飛びたいという夢と、12,000キロも離れた安全な場所から、攻撃されることを予想もしていない相手を爆撃する卑怯さ、実感のなさに生きてる意味を失いかける兵士。
最初、民間人を爆撃することに躊躇していたが、だんだん作業のように無感情になっていかざるをえない葛藤が上手く表現されていた。
テロリストの工場は、中東でなく、殺している私たちだというセリフがアメリカ国民にはどう刺さったのだろう。
相手が攻撃するのをやめないなら、こちらが攻撃するんだ、という上官の言葉。それに対して、それだと相手も同じで終わりがない、と反抗する部下。悪循環とわかっていても辞められない中で良心を保つのは難しいはずだ。
アメリカ映画の割に、反政府、反戦争を戦争をテーマに描くなかなかの作品だった。
ゾーイ・クラヴィッツが、エックスメンの雰囲気とは違い魅力的だったことに驚き。どことなく広瀬すずに似ていた。
2010年の戦争
戦争の定義が・・・
無人機(ドローン)で上空から標的を爆撃する。無人機だから反撃されることも無く次から次へと平然と民間人も巻き添えにして、攻撃は続行される。攻撃を受けるほうは、はるか上空の小型無人機に気づくわけも無く、狙われていることに全く気づかない。これでは行っていること自体が「暗殺」と同じことであり、次のテロリストを生みだす負の連鎖にしならない。そして、今はアメリカが一方的に無人機で攻撃しているが、アメリカが敵国とみなしている国が、無人機を開発すれば、アメリカの軍事基地がある日本も攻撃対象となる可能性もある。
実際に攻撃を遂行する部隊の人間は、非常に強いストレスにさらされ、精神を病みそうになるのだが、命令する上層部はいつの時代もそうだが、現場を無視している。ドローンもドローンを操作する人間もいくらでも代わりがきくからで、延々と「敵・悪」と見なされた国は攻撃され続ける。今の集団的自衛権や憲法改正も、現在の軍事技術をベースに議論されるべきで、何がテロで何がテロでないのか、等々いろいろと考えさせられる映画であった。
ラストに極悪非道な人間を爆撃するところ(実際には無理だと思うが)に、上層部からの命令から一時的にでも解き放たれ、何らかの「救い」にも見えなくもないが、それ以上に「こんなことまでできる」としか思えずただ寒い思いをしただけだった。
この映画には感動も涙もないが、時節柄見ておいてよかったと思いえる一本だった。
全48件中、1~20件目を表示