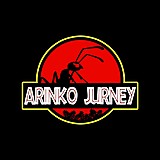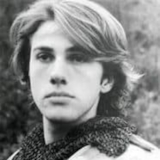Mommy マミーのレビュー・感想・評価
全116件中、21~40件目を表示
息の詰まるような密着する母子関係を描写
「僕は暴力的な扱い難い子供で、親がそういう子供向けのサマーキャンプに入れたんだ。僕の場合はそこで文章で自分を表現できることを知って良くなったんだけど、もし、S14法=取り扱いの難しい14才以上の子供は施設に入れていい、という子捨ての法律があったらどうなるだろうって考えてみたんだ。」とドラン監督はインタビューに答えていた。
母一人子一人で互いに溺愛しあい依存しあって生きてきた。だが、息子の自分の思い通りにならないと癇癪を起こす激しい気性は成長期に入って大人の手に負えなくなり、母親は疲れ果ててしまう。こんな子いなければとさえ思う。その過程の描写が細かく説得力があるので分かりみが深過ぎて哀しくなる。途中、第三者の隣人の女性が加わるという変化もあったのだが…。
ドラン監督らしい若々しいラストの演出が鬱積した暗い気分を少し軽くしてくれたのはよかった。また、息子役、隣人役共によかったが、母親役の演技力が特に光った。
スクリーンサイズ
スクリーンサイズが1:1という、TVではちょっと鑑賞しにくい画面。アップになると表情がわかりやすいけど、どことなく絵画的であるのも面白い。
火災を起こして施設を追い出されることになったスティーヴ(ピロン)。最初から黒人のタクシー運転手とトラブルを起こし、職場についたダイアンは突然の解雇。普段は優しい子なのだが、注意欠如・多動性障害というスティーヴは時折暴力的になるのがやっかいだ。父親が死んでから一人で育ててきたが、今は子供向けの翻訳の仕事を見つけたダイアン(ドルヴァル)。
そんな中、隣人のカイラ(クレマン)と仲良くなるが、彼女もまた教師でありながら2年前から言語障害を患い、長期休職している。次第に交流が深まると、スクリーンサイズは普通のビスタサイズに戻るが、放火によって傷を負った家族から25万ドルを請求する訴状が届き、再び暗い1:1の画面に・・・そしてスティーヴがスーパーでリストカットして登場人物の心が揺れ動く。問題を抱えながらもドライブに出かけ、そこでまたビスタサイズになるという、心理描写をスクリーンサイズに投影しているのだ。
そんなスティーヴを結局は施設に入れる決断をするダイアン。母と息子の心理もよくわかるけど、実際に知的障がい者が身近にいないので隣人カイラの気持ちがより伝わってくる。
閉塞感を感じる映画
天才。
多動性障害を持つ少年とシングルマザーの母親と吃音症のお隣の奥さん3人の交流を描いた話。
.
この映画、ほぼずっとアスペクト比1:1のスマホの画面のような狭い画面で話が進行する。画面が狭い時ってだいたいその中の人がいかに狭い世界で息苦しく生きているかを表してるんだけど、2回そのアスペクト比が広がるシーンが出てくる。
.
最初のテロップからもうこの3人が良いエンディングに向かうことは何となくわかっているからこそ、その画面が広がるシーンが泣ける。
.
画面の比率だけじゃなくて、ほとんど画面に一人しか映らない中、いつ誰が同じ画角に収まるのか、誰と誰が絶対に同じ画角に入ることがないのか、全部が計算されてる。
.
グザヴィエドラン監督、音楽の使い方がやっぱ上手いよな〜.
.
あとは私の中の青いポスターの映画だいたい面白い説にまた1つ作品が加わりました(笑).
.
Mommy
ADHD(注意欠陥・多動性障害)を抱える人々の存在をSNSなどを通して知る機会が多くなっていた。その症状について「遅刻が多い」だとか「片付けができない」だとか、とにかく漠然とした知識しか持っていなかった。もちろん人によって症状の程度に差はあるのだろうが、彼らが直面する現実をこの映画を通して垣間見た気がすると言ったら稚拙だろうか。
冒頭からダイアンとスティーブの放つ言葉は刺々しく、お互い比例し合うように感情を剥き出しにする。それと対比するようなカイラの吃音。「キャラクターが主役になって、観客の視線も否応なしに集まり、目が離せなくなる。」という理由のもと設定された1:1の画面比率も手伝って、彼らの感情の機微を感じ取ろうと必死になれた。
この映画で一貫して描かれているのは「母子の愛」なのであるが、それは時に率直であり、時に歪なものであった。ダイアンとスティーブに通底しているのは互いに必要とし合っているという穏やかな愛情であるにもかかわらず、どうしようもない現実や未来への不安を目の当たりにするたびに、そんな愛情を守るべく交わされる言葉で、見失いそうになる愛の存在を確かめているのだろう。
痛々しい
暗さと、すがすがしさと、
そうだよね。
そうだよね
と、思うというか。
ADHDとか、障害の有無に関わらず、
ただでさえ、人間って、難しい。
一筋縄じゃない。
ひとつの事象に、ひとつの感情
ではない。
序盤の方でのメッセージ
「愛があれば、なんとかなる
というわけじゃない。
愛情があっても、どうにもならないこともある」
これが、この映画のテーマともいえるのかな。
そしてこのテーマは、
障害者の子と親、という関係のみならず、
家族、恋愛、友情、仕事相手...
どんな人間関係においてだって言えることだ。
スティーブは、
感情の出す量、
伝え方、抑え方、
それをコントロールするネジを
人よりも、グングン回す。
この世界で生きるには
窮屈だよね。
きっと、スティーブにもピッタリの
世界があるはずなんだけど。
この地球では、そのコントロールネジの幅が
そんなに回らない人の方が多いから。
愛情のあまり、
強く抱きしめても
相手に「苦しい、痛い」と思わせては、
それは愛ではないと
受け取られてしまうのかもしれない。
相手にとって、
ほどよく、心地よい力具合で抱きしめることが
愛、なのだろうか。
わかんないけど。
自分の心地よい「愛のでかさ、強さ」が
同じように感じれる相手だと
ベストだけどね。
ほどほどの価値観って、
人それぞれだから
難しいし、
だから面白いし、複雑だね。
そんな、
「人間って複雑でシンドイけど、
素晴らしい時間も、あるんだよね。」
を、繊細に、そして大胆に、
表現した監督は、
すごいね。
音楽の入れ方も、好きでした。
冒頭のs-14法案の物語への絡み方が、お洒落な世界観に飲み込まれて...
Xavier Dolan
日本ではすでに名前も知られ、人気の監督ですが、この作品は彼の名を日本に広めた作品と言ってもいいでしょう。私もドラン初観賞作品はこの作品でした。
まず最初にこの映画を見て出てくる言葉は、美しい。そして最後に出てくる言葉は、美しい。映画が始まって、私が死ぬまで私の中でこの作品は美しいの定義となるでしょう。
撮影
今作で最も目に止まるのは、何と言ってもアスペクト比。このアスペクト比を採用したことは、この作品の全てにつながっていて、フレーミングの美しさが際立っっていました。
1:1の正方形の画面では、幅広いのが映画という、これまでの常識が通用しない世界。映画の特徴とも言える画面いっぱいのに広がる景色や、3ステージを使ったストーリーテリングなどの映画の最大のパワーを捨てててまで採用したアスペクト比。しかし、彼はさらに新たな方法を発明することでさらに強力なものへと仕上げました。それがフレーミングの決まりを作るということ。この作品の90%のフレーミングがキャラクターが真ん中にいるというもの。たとえ会話のシーンであっても、キャラクターは常に真ん中。ウェスアンダーソンのようなシンメトリーの構図に加え、彼がストーリーテリングの方法として用いたのは、サイズ。単純に、ワイド、ミディアム、ミディアムクロースアップ、クロースアップdすが、そのサイズの違いを主体としてキャラクターアークを作る。それによって、この正方形の狭いアスペクト比をつかって、塞ぎこんだ感情と、寄添い合う愛情の2つを表現したのです。これはまさに発明。まぁもうドランは一生使わないだろうけど。会話でのシングルと、写真を撮るときの3人が1つのフレームに入るワイドのコントラストがとても強力。まさに、ビジュアルストーリーテリング。
それに加えて、フィルム特有のハイライトカラーの使い方、ししてエピックなライティング、アンドレターピンお天才か。
編集
編集者としてのドラン。フレンチニューウェーブに強く受けた編集スタイルだけでなく、私の好きなところは、間の取り方。怒涛の口喧嘩の後にくるのボイスオーバーのモンタージュや叙述的なショットを並べた音楽主役のシーンなど、ドランの作品には欠かせない要素。そのまさに芸術とも言える、意識の枠を超える、感覚の部分で脳に、心に強く印象に残るシーンは最高。このストーリーが一旦止まり、感情に深く入って行くところは、ヒューマンドラマではなくてなはらないもの。ドランはその入れ方、そこへの持って生き方が天才。泣かないわけにはいかない。
スティーブの心の映像
悲しい
母子再び
2015年の公開時にも見たのですが、昨日まで恵比寿でやっていたのでまた見てきました。
個人的にはドランの処女作「マイ・マザー」が一番好きです。この「マミー」を見て良かったなと思った方には是非「マイ・マザー」「わたしはロランス」等も見て下さい!と言いたいです。
テーマは母と息子の葛藤。アンヌ・ドルバルが母を演じています。彼女のフランス語が非常に聞き取りにくい。すごく訛りがあって。他の作品ではドルバルはきれいなフランス語を話しているので、恐らくこれはわざとなんですよね、主人公一家のポジションを示すための。
1対1の画面が話題になりましたが、正方形だと画面がひとりのアップになりやすい。これが「たかが世界の終わり」の撮り方につながったのかなと思いました。父親が亡くなり引っ越した点など、いくつか重なるところがあります。
隣人のカイラは息子を亡くしていて、恐らくスティーヴに息子の成長したときの姿を重ねている。
子どもを持てば、どうしてもその子が卒業して結婚して孫が生まれて…と想像するかと思います。それだけにラストが悲しい。
いい意味で「マイ・マザー」をより洗練させた作品ではないでしょうか。
グザビエ・ドランの次の作品が早く日本で公開されることを首を長くして待っています。
oasisのワンダーウォールがかかりスクリーンが広がるシーンは鳥肌...
oasisのワンダーウォールがかかりスクリーンが広がるシーンは鳥肌!
たかが世界の終わりから入り、私はロランスと見てきましたが映像と音楽のかっこよさはさすがドラン監督でした。
話としては障害と貧困の二重苦の中、どの選択が正解だったんだろう、誰がいけないんだろうと考えさせられてしまいました。。後半の夢のような素敵な将来のシーン(実際、夢)を見てしまうと、スティーブ、暴力振るうなよ。。。と思ってしまう。でも本当は暴力のきっかけになった、障害を理解しない人びとと社会構造がダメなんだろうなあ。
障害による貧困対策が施設提供じゃなんかなあ。でもそれがベストなのか。。。うーん勉強不足。
ネタは重かったけど映像美のおかげで見やすかったかな。面白かった!
初ドラン!!
親として
冒頭から画面が小さくて、「ワイド画面に対応してないのか?」とか思いながら観てたら、後々意図的な作りだと分かり、それや音楽の使い方も含めて非常に凝った作りの映画でした。今までであまり観た事のない演出多数で、話に入り込むより作りに驚く映画。
この映画はこれが売りなのかな。
話は所謂問題児の息子を抱えた母親の苦悩。そして国の制度に翻弄されていく母子。しかし母は強し。息子は母の愛情が冷めるのを心配しながら、母は息子を「特別な存在」と愛し、何とか自力で育てていこうと努める。
自分も親として、子どもへの愛は無限だ。冷めることはないと思う。しかしスティーブの様な問題児となった場合でもそれは言えるのか。それは誓うものではなくて、その時次第だと思う。でも、子どもがそれだけ間違った事をしても、親としては常に味方でありたいと思ってます。
強き母の映画
母の日にて鑑賞。発達障害を持つ息子(軽度ではある)が抱え、起こしていく様々な問題や苦悩を、心を折られそうになりながらも、愛をもってしっかりと受け止める母の姿に感動する。その愛が一方通行ではなく、息子もまた母を「誰よりも大切」に思っている、その親子愛が涙を誘う。互いに不器用で、すれ違って自殺未遂までに発展してしまうが、最終的な母の決断は簡単には理解できないものだろう。
個人的には隣人のキャラクターがとても好きだ。彼女がこの家族に与えた影響、彼女が与えられた影響はとてつもないものだろう。彼女が家族と話している時よりも、彼らと会っている時の方が楽しそうで、饒舌になっていると感じたのは私だけだろうか。3人でダイニングで写真を撮るシーン、あのシーンほど幸福感に溢れたショットはなかなかないだろう。そんな愛すべきキャラクタなだけあって、ラストの引越しを告白するシーンは、両者の心情が痛いほど伝わってきて、胸が張り裂けそうになる。
グザヴィエ・ドランは選曲もよく、oasisのwonder wallは信じられないくらい映像とマッチしており、あのアコースティックギターの音が鳴った瞬間、震えた。
全116件中、21~40件目を表示