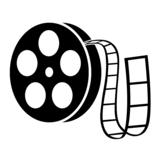野火のレビュー・感想・評価
全161件中、81~100件目を表示
美しいわけがない
肉片が散乱し、ウジが大量にわき、唇を真っ赤にして人肉を貪る。想像以上のおぞましさにしばらくの間、スクリーンを直視することが出来ずにいました。
この作品はあくまで田村一等兵ひとりの体験がベースです。100人の兵隊がいれば100通りのおぞましい体験が各々にあったのではないでしょうか。もちろん、田村一等兵以上の体験もあったかと、容易に想像がつきます。
昨今、戦争を美化する様な作品もありますが、私は「野火」の様なおぞましさ以外に戦争の真実はないと思います。
というのは、10年程前にひめゆりの塔を訪れた際に、ひめゆり学徒隊だった語り部のおばあから「映画ひめゆりの塔(1953)で、キャベツをボールにして遊んだり、笑ったりするシーンがあったけど、あんなことは微塵もなかった。楽しいことや美しいことは、ひとつもなかった。あれは映画だから。」と聞いたからです。
塚本監督は、映画だからという理由ではなく、戦場の真実をフィルムにしました。それは、人の身体は簡単にバラバラになり、腐敗しウジがわくこと。そして、異常な環境にもやがて慣れ、人を殺せる様になるということ。
そして、この戦場に敵は不在です。何の為にこの場所にいるのか、もはや誰も分かりません。日本の為なのかどうかも、誰も分かりません。分かることは、日本という国家が想像を絶するほどに「狂っていた」というたったひとつの事だけです。
リバイバル映画・・
再び野火を見る。
2度目の野火を観た。監督は舞台挨拶で各地を回っている。
生で見る塚本監督は静かな、それでいて「自分の映画はヘンテコリン」と言いながらも、その映画に身一つ体当たりして行くような、そんな人だった。私この監督、大好きです。
まあ、それは置いといて、以下は15年公開当初の感想の再掲だが、考え方はさほど変わらないのでレビューとします。
「ネタバレを含むーこう前置きする事がこの場合正しいのか。何より映画「野火」は、大岡昇平の同名小説の映画化である。それをやったからとて、この映画と小説の価値が下がるわけではない。そもそも、これはエンタテインメントではないのだから…。という逃げ口上。
ー大岡昇平の「野火」を最初に読んだのは、確か図書館であったと思う。三島由紀夫熱が一時的に下がり、その合間に様々な作家の本を読んだ記憶がある。結局、最後には元の位置に戻ったのだが…。
「野火」を最初に読んだ時、私が何を思ったのか、今もって思い出せない。随分ミーハーな私であったから、軍隊における人肉食というセンセーショナルな部分にばかり興味が湧いたのだろう。そんな私であるから、また塚本晋也監督が取り組んだ「野火」を見るまで、またその前にもう一度原作を読み直した時点までで、長い間その程度の知識しか持っていなかったということになる。甚だ浅はかな読書で、全く何のための読書だったのか。あの頃の自分を殴りたくなる。せめて読書ノートぐらいつけろ。
そうしたわけで映画を観るために、私はもう一度小説を引っ張り出して読んでから、準備を万端にして映画を観に行った。
物語はだいたい要約するとこのようになるだろう。
… 塚本晋也扮する田村一等兵は肺炎を患い、原隊と彼を受け入れない野戦病院とを行ったり来たりする。病院の外では、安田という男が淋しがり屋の青年を使ってタバコを売りながら兵士たちからなけなしの芋を巻き上げる。
そのなか野戦病院、そして田村の原隊は攻撃を受け全滅する。どぎつい緑の世界を田村はさまよう。
餓え、フィリピン人の殺害などを経て、彼はパロンポンへの招集が発令された事をその過程で知る。しかしパロンポンを目前にして、兵士たちは次々殺されてゆく。その内飢餓感から、彼は人肉食に惹かれてゆく。
野火において敵は見えない。野火における主人公たちの敵は、現実通りアメリカ(連合国軍とは言うまい。大東亜戦争は世界大戦における"地域戦"である) だが、まるで得体の知れない未知の敵から攻撃されたかのように、何も守るすべなくなぎ倒され、しかばねを積み上げる。何よりもこの「ただの肉塊になる虚しさ」をこれでもかと突きつけてくるのがこのパロンポンへ向かう日本兵が一方的に殺されてゆく場面である。「鬼畜米英」や大本営発表の虚偽、連合国を過小評価していた当時の軍部のリテラシーの低さを考えると、この未知や「得体の知れなさ」というのは、切実な意味を持ってくるように思われる。
説教臭さはない。ともかく説教というのはどこかしら上からである。もっと塚本映画というのは暴力的である。同じ地平の確かな陸続きなのだ。そして地平からやってきて、こちらが観客であると言う安全地帯を徹底して切り崩そうとする。
食べ得ざるものを食べた人間の口許にはぬらぬらした血が滴っている。原作には神(のようなもの)が現れ、食べる事に警告を発するが、塚本版「野火」では、復員後、田村が奇妙な祈りを捧げているにとどめている。しかもその祈りは、食べ得ざるものを食べる前の行為に似ている。つまり屠殺という行為に…
彼は書斎を出る。その窓越しに"野火"の揺らめきを見る。
書斎を一歩出、その窓越しに"野火"を見る事は、結果として田村の中にある戦争が継続途中である事に他ならないのである。継続、あるいは永久戦争であろう。
ドイツワイマール体制下において、作家エルンスト・ユンガー曰く「両親の実家に復員していながらも、居間で野営している」(「冒険心」)という事そのままではないだろうか。
ここからある共通項を見出しえないだろうか?即ち、平和主義者も、対局の好戦主義者(これを対局と言えるのかどうか…)も、一度"野火"ーそれに類似する表徴を見てしまった以上、嫌が応にも戦争を継続せざるを得ないのではないかという事である。もっと言えば、戦争という宿命の場面に強制的に立たされる事を意味しないか。この位置から決して逃げ出す事はできない。特に一度体験したものは、そうであろう。
戦争は彼ら体験者にとって終わるものではない。(知った風な口きくな?ごもっとも)ポツダム宣言の受諾、終戦の詔勅、連合国軍による占領統治、サンフランシスコ平和調印によるカッコつきの主権回復を経ても、それでも戦争は終わらないのだ。人々は如何しても戦争を終わらせたいらしいが…。だが、戦争を継続するという事がどれほどの苦難か。
そのカッコつきの「戦闘」シーンについては如何やら「やりすぎだ」との意見もあったようだ。しかしそもそもこの映画が、あるいは現実が映す戦争とはやりすぎかそうでないかの「程度の問題」を比較するようなものであろうか?
戦争とは「徹底」している事だ。「貫徹」するという事だ。「徹底」したもの「貫徹」したものに、やりすぎも何もない。
創作物は製作者の意図を越える。いや寧ろ多様化する。人が考えるのは、その作品から受け取る、いわばプラスαの部分である。作られた時には個人的でしかなかった者が、ミームの受取手の誤読によって全体へと変化する。
この時大岡昇平の市川崑のそして塚本晋也の、彼らが意図していた意図を越え、ともすれば読者、視聴者の意図も越えてしまうのである。私の意図も越えるだろう。この時物語は独立し、全体になり、支配する。
塚本晋也は「徹底」し「貫徹」している。氏は了解しないだろうが、彼こそ"戦争"ではないだろうか。支配的なものに対する新しいやり方の"戦争"」
人肉食べる歴史はつい最近まであった
昔の野火をよりリアルにした話だけど、東北の飢餓の時は、間引くって言って子供を食べるってお婆さんが言ってた。
亡くなった叔父さんも、戦争中に米軍の飛行機が墜落した時、凄く美味しい匂いがして、みんな猿を探しに行くと一人一人森に消えていったと話していた。
だけど、何故今人肉?
まぁ、東京喰種も人肉食べるけど
今、野火をリメイクした意味がわからない。
好きではないが観ておくべき映画
渋谷ユーロスペース初見参
ホテル街に突然、文化の香り
(学生時代に「ゆきゆきて、神軍」を観たはずだが記憶になかった。wikiによると2006年現在地でリニューアルオープンしたとのこと)
興味ない•2•••好き/並••••5すごい
無••••5社会派/大衆••••5カルト
損はしてない/紹介する
俺の満足度 60点
作品賞ノミネート可能性 40%
なんか、怖い。
90分、身じろぎもせず。疲れた。
好きではないが、観ておかないといけないという映画。
ジャンルは戦争映画だが、敵との遭遇は1回、現地住民との接触も実質1回、あとは味方であるはずの自軍兵士との行動がほとんど。それなのに圧倒的な孤独感。微かな希望に向かっている気も全くせず。
極限ではさまざまなことが起きる、誰がどう行動するかもさまざまだ、ということを疑似体験できてよかった…のだろうか。
2020/8/25 追記
白波さん> 戦場という異常な空間をただひたすらに描いています
ホントですね。これ観たことで、「戦争は、嫌だ」という "考え" ではなく、生理的感覚が、自分のどこか深いところに植え付けられました。
今この映画を撮る必然
究極のサヴァイバル映画
吐き気がする。でも、これが戦場なんだろう。
観ていて辛い映画だ。
正視出来ない場面が続く。
でも、観てよかったと心底思う。
「戦争の真実を暴こうとする映画を作ろうとするとお金が集まらない」と、この映画の監督の塚本晋也はインタビューで語っていた。
特攻を美化してコテコテにCGを使いまくった某戦争映画がメジャー系列で公開されて大ヒットして、こうゆう映画はインディペンデント系の小規模な予算で作られあまりメディアも取り上げないのがこの国の戦争映画製作の現状だ。
ここには何のヒロイズムもない。
ただ密林を飢えたまま歩き回る兵士の姿だ。
戦争を経験してない世代である以上、何がリアルかなんて分からないかも知れない。
しかし、及ぶ範囲で想像して、考える事は出来る。
観るのに覚悟がいる。
でも、観てよかった。
テーマ
映画しか見ていないので、その範囲でしか言えませんが。
主人公の田村は非常に優しい人物として描かれています。芋を盗もうとして上官に殴られる永松をかばって、田村は自分の芋を差し出して許しを請います。その直後、アメリカの機銃掃射で日本軍の基地は火の海になり、永松はどさくさに紛れて田村の芋を奪おうとします。
恩を仇で返されたわけですが、その後再会したときも、永松の境遇を不憫に思った田村は、再び芋を差し出します。一度裏切られた相手に二度も親切にします。このときに主人公に感情移入できる人もいれば、仕返しをするくらいに思う人もいるかもしれません。
田村にしても芋をあげた直後に襲ってきた空腹で、「あんなやつにやるんじゃなかった」と後悔するわけですがw
しかし、このことが後に田村自身を救うことになります。
いよいよ空腹で、千切れた人間の四肢を目の前にして、ムシャぶりつきそうになっているときに永松に再会します。そして猿の肉をもらって食べることで命をつなぎます。猿の肉というのは嘘で本当は人肉です。
騙されて人間の肉を喰わされるわけですが、千切れた人間の四肢を目の前に自分の倫理観と戦って、絶命するかもしれないところを救われたわけです。
安田を殺して食おうとする永松を、田村が止めようとすると、永松は「じゃ、俺がお前を食うか、お前が俺を食うかどうするんだ?」と詰め寄られます。極限まで追い詰められて、生き延びるためにどちらか一方が食われるしかない状況のように思われます。
しかし、お互いに殺し合うことはありませんでした。田村は永松になぜ自分を殺さないのか?と聞きますが答えは返ってきません。長く行動を共にした安田を食べようとするほど、人として壊れているように思える永松が、田村を食べなかったのはなぜでしょうか。
田村は自分さえ生き延びればいいという発想とは逆の、いわば人間としての感情を失わないことで、逆に生き延びることになります。フィクションなので、お人好しが都合良く生き延びられたと言われればそれまでですが、少なくとも作者は極限の状態でも人間性への可能性を読者に提示したかったのかなと。
近頃は攻めるか攻められるか、殺すか殺されるかといった二者択一的な思考が流行っているようですが、そうじゃない第三の可能性もあるのではないか。そんな問いが発せられているように思えます。
第三の可能性とは何かと聞かれれば難しいのですが、なぜ永松が田村を殺さなかったのか?そのへんがテーマになるのかなと。
全161件中、81~100件目を表示