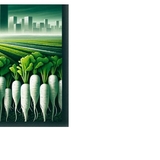イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密のレビュー・感想・評価
全457件中、101~120件目を表示
50年という歳月
絶対に解読不能と言われたドイツ軍の暗号エニグマを解読した、アラン・チューリングというひとりの数学者の話。
全く予備知識なしで観始めたので、まさかLGBTQの要素が入ってくるとは思わなかった。ほんの50年くらい前まで、イギリスでは同性愛が犯罪だったとは…申し訳ない、全く知らなかった。
捕まった者には、投獄かホルモン投与という恐ろしい二択が待っている。人権も何もあったもんじゃない。
「あなたが普通じゃないから、世界はこんなに素晴らしい」
彼に大きく影響を与えた女性からの心を揺さぶる一言も、迫害を受け衰弱しきった彼の耳には届かなかったのか。
第二次世界対戦を2年早く終わらせた上にコンピューターの礎まで築いた彼の人生は、あまりにも早く幕を閉じた。惜しくてならない。
普通が嫌いな人は観るべき1本
戦争後もエニグマ解読を隠していた本当のわけ
面白かった。
調べたら益々面白かったので見た後に検索かけるのをオススメします
エニグマ解読のみかと思えば戦争を終わらせるために目的が変わっていて面白かった
主人公がなんだがいたたまれない、
コンピュータの名前も興味深かった
インターネットの知識だが、戦争後エニグマ解読を隠していたのはエニグマを手に入れたイギリスが他国に解読困難な暗号機のエニグマ!と言って売りさばいて、他国のエニグマでのやり取りをイギリスで解読して外交関係を優位に立つという理由だったとして鳥肌が立った
二本立て二本目。一本目と似た天才数学者のお話。実話の分、こちらに重...
普通とは
「時として誰も予想しないような人物が想像も出来なかった功績を成し遂げる」ー
当時世界最高峰の暗号とされたドイツのエニグマ。
エニグマ解読を任され、果たしたチューリングの生涯を描く本作。
ストーリーは大きく分けて3つ。
チューリングの幼少期、
エニグマ解読までの道のり、
そして戦後の人生を入り交ぜながらも
巧みに描いている。
天才ゆえの苦悩や後のコンピュータへ繋がる暗号解読機開発となるストーリーがメインにありながらも、
「普通とは何か」を常に問いかけてくる。
チューリングが誰にも称えられることもなく、
ホルモン治療を経て41歳の若さでこの世を去った。
しかし2013年に女王陛下より勲章を授与されたことにより彼の生涯と功績が表沙汰となる。
実に60年後のことである。
変わり者として扱われる主人公を通して
何が普通で何が普通でないか、
普通と違うことが悪いことなのか、
必ずしも普通が普通でないことを考える必要があることを改めて気付かされる。
チューリングの名を全ての人が知るべきだ。
コンピュータサイエンスのノーベル賞はチューリング賞。
「チューリング」は、本作の主人公であるアラン・チューリングから取られた。
本作は、チューリングの生涯を、
・第二次世界大戦におけるイギリスの対独戦
・チューリングのエニグマ解読の功績
・同性愛者であるが故の不遇な人生
3つに焦点を絞って過不足なくまとめた、という印象。
アラン・チューリングを知っている人(プログラマや数学に嗜みのある人)は楽しめるはず。僕は、エニグマの解読過程の描写をニタニタしながら観ていた。チューリングを知らない人は、とりあえずこの映画を見て、知れ!(理由は後述)
また、彼の不遇な人生を、この映画を通して初めて知った。多大なる功績を納めた(決して言い過ぎではない)人なのにね・・・。同性愛者という理由だけで、人を迫害してはならない、と思った。彼ら(彼女ら)は、同性愛者というだけで生き難いはず。それに追い討ちをかけるように迫害しちゃいけないね。
チューリングのことを知らない人もこの映画を見なければならない。なぜなら、チューリングは現在のコンピュータの生みの親だから。みなさんが使っているiPhoneだって、彼の功績なしには今ここに存在していなかったかも知れませんよ?
本作中では、チューリングのコンピュータ発展における功績についてはあまり語られていない。まぁそれは仕方ない。だってとても映画にできないもん、観念的すぎて、難しすぎて・・・とても映像化はできないwww。その功績は計算理論面での貢献。コンピュータサイエンスという学問分野では、多くの研究が、彼の理論を基礎に進められている。だから「生みの親」なのだ。
最高… 絶対みて… これが実話だなんて… 鑑賞後ネットでアランチュ...
【自らの性癖への偏見を乗越えた天才数学者”アラン・チューリング”という第二次世界大戦の終戦に貢献した方を知った作品。面白き事、限りなし。】
天才数学者であり、ドイツ軍の誇る暗号機エニグマの暗号を解読したアラン・チューリング(ベネディクト・カンバーバッチ)の数奇な人生を描いたドラマ。
この方の性癖を含めて、数奇な人生を見事に演じたカンバーバッチ氏の佇まい及び周囲(学友ジョン・クラーク(キーラ・ナイトレイ)等)の暗号解読に眠る時間も惜しんで取り組むチームの奮闘振りにも思わず引き込まれた作品である。
アランが、ジョンに自らの性癖を告白し、婚約を解消するシーンの二人の表情。(それは、ジョンの身を案じての事でもあった。)
戦争終結に多大な貢献をしながら、その性癖故に人間性を打ち砕かれるような仕打ちを”英国政府”から受けたアランの謎めいた死。
だが、英国政府がアランの功績を50年以上秘匿し続けた事は、矢張り彼の不自然な死には、何らかの政府の関与があったとしか思えないよなあ、と思ってしまった作品。
<第二次世界大戦後の時代、同性を愛する性癖を持つ人間は、あれだけの功績を残していても、死を選択するしかなかった時代だったのか、という哀しい想いを見る側にしっかりと伝えた作品。>
<2015年3月15日 劇場にて鑑賞>
国益の名のもとに
予告で流れる「英雄か、犯罪者か」とはこういう事だったのか…。
『ダンケルク』の彼らが浮かんできてしまった。
どんな勝負も、戦略がなければ勝てない。
結果として、最後のテロップにあるように、大勢の命を救ったのだけれども。
そりゃ、封印しなければ、助けられなかった兵士や民間人の遺族から袋叩きに合うよ…。英国にとっても、闇歴史だったんだろうな。
さらに、つきつけられるスパイ合戦。そのために利用される人々。
そもそも、彼らの提案を採用するかどうかの決定は、彼らとは関係のないところで行われているはずだ。
結局は、釈迦の掌の中で踊っていただけか。
そして、彼自身も一番大切なもう一人を手放さなければならなくなる、その人の安全のために。
大きな代償を払いつつ、なかったことにされる実績。最終責任を取る立場にはないものの、純粋な彼の魂は、自分にすべての責があるかのように自分に問いかけ続ける。「私は、神か、悪魔か、英雄か、犯罪者か」
自分が機械だったらどんなにか楽だったろうに。
コンピューターの誕生秘話であり、第二次世界大戦での偉業の話であり、人との繋がりの話でもある。
ジョーンが、アランの偉業を称えて言う言葉がキーワードとして何度か出てくる。感動的な言葉だ。
この映画は、アランを称える映画だから、当然繰り返される言葉であり、今を一生懸命生きる私たちに勇気をくれる言葉でもある。
けれど、日々、自閉症スペクトラム障害(アスペルガー障害含む)と、その近縁の困難を抱えていらっしゃる、多くの方がたと出会っていると、若干の違和感が禁じ得ない。
「別に偉業を成し遂げなくたって、貴方達は存在しているだけで素晴らしい」って言いたくなる。
アランが天才風を吹かせて高飛車なのは、アスペルガー特有の症状ではない。 ずっと馬鹿にされ虐げられてきた者の、反動形成だ。
事実を事実として周りの空気読めずに言っちゃって、何がまずかったのか理解できないところはアスペルガーの特徴だけれど。だから、ジョーンに諭されて、納得すれば、 かんたんにその教えに従ったりする。そのあとのジョークが、そのあとの展開につながっていて、うならさせられる。
ラスト、アランがクリストファーのことを「友達じゃない」と繰り返す。
うん、友達なんかじゃない。もっと大切な魂の片割れ。
たんなる性的志向じゃなく、もっともっと深い魂の結びつき。当時の風潮としては全力で隠さなければいけない想い。
とはいえ、クリストファーのことを想うことを否定されて”治療”させられたら、自分の存在そのものの否定だろう。
林檎に青酸カリをつけて自死されたとか。
事実なのか脚色なのか知らないけれど、映画の途中の、林檎のエピソードを思い出すと胸が苦しくなる。
人が大切にしているものを奪っちゃいけない。
人を人として信じてあげること、それは人にしかできない
AIが恐らくついに花開こうとしている今、それをどう使い世界をどう動かすかは、人間に突きつけられた最後のテーマと言えると思う。
この映画は教えてくれる、「人を人として信じてあげることは、人にしかできない」と。「モンスター」のような異端児の彼をイジメから救って信じてくれた彼の中学の親友、チューリングを人として信じたフィアンセ、そして彼の仲間。
そしてその信頼が結実した結果、英国が成し遂げたナチスドイツの暗号解読という奇跡。そのきっかけが、実は恋だったという、いかにも人間らしいストーリーが、コンピュータ開発の原点にあったことを、私はこの映画で初めて知った。
人はそれぞれが他人にはなかなか言えない、人とは違った面を持っている。それを感じ取り、認めあってこそが人間であり、だから我々はAIという「モンスター」と、これからどう付き合っていくかを決めないといけない局面に今来ていると思う。
題名は「エニグマ」がよかったな、と。
敬遠しがちな緑色の画像と、イミテーションゲーム〜エニグマと天才数学者の秘密〜という面倒臭そうな題名。。。
それを1ステップ乗り越えてぜひ色んな方に一度観て頂きたい。
実話に基づくはなしだが、脚本が秀逸。数学など関係なく分かりやすい内容になっている。
良かった点3つ
1.暗号解読の話と、ソ連の二重スパイがいる事の同時進行。誰がスパイかさぐりながら観れる楽しみがあった。
2.裏で操っている上司の、頭のキレ具合い。唸る物があった。台詞も良い。
3.冒頭シーンからエニグマ解読まではさほどでも無く観ていたが、その後のわずか30分程度の怒涛の展開。尺の使い方にセンスを感じる。
イマイチな点2つ
1.野暮ったいシーンが数ヶ所あり、残念であった。
・ジョーンの家族にアランが説得しに行った時のジョーンの表情がオーバー。
・研究を止められそうになった時の仲間の団結感と音楽が私的には寒い。
・ジョーンの職場仲間の女性のビッチ感がオーバー。
・エニグマ解読直後、僕の兄さんが乗ってる船なんだ&何故助けてはいけないのかの説明(ジョーン)はしなくて良い。分かるから。
その辺り、もう少しだけクールに作ってほしかった。
2.題名も含め、全体の雰囲気や印象が芸術性に欠ける。
主役がカンバーバッチである事が芸術性の集中点のようにも感じる。それ程までに彼は個性的な役者だし、この役に合っている。
それ以外は芸術性の高いシーンが無く、敢えて削ぎ落としているのか、と思うほど。
あと20分長尺にして美しいシーンや、印象的なカットを作り込んで欲しかった。全体的に残る雰囲気が映画として物足りなく、内容が良いだけに勿体無い。
以上
アランは青酸カリを含んだ林檎を食べて死んだという事を記事で読んだが、それは映画内ではなぜ語られなかったのか…
やはりスティーブ・ジョブズのアップルはアランの林檎からきているのだろうか…
鑑賞し終わってもなお広がりを持たせる映画であり、歴史のある意味での中枢部を垣間見せられ、現在までの繋がりを感じさせる良い話だった。
ゾクっとくるよね。
amazonプライムで観る。
ベネディクト・カンバーバッチのファンだけに、気になっていたものの、観る機会を失っていた。
この作品は現代の我々が知らなければならない戦争の真実の一面を描いた作品だと思う。
アラン・チューリングについては、スティーブ・ジョブズの伝記などで何回か目にしていた名前だが、どういう人物なのかまるで知らなかった。
現代の電子計算機の誕生の秘密がここにある。戦時下のイギリスでどのようなチームによってナチスドイツの暗号解読がなされたか。
「ダンケルク」「ウィンストン・チャーチル」と繋がって、イギリスの対独戦の秘密が語られる。
諜報合戦、やるかやられるか、暗号解読が間違っていたり失敗したり時間がかかりすぎたりすれば、味方の被害、死者は確実に増えてゆく。
全457件中、101~120件目を表示