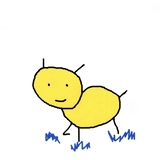家族の肖像(1974)のレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
教授のメランコリー
若さを失うほど、若者との隔意とともに「おれはもう若くないんだな」という実感がやってくる。おおむね30代以降にそれがきて年をとるほどゆるやかに静まっていく。ゆるやかに静まっていかない奴もいて、そんな奴が若い女に執着して事件化することが定期的にある。
たとえば職場で若いアルバイトたちが休暇の旅行計画をねっしんに話し合っているのを小耳にはさむ。そこに仲間入りしようとは思わないが、もし誘われたらほいほいとついていくかもしれない。
じっさいには面倒だから仲間になりたくはない、だとしても、もし頼りにされたなら、たとえば運転手を頼まれたなら「しょうがねえな」と嫌がりつつ、内心喜んで足になるかもしれない。
じぶんがすでに若くはなく、もう若いひとたちの仲間に入れないことに、悔いのような気持ちをおぼえることがある。若い頃に戻りたくないし、仲間になりたいとも思わない。しかしわたしは若さを謳歌することなく、若さを発揮したこともなかった。青春がなかった自分への憐憫とともに、寂しさに似た気持ちが湧いてくることがある。
役名のない引退した教授(ランカスター)はローマの豪奢な楼閣に名画と蔵書に囲まれて暮らしている。孤独だが、孤独を愛していることを自得している。そこへブルモンティ伯爵夫人(シルヴァーナマンガーノ)が上階を間借りしたいと言ってくる。貸すつもりはなかったが夫人の強引さに圧されて貸すと、娘のリエッタ(クラウディアマルサーニ)や同居人のステファノ(Stefano Patrizi)や夫人の愛人であるコンラッド(ヘルムートバーガー)がやってきて、教授の静かだった日常が、ことごとく破壊される。
しかし、コンラッドは挑発的な左翼活動家だが芸術への造詣があり、放っておけない危うさがある。かれは上流階級と資本家を憎みながら、その実自身は伯爵夫人のジゴロとなって、その財貨に寄生している。その労働階級のジレンマ・自己嫌悪が、かれを激しやすくさせている。教授はそんな刺々しいコンラッドに不図、親心のようなものをおぼえる。
リエッタは現代的な不謹慎さ、今で言うならZ世代の不可解さがあるが、天衣無縫な若さと美しさを併せ持っている。コンラッドと教授がプロレタリアートとブルジョアの対比であるなら、リエッタと教授は生と死の対比である。死の匂いがする教授にたいして、リエッタは迸る(ほとばしる)ような生として顕現し、出てくるたびにパッと画が華やぐ。マルサーニは撮影時15歳だったそうだ。
教授はかれらに気分を害されながらも、手の焼ける家族ができたような父性(父代わりの気分)もおぼえるのだ。
伯爵夫人、コンラッド、リエッタ、ステファノの介入によって教授は平安をうしなう一方、かれらの喧騒に触発され、自身の家族(母や妻)の甘美な記憶がよみがえる。
しかしブルモンティの4人は結局思想的決裂をきたして離散し、コンラッドは非業の死を遂げる。教授は心身ともに打ちのめされ病褥で目を瞑る。
家族の肖像は新古や老若の断絶と、そこからくるメランコリー(憂愁)を描いている。と同時に、老齢の教授が、ブルモンティの4人に対してなしえることの限界が、そのままヴィスコンティ監督の限界につながっている。
『撮影は全て教授のアパルトマンのセットの中で行われ、これは教授の閉ざされた内的世界の表現であると共に、血栓症で倒れたヴィスコンティの移動能力の限界でもある。』
(ウィキペディア、家族の肖像(映画)より)
教授が画廊の売人から絵を売りつけられようとしているシーンで映画ははじまる。教授はかつてブランシャール画廊の常得意だったが、もう絵画を買う経済的余裕はなく、教授は売り口上に抵抗している。
ヴィスコンティを貫くテーマはヴィスコンティ自身がもつ境遇「没落する貴族」であり、享楽や文芸を捨てざるを得なくなった知識階級が、かといって労働階級になることもできず、凋落する様子が切り取られる。
教授もいわば絶滅危惧種として描かれる。かれは学識が深く、名画のコレクションも蔵書もすばらしい。しかし、間借り代金目当てにブルモンティの4人の介入をゆるしたかれは、結果さんざん翻弄されて心身をそこねる。そのとき教授の学識はなんの役に立ったであろう。アーサー・ボーウェン・デービスの家族画は、なんの慰めになったであろう。
けたたましく容喙してくるかれらに対して「家族ができたと思えばよかった」と教授は後悔するが、そんなことを思ったとしても、根本的な断絶は避けられなかった。年齢から価値観から思想から感受性から何もかもが違う人種なのだ。
そのように内実がいくら壊乱していようとも家族は「家族の肖像」画のごとく見えるものだと映画家族の肖像は言っているのである。
イタリア語の原題の訳はだいたい家族の肖像でいいと思う。英語タイトルのConversation piece(会話の断片)とは人々が交流する様子が描かれた定型の群像画のことだそうだ。
Imdb7.4、RT82%と83%。
海外ではヴィスコンティのなかではさほど評価されていない。が、日本では家族の肖像がヴィスコンティ映画のなかで認知、人気ともに高く、ウィキに『日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開され大ヒットを記録、ヴィスコンティ・ブームが起こった。』とあった。個人的にも絢爛と退廃のヴィスコンティよりも、これが気に入っている。黒澤明の100選にも入っているそうだ。
前述した通り映画は新古、老若の断絶を描いているが、教授が人生をかけて築き上げたものがなんだったのか疑問を呈している気配が大きい。教授は孤独を愛しているようだが、ほんとうに孤独を愛しているのか試されているようでもある。教授のメランコリーの核には若さへの憧れもあったであろう。そして、それらはすべてカメラのこちら側にいるヴィスコンティ自身の気持ちの投影だったにちがいない。
【孤独なる”教授”の老いたが故に求めた疑似家族の仮初なる形成と崩壊を描く。”教授”が住む大邸宅の一階の豪奢な絵画、意匠と、疑似家族が住む二階の現代アートの如き意匠の対比も見事なる作品である。】
<Caution!内容に触れています。>
■豪邸に住む”教授”(バート・ランカスター)は、「家族の肖像」と呼ばれる絵画のコレクションに囲まれて孤独に暮らしている。
ある時、フルモンティ婦人(シルヴァーナ・マンガーノ)が現れ、自分の娘リエッタや若き情夫たちコンラッド・ヒューベル(ヘルムート・バーガー)とステファーノと豪邸の2階に住みついてしまう。
新しく現れた”家族”により、教授の生活はかき乱されていくが、彼は美術に長けたコンラッドと友情を交わして、同居を認めるのだが。
◆感想
・物語は全て、”教授”の豪奢な邸宅のみで展開する。教授の住む一階の多数の絵画をを含めた意匠が豪奢であり、映画美術として見応えがあるし、それがこの作品の趣を醸し出している。
特に、書棚の奥に設置された隠し部屋の存在であろう。
・”教授”は最初は彼らが二階に住むことに嫌悪感を隠さない。音量の大きいポップスが流れて来るシーンは、静寂を好む”教授”の苛立ちを描いている。
・だが、”教授”は眉目秀麗なコンラッドが美術に長けている事を知り、彼に親近感を覚えコンラッドも又、”教授”を父のように思って行く。
■そんな中、”教授”は新しく現れた”家族”を、一階でのディナーに誘い疑似家族は夕餉を共にし、”教授”は穏やかな表情で新しく現れた”家族”達と卓を囲むのである。
このシーンは、孤独だった”教授”が”家族”の団欒を求めたように描かれる。
だが、その後、コンラッドは実は過激な左翼思想の活動家であり、ファシストで右翼のフルモンティ婦人の夫を殺そうと近づいていた事が明らかになる。
<そして、二階の新しく現れた”家族”は居なくなるが、逃走していたコンラッドだけは一人戻って来て、二階で爆死する。
その死体を抱いた教授は、一人一階のベッドに横たわり、医者が脈を図る中、静かに眼を閉じて動かなくなるのである。
今作は、ヴィスコンティ監督が、”家族”とは何か、”伝統と革新”とは何かという意味を問いかけた作品である。>
扇町キネマで 嫌いだな… とにかく侍従のようにそばに立つ娘と娘の恋...
扇町キネマで
嫌いだな… とにかく侍従のようにそばに立つ娘と娘の恋人が不気味
ファラオの墓の横に侍ってる二頭の犬みたい
みんな性的関係をもつ兄弟だしタブーなんてなさそう薬もやってそう 貴族である監督にとって世界はこのように映っているのか…
ハプスブルク家 イタリアの庶民「ニューシネマパラダイス」と貴族「家族の肖像」
ヴィスコンティのヘルムートバーガーは私より上の世代の方たちにはとても人気があるが
彼自身ファッションセンスがまるでなさそうだし…彼のどこが魅力的なのだろう?
老紳士のバートランカスターがイケメン 彼はイタリア人ではなくてアメリカン人だった驚き
シルヴァーナマンガーノは貴婦人役 メイクがすごい素顔 確かに彼女はすごい
イタリアの右翼と左翼 家の乗っ取りばなし
動けない人(この頃監督は病気の為)のとりとめのない妄想のような
私はこの老紳士は結局ヘルムートバーガーに恋した相思相愛 そういう話だと思った
1978年に日本で大ヒットしたらしい 日本人ってなにもわかってなかったのねと思った
澁澤龍彦は老紳士の生き方に憧れたらしい
私にはこの映画の魅力がよくわからない 途中で寝たし ビィスコンティは寝るらしい
彼ら家族のたたずまいがまるで地下芸人グループや学生運動のような連中抜けるに抜けられない好きでつるんでるわけじゃない泥のような同じ匂いになってしまった集団そういうグルーブがあるのだろうなと想像してみたり 彼ら自身は性格あうあわないもあるのにそのグループから抜けることはできない
主人公の心の振り子が身につまされて…
私の若い頃、片想いをしていた女性の
大好きな作品だったので、
今年閉館した岩波ホールで
ひとり鑑賞した苦い想い出の作品。
しかし、
ヴィスコンティ作品としては初めての、
しかも若い頃の鑑賞だったこともあり、
当時は、その難解さに
全く理解が及ばなかった記憶がある。
今、何十年ぶりかでこの作品を再鑑賞する
について、
内容も描写もほとんと忘れており、
ほとんどが絵画のある部屋での
話の展開だったような気がしていたので、
教授の上階が白いモダンな部屋に改装されて
いたシーンなんて全く記憶の外だった。
全般的な家族テーマとは別に、
終盤の右派左派ディスカッションについても
たくさんの示唆に富む台詞が出てきた中で、
「左翼の実業家がいる?」には
至極考えさせられた。でも、
富の再配分には左翼的思想が良さそうで、
ならば両者の利点をミックスしたらと
考えていたら、
斎藤幸平の「人新世の資本論」の本が
思い出された。
しかし、この作品の本筋は、
「結婚は家族のため、離婚は自由のため」等の
台詞もあった、
“孤独と家族”や
“孤独への希求とそこからの解放”等に関する
それぞれの交差についてなのだろう。
孤独を愛しながらも
主人公の台詞を借りると、
それが怖くなったり、
主人公の家族の喪失感は、
たくさんの「家族の肖像」画のコレクション
からは元より、
ドミニク・サンダの母と
クラウディア・カルディナーレの妻への
追想シーンの演出からも垣間見れそうだ。
そして、結果的には、
孤独からの解放を夢見ながらも、
主人公は激しい時代の変化にも
あがらえずに亡くなってしまう。
私も年を重ねる中で、
これまでの関係した方々とのお付き合いも
徐々に面倒に感じ、一人読書や映画鑑賞が
心地良く感じてきている一方、
確かにこの作品の主人公のように
他人との関わり合いの減少に
喪失感も身につまされる今日この頃
ではある。
貴族的な
気の毒なお話
「午前十時の映画祭」で鑑賞。
世間と距離をおき、孤独に暮らす美術愛好家の老教授が、彼の家に住みついた厚かましい、礼節を欠いた連中に翻弄されて……という、なんとも気の毒なお話。
世代や価値観の対比を通して、拒絶と受容のあいだを揺れ動く教授のこころの変化を描こうとしているのはわかったのですが、僕はこの作品の味わいがどうも好きになれませんでした。たしかに巨匠の作品ならではの重厚さのようなものは感じられたのだけど……。
ところで、今回も鑑賞中に、カサカサとビニール袋の音をたてる人や、なんかカバンを触っているのか、ずっと音をさせている人がいて、かなり集中力をそがれました。
こういう人は、どこの劇場でも見かけますが、人に迷惑をかけているということがわからないのでしょうか?
こういう、周囲への配慮を欠く人が最近増えているように思います。
僕なんかいつも地蔵のように静かに鑑賞しているのに。
家族とは・・・
午前十時の映画祭12にて。
ローマの豪邸にメイドはいるが、ひとりで暮らしている老教授がいた。その邸宅へブルモンティ夫人とその愛人、夫人の娘らが上の階を貸して欲しいとやってきた。最初は平穏な生活をじゃまされたと感じていた教授だったが、次第に彼らに興味を持ちはじめ、家族のように接していく、という話。
夫が妻の愛人を公認するのがよくわからなかったが、娘も母が愛人を持つ事を反対しないし、その母の愛人とセッスクする感覚もよくわからなかった。
当時の?今も?恋愛にオープンなのが良いのか悪いのかわからないが、結婚って家柄だったのかな?
教授は本と絵画に囲まれて変化のない生活をしていたのが、びっくりするような出来事の連発で、挙句に夫人の娘から誘惑されたり、夫人の愛人と芸術について語り合ったり、刺激的な出来事を体験するのが良かったのかな?
いつまでたっても新たな刺激が必要なんだろうと思うし、困った人を助けるのが家族?なのかなとも思った。
余韻が残る作品だった。
夫人の娘役のクラウディア・マルサーニが、トップレス含め美しかった
重厚な演劇を観ているみたいだ。
ビィスコンティーは、フェリーニと並んで私が一番好きな映画監督である。この作品を公開時に鑑賞しているから、40年以上経過している。
私も老人と言われる年齢となったが、印象は40年前と余りに変わっていない。変わったと思うところは、家族の肖像の絵画は、皆よそ行きの顔をしていることだ。写真などない時代だから、絵画として残すしかなかった。当然、表向きの顔で、現実はこの映画のように、ドロドロの生活を送っていたはずだ。もちろん、教授も解っていたはずだか、それでも家族を求めざるを得ない人間の業を描いた作品だ。
中日新聞夕刊のコラムで知ったが、モデルはイタリアの文学者と知って驚いた。勿論、ビィスコンティ自身も投影されていると思うが。澁澤龍彦にも影響を与えているそうだ。
ドミニク・サンダやカルディナァレが出てくる。もうちょっと若いCCだと良かった。
ふくよかな熟成されたお酒に例えるべきか
ランカスター氏に魅了されているからなのか。
「つまらない」と一蹴すればいいのに、何故か気になる映画。鑑賞するたびに感想が変わる。
初めて見たときは、伯爵夫人一行の振る舞いに腹を立てて、気分は最悪だった。
書物が積み上げられている部屋に、煙草の投げ捨てをする?
人の家に不法侵入して裸になってあんなことする?ベルベットや刺繍をこらした布製の家具を総取り換えしたくなった。
全く、以前の面影のない貸部屋。趣味はいいけれど。
そんなひどいことをしても、悪びれた感じすらない。
教授が言う「言語が違う」。同じ言語を話していても通じない…。
持つ者と持たざる者との対比。
資産。教養。品格。他者への配慮。自分が根ざすべき足場。未来。世間に対する顔。こそこそしなければならない事情。心の繋がり。秘める想い。
伯爵家とその取り巻き。お金で爵位を手に入れた系の?それでいて、生まれながらの特権階級特有の、人を人として扱えない傲慢さをまき散らす。
『山猫』の人々とのあまりにもの違いに唖然となった。
教授も、その世界をどんどん浸食されて。でも…。
それを情けないと見るか、教授の孤独をそこに見るか。
教授の愛おしんでいる世界を、「趣味がいい」と理解してくれる者。利益のためだとか、見栄の為ではなく、その価値を分かち合える者。蜜月のような時間を共有できそうなのに、すぐに手からすり抜けてしまう…。何度も何度も。そして…。
でも、単なる老境の孤独の話?
コンラッドの立ち位置ー登場人物の中で、唯一コンラッドだけが根無し草。それ故のコンプレックス。足掻き。
伯爵夫人とその娘。工場主の次男ーただ与えられたものを享受するだけの存在。多くの物を手にしているようで、その権利をはく奪されたら…。
教授と呼ばれるインテリー遺産として手にした物を基盤として、自分で生み出したもので手に入れたものに囲まれて…。だが、失ったものも…。半ば墓場のような住居に住まうもの。
(明治の頃は「末は博士か大臣か」と言われるように、現代よりも大学自体が少ない希少職業だったから社会的地位は今よりずっと上?)
コンラッドが身を投じた活動とはどういうものなのか?
イタリア史には疎いから、日本で考えると、あさま山荘事件が起きたのが、この映画が公開される前の1972年。いわゆる、日本で勃発していた大学紛争みたいなものか?映画の中でもストライキの話が出ていたし。
映画の中でコンラッドは左翼とも言っていた。ブルジョアジーへの糾弾。
それなのに、ブルジョアから離れられないコンラッド。自分はペット扱いしかされないと言いながら。対等な関係になりたかったのは解るけれど、どんな対等?蛭のようにくっついて自分もブルジョアの仲間入り?
消費するだけで、愛すらも生み出さない。
そして隠し部屋。教授も、母のようにレジスタンスを庇護したつもり?
その時々を共有するだけで、そのことが終われば違う道をいく関係?ステイタスの共有?趣味の共有?
与えるものと与えられるもの。庇護するものと庇護されるもの。”対等”とは何なのか。
何をなし、何を残し、どのような時間を重ねていくのか?
人生の四季。
春の嵐の如く、奔放に若さを謳歌する三人。
夏の嵐の如くな激情を振りまく婦人。
実りの秋の如くな知識と趣味・調度類に囲まれて、豊かな時間を過ごすはずだった教授。
そして、冬が…。
そして、映画のキーワード『家族』。
家族の肖像画で埋め尽くされた家。家族もどき。たんなる”家族ごっこ”ではなく、監督ならではの想いが込められていそうな…。
監督の”遺作”と聞く。己の半生に寄せたとも。
意図して描かれたものだけでなく、意図しないものまでがにじみ出てきて…。
ネタバレになりそうなことを書き連ねても、この映画のことを理解したとは思えない。
一見理解しやすそうで、難解。
見直すたびに味わいが変わる。ふくよかな熟成されたお酒にたとえるべきか。
≪蛇足≫
『蜘蛛女のキス』のDVDについていた解説で、
原作者がだったと思うが、モリーナの役に、ランカスター氏を希望していたと言っていたと記憶する。でも、断られて、ハート氏が演じることになったので、原作者がハート氏ではイメージが違うと怒ったとか。
ハート氏はカンヌやアカデミー賞で主演男優賞を受賞されるほどの名演なのだが、
『山猫』のランカスター氏ではモリーナのイメージではないが、この『家族の肖像』のランカスター氏を見ると、ランカスター氏のモリーナも観たくなる。
ハート氏とはまた違うゾクゾク来るような怪演が見られただろうな。
1968年後のヨーロッパ
ビスコンティ!長尺、そして勉強モードに自分がなってしまいそうで離れていましたが、こんなに面白い映画とは!
一人、静寂の中、幸福で平和で美しい家族の肖像画に囲まれていた教授の前に、突如として何の文脈もなく現れた「家族」。めんどくさい、煩わしい、うるさい、どっかに消えて欲しい存在。よりによって68年以前と以後がごちゃ混ぜで、煩わしさと騒々しさと迷惑の塊の「家族」。それとの遭遇で、俄然、教授は心の中に何かが蘇り、馬鹿馬鹿しいと思い呆れながら芝居じみたことをしながら、この、めんどくさくて訳の分からない「家族」を結果的に、もしかしたら、生きる力を得て好奇心が芽生えて、無意識の内に喜びと共に受け入れる。それから教授は、自分の母を、妻を思い出すようになる。
68年、コンラッドの世代と教授の世代は激しく対立していたはずだ。でもコンラッドを一番理解し愛したのは教授で、教授の職業の転換の意味と孤独を一番理解したのはコンラッドだと思う。
教授の重厚な書斎であり客間、壁を埋め尽くす肖像画と書籍、家具、しずしずと運ばれる銀食器。台所ではワインはコップで、ディナーではトスカーナのワインを美しいグラスで。ベッドリネンは白。複数の使用人を使ってあんな風に暮らせる場面を作り出せるのはビスコンティならではと、一人、心の中で盛り上がり感動しました。
英語だけだったのが残念で、イタリア語メインで、たまにドイツ語が混じったら良かったのにと、思った。
そして、役者の素晴らしさ!まず、シルバーノ・マンガーノに痺れました。彼女がバート・ランカスターに猫のように引っかきまくって言い立てる場面は美しく最高だった。役者は台詞!!と外見!!
そしてHelmut、こんにちは、お久しぶりです。美しい。あなたが最後に言った言葉は、最近見た映画、Martin Edenを思い出させてくれました。
対立に拘り敗者に心砕いたヴィスコンティ監督の遺言の様な演劇映画の傑作
2年前の「ルードヴィッヒ」の撮影中に心臓病で倒れ、死の宣告を受けたルキノ・ヴィスコンティ監督は、車椅子に着座したままの演出でこの作品を完成させた。ヴィスコンティ監督の体調を考慮したことで、セット中心の室内撮影が全編に渡り、映画的な広がりは無いが、演劇の密度の濃いドラマが展開する映画になっている。いつ撮影が中止になるかも知れない状況下での緊張感が、作品の完成度を高めているのではないだろうか。死を意識した老巨匠の人生行路を反映した内容からは、最後の告白であり白鳥の歌と捉えていい。ヴィスコンティ監督と同世代の知識人の主人公が、ヨーロッパの旧文化の終焉を惜しみ、新しいヨーロッパ文化を身に纏った変形家族の一員に余生の生活を狂わされる。主人公の教授を「山猫」のバート・ランカスターが演じ、彼を時折父親のように接する青年コンラッドにヘルムート・バーガーが扮するキャスティングが、まさに監督自身を投影したものである。ただ、バート・ランカスターの貫禄と深みのある演技と比較して、バーガーの演技が最良とは言い難い。これが「山猫」の時の若いアラン・ドロンならば、更に完璧であっただろう。
舞台はローマ市内の古く堅牢な教授の屋敷。孤独を愛する独り身の教授と管理人と家政婦だけの時代から取り残された静かな空間。書斎を飾るのは、18世紀のイギリスで流行した(カンバセーション ピース)の絵画たち。上流家庭の家族団欒の様子が記念写真風に描かれたものだが、他人と接するのを嫌う教授がそのような絵画の蒐集家という矛盾がまず生まれる。そこへ、上階を借りたいと現れるのが、実業家夫人ビアンカ・ブルモンティ。それも年下の愛人コンラッドの為の部屋という。娘リエッタと婚約者ステファノの試験的な同居も臆することなく喋りまくる。凡そ交友関係を結ぶことはない教授と富豪一族の物語の端緒が、パリから来た画商が薦める一枚の(カンバセーション ピース)になる。頑固な教授も、欲しい絵を家賃の前払いとして交渉するリエッタらの要求に結局折れる。この導入部の人物紹介と展開予想できない設定の興味深さは秀逸である。登場して存在感が圧倒的なビアンカのシルバーナ・マンガーノが素晴らしい。「ベニスに死す」の殆ど喋らない貴婦人とは正反対の、欲望を晒しても美しい自由気ままな上流階級の婦人を完璧に演じている。ランカスターとマンガーノ二人のやり取りを観ていると、上質な演劇を鑑賞しているようだ。
教授とコンラッドが芸術に関して会話する場面に、二人の決して理解し合えない微妙な関係が表現されいる。モーツァルトのアリアに聴き入るコンラッドを見詰める教授に対して、その青年はレコードが鳴り続ける間何度も電話を掛ける。それでも目にとめた一枚の絵画の作者アーサー・デーヴィスを語り、類似した作品の東屋の位置が違う絵を写真で知らせてくれる。これが、昼食を共にする場面に続き、ディナーの約束に繋がる。(ここで映画とは直接関係ないが、モーツァルトのオペラの話の中で、教授はカール・ベームとレナード・バーンスタインのレコードの話に及ぶ。当時の一番高名な指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンの名を敢えて使わなかったのは、やはりヴィスコンティ監督の好みなのだろうかと詮索してしまった。)しかし、ブルモンティ一族はディーナーの約束を反故にして一ヵ月もの間ヨット旅行をする。礼儀も知性も無い彼らによって、教授が心身共に疲弊していくのだが、無意識に家族の団欒を乞う自分の半生を回顧するフラッシュバックで、母ドミニク・サンダと妻クラウディア・カルデナーレが登場する。ここにもヴィスコンティ監督らしい女優の好みが表れている。
爆弾襲撃に合い血みどろになったコンラッドを囲うように秘密の部屋で世話をする場面は、ヴィスコンティ監督自身が若い時に”赤い公爵”と言われる政治活動をしていた過去を窺わせる。作中でもコンラッドをドイツの左翼学生の生き残りと説明するが、それ以上の深入りはしない。最後の晩餐の如く教授とブルモンティ一族が食事する場面の、コンラッドとステファノが対立し喧嘩になる演出の緊迫感が素晴らしい。テネシー・ウイリアムズの舞台やオペラの演出を数多く手掛けてきたヴィスコンティ監督の本領が、クライマックスとして見応え充分だ。二人の間に入り仲裁する教授だが、若い世代との断絶が明確になる。ここに、死を覚悟したヴィスコンティ監督の自伝的舞台劇に込めた対立と敗者の概念が浮かび上がる。それは政治的な思想の対立、男女の対立、世代の対立、芸術の対立であり、どちらかが敗者となる側への作家ヴィスコンティの熱い眼差しである。
イタリアデザインの洗練さと高級感溢れる家具や部屋作りの新旧の対比も視覚に訴える美術の素晴らしさ。フランコ・マンニーニの重厚で哀切な音楽の調べ。美を愛するヴィスコンティ監督が寵愛した俳優たちの演技のハーモニー。そして巨匠の渾身の演出力。音楽、美術、演技、演出すべてが溶け合う贅沢な演劇映画として本物の傑作だった。
1978年 11月27日 岩波ホール
この頃から鑑賞の参考にしていた映画批評家の中で、個人的に別格として尊敬していた人が、飯島正氏と淀川長治氏であった。勿論どちらも雲の上の批評家ではあったが、自分が良いと思った作品を調べるとお二人が高評価していたものと重なり、勝手に親近感を抱いていた。全てが当て嵌まるわけではないが、その価値観は今も変わらない。この作品は、その年のベストワンにお二人とも選出したことで珍しいことだった。特にヴィスコンティ監督の「夏の嵐」を高く評価していた飯島正氏が久し振りにヴィスコンティ作品を大絶賛していたのが印象に残っている。
バッドエンド野いちご(ベルイマン)?
沈黙は非なり
伯爵夫人ラブ🖤
苦手でした。。。
仲良くなくとも一緒に!
全23件中、1~20件目を表示