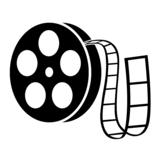あなたを抱きしめる日までのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
ラスト10分
全てが判明し、フィロミナお婆さん(以下、婆さん)がシスターに語る。
『私はあなたを赦します。
赦しには大きな苦しみが伴います。
私は人を憎みたくない。』
なぜ赦す!!
あんなに会いたがっていた息子に会わせなかったのに。
大きな苦しみを伴う赦しがなぜできる。
人を憎みたくないことが、シスターを赦すことか?
シスターの気持ちを楽にさせるだけでは。
婆さんの言葉が私の心をざわつかせる。
ラスト3分
息子の墓前でマーティンへの一言、私の気持ちは収まった。
『記事にしていいわ
人々に知ってほしい』
婆さんもどこか釈然としなかったのだ。
世に事実を知らしめることで、心のわだかまりに区切りをつけたのだろう。
派手さはない
結果(息子発見)が出るのは割と早かった気がした。
間違いであって欲しい、人違いだった!という展開を期待してしまったが、実話なので仕方ない。
マーティンが最後まで修道院に怒っていたのに対して、ひどい仕打ちをしたシスターに赦しを与えるフィル。
赦しを乞われているわけではないけどね。笑
でも私もマーティンに激しく同意。
せめて謝ったら?
火事に見舞われ何も残ってないと言いながら、ちゃんと契約書は出してくるというシスター達の周到さ!
ひどいわ〜。
そこは厳しく追及して欲しかったな。
子供と引き離されるシーンは辛い。
フィルは息子がゲイだったというのを受け入れるのは早い。笑
昔の映像を織り交ぜながらテンポよく進むのでストレスはなかった。
今もお互いを探してる親子がいるとのこと。
少しでも再会出来たらいいな。
アイルランドの景色もよかった。
仰天実話
アイルランドの修道院で暮らす10代前半でワンナイトラブが原因で出産した老婆。
実は修道院がアメリカに人身売買で子供を売っていたという実話。
仰天実話だけれど、胸の悪くなるドキュメンタリー風ではなく、映画のように(映画だけど)仕上げられていてる。
昔ももちろん犯罪だっただろうが、なんとなしに昔はこういうことがかげでまかり通ってたんだろうと想像がつく。
今は良い時代になったものだとつくづく思う。
母はなぜ?
修道院って映画作品に出てくるの、
ロクなのがない、
『ベネデッタ』しかり『尼僧物語』しかり。
イギリスで。
本作なんか、人身売買❗️
望まずして妊娠した為、家族からか、
強制的に修道院にやられ、
出産後、4年間のタダ働き。
出産前後の世話賃と4年分の若い労働賃金を
比べてみた。
おのずと明らか。
さらには、子供を取られてどこかへ
やられてしまった。
50年後にその息子を探す母。
TVキャスター後、記者になった
マーティン•シックススミスに出会い、
番組に出演する条件で、
息子探し、所在地への随行等
全部お世話してくれる。
アメリカで見つかった。
超優秀な人物に成長していた。
誇りに思うが、
既に亡くなっていた。
なぜもっと早くに探さなかったのだろう?
と思ったに違いない。
意を決して息子のパートナーに会いに行く。
驚いたことに、お墓はあの修道院にあると。
さらには、修道院のエゲツなさが露見する。
母はなぜ、もっと早くに探さなかったのか⁉️
【”赦しの心。”若い時に生まれた息子を、修道女の女性が年老いてからインテリジャーナリストの助力を得ながら探す作品。後半の展開は可なり心に沁みる作品である。女性ってヤッパリ偉大だな、と思うのである。】
■主婦・フィロミナ(ジュディ・デンチ)は、50年前に未婚のまま出産して養子に出された息子・アンソニーに会いたいとの思いを募らせつつ、カトリックの修道院で働いていた。
それを聞いた娘のジェーンは元ジャーナリスト・マーティン(スティーヴ・クーガン)に話を持ちかけ、フィロミナとマーティンによるアンソニー探しの旅が始まる。
ー 個人的に、イギリスBBCが製作する映画は好きである。理由は品性が高い事に尽きる。映画ではないが、ベネディクト・カンバーバッチ主演の「シャーロック」シリーズは名作だと思っている。-
◆感想<Cautin!内容に触れています>
・若き時に恋に落ち、息子アンソニーを生みつつも当時、禁忌であったがために、修道院に入れられたフィロミナ。
ー 彼女が、週に一度だけ幼き息子と会うシーンは可なり沁みる。だが、息子はある日、米国の富裕なるヘス夫妻に養子として引き取られるのである。-
■時は過ぎ、息子に会うためにフィロミナは行動を起こすのである。同行するのは、政争の末報道官の地位を追われたシックス・スミス・マーティンである。彼が最初はスクープを得るためにフィロミナと米国に行くのだが、彼がフィロミナの長年の息子への想いを知るにつれ、彼女に寄り添う姿が心に沁みるのである。
・フィロミナと、シックス・スミス・マーティンが米国に渡って知ったアンソニーの生涯。それは、レーガン政権とブッシュ政権で筆頭法律顧問を務めていた事。
そして、彼がゲイでありパートナーであるピートと付き合っていた事。
【彼の背広の襟にはいつも”ケルティック・ハーブ”の装飾品が付けられていた事。】
ー もう、このシーンで涙腺が崩壊しそうになるが、我慢して鑑賞続行する。-
■フィロミナは息子とは会うことが出来ない。それは、彼がHIVにより1995年に歿していたから・・。だが、彼女はシックス・スミス・マーティンが訪れたピートの家に行った際に断られつつも、彼の代わりに毅然とした表情で、再びピートの家を訪れる姿。
そして、亡き息子が米国ではなく、彼が生まれた英国の修道院がある地にが、亡骸を埋める選択をしたことをフィロミナが知るシーン。
ー 涙腺が崩壊する。フィロミナの息子アンソニーは、彼女を忘れずに自らが生まれた地に、自身の骨を埋める選択したのである。-
<今作は、母が息子を想う気持ちと、息子が母を想う気持ちが見事に表現された秀作である。
私は男であるが、今作の様な作品を鑑賞すると、女性ってヤッパリ偉大だな、と思うのである。>
赦し
意に反し幼い息子アンソニーと生き別れとなってしまう女性フィロミナをジュディ・デンチが好演。顔に刻まれた皺が歳月の長さを感じさせる。華やかな人生を送る息子マイケル・ヘス( 幼少期名:アンソニー )のビデオ映像を見つめるフィロミナの心の内は…。
終始誠実な対応をする元BBC支局員、ジャーナリストのマーティンをスティーヴ・クーガンが知的な魅力で演じる。
ー聖心修道会
ーレーガン&ブッシュ政権の主席法律顧問
ーケルティック・ハープ
NHK-BSを録画にて鑑賞 (字幕)
人としての強さ
「私は純潔を守った、そんな私の行いを裁けるのは神だけ」という車椅子に乗った高齢のシスター。高慢というより、箱庭の中で自己肯定を繰り返すだけの孤独で哀れな老人。
私もマーティンと同様に、自分の行いを棚に上げて人の過去をなじる不寛容な姿勢に強い憤りを感じた。
しかし、フィロミナは、そんな相手に許しを与えるという。教会に盲従し自らを貶めていた頃とは正反対の姿。
そこに、私もこうありたいと思わせる、人としての強さを感じた。
人身売買を許すって…
確かに主人公の真の信仰心と「赦すことは大きな苦しみを伴う」はクライマックスに相応しい精神性の高さを感じました。
しかし、客観的にみて当事者達の複数の人身売買について許しちゃって話が終わった事に驚きを隠せません。
フィロミナさんこそ奇跡。人としての器。
「赦しには苦しみが伴うのよ」それでもあなたは「赦す」という。どれだけの思いで発せられた言葉なのだろうか。
この、人としての器の大きさを示す言葉を、絞り出すように口にしたのは、
宗教者でもなく、
国一番の大学を出て政治の中枢に関わっていた、知的なエリートでもなく、
車に乗ればお菓子を差出し、ビジネスクラスや高級ホテルのサービスに興奮し、今直面している悩みのためとはいえブランデー1本を一人で空けてしまい、とんでもない言葉を口にし、リンカーン記念館よりTVドラマに興味を示し、ロマンスが大好きな、下世話で俗物っぽく描かれる田舎のおばさん。
正直、品性が劣ると見下しがちなおばさんが、シスターよりも、かってファーストクラスに乗っていた記者よりも、実は人としては格段に人格者というラストの衝撃。
勝ち組・負け組という言葉は嫌いだとか言いつつも、どこかで人を値踏みしていた自分に気づかされて、冷や水を浴びせられたような気分になった。
他にも「上り坂の時に会う人は、下り坂の時にも会うから、いつでも感謝を忘れないことよ(思い出し引用)」とか、はっとさせられた。
趣向もそれまでの生き方も合わない二人の珍道中で、重くなりそうな話を重苦しくさせないための脚本と思っていたエピソードの数々。それが最後に大逆転として意味を持つ。
勿論、息子の生きざまによっては赦しどころの話ではないだろう。
そして、どんなふうに成長しようが、成長を見守り育てたかったという時間のロスは埋めようもない。
簡単に”赦す”という言葉ですむ話ではない。苦しい。苦しさに押し潰されそうになる。心がどす黒く染まっていく。そこに一条の光=”赦し”。その葛藤の繰り返しなのではないか。苦しさを手放す手段としての”赦し”。尤も、これが一番難しいのだけれど。
フィロミナさんは敬虔なカソリック信者だが、ある場面で教会に告解に行くものの、教会を出る時、聖水をまかなかった時がある。信仰を捨てたのか?
そして、”赦し”。
既存の”神””宗教”という枠組みを超えた”赦し”? 教義とかそんなものに縛られない、もっと高次元の、普遍的な”赦し”。
だから、カソリックを糾弾するのでもなく、一つの事実として、息子の生きた証として、本にまとめて欲しかったのかな。
この時代の教会での人身売買を簡単には非難できない。
『この道は母へと続く』でも、孤児の人身売買は描かれていて、もっとシビアな現実まで盛り込まれていた。
未婚の母。カソリックの根強い地域では、相当な苦労を強いられて、母も、子も、まともに生活できないと聞いている。売春婦や乞食等になって生きていく以外なかったと聞いている。
そして、子を育てるにはお金がかかる。昔の孤児院のイメージとしては『赤毛のアン』の栄養状態も悪くガリガリの体。今も昔も寄付や税金をつぎ込む以外に道がない。今の日本はタイガーマスクが時折現れるし、税金もあるけれど、昔は?
親と子。両方への情報提供も難しい。中には、実の親子とはいえ、恐喝ネタになる場合もあるし、それぞれの家族のこともあるし。
事態は複雑で一概に”こう”すればいいというものではない。
という事情を考えたとしても、
希望しない親の子を養子に出すなんて。
亡くなった方のお墓もちゃんとされていないなんて。
お互いが求めあっているのに、ひきあわせないなんて。
それが、快楽を求めた罰だなんて。
それが、宗教の教義だなんて。
否、聞くところによるとイエス・キリストは売春婦を弟子にしたとか。
となると、神の前に、自分だけ良い子でいればいいと言う、自分だけが正しいと言う、他を顧みない傲慢な態度が一番問題なんだろう。
だけれども、フィロミナさんは赦した。心の中に息子を抱きしめて。
まるで、観音様のようだ。
演じるデンチさんが素晴らしい。
ク―ガン氏は、『80デイズ』でも絶妙な演技をしていらしたが、ここでも良い味出している。
このお二人の抑えた、けれど、十分に伝わってくるおかしみ、悲しみ、怒り、絶望と救いがあればこその映画だと思う。
フィロミナさんは、ご自身の中でご自身なりの着地点を見つけられたようですが、他の引き裂かれた母子にも幸せが訪れますようにお祈りします。
素晴らしい
ジュディディンチは最高の女優。
眺めの良い部屋も007シリーズもショコラでも他の作品全てがキマッてて大好き!
もちろん今作も凄く素晴らしかったです。
気の強い、優しさを持つ母親役。
騒ぐつもりはないの。
私はあなたのことを赦します。
赦しには大きな苦しみが伴うのよ。
私は人を憎みたくない。
怒りは疲れる。ひどい顔になる。
毎日赦していこう。
言うのは簡単だけど、至難の技ですね。
本当に素晴らしい作品でした。
信仰の意味を知っている女性が、ただ「赦す」映画。
1952年のアイルランド。フィロミナ(ソフィー・ケネディ・クラーク)は、18歳で妊娠したことから強引に修道院に入れられ、過酷な労働を強いられたあげく、生まれた息子と引き離されてしまう。
50年後。イギリスで娘と暮らすフィロミナ(ジュディ・デンチ)は、息子を探す決心をする。元ジャーナリストのマーティン(スティーブ・クーガン)に協力を依頼して、一緒にアメリカに向かったフィロミナだったが……。
当時のアイルランドはカトリックの規律が厳しく、未婚女性のセックスや妊娠は御法度とされていました。そうした少女たちは、マグダレンという修道院に強制的に入れられ、過酷な労働を強いられたようです。
※当時の修道院の生活を描いた、「マクダレンの祈り」という作品があります。
本作はその実話を元にした、映画化となります。
フィロミナはそこで出産するのですが、子供は勝手に養子に出されてしまいます。これはどうやら、人身売買のようです。修道院には「ジェーン・ラッセル」のポスターが貼ってあるのですが、彼女はこの修道院から子供を買っていた一人のようですね。
さて、フィロミナはマーティンと共に、息子アンソニーの足取りを追ってアメリカへ渡ります。予告編でも流れているのでネタバレしても良いと思うのですが、アンソニーはレーガン政権の法律顧問をしていました。
フィロミナは「私と暮らしていたらここまでの仕事はできなかった」と、起こった悲劇を自分なりに納得します。
長らくこの修道院は、神の名の元に人権侵害を行ってきました。
でもネット上に散見される、だからカトリックは、だから宗教は……、なんて議論はちょっと違うと思うんです。
あの、なんで人は、宗教ばっかり語るんですしょうね。
重要なのは「どう信じるか(信仰)」だと思うんです。清く、正しく、美しく、毎日ハッピーに、自分にとって何かしらプラスの方向に働くなら、道端の石だって信じていいんです。
問題は何を信じるかではなく、どう信じるかでしょう?
神の名の元に他者を傷つける人達は、宗教を間違えたのではなく、信仰の仕方を間違えているのだと思います。カトリックだから、とか関係ありません。
フィロミナは辛い経験をしながら、ユーモアを忘れません。この重々しいストーリーの中で、フィロミナの陽気さ、愛らしさが救いです。その強さは、信仰のお陰なのかもしれません。
実はフィロミナの息子は、母を探して修道院を訪れていました。けど、それはフィロミナには教えられませんでした。修道女達は「快楽に溺れたフィロミナの罪」を赦してないからです。自分達は禁欲しているのに、10代の女の子が!という嫉妬です。
快楽は罪、笑った顔は猿に似ているから笑いは罪(薔薇の名前)でしょうか。
しかし、フィロミナは、その酷い仕打ちを「赦す」と言います。キリスト教は「赦しの宗教」と言われたりしますね。しかし何でも「許す」のではなく、罪を「赦す」のです。
神の名の元に自分の子供を売られたフィロミナは、神の名の元にその罪を赦す。信仰の強さを、信仰の本当の意味を、私はここで初めて知ったように思いました。
本作は子供も見つからず、修道院のおぞましい実態も暴かれず、何も変わりません。何も解決しません。
信仰の意味を知っている女性が、ただ「赦す」映画です。
赦しには大きな苦しみが伴うのよ
映画「あなたを抱きしめる日まで」
(スティーブン・フリアーズ監督)から。
「驚きのある結末は面白い」「最高の結末だわ。100万年に一度よ」
などの台詞が繰り返されて使われていたので
ラストに向かう展開に期待し過ぎたのか、意外とあっけない結末、
邦題とストーリーがかけ離れていて、ちょっと戸惑った、
そんな気がして、メモ帳を閉じた。
実話だということも含め、この物語が伝えたかったのは、
50年前、イギリスの修道院で引き離された息子が、
アメリカで立派に活躍していたという「驚きの結末」ではなく、
人身売買していた修道院などの関係者に対して、
主人公の女性・フィロメナが、その悪意・行為を含めて
「赦す」としたことであったと思う。
「赦しには大きな苦しみが伴うのよ。私は人を憎みたくない」と
言い切り、憤慨するジャーナリストに対して
「あなたと違うの」と鼻で笑うシーンは、圧巻だった。
「ひどい顔よ」「怒っているんだ」「さぞ疲れるでしょうね」
という会話が物語るように、今更、過去について怒っても、
何も解決しないことを理解したうえで呟いた、
「赦しには大きな苦しみが伴うのよ」が、心に残った。
その判断や考え方こそ「最高の結末」であり、
赦されたことで、皆の心が動いた瞬間であろう。
邦題は微妙。
頭が固いほど道徳的。敬虔なクリスチャンはこういう感じなのだろうか。フィロミナのキャラクターが「お年寄り」をすごく象徴的に表現していました。
重いはずのストーリーですが、この可愛らしいおばあさんと記者のやり取りが微笑ましい。予想していたよりもさり気ないラストだったのですが、実話なのですね。
ジュディリンチが愛くるしい
本当にあった話と言う事でとても許せる話ではなかったけど、眉間に皺を寄せてイライラせずに観れたのはジュディリンチの愛くるしさのおかげだったように思う。何度も抱きしめてあげたいと思った。しかし、死が迫ってるにも関わらず母親を探しに来た息子に対する修道女の行動は腹立たしかった。結局宗教は人間性までは救ってくれないのだな…
実話なのは驚いた
フィロミナの娘がマーティンと会っていなかったら、息子を見つけることはできなかったかもしれないね。マーティンとフィロミナの会話が面白くて、終始笑っていた。息子のビデオを観ていたら意外な真実を知ることになるんやけど、マーティンは怒るけどフィロミナは許すんよな。母親の息子に対する純粋な愛にはぐっとくるものがあった。
100万に一つの…
50年の時を経て生き別れた息子を捜すアイルランド人女性の姿を描き、アカデミー作品賞にもノミネートされた感動作。
良作だった!
ドラマチックな題材なのは当然、実話の映画化。事実は小説より劇的。
ベタな邦題から温かな作風を想像するが、ユーモアと批判精神のスパイスが効いている。
息子を捜す母フィロミナと、協力する記者マーティン。
片や、小さな事にも素直に感動し感謝する、子供のような性格。
片や、職業柄か、何事も斜めから見る皮肉屋。
性格も考え方も正反対の二人のやり取りが面白い。
息子の消息を追ってアメリカにやって来たフィロミナのカルチャーギャップも充分なユーモア要素。
その昔、修道院で出産したフィロミナ。
カトリックにとって、未婚の母は罪(らしい)。
愛する我が子は養子に出され、無理矢理引き離されてしまう。
これは、以前見たある映画でも取り上げていた、この当時のイギリスの社会問題の一つでもある、児童移民。
修道院が養子斡旋していたという、衝撃の事実。
修道院=清らかな善のイメージの裏側の闇を暴く。
物語の中盤で、息子の消息は意外な形を迎える。
そこで終わらず、息子の形跡を追う。
(↑ちょっとネタバレか?)
辿り着いた先が、再び修道院。
ここで、さらに隠されてきた真実が語られ、マーティンは激昂する。
それが罪の償いだと主張する修道院側。
その時、フィロミナは…。
宗教に馴染み無い日本人にとって、この時のフィロミナの行動はなかなか理解し難いかもしれないが、フィロミナはカトリック信者。これが彼女なりのけじめ。
お茶目に、哀切滲ませ、清く正しく。ジュディ・デンチが何のケチもつけられないさすがの名演。
マーティン役のスティーヴ・クーガンはイギリスのコメディアン。本作では脚本も担当、マルチな才能を見せる。
スティーヴン・フリアーズは「クィーン」に続いての好演出。
フィロミナがまだ見ぬ息子を思いやる気持ちが、何処までも一途で温かい。母の愛は深い。
実は、息子も…。
親子の絆は固い。どんなに時が離れようとも。
普遍的ではある。が、それこそが、“100万に一つ”の奇跡なのだ。
聖なるもの
原題は「Philomena」Philo(愛)と me(私)意訳すれば「私を想っていた」
インテリで無神論者のマーティンと無教養で敬虔なフィロミナとのギャップでの笑いで映画は進み意外な最後へとたどり着く。
クライマックスのシスター・ヒルデガードの台詞も意訳すれば「真面目にやって来た私を貴方たちに批判される筋合いではない」であり、逆切れでもある。
そして対比として息子の本心を知るのを恐れていたフィロミナの終盤への教会からクライマックスそして終焉までの行動からみえるのは「真に必要なことは教条を守ることではなく試練を乗り越える」である。
試練を乗り越えたフィロミナは聖なるものを得た。だからこそ修道院の残忍な行為を赦すことができたのだ。
罰を与えるのは神か?教会か?
これこそ、正に事実は小説より奇なり!
もしかするとフィクションではこういうキャラクターもストーリーも生み出すことは出来なかったかもしれない。
カトリック教会(修道院)による人間性を否定する酷い行いというのはやはり事実が元になった『マグダレンの祈り』で目にしていたし、オーストラリアへ養子に出された子ども達の親探しについては『オレンジ太陽』で見ていたので、フィロミナの身の上に起きたことについては一応免疫があったのだが、とても意外だった、というか驚きだったのは、その後の展開だった。
この展開はフィクションでは思いつかなかった、もし思いついていたとしても、リアリティがないと批判の対象にさえなっていたのではないか?
日本人的感覚いえば、子供を自分の手で育てようという意思を持つフィロミナから息子を奪うこともあってはならないことだと思うが、将来を考えれば恵まれた環境で育てられたことは息子にとって幸せだったと言えないこともない。
しかし、大人になった息子と母親の再会を妨害するというのは、フィロミナに対する罰というにはいくらなんでもやり過ぎに思える。
フィロミナは息子を産んだこともその父親と恋に落ちたことにも後悔はないし、修道院に対する恨みみないように見える。
(マーティンや観ている私達にとっては、それが理解出来ない。)
しかし、彼女はセックスを楽しんだことは罪だというのだ。
たとえそれが罪だったとしても、罰を与えるのは教会や修道院、ましてシスター・ヒルデガード個人だろうか?
罰を与えられるとしても、それは神の仕事ではないのか?
シスターの行き過ぎた行為は、彼女の個人的な嫉妬、恋をしセックスを楽しみ、息子を授かったフィロミナに対する彼女の女としての嫉妬ではなかったか?
私にはそう思えて仕方なかった。
全23件中、1~20件目を表示