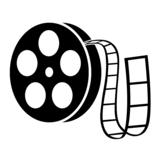あなたを抱きしめる日までのレビュー・感想・評価
全85件中、41~60件目を表示
信仰の意味を知っている女性が、ただ「赦す」映画。
1952年のアイルランド。フィロミナ(ソフィー・ケネディ・クラーク)は、18歳で妊娠したことから強引に修道院に入れられ、過酷な労働を強いられたあげく、生まれた息子と引き離されてしまう。
50年後。イギリスで娘と暮らすフィロミナ(ジュディ・デンチ)は、息子を探す決心をする。元ジャーナリストのマーティン(スティーブ・クーガン)に協力を依頼して、一緒にアメリカに向かったフィロミナだったが……。
当時のアイルランドはカトリックの規律が厳しく、未婚女性のセックスや妊娠は御法度とされていました。そうした少女たちは、マグダレンという修道院に強制的に入れられ、過酷な労働を強いられたようです。
※当時の修道院の生活を描いた、「マクダレンの祈り」という作品があります。
本作はその実話を元にした、映画化となります。
フィロミナはそこで出産するのですが、子供は勝手に養子に出されてしまいます。これはどうやら、人身売買のようです。修道院には「ジェーン・ラッセル」のポスターが貼ってあるのですが、彼女はこの修道院から子供を買っていた一人のようですね。
さて、フィロミナはマーティンと共に、息子アンソニーの足取りを追ってアメリカへ渡ります。予告編でも流れているのでネタバレしても良いと思うのですが、アンソニーはレーガン政権の法律顧問をしていました。
フィロミナは「私と暮らしていたらここまでの仕事はできなかった」と、起こった悲劇を自分なりに納得します。
長らくこの修道院は、神の名の元に人権侵害を行ってきました。
でもネット上に散見される、だからカトリックは、だから宗教は……、なんて議論はちょっと違うと思うんです。
あの、なんで人は、宗教ばっかり語るんですしょうね。
重要なのは「どう信じるか(信仰)」だと思うんです。清く、正しく、美しく、毎日ハッピーに、自分にとって何かしらプラスの方向に働くなら、道端の石だって信じていいんです。
問題は何を信じるかではなく、どう信じるかでしょう?
神の名の元に他者を傷つける人達は、宗教を間違えたのではなく、信仰の仕方を間違えているのだと思います。カトリックだから、とか関係ありません。
フィロミナは辛い経験をしながら、ユーモアを忘れません。この重々しいストーリーの中で、フィロミナの陽気さ、愛らしさが救いです。その強さは、信仰のお陰なのかもしれません。
実はフィロミナの息子は、母を探して修道院を訪れていました。けど、それはフィロミナには教えられませんでした。修道女達は「快楽に溺れたフィロミナの罪」を赦してないからです。自分達は禁欲しているのに、10代の女の子が!という嫉妬です。
快楽は罪、笑った顔は猿に似ているから笑いは罪(薔薇の名前)でしょうか。
しかし、フィロミナは、その酷い仕打ちを「赦す」と言います。キリスト教は「赦しの宗教」と言われたりしますね。しかし何でも「許す」のではなく、罪を「赦す」のです。
神の名の元に自分の子供を売られたフィロミナは、神の名の元にその罪を赦す。信仰の強さを、信仰の本当の意味を、私はここで初めて知ったように思いました。
本作は子供も見つからず、修道院のおぞましい実態も暴かれず、何も変わりません。何も解決しません。
信仰の意味を知っている女性が、ただ「赦す」映画です。
赦しには大きな苦しみが伴うのよ
映画「あなたを抱きしめる日まで」
(スティーブン・フリアーズ監督)から。
「驚きのある結末は面白い」「最高の結末だわ。100万年に一度よ」
などの台詞が繰り返されて使われていたので
ラストに向かう展開に期待し過ぎたのか、意外とあっけない結末、
邦題とストーリーがかけ離れていて、ちょっと戸惑った、
そんな気がして、メモ帳を閉じた。
実話だということも含め、この物語が伝えたかったのは、
50年前、イギリスの修道院で引き離された息子が、
アメリカで立派に活躍していたという「驚きの結末」ではなく、
人身売買していた修道院などの関係者に対して、
主人公の女性・フィロメナが、その悪意・行為を含めて
「赦す」としたことであったと思う。
「赦しには大きな苦しみが伴うのよ。私は人を憎みたくない」と
言い切り、憤慨するジャーナリストに対して
「あなたと違うの」と鼻で笑うシーンは、圧巻だった。
「ひどい顔よ」「怒っているんだ」「さぞ疲れるでしょうね」
という会話が物語るように、今更、過去について怒っても、
何も解決しないことを理解したうえで呟いた、
「赦しには大きな苦しみが伴うのよ」が、心に残った。
その判断や考え方こそ「最高の結末」であり、
赦されたことで、皆の心が動いた瞬間であろう。
程好く笑えて程好く泣ける感動作
これが実話と言うのですから驚きです。
修道院が50年前に行った行為も、終盤に明かされた修道院の真実も、本当なら全くもって赦されることではないでしょ・・・。
それだけでも衝撃的だったのに、それを目の当たりにした主人公フィロミナのとった行動は、ある意味もっと衝撃的でした。
事実は小説より奇なりとはまさしくこのことか。
まあ映画的には、とてもシリアスで深刻な話ながら、コメディにならない程度のユーモアが盛り込まれていて、ある種微笑ましい気持ちで楽しむことが出来ました。
フィロミナとマーティンのキャラクター設定が何とも絶妙だった印象です。
純真なお婆ちゃんと皮肉屋なジャーナリスト、この掛け合いが本当にユーモアに溢れていて可笑しいんですよね。
フィロミナに感化されて少しづつ成長していくマーティンの様子も見所の一つだったと言えましょうか。
ロマンティックお婆ちゃんっぷりが可愛かったジュディ・デンチは、さすがの演技でしたね。
しかし息子アンソニーの行方が思いのほか早く判明した時は、意外とあっさりだったなと思ってしまいましたが、クライマックスのあのシーンは、本当に衝撃、私には出来ないなぁ・・・この辺はある意味信仰の差もあるのでしょうか。
しかしよくよく考えれば修道院もフィロミナも同じ信仰を志す者、難しいものですね、信仰心って・・・。
赦す、ということ
感慨深いとやりきれない感がのこるな。
演じるとはこういうことなのかも…
まるでその人そのもののように思えてくる。ジュディ・デンチもスティーブン・ジョン・クーガンも。子役まで出演者すべてがその瞬間にそこへ行けば、そこにいるような気がする。
・・・なんちゃって~というような場面がない。映画の中の空気感が最初から最後まで変わらない。そして静かな音楽が寄り添うように流れる。人生は思い通りにいかないものだけれど、救いはあなたのすぐ隣にもあるのよというように。
長年の労働のあとに手にしただろう平穏な日々と家族を大切に思うどこにでもいるおばちゃん。大学などには行かなくても物事の本質をあるがままにとらえようとして生きてきた人の賢さを感じさせるセリフたち。ジュディ・デンチの寡黙な青い瞳に吸い込まれそうになった。
人にとって<許される>ことはさして重要な事じゃないのかも。表面上ではなく心から<許す>ということは意味深いけど。あのシスターはフィロメナに<許された>けれど、自分で自分が<許せる>のか。それとも自分の罪には思い及ぶこともなく生涯を終えるのか。
邦題は微妙。
頭が固いほど道徳的。敬虔なクリスチャンはこういう感じなのだろうか。フィロミナのキャラクターが「お年寄り」をすごく象徴的に表現していました。
重いはずのストーリーですが、この可愛らしいおばあさんと記者のやり取りが微笑ましい。予想していたよりもさり気ないラストだったのですが、実話なのですね。
意外な
ジュディリンチが愛くるしい
本当にあった話と言う事でとても許せる話ではなかったけど、眉間に皺を寄せてイライラせずに観れたのはジュディリンチの愛くるしさのおかげだったように思う。何度も抱きしめてあげたいと思った。しかし、死が迫ってるにも関わらず母親を探しに来た息子に対する修道女の行動は腹立たしかった。結局宗教は人間性までは救ってくれないのだな…
実話なのは驚いた
フィロミナの娘がマーティンと会っていなかったら、息子を見つけることはできなかったかもしれないね。マーティンとフィロミナの会話が面白くて、終始笑っていた。息子のビデオを観ていたら意外な真実を知ることになるんやけど、マーティンは怒るけどフィロミナは許すんよな。母親の息子に対する純粋な愛にはぐっとくるものがあった。
100万に一つの…
50年の時を経て生き別れた息子を捜すアイルランド人女性の姿を描き、アカデミー作品賞にもノミネートされた感動作。
良作だった!
ドラマチックな題材なのは当然、実話の映画化。事実は小説より劇的。
ベタな邦題から温かな作風を想像するが、ユーモアと批判精神のスパイスが効いている。
息子を捜す母フィロミナと、協力する記者マーティン。
片や、小さな事にも素直に感動し感謝する、子供のような性格。
片や、職業柄か、何事も斜めから見る皮肉屋。
性格も考え方も正反対の二人のやり取りが面白い。
息子の消息を追ってアメリカにやって来たフィロミナのカルチャーギャップも充分なユーモア要素。
その昔、修道院で出産したフィロミナ。
カトリックにとって、未婚の母は罪(らしい)。
愛する我が子は養子に出され、無理矢理引き離されてしまう。
これは、以前見たある映画でも取り上げていた、この当時のイギリスの社会問題の一つでもある、児童移民。
修道院が養子斡旋していたという、衝撃の事実。
修道院=清らかな善のイメージの裏側の闇を暴く。
物語の中盤で、息子の消息は意外な形を迎える。
そこで終わらず、息子の形跡を追う。
(↑ちょっとネタバレか?)
辿り着いた先が、再び修道院。
ここで、さらに隠されてきた真実が語られ、マーティンは激昂する。
それが罪の償いだと主張する修道院側。
その時、フィロミナは…。
宗教に馴染み無い日本人にとって、この時のフィロミナの行動はなかなか理解し難いかもしれないが、フィロミナはカトリック信者。これが彼女なりのけじめ。
お茶目に、哀切滲ませ、清く正しく。ジュディ・デンチが何のケチもつけられないさすがの名演。
マーティン役のスティーヴ・クーガンはイギリスのコメディアン。本作では脚本も担当、マルチな才能を見せる。
スティーヴン・フリアーズは「クィーン」に続いての好演出。
フィロミナがまだ見ぬ息子を思いやる気持ちが、何処までも一途で温かい。母の愛は深い。
実は、息子も…。
親子の絆は固い。どんなに時が離れようとも。
普遍的ではある。が、それこそが、“100万に一つ”の奇跡なのだ。
まるで“M”のスピンオフ映画
メロドラマ風のタイトルとは裏腹に非常に力強く、信念に満ち溢れた作品である。
未成年で妊娠したことから修道院に入れられ、生まれた息子を養子に出されたひとりの女性が50年の時を経て生き別れになった息子を探す旅に出る。母親の息子探しという目新しくはないプロットでありながら、テンポの良いストーリーとウィットに富んだ会話でグイグイと観客を引っ張っていく。
主人公フィロミナを演じるのがジュディ・デンチ。ひとつの手掛かりを基に記者のマーティンと共にBMWに乗って息子の行方を追っていく様子はまるで007の“M”のスピンオフ映画を見ているかのような気分になる。
旅を通じて徐々に明らかになる息子の行方とその素顔。時に喜び、時に感情が揺らぐフィロミナの姿は50年間会えなかったとしても母親としての愛情の深さを感じさせる。しかし、今作の特筆せねばならないところは息子探しの旅を通じてフィロミナ自身の過去の過ちと宗教的な信仰と向き合うことになる点である。
それぞれの信念が交差する結末。この物語が実話だというから最後の驚きは半端ではない。どの価値観も考え方も決して間違いとは言えないのだろうが、もし、自分がフィロミナの立場だったらと思うとあの決断はできないだろう。そんな彼女の勇気こそ“100万年に1度の結末”を生み出している。
主演のみで引っ張るのも、限度があると…
聖なるもの
原題は「Philomena」Philo(愛)と me(私)意訳すれば「私を想っていた」
インテリで無神論者のマーティンと無教養で敬虔なフィロミナとのギャップでの笑いで映画は進み意外な最後へとたどり着く。
クライマックスのシスター・ヒルデガードの台詞も意訳すれば「真面目にやって来た私を貴方たちに批判される筋合いではない」であり、逆切れでもある。
そして対比として息子の本心を知るのを恐れていたフィロミナの終盤への教会からクライマックスそして終焉までの行動からみえるのは「真に必要なことは教条を守ることではなく試練を乗り越える」である。
試練を乗り越えたフィロミナは聖なるものを得た。だからこそ修道院の残忍な行為を赦すことができたのだ。
全85件中、41~60件目を表示