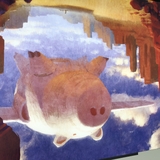インターステラーのレビュー・感想・評価
全986件中、301~320件目を表示
SF感動作/宇宙の壮大さを感じられる作品
IMAXの再上映で鑑賞。宇宙の映像美と音楽、振動に圧倒された3時間でした。真空の宇宙が無音でも、その場の緊張感や迫力が伝わってくる演出でした。
SF映画の『メッセージ』が好きな人は楽しめると思います。時間を超越する宇宙の壮大さと途方もなさに圧倒されて、鑑賞後に寂しくなる感じが似てました。
最初の惑星に仲間を助けに行くとき、マーフィーは時間を費やすリスクを指摘して反対したけれど、仲間の信号を無視できないアメリアの情に流された。結果的にはその判断は間違っていた。
次に行く惑星を選ぶ時、マーフィーは恋人がいる星に行きたがるアメリアを制して、計画に多大な貢献をしたというマン博士の星を選択した。合理的な判断をしたはずなのに、今度はそれがまた間違っていた。
情で選択しても、合理的な判断をしても、いずれにしても結局人間は間違えてしまうものなのだと、正しい選択を出来るかなんて運のようなものなのだと二つを比較して思いました。
あと、全体通してマシュー・マコノヒーが格好良過ぎました。娘を愛する父としても、最後のアメリアの元に駆けつけるために宇宙船に乗り込む横顔も、本当にセクシーでした。娘や息子を思って泣くその表情や嗚咽がとても切なかったです。
再上映は別格
宇宙に行って娘と会話する話
本格SFかと思いきや、愛こそ全ての映画だった。
難しい宇宙理論が展開されるが、
「つまりAプランとBプランがある」
「2つの惑星のどちらかにしか行けない」など、ストーリーの分岐点が分かりやすい。
あの出来事はここに繋がるのか〜と。
やってる内容は分からないけど、意思疎通しようとしてるのは分かるぞ!
話が5次元まで行ってしまうと想像できないばかりか、頭がショートする。
細かいツッコミを入れずに見るのが正解かも知れない。
俳優陣も豪華で、見応えがある。
嘘を吐き、自分のエゴの為に動く人間。
粛々とプログラムを実行するロボット。ロボットの方がなぜか人間らしいと感じる不思議さよ。
一度の鑑賞では疑問も残る。
二度目の鑑賞でクーパーが泣くシーンで一緒に号泣できる。
いつ・どこで・誰が・誰と・何をした
5W1Hの描き方が独特なノーラン監督。
だが、そこが良い‼︎
SFはどこに焦点を置くかで、物語の重さが変わってくる。
自分が引き寄せられる重力のある映画だった。
劇場で観ても絶対に後悔しない作品。
まだご覧になっていない方は、是非劇場でご覧ください‼︎
ノーラン
久しぶりに映画館に行きました
なんか映画でも観てきたら?と夫に急に言われて、えー、急、と思ったけど、今何やってるのかな〜って調べたら、テネットがもうすぐ公開なのでインターステラーがIMAXでやってて、これを観るかと行ってきた。確か飛行機の中で観て、飛行機の揺れが映画の内容とシンクロしたりして、それはそれで面白かったけど、やっぱり大きな画面で観ると全く違う、迫力だった。あと子どもが出来てから観たら超泣けた・・・。
時間がめっちゃ遅く進む星から戻ってからの絶望感・・・この星では1時間が地球の7年だから、とにかく急がなきゃ!っていうのが前に観た時よりひしひしと、子どもの成長を10年も20年も見られないなんて、辛過ぎる・・・最後お婆さんになった娘と再開する場面も、前観た時はやっと会えたねという感じで観てたけども、今観ると、それよりも失った時間の長さを考えてしまって、悲しかったな。
1回目に観た時に、地球規模で危機的な状況にあるらしいのに、映画に出てくるのが一部の場所の一部の人々なので、他の場所がどうなってるのかよく分からないのがモヤモヤしたなと思ったけど、見せるのを一部分にすることで寓話っぽい感じが増してるのかも、あとは結局はとても個人的な話というか、父と娘の話というか、だからこれでいいのかも、と思った。アメリアがエドマンズの星に行きたくて愛の話をとうとうとして2人に引かれる、みたいな(みたいな?)場面があったけど、最後は父と娘の愛がどうたらで次元が繋がってどうたらみたいになっていって、よく分からないけど、ここをまあいいかと思えるかどうかで好き嫌いの分かれる映画かな、私は好きだった。
本編前の予告が面白そうな映画と思ってたら途中で「テネット」と出て、はあ!っと、テネットも映画館でIMAXで観たいなぁ、でも予告とかあんまり観たくない派だから途中から目をつぶっていた。楽しみ。
コロナが流行り出してから初めて映画館に行ったけど、座席前後左右空いてて観やすいし、1人で行きやすいし、良かったな。
10年の1本あるかないかの名作
TOHOのリバイバル上映で鑑賞しました。公開当時の劇場が1回目、自宅で2回目、今回が3回目です。3回目にも関わらず、父娘の別れのシーンは泣けたし、ワームホールやミラーの惑星(波が来るところ)のシーンは圧倒されました。10年に1本あるかないかの名作だと思います。
ノーラン監督の映画は難しいだけあって、観る数を重ねるたびに理解度が増して本当の面白さがわかるような気がします。
五次元からの導き
・初見2020年9月12日 二度目2024年11月26日
・初見はアマプラ。その時に価値観を反転させられるような感覚になってから好きな映画になった。今回、劇場で観られる機会に恵まれて幸運を感じた。
・身の回りの出来事が、もしかして五次元からのメッセージかもしれないのような気がしてくる。特に本棚から本が落ちたりした時は。それが楽しくなる。
・初見の印象は他の星に来たら時間の流れ、そんなに違うんだっていうのと生きて帰って家族と仲良く暮らせるんだろうと思って観たら、最初の星で一時間で地球は七年っていう度肝を抜かれる時空であっという間に家族が元通りになる事がなくなって絶望的だなぁっていう気持ちになった。のをいまだに憶えていたせいか、二度目の今回はあぁここでそうだったなぁっていう感覚だった。で、板状というべきか棒状というべきなのかロボットがいたなぁっていう。あんなにジョークがきつい感じだったのはすっかり忘れてた。
・本棚の裏側というべきか、そこからメッセージを送っていたシーンがとにかく頭にやきついていて、それを観に行ったようなもんだった。とはいえ二度目だしなって思ったけど涙がボロボロ出てきた。同じような苦労を知らないし、自分には別に娘もいないし家族関係が別にいいわけでも悪いわけでもない(と思う) のに涙が出た。一体なんでなんだろう。
・改めて観て、知らない単語や前提が多々あったのに何であんなに理解している感覚でおよそ三時間も観てられたんだろうと疑問に思った。プランAが移住計画だけかと思ったら、重力の問題を含んでたらしくてそれを解くためにはガルガンチュアの特異点の計測って話になったところはわかった気がするけど、わかって計算して大きな問題が解決したっていう事になっていたけど、一体なにが解決したんだろうと思った。その後ググってわかったのが、重力をコントロールできるようになるための問題が解けないままだったのが解決して宇宙ステーションを製造して打ち上げるというプランって事だった。わからなかった箇所を観返したら思いっきりそういう風に言っていた。そもそも重力をコントロールできるようになるために画策している状況が想像つかなかったのと移住計画とくっついているというのがわかってなかった。どうもぼんやりしていたらしい。というかプランBの映像のインパクトが強くて重力云々の所が記憶に残ってなかった。プランBありきのプランAは建前っていうことだったんだろう。あと初見の時は考えてなかったのが地球はどうなったんだろう。
・劇場で観てたので周りですすり泣いてるようで、泣ける映画ってカテゴリだったんだなと思った。
SFとしては
人によって見方様々と思いますが、SFとしての評価をレビューします。
物理は過去に発見された法則を内包する形で進んでます。古典物理に対する相対論しかり、量子力学しかり。そういう意味でブラックホールの内側、向こう側みたいな未知の世界に関してはSF作家が自由に表現できる。でも、日常と接続した部分では古典物理が成立していないとおかしい。この制約がSFを作る難しさであり、面白さ、挑戦でも有ると思う
。
そういった観点で最初に交信に気づく重要な場面が物理的に正しくないのが気になって楽しめなかった。重力波と重力の区別がついてないことや、重力の特性が正しくないこと。一つめの惑星の設定も、無理があった。
映画としては名作の類いではなく駄作、B級映画の類い
これは、映画としては、決して名作の類いではなく駄作、B級映画の類いでしょう。
相対性理論の説明教材のような映画というか。
この映画を名作とか傑作とか言っているのは、ステマ活動の関係者か、映画スキルが余程低い方々だと思います。
アマゾンプライム会員の特典で無料だから観ましたが、わざわざお金を払ってまでして観る映画ではないですね。
他の映画にも言える事ですが、製作年度が比較的新しく、尚且つ、名作、傑作の類いの評価が高い映画であるならば、アマゾンプライムビデオの実績的に考えても無料で観れるワケがない。
このインターステラーのような映画を観ると、2001年宇宙の旅 を超える映画はなかなか出てこないだろうな、と再認識させられますね。
タイトルなし(ネタバレ)
もう本当によかったです…だいすきな映画…IMAXで見れたのが本当に嬉しい…大迫力でした
アップされた土星に宇宙船が本当に小さく写っているシーンや、ブラックホールに落ちたクーパーの顔に光が反射するシーン、氷の星や水の星など印象的な画ばかりでわくわくしました!
いろんな伏線が綺麗に回収されていって気持ちよかったしわかりやすくていい映画でした
マーフとクーパーの再会シーンで、マーフが「親が子を看取るなんてだめ」と言っていて、娘の方が精神的にも年上になってしまったんだなあと実感しました
あと、冒頭の三者面談で家族の状況や性格をまるっと説明してしまうの、上手だな〜〜と思いました!この繊細な感情や言葉のニュアンスって小説や舞台じゃ難しい、映像ならではのものですよね!
つくづく映画って総合芸術なんだなってぐっときました
SFってなんとなく難しいイメージだったけど、インターステラーはわかりやすくて他のもたくさん見たいなと思いました!間口を広げてくれた大事な映画になりそうです。
あと結構2001年宇宙の旅のオマージュでてきますよね?!
IMAXで鑑賞すべき作品
ノーラン祭り第三弾!!
封切り時に普通のスクリーンで鑑賞済。
そんなに感動しなかった記憶が残ってますが…IMAXだとこんなにも違うのか!!
まず、音響。音というよりは振動ですね。そして映像のクリアさ。ホントに宇宙飛行してるかのような感覚は今までにない体験でした。
お話しは壮大で少しオカルト要素も含まれます。このオカルト現象が最後に解き明かされます。時間の流れ方が違うので
宇宙旅行から帰ると子供が自分より、老けている。そこはなんとなく理解出来るが、ブラックホールや物理の難しい事にはついていけなくて…
家族を思いやる気持ちが人類を救えるのか?父と娘の絆は修復出来るのか?
TENETの予告、何度観てもドキドキする。IMAXで観るか?ドルビーシネマで観るか?悩む(>_<)でも2回観ないと理解出来ないらしいから…両方かな(((^_^;)
息詰まる展開の連続。予想のできないストーリーとトリッキーなノーランワールドを堪能。
凄いっっっ‼️
昔からSF🛸は難しいイメージがあってあまり観なかったが、アド・アストラをTVで観た時に宇宙空間は映画館の大画面の方がいいよな〜と思った。そんな時にノーラン夏祭りの「インターステラー」これは観るしかないでしょ〜IMAXで❗️
SFあまり観ていないので当然初インターステラー。
こんな凄い映画を今まで観なかったとは、、、なんて愚か者だったのか😫科学的な話はやはり難しくてチンプンカンプンだったけど、チンプンカンプンなままでも全く飽きることなく、時間の長さも全く気にならず、マット・デイモンが曲者だったあたりから(あんな所で争って取り残されても困るじゃん)喰い入る様に観ていた!
ストーリーも面白いけど、とにかく映像が凄いっ❗️ワームホール、水の惑星での大津波(名前を忘れたけど四角いロボットが素早く回転してたのは驚いた😳)氷の惑星、宇宙空間もスゴイ迫力❗️
合体する時はハラハラして思わず力が入ってしまったし、ブラックホールに入ったあたりのスピード感、4Dでもないのにディズニーランドのスターツアーズみたい😅IMAXの音響効果もあるが、冷房が効きすぎて冷たい空気が丁度当たっていたので尚更。
5次元もよくわからないけど、わからなくても充分楽しめるし、哀しくもあり、もっとはやく観るべきだった。凄い映画、その言葉に尽きる‼️
愛は5次元を超える
圧倒的
想像力の挑戦が素晴らしい!!
何年か前にDVDで鑑賞。
なんというスケール!居間ごと宇宙空間に放り出されたかのような恐怖と孤独感。存在の不安感、、、。
そして 何より圧倒されたのは5次元?の世界観が非常に興味深く、面白く表現されてれていた事。目眩がしそうなくらい興奮した!誰も見たことない次元をどうしたら想像出来るのか 万人がほぼ納得できる表現なんてあろう筈は無い。これは読み手の想像力に任せる小説の方が易いのかもしれない。そんな中で この作品が挑戦した事には尊敬しか無い!
なんで映画館で見なかったんだよー!と悔しくて仕方なかった。
SF映画は好きで色々観たが、この映画は2001年宇宙の旅以上の果てしなさを感じさせ、私の中ではN o.1のSF(宇宙を描いたSFの中で)この座はこの先も動かない。きっと!😃
♪ 2番目に好きな《コンタクト》に出ているマシュー・マコノヒーが主演しているのも嬉しい ♪
IMAXで再鑑賞。やっぱり映画館で観るといいですね。宇宙船の窓から...
全986件中、301~320件目を表示