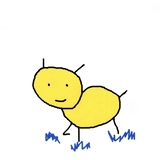カサンドラ・クロスのレビュー・感想・評価
全44件中、1~20件目を表示
元祖トレイン・パニックの残す余韻
Blu-rayで鑑賞(吹替【水曜ロードショー版】)。
原作は未読。
過激派の青年によって、アメリカ軍が極秘裏に開発していた細菌兵器が大陸縦断特急の中に持ち込まれてしまう。
汚染されていく車内の様子を、乗客たちの紹介を兼ねた群像劇でもって見せる。完璧なプロローグだなと思った。
どんどん物語のギアが上がっていく。なんて面白い脚本なのだろう。高まるサスペンスに手に汗握りまくった。
演技巧者な豪華キャストを揃えているからこその重厚感も堪らない。ソフィア・ローレンの美しさと言ったら…
全てを隠蔽し闇に葬ろうと画策するアメリカ軍情報大佐の企てる計画はあまりにも非情で、未必の故意そのものだろう。
その企みに抗うべく立ち上がる乗客たち。特殊部隊を相手に銃撃戦を挑むのである。彼らの戦いの行方に手に汗握った。
その後の結末には驚愕を禁じ得ない。全員生還のハッピーエンドを期待していたのにまさかこんな大惨事になるなんて…
列車が崩落した鉄橋から落ちていくシーンが生々しい。乗客を貫く鉄骨、苦悶に喘ぐ表情のアップ…地獄絵図であった。
自らの職務を全う(本当は上手くいっていないが)した大佐にも監視がついており、その後の彼(と巻き込まれた女医)の運命を想起させるラストがなんとも言えぬ余韻を残す。
手段を選ばぬ隠蔽の動きが止まらないのならば、生き残った乗客たちのその後にも、恐ろしいことが待っているのではないか。そんなことを想像させる幕切れが素晴らしかった。
織田裕二主演の踊る大捜査線の映画の決め言葉が事件の捜査の指示命令が...
織田裕二主演の踊る大捜査線の映画の決め言葉が事件の捜査の指示命令が上官の執務室ではなく、この事件の現場にあるんだがありますが、本映画の結末がその執務室内でその列車の電光掲示板を見てその事件の拡大を未然に防いで安堵するその米軍の大佐でしたが、その大佐も自分より上の上官に命令されてその任務に就いた訳ですが、彼に対しての監視活動も続くだろうのナレーションが最後でしたが、本映画の実際が伝染病に感染したそのテロ犯が乗った列車をその伝染病の事件と無関係の乗客も乗った列車諸共、廃線したポーランドの奥地で事故に見せかけて脱線事故にしようとした訳ですが、その執務室の電光掲示板ではその列車が脱線事故をし、そのランプが消えてましたが、実際のその列車の脱線事故の現場ではその伝染病の感染が解かれ、その列車の乗客がその列車から救出されてでしたが
パニック映画が飽きられ始めた頃?
米軍が内密で開発を進めていた細菌に感染した患者が列車に紛れ込み感染が広がるという当時流行のパニック映画の一つです。僕は、公開時以来約50年ぶりの再見。ソフィア・ローレンやバート・ランカスター、リチャード・ハリス、マーチン・シーン、更には アメリカン・フットボールのO.J.シンプソン(この頃は殺人容疑スキャンダル勃発の前)までビッグ・ネームが並ぶ作品ですが、やはりオールスター・キャストに頼り過ぎで緊迫感が希薄な大味の作品に思えたなぁ。「パニック映画」と言われるジャンルがそろそろ飽きられる頃だったのかな。
同時期に公開の『キングコング』(こちらも大味だったが、ジェシカ・ラングのダイナマイト・ボディの魅力で高得点獲得)に興収で敗れたのも納得でありました。(2024/1/3 鑑賞)
123 あいつ知り過ぎやな。わかってるよね?心得ております。
1976年公開
キングコングのディーノ・デ・ラウレンティス
本作のイタリア拠点カルロポンティの
2大プロデューサーが同じ年の正月映画で対決。
最初に言っとくがリチャードハリスがヒーロー
ってやめてくれ!
ウイルスが飛び散るシーンはスローモーションの
効果もあって正直震えました。
この手のサスペンス物ははじめ静かにジワーっと
拡がって最後にドッカ―んなんだけど王道の作り方。
キャストもイタリア映画界オールスター総出演。
まあイタリア映画となると若干しょぼいが。
で、
全員死亡を目論むも助かった人がいるのは
お上からしたらまずくないですか?
ジェリーゴールドスミスの主題曲
映画のタイトルバックなんかよりサントラ版の方が
アレンジは数段上なのになんで使わなかったのか?
70点
テレビ初鑑賞 1979年10月24日『水曜ロードショー』
パンフ購入
当時は1シーズンに2作も梅田まで行って観るほどの
金銭面に余裕はなかったわけで
せいぜいパンフを買って見た気になることが多かったです。
救いのない死のスパイラルを予兆させる、異色のパニック映画
午前十時の映画祭13にて。
70年代パニック映画ブームの一作とされる本作。
軍事陰謀サスペンスでもある。
『大空港』(’70)を先駆けに、『タワーリング・インフェルノ』(’74)を頂点とする70年代にブームとなったパニック映画は、スリルとスペクタクルに加えて、オールスター・キャストによるグランドホテル形式の群像劇が特徴の大作群だ。
本作が公開された1976年はブーム終盤の時期で、その後このブームは徐々に終息していった。
本作のクライマックスはカサンドラ・クロス鉄橋の崩落シーンだ。ミニチュア撮影を組み込んだ映像が迫力満点で、こういう特撮も70年代パニック映画の魅力の一つだった。
しかし、わずか1年後に『スター・ウォーズ』が公開され、その視覚効果に世界中が衝撃を受けたのだ。それ以降、スペースオペラやSFが特撮技術発展の題材となったことが、70年代パニック映画ブームに引導を渡したのではないだろうか。
そして、最新技術がパニック映画というジャンルに投下されるようになるのは、20年強待たなければならなかった。
『タワーリング・インフェルノ』に比べると小粒な印象ではあるが、イタリアとイギリスの大物プロデューサーが西ドイツ・フランスなどからも資金を調達して製作しただけあって、ヨーロッパ色のあるオールスター・キャストではある。
最初にクレジットされているのはソフィア・ローレン。
イタリアの女優で、ヨーロッパとハリウッドの両方で活躍していた。スラリと伸びた美しい脚とグラマラスなボディでセックスシンボルと言われた時期もあるが、元々ヴィットリオ・デ・シーカ作品などで演技者として高く評価されていた女優だ。
本作の製作者の一人カルロ・ポンティは夫である。
本作が日本で公開されのは、大林宣彦が撮ったホンダの原付のCMが一世を風靡していた頃だと思う。彼女の出演は日本の興業に大きく貢献したことだろう。
色っぽい演技から体力勝負のアクションまで、芸達者ぶりを発揮している。
二番目にクレジットされているリチャード・ハリスは、アクション映画のヒーローを演じるイメージがなかったが、これ以前に『殺し屋ハリー/華麗なる挑戦』『ジャガーノート』などのサスペンス・アクションに主演していた。
理知的なイメージで、本作での世界的な神経外科医という役に説得力がある。
新婚旅行カップルの新妻を演じたアン・ターケルは当時の奥様。
キャリアの後半は独特の存在感を示した俳優で、私は伊丹十三と重なるイメージを持っている。
バート・ランカスターの名は、主要キャストのトリにクレジットされている。
若い頃はアクションスターでもあった名優で、この頃は風格が伴ってアメリカ陸軍大佐という役に違和感がない。
出番がほぼ指令室のセット撮影だけなのは、出演料を抑えるためか、スケジュール調整ができなかったのかだと思うが、恐らく前者だろう。
国(軍)の立場でミッションを遂行する冷徹な軍人を演じているが、女医と対峙するなかで若干人間味を匂わせているようにも感じる。
『大空港』のオールスター・キャストにも名を連ねていた。
国際保険機構の主任医師としてバート・ランカスターと対峙するイングリッド・チューリンはスウェーデンの女優で、イングマール・ベルイマン作品で知られ、カンヌ国際映画祭で女優賞を得ている。
人道の立場で大佐と対立する強さと、作戦を制することができなかった無力感を表情のみで演じている。
ユダヤ人セールスマンを演じたリー・ストラスバーグという人は、映画にはあまり出演していない舞台俳優であり演技指導者だ。技術で演じるのではなく役の感情を自身の中に作り出して自然に演じる「メソッド演技法」を確立した人…らしい。本作の前に『ゴッドファーザー PART II』でアカデミー賞にノミネートされている。
当初はイカサマ師的な怪しげで快活な老人だったが、列車の行き先がポーランドに変更されたと知ってアウシュビッツの悪夢を想起して怯え、無謀な逃亡を図るという、本作で最大の悲劇を演じている。
ウクライナ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国)出身のユダヤ系アメリカ人。
兵器製造業者の妻役のエヴァ・ガードナーも50年代のスクリーンを飾った名女優。キャストクレジットではバート・ランカスターと彼女の二人だけが役名を併記した別格の扱いだ。
フランク・シナトラの元妻でもある。
若い愛人を堂々と列車旅に帯同し、その愛人の正体を知っても動じない貫禄は迫力さえある。
その愛人を演じたマーティン・シーンは、同じ年に公開された『白い家の少女』でジョディ・フォスターを脅かす不気味な二枚目を演じた。
本作でも麻薬密売人の裏の顔を持つ登山家という影のある役で、前髪を垂らした色男ぶりだ。
佳境に差し掛かると活躍の出番が回ってくるが、割とあっけなく非業の最期をとげる。
今のボルダリングの金メダリストクラスが走行する列車で同じことをやったらどうだろうか…と、思ったりした。
その密売人を追って神父になりすまして列車に乗った捜査官をO・J・シンプソンが演じる。この時点ではまだ現役のNFL選手でもあった。『タワーリング・インフェルノ』にも出演している。
登場当初は善人か悪人か分からないキャラクターだったが、自分が盾となって少女を救う。
その少女の乳母役のアリダ・ヴァリはアルフレッド・ヒッチコックの『パラダイン夫人の恋』でタイトルロールを演じ、キャロル・リードの『第三の男』では、有名なラストシーンでジョセフ・コットンの前を通り過ぎて歩み去っていくアンナを演じた人だ。
クロアチア出身のイタリア人女優である。
車掌役のライオネル・スタンダーは見覚えがある気がしたので、アーネスト・ボーグナインに似てるからかと思ったのだが、TVシリーズ「探偵ハート&ハート」の執事役で人気を博した人だった。
アメリカ軍が極秘裏に培養している細菌に感染したテロリストが、上記の豪華キャストが乗り合わせたストックホルム行き特急列車に逃げ込む。
その前に、ジュネーブの国際保健機構本部のアメリカセクションをテロリストが急襲し、逃げた一人が細菌を浴びていたのだ。
感染した犬とテロリストを走る列車からヘリコプターで回収しようとするミッションが、最初のダイナミックな見せ場だが、列車を停めて良いシチュエーションに思えて、引っかかる。
ここでソフィア・ローレンが髪を振り乱して大活躍。
列車内に感染者が続出し、車両を病室代わりにしてチェンバレン医師(リチャード・ハリス)が治療に当たる。
コロナ禍を経験した今の私達は、この光景を絵空事とは思えず、また自ら感染するリスクを顧みず患者に接する医師の姿に畏敬の念を抱くのだ。
マッケンジー大佐(バート・ランカスター)の計画を知ったチェンバレンたちは強硬手段に移る。
ここからは反乱する乗客たちと、自分たちも列車もろとも葬られる運命であることを知らない軍人たちとの熾烈な攻防戦が展開する。
スリリングな緊張感の連続の末に、遂にカサンドラ・クロス鉄橋のスペクタクルに突入する一大アクションであるが、そこに人間ドラマをにじませる演者の力を感じる。
かくして、大勢の犠牲者を出しながらも一部の乗客は助かり、列車を降りて歩き始める。
指令室では、マッケンジー大佐とシュトラドナー主任医師(イングリッド・チューリン)が複雑な空気の中で作戦の終了を迎えていた。
『アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場』で女性政務次官が中将に向かって「恥ずべき作戦」と言うラストのシークェンスを思い出す。
だが、この時点で、大佐も側近のスタック少佐(ジョン・フィリップ・ロー)も現場の状況確認を怠っている。
さて、生き残った乗客たちはいったいどこへ行くのだろう。水も食料も持たず、女子供も連れて森林の中を彷徨わなければならない。
米軍は隠蔽を図っているのだから、救助隊ではなく抹殺するための追手を派遣するのではないか。
米軍が生存者を知る前にポーランドの政府に保護されるだろうか。いや、保護されたとしても秘密裏に米軍に引き渡されそうだ。
生存者の有無を確認しないままミッション・コンプリートを確信している司令室では、マッケンジー大佐がシュトラドナー医師に、医師を続けて欲しいから口をつぐむよう言外に脅しをかける。女医は状況を理解したように大佐を一べつして部屋を出る。
スタック少佐は、司令室を出るマッケンジー大佐に労いの声をかけるが、手元は忙しく作戦の証跡となる書類をシュレッダーにかけている。
そして、彼には上層部から次のミッションが与えられる。残る口封じの対象は、マッケンジー大佐その人なのだ。
だが、そのミッションを遂行したのち、スタック少佐もまた…と考えると恐ろしい。
70年代パニック映画は、大惨事を乗り切って必ず誰かは助かるのがセオリーである。
監督のジョージ・P・コスマトス(当時のカタカナ表記はジョルジュ・パン・コスマトス)は、原案と共同脚本を兼ねている。彼が選んだ結末は、セオリーに従わず全員が悲惨な最期を迎える後日譚しか想像できない救いのないものだった。
コロナ禍を予見したような映画
「午前十時の映画祭」で鑑賞。
まず、オープニングにグッときた。空撮の映像と哀愁ただよう流麗なテーマ曲に感動。
同じような題材を扱った『復活の日』の冒頭(潜水艦が氷の海を進むシーン)にどことなく似ている。「ひょっとしたら、本作のこの空撮によるオープニングが深作欣二監督にインスピレーションを与えたのかもしれないな」などと思っていると、やがて曲調は不穏さを増してくるのだった。
現代のコロナ禍を予見したような本作。ダイヤモンド・プリンセス号の騒動を想起したりもして……。
そして「正しく怖がろう」というところに落ち着くのも同じ。
見どころはなんといっても、豪華キャストの共演。ソフィア・ローレンがとにかくセクシーで魅力的だ。マーティン・シーンは『地獄の黙示録』の精悍さはなく、ちょっと別人のよう。
凝ったシナリオでまあ楽しめたけれど、悲惨な結末にはこころ暗くなった(観たのが正月の4日だから、能登の震災のこともあって、なおさら)。
しかし、濃厚接触者である医者たちが列車の中をうろうろするという初期対応はまずいですね。
改めて思い出したコロナ禍
闇は深い
午前十時の映画祭13にて。
ジュネーブにある国際保健機構に侵入し爆弾テロを企てたゲリラ3人のうち1人が伝染性病原菌を浴びて逃走した。追跡調査したアメリカ陸軍情報部はその逃走犯がストックホルム行きの大陸横断列車に乗り込んだことを掴んだ。約1,000人の客を乗せた列車は途中で窓を開かないように外から鉄板を溶接され、密閉された状態でコース変更し、カサンドラ・クロスと呼ばれる鉄橋へ向かうことになった。カサンドラ鉄橋は1948年以降使用されてなく、崩壊の危険があるものだった。
チェンバレン博士を始めとする乗客たちは何とか列車を停めようとするが・・・てな話。
細菌やウイルス絡みの作品はよく有るが、橋から落として抹殺なんてそんな馬鹿らしいことを考えるのはいくら50年前といってもおかしいだろ、って思った。
川に病原菌が流れたら下流の人はどうなる?
最後の2人に監視が付いてると言うのは、彼らも抹殺対象って事なんだろうけど、生き残った人があれだけ居たらこれからどうなるんだろう?
事後処理が気になった。
抹殺指示を出したのがアメリカ陸軍だとしたら、闇は深いと思った。
ウイルス 列車 オールスターキャスト
虫の知らせ
2023年見納めが午前10になってしまった😑
コロナ予見?話題になったのだろうか、知らんかった。アウトブレイク、コンテイジョン、12モンキーズ辺りは見たけど
最初のテロリストと元妻の動機が分からない お医者さんがアクション、しかしあんなに遠慮無くお互い撃ち合うかな?夫婦の絆を取り戻すお話でもあり
細菌兵器みたいな研究が我々の全く知らない所で進められていて、もし感染でもしたら秘密裡にされてしまうかもというのは恐怖を覚えました ナチス✕ユダヤ人みたいだなとも 登山家の彼も列車もああだったし、エンディングは現実ならあんな風に苦い物だろうなとは思った
パニック映画全盛期だったよなー。
まあまあだった
コロナ禍を経て見ると、感染者との接触が無防備だ。マスクをしなければ手洗いもしない。また、警備の兵士が変に職務に忠実で無益な銃撃戦が起こる。お互いに殺し合うほどの理由はないはずだ。また、食堂車を爆破するのだけど特に意味がない。退屈はしなかったけど名作映画かと思ったら全然違った。こういうのは日曜洋画劇場で見ておくべきだ。
大陸横断列車 like the 新感染
感染症を扱った昔の作品です。コロナ禍が収まって上映リストに加えたのかな
全44件中、1~20件目を表示