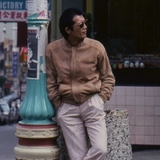影武者のレビュー・感想・評価
全36件中、1~20件目を表示
仲代達矢をずっと目で追い魅力され続ける
個人評価:4.5
赤は紅く、黒は漆黒に。美しく壮大なひきの画。
特に長篠の戦いは屏風絵を見ている様に圧巻である。倒れた馬の撮影は麻酔を打って臨むなど、黒澤伝説の一つなのだろう。
劇中の馬で走るシーンはどれも迫力があり、騎馬に強い武田軍をリアルに描いていると感じる。
史実を交え、信玄の偉大さと影武者の葛藤を描き、文学作品としても素晴らしい。
仲代達矢は言うまでもなく圧巻の演技で、信玄の動かざること山の如しを体現した迫力のある演技だ。仲代達矢をずっと目で追い魅力され続ける3時間でした。
信玄の影武者と武田家滅亡の話
感想
黒澤作品唯一の史実物の作品である。
作風として監督の構図内での色彩感覚が爆発的に映像構成に生かされ表現されており、カラー映画作品としての芸術的意義を強く感じられる作品となっている。脚本は三方ヶ原の戦いの後、武田信玄は西上作戦を継続し三河方面へ進出、野田城攻略時に狙撃され重傷を負い甲斐へ帰国途中死亡した説を取り上げ物語に反映させている。フィクションとしての大きな捻りは無く無難な仕上がり。配役は監督肝入りのオーディションで抜擢された油井昌由樹氏が徳川家康を、また無名塾出身の隆大介氏が織田信長の大役に抜擢され各々演じている。
影武者(武田信玄)役の仲代達矢氏は途中降板した勝新太郎氏の代役での出演であったが、武田信廉役、山崎努氏と共に重厚で安定した演技を見せている。コッポラ、ルーカスからの資金援助もあり作品は完成。第33回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール(最高賞)を受賞。また今では普通だが本作はハリウッドメジャーの配給会社か初めて日本映画として配給した作品であった。
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
物語
躑躅ヶ崎館一の間にて武田信玄、武田信廉の目前に座らされている信玄と全く同じ装束を纏う一人の男。その男を見ながら頷き呟く信玄。
「うむ。よく似ておる。」
信廉「兄上がもう一人いるとしか思えません。長年兄の影武者を務めたこの信廉もこのようには参りません。」
信玄「何処で見つけて参った?」
「釜無川の仕置き場で拾ってまいりました。」
「逆さ磔になる処を通り連りに見掛けまして何かの折兄上の影武者に如何かと貰い承りました。」
信玄「何者じゃ?」
「領内を荒らし廻っていた盗人で御座ります。」
信玄「盗人?」
「強か者、いかなる責苦にも口を開きませぬが人を殺めている疑いもあると検事の者が申しておりました。」
信玄「その検事の者共、この男がわしに瓜二つであるのをなんと申しておった?」
「なにも。肉身のこの信廉で故兄上に瓜二つと見えました。髪形なり振り、言葉遣いは全くの無頼。誰もこの者が兄上に似ているなどとは考え及ばぬ体で御座いました。いや、この信廉もこのように取繕わせていまさら余りに兄上に瓜二つなのに驚き入っている次第であります。」
「それにしても信廉、逆さ磔に繋ろうという程の無頼の者、如何に似ているとは申せわしの影武者にとは與であろう。」
話を聞くや突然下品な笑い方をする影武者の男。〜
「俺は高々5貫、10貫の小銭を盗んだ小泥棒だ!国を盗むために数え切れねえほど人を殺した大泥棒に悪人呼ばわりされる...覚えはねえ!」
信玄を指刺し罵倒しようとするもその威厳に圧倒され尻込みする男
信廉「黙れ!無礼者!」
「ふん!逆さ磔になる身の上だ!片足地獄の釜に突っ込んだこの身体!手打ちだって屁でもねえ。煮て食うなり焼いて食うなり勝手にしろ!」大の字に寝そべる男。
大刀を持ち手打ちにしようとする信廉。その時、信玄がその男に向かって、
「構わん。何なりと申すが良い。申せんならわしが申そう。確かにわしは強欲非道の大悪人じや。実の父を追放し我が子も殺した。わしは天下を盗むためには何事も辞さぬ覚悟じゃ。血で血を洗う今の世に何者かが天下を取り、天下に号令せぬ限りその血の川の流れは尽きず屍の山は築かれるばかりぞ。」
立ち上がり一の間を去ろうとする信玄。去り際に、
「冷えて参ったな。冷えると古傷が痛む。信廉、この男よくぞ付付と(我に)申した。使えるかも知れん。その方に預ける。」
話を承りお辞儀をする武田信廉と聞き入る影武者の男(暗転)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1573年(元亀3年12月22日)甲斐 武田信玄は兵ニ万にて遠江国敷知郡三方ヶ原に西上作戦と称し進出、遠江三河を本拠地としていた徳川家康、織田方(佐久間信盛)兵一万三千を擁した連合軍で浜松城に於いて迎え打たんと城の防御を固めていたが、武田方が浜松城を横目に急激に進路を西へ変更。それをきっかけに徳川方は揺動され城を出て攻撃に転じたところ、武田方の鶴翼の陣で迎撃され徳川方は浜松城へ敗退し決着がついた。
同年(元亀4年1月3日)武田信玄はそのまま西進し三河に進出、東三河の要衝にある野田城の攻略を開始する。城主の菅沼定盈は信玄の降伏勧告を拒絶して徹底抗戦を選択、武田方は金堀衆に城の地下に通じる井戸を破壊させる工作、所謂水攻めを行い井戸を破壊する事に成功する。事件はその直後に発生した。
水攻めの最中より本丸から夜毎見事な笛の音が響き渡る。哀愁唆るその美しい響きは攻め手である武田方の多くの将兵も感じ入り夜を待ち遠しく感じる者もいた。敵方とはいえ武家の嗜みとして風雅を感ずる話を聞きつけた武田信玄は水攻めの夜に笛の音色を直に聞きたいと欲し隠密のうちに城へ出向くも城内より鉄砲にて狙撃され大怪我を負い軍勢は急遽一路甲斐へ反転する事になった。
武田勢西進反転の報は直ちに様々な憶測を持って徳川家康、織田信長、上杉謙信の諸将に伝えられるが、詳細な消息については間者に依る隠密捜査でも確認が出来ない状況が続いた。
手傷を負った武田信玄は家臣団に、
「我が旗を京の都に裁てる事はこの信玄の生涯の夢である。しかしこの信玄にもしもの事あらばその志に拘るな。我もし死すとも三年は喪を秘し領国の備えを固め努努動くな。これに背き妄りに兵を動かす時は我が武田家の滅ぶる時ぞ。一同よく聞け。この事我が遺言と心得よ。」と伝える。
生きる事に固執し続けた信玄だが、甲斐に辿り着く事なく帰途中に死去する。享年数え52歳。山縣昌景は近習と共にに同行した医師を口封じに殺害し街道筋に遺棄、その夜野営先の陣内で武田信廉他の家臣団に内密裏に報告する。武田信廉が予ねてより信玄より預けられていた影武者の男を家臣団に引き合せる。山縣昌景、馬場信春、内藤昌豊、高坂弾正ら家臣団はその余りにも生前の信玄と瓜二つの容姿に驚嘆する。その日以来、軍勢の士気を鼓舞する場にも登場していく影武者。その姿は生前の武田信玄公そのものの所作を真似たものであった為、織田・徳川の間者の目をも欺いていく。
甲斐の躑躅ヶ崎館に帰着した後も諏訪勝頼の嫡男竹丸の幼子ならではの純粋な視点に正体を暴かれそうになるも上手くその場を取り繕い躱わす事に成功する。更に側室達も気付かず信玄本人と信じていく。武田信廉は武田家の難局を影武者の男に全て押し付ける事を気の毒がり、三年務め上げ何事も無かった後に男を自由の身とすることを確約する。男も次第に助命の恩もあり信玄公の役に立ちたいと懇願し影武者に本腰を入れ出し正に武田家兵法の基本思想である「疾きこと風の如く、徐かなること林の如く、侵し掠めること火の如く、動かざること山の如し」 信玄本人が山そのものである事を身を以って配下の者に顕示するのであった。
徳川家康は浅井・浅倉連合軍の反撃、摂津石山本願寺鎮圧、さらに伊勢一向一揆征伐、そして信玄の西進により全く手も足もでない状況で四苦八苦している織田信長に向けて再度進軍しようとしない武田勢の様子から信玄死亡の疑いを捨て切れず様々な揺動作戦を展開し武田勢の出方を推し図ろうとする。影武者に言い様に扱われ納得のいかない武田勝頼は独断で揺動に応じてしまい武田家臣団が一枚岩ではない事を家康、信長に悟られる事になってしまう。これが武田家滅亡に向けての災いの発端となっていく。
武田家中の信頼を得た事で己を過信した影武者の男は信玄しか乗りこなす事の出来なかった名馬黒雲を乗り熟そうとして家中の者が見ている前で落馬する。その騒動からかつて川中島で上杉謙信から受けた刀傷も無いことが妾達に判ってしまい影武者である事が家中に知れ渡ってしまう。
武田信廉をはじめとする家臣団はこの機会に乗じて武田信玄の訃報を正式に発し仮葬儀を実施する。武田家の跡取りは正式に武田勝頼となった。勝頼は信玄公の動いてはならぬという遺言を守らす長篠への出兵を家臣団の静止を振り切り決断する。影武者の男は信廉や家臣団に感謝されながらも放免される。信玄の死から三年が経とうとしていた。織田信長は仮葬儀の報に接して、
「三年の間、よくぞこの信長を謀った!」として幸若舞敦盛の一節を謳い舞う。
「人間五十年下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり一度生を享け、滅せぬもののあるべきか」
1575年(天正3年5月21日)三河国長篠、設楽原に於いて新兵器である鉄砲を多数用意し、隊列を編成した織田信長、徳川家康連合軍三万八千と武田勝頼率いる二万五千全軍の内一万五千の長槍編成と騎馬隊を中心とする軍勢が戦闘を行い武田軍は鉄砲の前に完膚なきまでに叩きのめされ壊滅、武田軍は死者一万人を数え武田四天王の内、山縣昌景(火)、馬場信春(風)、内藤昌豊(林)が壮絶な戦死を遂げる。この戦を以って武田家は滅亡を迎えた。その最後の戦を物陰から終始観続けた影武者の男。最後に自ら鉄砲隊の陣に突入、被弾する
命からがら川まで歩きつくと川の中に信玄の風林火山の旗印が落ちているのを見つける。旗印を拾おうと川に分け入る男。しかし途中で力尽き溺れる。亡骸となった遺体が旗印を掠めて流されていく。
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
製作:黒澤明 田中友幸(東宝)
製作総指揮:フランシス・F・コッポラ
:ジョージ・ルーカス
監督:黒澤明
脚本:黒澤明、井出雅人 アドバイザー橋本忍
監督部チーフ:本多猪四郎
撮影:齋藤孝雄 協力 宮川一夫
武家作法:久世竜
配役
武田信玄、影武者の男:仲代達矢
武田信廉:山崎努
武田勝頼:萩原健一
近習土屋宗八郎:根津甚八
山縣昌景:大滝秀治
馬場信春:室田日出男
跡部大炊助:清水綋治
小山田信茂:山本亘
田口刑部:志村喬
医師:藤原釜足
お津弥の方:桃井かおり
於ゆうの方:倍賞美津子
織田信長:隆大介
徳川家康:油井昌由樹
1980年5月 日比谷映画劇場にて初鑑賞
⭐️4.0
戦国スペクタクル絵巻
TSUTAYA discasで見ました 昔見たかどうか定かでなく今回しっかり見ました 重厚な作りですね 前半から中盤までは信玄が亡くなり影武者をたてる 信長、家康という敵対勢力の反応などが描かれています この辺り3人の勢力分布や時代背景などがわかっていないと ストーリーに入っていきづらいと思います 自分は日本史好きなので問題無しです 後半は勝頼が後を継いで 信長家康連合軍との対決 長篠 設楽が原の戦いが描かれています これだけの馬と火縄銃そして武士たちの甲冑や武具などの装備を用意したのはすごいですね 他の映画ではムリではないでしょうか たくさんの馬を乗りこなせる人々もいなければならないわけです 信長と家康の配役はあってましたね 家康も良かったし特に信長は良かった 敦盛を舞うシーンは素晴らしい ただこの2人を演じた俳優さんの名前はわかりません まあこの作品は日本史や戦国時代などが好きでないと入っていけないですよね 自分はその点はクリアです 面白い映画というよりは黒澤監督が描きたかった戦国時代の空気を描いた趣味の作品という感じ でも映画というのは本来ははそうであって監督のものなんでしょうね
CG技術が到達点を迎えた今、リアルの良さを再発見、こういった大掛かりな撮影ができる日本映画にお目にかかる機会はなさそうですね。
惜しまれつつ25年7月27日(日)閉館を迎える丸の内TOEIさんにて「昭和100年映画祭 あの感動をもう一度」(3月28日(金)~5月8日(木))と題した昭和を彩った名作42本が上映中。本日は黒澤明監督『影武者』(4K版)を鑑賞。
『影武者』(1980/180分)
黒澤明監督が『椿三十郎』(1961)20年ぶりに手がけたスペクタクル巨編時代劇。
CG技術の進化で何でも自由に表現できる昨今、本作での数千にもおよぶ実在の足軽や騎馬隊の軍勢の動きはコンピューターで計算された動きではなく、実在する兵の一人ひとり、馬の一頭一頭が自由に躍動、リアルな迫力で思わず画面に惹き込まれてしまいます。
CG技術が到達点を迎えた今、リアルの良さを再発見、こういった大掛かりな撮影ができる日本映画にお目にかかる機会はなさそうですね。
撮影方法はワンシーンワンカットの数分にもおよぶ長回しですが、画面奥に微かに映る人物や天候、小道具など徹底的に細部までこだわった構図は絵画のようで180分の長編にも関わらず緊張が途切れることがありません。
キャスト陣も武田信玄と影武者の二役を演じきった仲代達矢氏は圧巻、傑出。
途中降板した勝新太郎氏の代役として急遽登板したとは思えないほどはまり役でしたね。
黒澤組常連の山崎努氏、大滝秀治氏の円熟味を増した演技のなか、諏訪勝頼役の萩原健一氏、土屋宗八郎役の根津甚八氏のフレッシュな演技、特に織田信長役の隆大介氏が信長らしいギラギラした面構えが実に良かったですね。
風林火山!歴史の一ページが迫る!
やっぱり黒澤明はスゴいですね〜。BSで見たテレビ放送ですが、迫力ある画面に圧倒されました。
1980年の公開当時は、まだ黒澤作品に興味はありませんでした。カンヌ映画祭でグランプリを取ったと言っても、見ようというまでは、いかない。なにかの機会にって思いながら、今に至りました。
それにしても、黒澤作品の画面はホンっと大迫力で見応え十分です。
撮影中は、かなりパワハラだったって噂も聞いたことありますが、監督としてのプロ意識?自己顕示欲が強すぎたんでしょうね。
人海戦術の合戦シーンは、ホンっとスゴい。倒れる馬の演技なんて、どうやってやらせたんだろうってくらいに釘付けになっちゃいました。
ただね、全体的に長い。
なんで、こんなシーンに時間かける?
このシーン必要?
失礼ですが、こんな風に思うところがいくつかありました。面白いことは面白い。でも、本当に楽しめる映画って、短く感じることが多いですよね。
面白いとは思うけど、好きではないって感じです。もう見ることはないかな。
まぁ、何年か経って想いが変わることがあるかもしれませんが・・・
黒澤渾身の時代劇
原作脚本、黒澤明。
海外版プロデュースにフランシス・コッポラとジョージ・ルーカス。
【ストーリー】
男はコソ泥。
ある夜忍び込んだ先で捕縛され、死刑を待つ身であった。
その折、三河野田城攻めで信玄が銃弾に斃れる。
死のまぎわ、信玄は「我が死を三年かくせ」と言葉を遺した。
息子の信廉は、信玄と瓜二つの男を影武者に立て、遺言を守る。
男は上手くたちまわり、武田の家はどうにか再興の道すじをゆく。
武田家に傾倒してゆく男だが、落馬した際に川中島で上杉謙信よりつけられた傷がないことで、影武者と露見する。
武田信玄には影武者伝説がいくつもありまして、それらを巧みに使って、栄枯盛衰のドラマに仕立てたのがこの『影武者』です。
圧巻なのが、織田の鉄砲隊と武田騎馬軍の衝突。
三段構えの鉄砲隊が、次々と騎馬を粉砕してゆく場面は、画面の迫力も相まって、忘れられぬ切ないシーンになってます。
今の学説によると三段構えの鉄砲隊は、後の世の創作だということになってます。
実際の話に話題を広げますと、影武者というのは本当にいたそうで、大体の武将が使っていたとか。
フィクションのようなドラマチックな使われかたではなく、武将ごとに複数いたとか。
武将と同じ装束で、戦場のあちこちに影武者を配し、
「われこそは軍団の将なり! ここが本隊であるぞ!」
とあからさまにアピールして敵を撹乱したり味方を鼓舞したりしてたそうです。やべえかしこい。
コッポラとルーカスは、昔からクロサワ好きで知られた面々なので、ファン参加枠?(笑)
悲劇の傑作も数おおい黒澤明ですが、スケール感と切なさの同居では、自分はこの『影武者』を推します。
海外版推奨
お行儀の良い歴史物は苦手だが、これは観れた。
黒澤明監督作品で観るのは二つ目だ。
80年代に入ってなお、新鮮でダイナミックな映像を撮り続けられるのは流石黒澤明といったところだろう。
衣装など、若干の違和感はあれど、内容の邪魔になるほどではない。役者の演技もそれぞれに良かった。特に、信長が良かった。今まで観た信長の中で一番信長らしかった。
姫路城を安土城に模しているのは笑えた。その他、姫路城が若干出てきて、姫路出身なので、少し嬉しかった。
史実と違うところは実際は3ヶ月でバレたらしい。
ネックになるのは、長すぎることと、音楽の主張が強すぎることだ。長すぎるのは、例えば上杉謙信のシーンは本当に必要か?全くストーリーに関わらず尺を取っただけだ。いくら日本人にとって信玄と謙信はセットだとしても、そのためだけに映画に入れるのは無駄だと言わざるを得ない。又、リアリティを出す為に段取りをカットせず、長回しで撮っているが、黒澤監督のやり方で、多くのカメラを用意しワンカットで一気に撮るというのを今作でもやっているからこうなったのだろうが、そんなに興味の持てないところまで見せる。ジャンプカットしても良かったのではないか?でも、それをやると歴史大作感が出ないのかもしれない。だから、僕は歴史大作が苦手だ。そういう人には勧めにくい。と、書いていたが、調べてみると、実は日本で公開されたものは未編集版で、海外では上杉謙信などのシーンはカットされているらしいが。黒澤明が編集する前に早く利益を出したい東宝が無理やり公開したのが日本版らしい。それなら黒澤明は悪くない。と、言うわけでできれば海外版をどうぞ。
ちょっとやりすぎ
この映画を創った人の命を感じる。
2度目の鑑賞。 黒澤監督のこだわりを随所に感じた。 仲代達矢扮する...
影武者として生きる一人の男の苦悩、 それを知っている臣下たちの苦労、 織田信長や徳川家康の武田信玄に対する畏敬や畏怖などを 179分間で表した映画である。
BS-NHKで映画「影武者」を見た。
劇場公開日:1980年4月26日
1980年製作/179分/日本
配給:東宝
仲代達矢48才
山崎努44才
萩原健一30才
根津甚八33才
大滝秀治55才
油井昌由樹
室田日出男43才
黒澤明監督・脚本70才
フランシス・フォード・コッポラ
ジョージ・ルーカス
製作総指揮
黒澤明監督の晩年の一本だと思う。
2023年の今から450年前の西暦1573年に
武田信玄は城内で鉄砲に狙撃された。
信玄は京都に入るという野望叶わずして命を落とした。
臣下たちは信玄にそっくりの盗人を影武者として使うことにした。
信玄として屋敷へ戻った影武者は、
幼い息子や側室たちにもニセモノと見破られることはなかった。
また評定(会議)の場においても信玄らしく振舞って場を収めるなど、
予想以上の働きを見せた。
これは影武者として生きる一人の男の苦悩、
それを知っている臣下たちの苦労、
織田信長や徳川家康の武田信玄に対する畏敬や畏怖などを
179分間で表した映画である。
満足度は5点満点で4点☆☆☆☆です。
映像は素晴らしいが長過ぎる(180分)上に、感動が薄い。
1980年。黒澤明監督作品。
外国版プロデューサーにフランシス・フォード・コッポラとジョージ・ルーカス。
カンヌ映画祭パルムドール受賞した。
アカデミー賞外国語映画賞と美術賞を受賞した。
配給収入は27億円でこの年の邦画第一位をたたき出した。
黒澤明監督はこの作品の前に「乱」を監督したかった。
製作費が膨大で実現が難しかった。
そこに「影武者」の企画が来て、まるで「乱」の予行練習のように、
この作品を先に監督したのだった。
実は私も、数日前に「乱」を観ました。
たしかに合戦の映像は酷似してきます。
聞けば、鎧、甲冑、鉄砲・・・などを「影武者」で使った物をそっくり「乱」に使うと言う算段が黒澤の脳裏には初めからあったそうです。
素人の私が言うのもおこがましいですが、この映画、心打たれませんでした。
時代劇スペクタル。
たしかに2000頭の馬、エキストラ2000人とスケールは大きいのですが、
合戦・・・「馬を狙え!」鉄砲隊に敵将は告げます。
しかし馬を撃つ場面はない。
騎乗で侍が相対して刀を奮って戦うシーンがない。
地上でも兵士の兵士が刀を奮って殺し合うシーンは皆無なのです。鉄砲隊は一列に並び一斉に鉄砲を打ちます→馬から騎乗兵が落ちる→また落ちる。
そんな繰り返しです。
合戦は平面的で立体感はない、平板なのです。
人間ドラマとしても武田信玄の影武者の葛藤はそれなりに描かれますが、ドラマとして薄い。
ドラマティックな映画とは思えません。
良くも悪くも超大作。
黒澤明監督作品として、私はあまり感動がありませんでした。
底に流れるヒューマニズムなど、黒澤映画に流れるテイストが薄く残念な感じを持ちました。
黒澤明編集のverも見たい
影武者の悲哀と幻のような栄華
影武者は随分昔にDVDをレンタルして見て以来となる。先日テレビで放映されていたのを録画して、2度目の鑑賞の機会に恵まれた。
見るにあたって、よく黒澤監督はカラー時代の作品を酷評されるから、それがなぜなのかということも頭の片隅に置いて鑑賞した。通して見た結果、観客側の気持ちを盛り上げようという姿勢が、モノクロ時代から比べてあまりないような気がした。あと誤解がないように付け加えたいが、だからといってこの映画がつまらない映画かというとそういうことではない。
むしろ私はこういう映画は好きな方だ。
これは私の勝手な推測だが、カラー作品である影武者を見ていると、より多くのモノ(あるいは情報)を画角に収めようとしているように感じた。映画が合戦モノだからかもしれないが、同じ合戦モノである七人の侍はもうすこしカメラはミクロに寄っていたように思う。あと、役者の立つ位置や動くときの導線、カメラの位置など含めた、構図全般に対して、より神経を使っているような印象だった。
とするとそれはどういう理由からきているのか、、、フィルムがモノクロだった時代からカラーに変わり、色というものをどのように料理すべきかという模索の最中にあったのかなと思えてならない。
結果的には、ドラマで客を盛り上げる映画ではなく、監督の言いたいことを構図で表現しようとした映画だったように思う。個人的には、旧ソ連のタルコフスキーのような作風だなと感じた。
申し訳ないけど途中で消した
影武者の度胸と覚悟
黒澤明の、黒澤明による、黒澤明のための映画の一本
用心棒(1961年)、椿三十郎(1962年)、天国と地獄(1963年)と立て続けに傑作をものにし、赤ひげ(1965年)では朝日新聞の悪評を尻目にその年の日本映画の興行収入ランキング第1位を獲得し、いよいよ自信を持った黒澤明がトラ・トラ・トラ!(1970年)で、気心の知れた黒澤組の不在、東映スタッフを使いこなせない、ハリウッドシステムに合わせられないなどから首になり、精神不安定下で放ったどですかでん(1970年)が当然のことながら大こけし、大借金を背負った傷心の黒澤明は、酔っぱらった勢いで1971年12月22日に自殺遊びをしてしまう。5年後にソ連製のデルス・ウザーラ(1975年)、その5年後にフランシス・フォード・コッポラ、ジョージ・ルーカスの出資を仰いで満を持して放ったのが影武者(1980年)である。27億円の配給収入(1980年邦画配給収入1位)を上げ、黒澤明は見事に返り咲いた。馬鹿にされたハリウッドに見事に仇を討ったのである。ところがである。黒澤明の傑作は天国と地獄(1963年)までで、赤ひげ(1965年)以降は次第に面白くなくなったと思うが、この影武者(1980年)も同様に面白くないのである。朝日新聞に見開きで役者スタッフ募集の大広告を載せてスタートしたのだが、ストーリー、音楽、出演者、テンポのどれも魅力がない。最もいけないのは、画面の外の黒澤明演出圧力が役者を委縮させてしまっており、登場人物の溌溂さが全くないのである。話も陳腐で目新しさはない。合戦シーンも、映画的ダイナミズムより、黒澤明の好きな馬のほうを大切にしているような気の抜けた演出で冴えない。赤ひげ(1965年)から始まった、黒澤明の、黒澤明による、黒澤明のための映画の一本でしかないのである。これ以降、乱(1985年)、夢(1990年)、八月の狂詩曲(1991年)、まあだだよ(1993年)と続くが、楽しめる作品が放たれることはついになかった。
滅びの美学を壮大に描いた黒澤監督の映画美術
国内での評価は色々と論争が繰り広げられているが、個人的には面白く鑑賞出来て大変満足した。特に黒澤時代劇の色彩の映像美のみを論じるならば、これほどまでの創造性豊かな古典的造形美は、今の日本映画では他に求められないと感銘を受ける。黒澤監督ならではの美意識と表現力に圧倒されてしまった。それでも早い時期に撮影監督宮川一夫氏が途中降板したことを、とても残念に思い危惧していた。それが杞憂に終わり、先ずは一安心と言える。
確かに、この黒澤作品を期待外れの失敗作と評する文化人や一般観客の反応は、解らないでもない。と言うのも、これまでの黒澤時代劇の最大の美点であるストーリーテリングの面白さやアクションシーンのダイナミズムが、全盛期と比較して弱い。ここには、すでに齢70歳を迎えた巨匠黒澤監督の武田軍に寄せる人生観が反映されている。もはや勝敗の先延ばしに過ぎない影武者の使命感と悲壮感の入り混じった敗北者の虚しさが描かれていた。負けを認めず最後まで戦い抜く者の滅びの美学が、映画の様式美として表現されていた。その拘りに、完璧主義者黒澤監督の力量が集約されている。
主演を演じるはずであった勝新太郎との軋轢は、関係者の予想するところであったようだ。監督としての威厳と役者としての拘りの対立と齟齬は、両者以外ではどうにもできない。とても恨めしい出来事だった。もしもそのまま勝新太郎が演じていれば、彼の代表作になっていたに違いない。個人的には返す返すも残念でならない。
1980年 6月8日 日比谷映画劇場
全36件中、1~20件目を表示