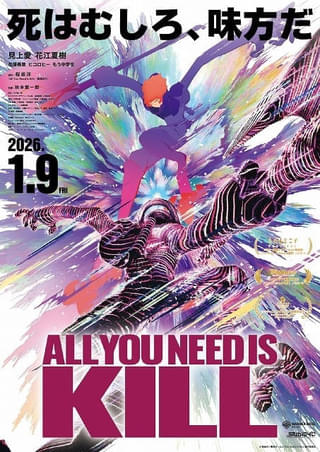オール・ユー・ニード・イズ・キル : 映画評論・批評
2014年6月30日更新
2014年7月4日より丸の内ピカデリーほかにてロードショー
メイド・イン・ジャパンの底力を感じさせる、ライトノベル史上初のハリウッド映画化
本作の舞台となるのは謎の侵略者「ギタイ」によって人類が危機に瀕している近未来。主人公であるウィリアム・ケイジ(トム・クルーズ)は、軍のプロパガンダを行っている広報担当の将校だ。
当の本人に実戦経験はなし。最前線への派遣を命じられた際には様々な言い訳を並べ立て、挙句の果てには脅迫まで行って命令を回避しようとするなど、トム・クルーズ史上他に類を見ない“腰抜け男”として描かれている。
そんな彼が悲惨な戦死をきっかけに無限の“タイムループ”に囚われ、やがて人類の命運を左右する存在へと成長していく。そのターニングポイントとなるのが、ループの秘密を知る“戦場の女神”リタ・ヴラタスキ(エミリー・ブラント)との出会いだ。

絶望的な状況下で、戦死を繰り返すたびにギタイの弱点へと迫っていくケイジとリタ。武器の安全装置すら解除できなかったケイジが、リタによる文字通り「死ぬほど辛い」特訓によって一流の兵士へと成長していく様は見モノである。
トムが序盤で見せた腰抜け演技が真に迫っていたぶん、中盤からクライマックスにかけてのアツい展開は彼の魅力をストップ高まで引き上げている。遠い“憧れ“ではなく、身近な“共感”を呼ぶ等身大のヒーローにもう夢中だ。
そしてループによって徐々に変化していくケイジとリタの関係性にも注目。安っぽい言葉で愛を語らうようなことはせず、必要以上にベタベタすることもない。しかし、それでいて2人が確かに強烈な“絆”で結ばれていくのを感じ取ることができる。ハリウッド流にアレンジされながらも原作に対するリスペクトを忘れておらず、確かに日本的な“情緒”を残した見事な演出には舌を巻くばかりだ。
大胆に変更されたラスト付近の展開も含めて、個人的にはハリウッド映画として“最適解”と言える仕上がりではないかと思う。メイド・イン・ジャパンの底力を感じさせる、この夏最高の娯楽映画を見逃すなかれ。
(マフィア梶田)