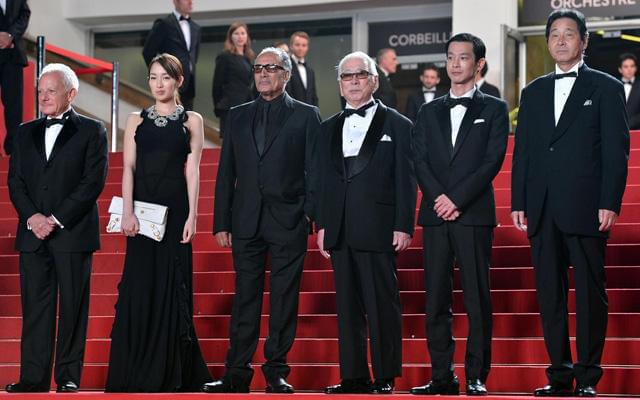愛と誠 : 映画評論・批評
2012年6月12日更新
2012年6月16日より角川シネマ有楽町、新宿バルト9ほかにてロードショー
猥雑でアモラルな雰囲気とオフビートな笑いに彩られた青春メロドラマ

高度経済成長期の只中で連載された梶原一騎の「愛と誠」は、ツルゲーネフの「初恋」、伊藤左千夫の「野菊の墓」、石原慎太郎の「青年の樹」などを本歌取りした、当時ですらかなりアナクロニズム臭が濃厚な純愛漫画だった。これを現代によみがえらせるにあたって、三池崇史はプロローグと終わりにアニメを使った<入れ子>風な語り口、昭和歌謡のつるべ打ちによるミュージカル仕立てというクセ球を次々に繰り出してくる。
だが、一見、原典を茶化すかのようなこの趣向はさほど奏功していない。すでに「カタクリ家の幸福」で露呈してしまったように、三池には画面に躍動感をもたらすミュージカル・センスが欠けているからだ。
ただし、不良の巣窟・花園実業高校に舞台が移ると、一気にボルテージが高まる。往年の東映の「恐怖女子高校」シリーズが純情可憐に思えるほど殺伐とした、異様にざらついた荒廃感が漂ってくるのだ。中でも、ガムコこと安藤サクラが好演で、いきなり誠(妻夫木聡)にキャンパスから下着むきだしのままに逆さまに吊るされ、以後、あられもなく誠にカミングアウトしてしまうのがおかしい。
一方、誠が並み居る大勢のスケ番たちを殴打しまくる場面などは、かつての「DEAD OR ALIVE 犯罪者」を思わせる、猥雑で、危ういアモラルな感覚で迫ってくる。さらに、オフビートな笑いと悲壮感たっぷりな母物メロドラマが微妙な均衡を保ちながら、着地点は、原作通り、究極の初恋神話の礼讃となる。三池崇史と、泥臭くて硬派な梶原一騎の稚気あふれるロマンティシズムは意外に相性が良いのかもしれない。
(高崎俊夫)