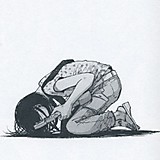ヒューゴの不思議な発明のレビュー・感想・評価
全138件中、61~80件目を表示
予想と違ったが・・・
もう少しファンタジー色の強い作品かと思っていたが、実在した映画の父的な人物へのトリビュートといった内容だった。そういう意味では、映画讃歌と少年と少女を主役にした冒険譚のどっちつかずになっているような気もして、アカデミー賞5部門を受賞したにしては物足りない印象。少女役の女優の笑顔がよかった。
タイトルも内容も意味不明。
心の修理
映画には、ヒューゴが機械人形を修理する、という大きな軸がある。しかし、本当の主題は、パパ・ジョルジュと鉄道公安官の心の修理である。彼らは心に傷を負い、荒んだ行動をとりがちであったが、ヒューゴとのやり取りを通して、人間らしさを取り戻す。ヒューゴは知らず知らずの内に、たいそれた事をやり遂げたのだ。
終始、おとぎ話を聞いているような、映画の雰囲気感がよい。登場人物一人一人に、丁寧にスポットライトが当てられている。完成度の高い作品ではある。
ファンタジーじゃなかった
不思議でもなければ発明でもない。誰だ邦題つけたの。
推理物でもどんでん返し物でもないのに、ストーリーがどこに向かっているのか焦点がぼやけていて脚本の完成度が低い。
キャラや映像は悪くないし、最後の実在する監督のくだりも興味深いので、それだけに残念。
切なくも感動
良かったですよ 邦題が悪いだけ
美しい映画です。
何といってもメカニカルな動きが素晴らしい!!
少し鉄道保安官?が少し鼻につくけれど他の登場人物は微笑ましい。
(悪人か善人か中途半端・・・・)
皆さんも書かれていますが、邦題が悪すぎ・・・・・
映画の映画なのに発明の映画と勘違いしますね。
そのため評価が悪すぎるのだと思います。
映画って本当にいいもんですね
映像を楽しむ作品
子役が美少年と美少女だから見れた
タイトルのネーミングが、、、
残念ながら引き込まれなかった
で・・???
万人の心の中の大切な子供心を再起させる秀作
巨匠とは言え、歳にはやはり勝てないのだろうか?
M・スコセッシ監督と言えば、私の中では、『タクシードライバー』を始めとし、『ニューヨークニューヨーク』『レイジング・ブル』などR・デニーロとのゴールデンコンビで撮影された作品が印象に残っている。
それらの作品の多数は、どちらかと言うと男性的な躍動感溢れる、痛快な画面で、熱く人々を魅了してきた。
ニューヨークの街、人種のルツボと言われるその街に起こる人々の多様な生き様を、臨場感有る映像を映画史にいつも創り上げてきた彼だ。
そんな、くせ者のスコセッシ監督ならではのカラーが溢れる群像劇が私は好きだった!
我が国日本では、黒澤監督がやはり、男臭いエンターテイメント映画を数多く制作してきたのだが、晩年は、『夢』などにみられるようフェミニスト的な、愛や夢と希望を真向から描き出した作品へと作風が変化した様に、スコセッシ監督も本作の様な可愛らしい、ファンタジー映画を作る様になったので驚いている。
しかし、そう言えばスコセッシ監督と黒澤監督はとても親交が深かったようなので、或る意味似たようなセンスを、同人は根底に持っているアーティストなのかも知れない。
主演のヒューゴを演じるエイサ・バターフィールドも『リトル・ランボー』でも個性的な少年を演じていたし、『縞模様のパジャマの少年』も見事な映画を頑張って演じていた。
イザベル役のクロエ・モレッツと彼が同年生れには見えないけれど、この2人の芝居の巧い子役を起用した事で、この映画は格段に出来が良くなったと思う。
ヒューゴとイザベルが裏口から映画館に忍び込んで、サイレント映画の名作を楽しむ辺りは何故か『小さな恋のメロディー』を思い出させるが、このシーンも監督の映画に対する熱い思い入れが強烈に感じられる。
ベン・キングスレーがメリエスを演じるのも何故かシックリとハマっている感じがして良かったな。『月世界旅行』を私は観ていないので、是非とも観たくなった!
ジュード・ロウがヒューゴの父と言うのも予想外に思える配役だが、良かったと思うし、何と言っても、映画をこよなく愛し続けているスコセッシ監督の映画へのオマージュ作品である本作ならではの目玉のキャスティングで、ピーター・カッシングと共に『ドラキュラ伯爵』シリーズや『フランケンシュタイン』などのホラー映画で、時代を風靡したあの名優クリストファー・リーを久し振りにスクリーン登場させてくれたのも見逃せない!
3Dにする必要価値が本当にあったか無かったのか、賛否の分かれるところだが、監督としては、常に新しい技術の工夫を凝らして、映画ファンを楽しませられる次回作を制作し、その為に、日夜研究し続ける情熱こそが大切なのだと言う監督の映画哲学が表れている作品なのだと思う。映像的には物凄く綺麗で、ファンタジー映画として気品が有り良かった。話しの展開に少々無理が有っても本作はファンタジーなのだ、野暮な事は言うまい。
邦題を変えた方が良い
ストーリーが弱い
一切の情報なしで観た
配給会社さん、タイトル詐欺はいけない
おかげでいつヒューゴが不思議な発明をするのかと、ミスリードされてしまったじゃないかw
映像は文句なく美しい、3Dで鑑賞したらさぞや素晴らしかったろう
『アバター』もそうだが、2Dと3Dで戦略的に効果を考え、ストーリーを単純化する傾向があるのかなーと思った
映画としてはストーリーの薄さが哀しかった
ヒューゴが孤児で、駅に住んでいて、玩具屋からメカを盗んでいる、そういう事がわかるまで十分以上かかる(映画パンフの最初には書いてあるんだろうが)
いきなり泥棒呼ばわりされ、大切な手帳を取り上げられるまでの流れが意味不明だし、何も言えない主人公の顔が恐くて引いた
後半はちょっと盛り上げては肩すかしというパターンの連続で、中途半端なカタルシスしか得られないので正直退屈した
古典映画にノスタルジーがない人間には「えっ、ヒューゴパパの話は? あれで終わり?」的なガッカリ感がつきまとう
ヒロインパパの栄光と挫折を禁忌的な「悲劇」に見せて興味を引っ張るやり方は、視聴者に不誠実ではないか
フィルムを見付けて、「パパもママも元気にさせてあげよう!」という、お決まりの子供パワーみたいなものもあんまり前に出ていない
家族連れの視聴者は楽しめたのだろうか
映画の素晴らしさを謳うなら、この作品自体のエンターティメントの部分もキチンと製作すべきではなかったのか
普通の映画として考えた時には、中途半端にリアルで、ハメを外すバカが一人もいないのでワクワクできないし、観た後も不完全燃焼な感じの残る映画だった
全138件中、61~80件目を表示