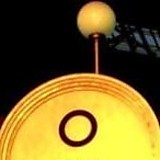わが母の記のレビュー・感想・評価
全59件中、21~40件目を表示
すれ違った母の想いと息子の想い
樹木希林さんの演技が圧巻でした。「しろばんば」や「夏草冬濤」で描かれていた勝気で厳しくユーモアからかけ離れた八重と樹木希林さんの印象は私の中では少し異なるものではありましたが、程よく力を抜いたような演技なのか地なのかわからない樹木さんの演技は私の中の八重像を変えていきました。
親に捨てられたとずっと思い続けていた洪作と戦中の混乱の中、実父の妾であるおぬいばあさんに洪作を預ける決断をしなくてはいけなかった八重。洪作が八重の本当の気持ちを知った場面は涙目なしでは見れません。
洪作が幼少期に過ごした湯ヶ島とおぬいばあさんや本家との関係、その時の洪作の目に映った八重や家族の、青年期に過ごした沼津での様子がもう少し丁寧に描かれていたらより良かったです。登場する人たちの会話の中で触れてはいましたが、「しろばんば」「夏草冬濤」を読んでいない人にとっては、洪作と八重の関係や想いを知るには十分ではないような…。
認知症に罹患してからも息子を想う母の気持ちに涙溢れる。故、樹木希林さんの代表作の一作。
こりゃ泣くわ…
親子というもの
おばあちゃんに会いたくなります。
伊豆
きききりん
母の愛
『わが母の記』
もの書きを題材するハンデは親近感が得られないとこなのよ。
一般家庭や一般社会からちょっとズレてる、観てて感情移入し難い。
これを逆手に取ったのか、そこが巧かったねこの監督は。
長く見せないでスッと切り替える、対面の使い方なんかも絶妙でした。
オープニングの小津安二郎へのオマージュのシーンに内田也哉子が出演してる、これが本当にバッチリでね良かったです。
浮草の匂いをさせながらもちゃんと紀子が出てくるしね。
樹木希林の十八番芸が炸裂、神の領域の演技はもう溜め息モノ。
言わずもがなこれと渡り合えるのが役所広司なわけですよ。
脇役陣も赤間麻里子、キムラ緑子、南果歩、遺作となった三國連太郎と実力派、技巧派が文句なしの演技を魅せる。
食堂での橋本じゅん、大久保佳代子の二人も良かったですよ。
こういうシーンなんか小津映画の匂いはしない。
この映画は原田映画ですよ。
良かった。
意外と面白かった
母と息子
見事な演技で魅せる
総合70点 ( ストーリー:65点|キャスト:85点|演出:80点|ビジュアル:70点|音楽:70点 )
井上靖の自伝的小説の映画化だそうで、彼の家庭人としての人柄に加えて、複雑な家庭環境の少年期の出来事とそこからくる彼の屈折した感情が垣間見れて興味深かった。
特別大きな物語ではない。昔のことならこのような親子関係なんてどこにでもあっただろうし、井上靖が小説家だったからこそこのくらいの話でも物語として成立したのだろう。だがこの作品の見所は登場人物の演技だった。樹木希林・役所広司・宮崎あおいの親子三代の、単純に家族愛の溢れているとは言えない一筋縄でいかない関係と感情を見事に演じていた。子供を手放したという悔い・家族に捨てられたという思いと互いに頑固な父娘が地道にぶつかりあう。小説家として大成した後でも、少年時代の心の傷が消えずにいる。時の経過とともに母への想いが変化していく過程が、一つ間違えば退屈なだけの話も役者の力によって上手に表現されている。派手さを避け物語を淡々と進行させ音楽の使用も最小限に抑えた演出も、地味だけどこの作品には合っていると思う。
和解
命が消える前に握った手は、暖かかったのか。
東京へ戻る際、寝たきりの父親が枕元で挨拶する井上に手を伸ばしてきて、その手を握った井上。大作家になった井上を褒める為に手を伸ばしたのか、それとも何か違う言いたいことがあったのか。その東京に帰った日に父は死に、もう判明することのない謎です。
父の死の知らせを聞いて、何となくの喪失感と共に吹き消した明かり。明かりを覆い息を吹く。かざした手に感じた仄かな暖かさは、人肌を思い浮かべることができるほど似通っていた。非常に文学的です。良いシーンだと思います。
『自分が捨てられた』と根強く持っていた母とのわだかまりも、母が過去を忘れていくことで何となく解消される。年月の経過で、母への態度も軟化していきます。それだけではなく、過去を忘れて耄碌していく母は自分の記憶のガードを緩めていき、はっきりした意識では決して言わなかっただろう事を口に出す。長年のわだかまりや不満も一気に氷解し、涙する。理想的な和解。こんなことが現実にあるなら……苦労しません!!ですが、現実にあったことなんでしょうね……
惚けが良い方に向かった例です。悪い方へ向かった例が沢山ある中で燦然とかがやく一例。
かつての家長を支える家族という像が劇中ずっと続きます。玄関まで妻が帰りを迎える、着替えを手伝う、などのシーンは今にないことです。時代が進むにつれて、そんなシーンも無くなっていくのが時代の変遷を感じさせます。最後のシーンでは一人で着物を着ていましたし。そういうところが映画として上手い。
井上は結構気難しい男のようです。しかし、子供のことも気にかけて「大きな声出してないだろ!」→「大きな声出してすまなかった」と謝るシーンは理不尽ではない父親像を描き出していていいですね。
次女がハワイに洋行、というシーン。いやあ、さすがに金あるなあ、と下衆い感想を抱きました。そりゃあ、ベストセラー作家ですもんね。あの時代にハワイに留学する娘(!)の為、一家でついて行き(!)、船の出港時刻に遅れそうな者には飛行機で来ればいい(!)なんて、セレブです。
シーン上ちょっと粗いと思ったのは三女琴子が運転手に告白するシーン。小説にこのシーンがあるのなら、やっぱりそのことをしった井上が後ほど想像で書いたシーンだからか少し唐突。映画だけのシーンなら、それまでのエピソードが小説準拠だったため、粗が目立つのか。
全59件中、21~40件目を表示