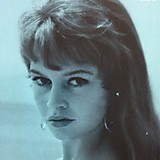東京家族のレビュー・感想・評価
全93件中、41~60件目を表示
家族を見つめ直すまでは…
そこまでは考えなかった
ちょうどああいう両親がいる世代が見れば、グッとくるのかもしれない
橋爪功の演技が良かった。本当に初めて東京見たような表情とか。なんか終始泣きそうになったのも、彼の演技の凄さだと思う。
あのザラついた画質に妻夫木と蒼井優がよく合ってた、透明感が伝わってくる
内容的には結構あっさりしてたかなというか、深さはなかったかなと感じた
滋子と紀子が好きじゃない
「シコふんじゃった。」から日本アカデミー賞受賞作品の流れで鑑賞。
・・・超ちんちくりんだった( °д°)
長女の滋子さん、ああいうタイプって超苦手。そればっかり考えてしまった。仕切りたがりで、話が長くて、口うるさくて、常に自分が正しいと信じて疑わなさそうで。あなたの価値観=世の中の価値観、じゃないですよ!って言ってやりたくなる。言っても響かなさそうけど。
一番のもやもやエピソードがこれ。
田舎からわざわざ出てきた年老いた両親は、長男の幸一と滋子が手配した高級ホテルに二泊するはずが、雰囲気と合わず一泊で帰ってきてしまった。その二人に対して、滋子は「今夜はうちにいられたら困る」なんて言い放つわけ。商店街の飲み会がどうとかご飯作ってあげられないとか。さすがに言わないでしょ。近所付き合いにどんだけいっぱいいっぱいなのでしょう。夜中までうるさくてごめんって言って、とりあえず出前でも取ってあげればいいじゃん。
そもそもホテルに泊まらせたのだって、いつまでも田舎に帰る日を言わない両親の相手が少し面倒くさくなってきたとかそういう理由っぽいし。まぁわかるけどさ、彼らにも彼らの生活があるから。とはいえ東京のこと右も左も分からない人たちに対して冷酷すぎて引く。
観光に連れて行こうともしてたけど、両親が何したいかとか、どこ行きたいかとか、一回でいいから本人たちに聞きましたか?って感じ。意見を聞いてから持て成せよ。もやもや。
ラストでも、病院では誰より激しく泣いてたし、「お父さんどうするの?」ってしきりに聞きはするけど、具体的にどうしようとか、嘘でも「うちに来たら?」とかは一切言わないし。結局さ、他人の心配しているふりして結局自分のことしか考えてない人。
あー、滋子が嫌い。どこまでも。笑
あと蒼井優が義両親(まだ結婚してないけど)にちょいちょいタメ語なのも超違和感だった。そもそも義両親じゃなくたって、初対面でめっちゃ年上の人に「大丈夫よ」とか言わないと思う。蒼井優は好きだけど、今回の役は全然魅力的じゃなかったから残念。
こういう古き良き日本の家族、って感じの映画、好きだったはずなんだけどなぁ。
ついこないだ観た「ALWAYS三丁目の夕日」シリーズは全部大感動だったから、時代云々じゃないんだろうな。この家族はなんとなく苦手だった。
東京物語のリメイクということで。 昭和のよき日本、人間模様を描いて...
確かに現代っぽい
上京してきた両親を東京に住む子供たちが迎えるっていうよくある光景を現代版でアレンジした作品。
普通、せっかく田舎から両親が来てくれたから家族皆で集まってもてなすっていうイメージだけど、映画では仕事で忙しい子供たちが東京に来て何もする事が無い両親を持て余すって言うような内容になってる。
もうちょっとちゃんと両親もてなすだろって思うところもあるが、登場人物の心情等結構リアルに描かれてて多分実際両親が上京してきたらこういう感じになるのかなって言う風に思わせて、今の仕事で忙殺される東京の人だったり家族の絆が希薄になっている現代を上手く描いている作品だなと感じる。
個人的にも今の東京の人は皆忙しすぎるし、常に努力して向上していかないとっていう状況にあってあまり余裕がなく、もっとゆったりした生活も必要なんじゃないかって感じてるので、今の自分に微妙にマッチした作品だった。面白いかって言われるとそこまで面白い作品ではないけど、胸には響く作品。
妻夫木くんの演技がすき
優しさと忙しさ
小津より泣ける感が多かった。
親孝行の基準って!?
邦画の良さが出てます。
名作と震災
この映画の元となっている小津安二郎監督の60年前の作品は世界中の映画人に愛される。なぜだろう。この答えを探しつつ鑑賞した。低いアングルからの画像。何気なくびっしり何か様々な生活道具。家族はいつかチリジリバラバラとなるのを予期させる身勝手な個々の言動。東京と瀬戸内海では明らかに異なる時間の流れ。山田監督やカメラマンたちはその何気ない風景などを音とともに静かにしかもシッカリ撮影し記録している。結果、人間の壊れやすい体質が暴露される。例えば老父、息子、娘や親族たちも全てが不完全な性格を宿したまま平然と生きている。老母のありがとうの言葉は相変わらず響きが美しいが。 ところで、老母の突然の死は東日本大震災の悲劇に直面しなければならない私たちに突きつけられる刃のごとし。家族は死を上手く引き受けることが出来ない。震災以後は絶望でなく「希望」が大切なことも再度痛感しました。
考えさせられる・・・
こうして空でも眺めてるしかなかろうが・・
映画「東京家族」(山田洋次監督)から。
親はいくつになっても親だから、子どものことが気になる。
だから、3人の子どもに会おうと夫婦で上京したにも関わらず、
子どもたちは自分の生活で精一杯、久しぶりに会った両親を、
素直にいたわれない現実が、待っていた。
みんな一所懸命生きている、それは親に伝わるが、
やはり夫婦の感じた淋しさは、隠し切れなかった。
親子の絆って、人間関係の一番基本的なところにあるのに、
なかなかうまくコミュニケーションがとれないもどかしさがある。
どこにでもいる家族、どこにでもある日常生活、
そして突然の母の死という出来事をを通して、
その理想と現実とのギャツプが、映し出されていた。
楽しみにしていた子どもたちとの再会と、のんびりした時間は、
影も形もなく、東京の空の下、老夫婦だけとなりふたりは戸惑う。
妻が「どないする?」と問いかければ、
夫が「こうして空でも眺めてるしかなかろうが・・」と答える。
「ええ天気じゃねぇ」と言いながら、なぜか淋しさが込み上げる。
私が一番、印象に残ったシーンである。
横浜の高級ホテルに泊まれることで喜ぶと勘違いしている子ども、
それを口に出さず、黙って受け入れる親。
忙しいのはわかっている、でも、もう少しゆっくり話したい、
それが3人の子どもを育て上げた親の気持ちだろう。
家族愛、親子愛、夫婦愛・・
山田監督は、どれを一番伝えたかったのだろうか。
全93件中、41~60件目を表示