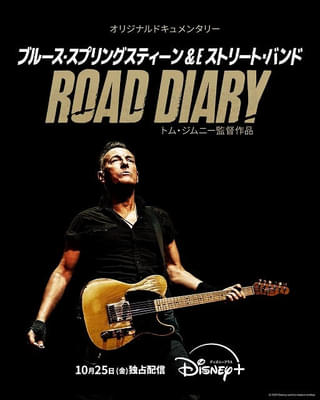クレイジー・ハート : 映画評論・批評
2010年6月8日更新
2010年6月12日よりTOHOシネマズシャンテほかにてロードショー
風景と溶け合うブリッジスのたたずまい。役者の映画はやはりしぶとい

「小さな映画に大きな俳優」という言葉が頭をよぎった。「役者の映画はしぶとい」という感想も浮かんだ。ありきたりな意見に聞こえるだろうが、そもそも「クレイジー・ハート」自体が常套句に満ちた映画だ。にもかかわらず、ただの紋切型とは片づけられない匂いがこの映画には漂っている。なんだろうか。
映画の主人公は、バッド・ブレイク(ジェフ・ブリッジス)というカントリー歌手だ。効かないブレーキという名前が笑わせるが、57歳のブレイクはとっくにピークを過ぎている。舞台はアメリカ南西部。酒場で歌い、ボウリング場で歌って、翌朝は名前も知らぬ女と安モーテルで目覚めることが珍しくない。声は嗄れている。腹は出ている。酒はやめられない。そして彼は、娘ほども年のちがう女(マギー・ギレンホール)と出会い、疲れた人生に絵具を塗り直そうとする。
よくある話だ。が、ブリッジスはブレイクにひがみっぽい眼をさせない。甘えた溜め息をつかせないし、しくじったときは過ちをきちんと認めさせる。すると、紋切型の陰から体温とハートとプライドを備えた男の姿がゆらりと立ちのぼってくる。観客も、ブレイクがセコい男ではないことに気づく。
私の見るところ、ブリッジスは「ビッグ・リボウスキ」以来の入念な芝居をしている。好みでいえば、アホと放心を体現していた「リボウスキ」に軍配を挙げたいところだが(本当はあの映画でオスカーを受けるべきだったと思う)、傷ついた熊を連想させるブレイク役も、記憶に残るものであることはまちがいない。カントリーの節まわしと南西部の風景とブリッジスのたたずまい。話は月並みでも、三者が溶け合う際の不思議な化学変化はけっして陳腐ではない。
(芝山幹郎)