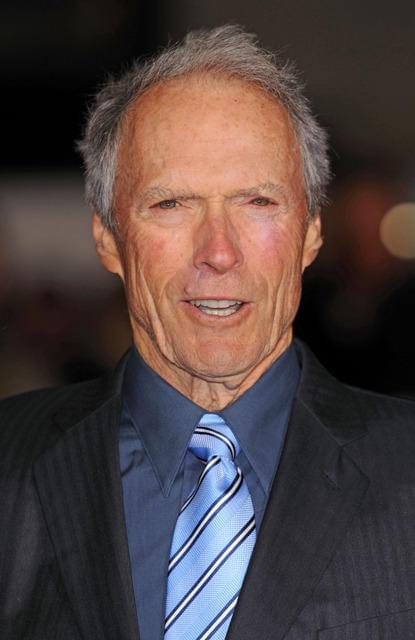久々にこれぞイーストウッドと呼ぶに相応しい作品である。今回は俳優イーストウッドとしてもまさしく集大成と言える役柄を演じており、監督=主演作として文句無しに最高傑作であると言い切りたい。
この映画の中で彼が演じる主人公のウォルト・コワルスキーは、イーストウッドと完全に同世代の人物であり、アメリカ合衆国盛衰の歴史を全て自分の眼で確かめて来た人物である。
朝鮮戦争に参戦しそこで苦い経験を味わった後は、デトロイトでフォードの自動車工として働き、結婚して家庭を築き平凡ながらも幸福な人生を送って来たことが、この老主人公の自宅にある想い出の品々から容易に想像出来る。
しかし定年後の時間が余りにも長過ぎた。自動車産業の街デトロイトは既に衰退し、 近隣からは白人住民が居なくなり、変わって増えて来たのは黒人、ヒスパニック系、アジア系移民といった様々な人種であり、彼等がギャングもどきの争いを繰り返しており、近隣の治安は悪化の一途を辿っている。しかしながら戦場で地獄を味わい尽くしたこの頑固一徹の老人は、その地から微動だにせず、仮に他人が一歩でも自分の敷地内に足を踏み入れようものなら、 M-1ライフルの銃口を相手に突きつけ、人種差別と偏見に溢れた最悪の言葉を放つのであった。
映画はこのウォルトの愛妻の葬式から始まる。葬式に参列した息子たち、孫たちとも一切コミュニケーションが取れず、悪態の限りを尽くし、早々に彼等を追い払うのだった。
今やこの男の楽しみはと言えば、家屋の修繕か庭の芝刈り後に、あたかも西部劇映画の主人公であるかのように、愛犬の横で庭のポーチにある長椅子でくつろぎ、煙草を吹かし、次々と缶ビールを飲み干しつつ、米国自動車産業全盛時の象徴であり、当時自らが製作に携わり今も新車の如くピカピカに磨いている愛車(1972年製のフォードのグラン・トリノ)を眺めることぐらいなのであった。
恐らくは映画史上もっとも汚らしいセリフの数々が、主人公の口から次から次へと吐き捨てられる映画であり、ある意味壮観ですらある。世間から完全に孤立した一匹狼であり、低い唸り声を発しながら絶えず怒りを内に秘め、口をひん曲げ、汚らしい唾を地面に吐き捨てるこの映画の前半部分の主人公の行動は、イーストウッドの第一の師匠であるセルジオ・レオーネ監督の下で主演した3本のマカロニウエスタンやその後ハリウッドへ戻り、第二の師匠であるドン・シーゲル監督作品を中心とした数々の西部劇やダーティハリー等の刑事物でイーストウッドが好んで演じて来たあのイメージをそのまま踏襲している。
そんなある日、アジア系移民のギャング・グループが、ウォルトの隣に住む従弟の若い少年に、例のグラン・トリノを盗むよう命令したことから事件が持ち上がる。
この事件をキッカケに、隣に住むアジア系移民(モン族)のこの少年とその家族との交流が始まっていく。初めのうちは干渉されることを拒み悪態をついていたものの、次第に彼等の純粋さや思いやりに気付き、心を許すようになり、いつの間にか偏見も無くなっていくのだった。そして本当の身内の人間以上に、この人種も習慣も全く異なる人々の方が、却ってウォルトにとっては家族のようにさえ思えるようになっていたのだった。
この辺りの老主人公の心の変化の過程が、説得力を持って描かれており、思わず引き込まれてしまう。1960年代半ばから1970年代後半頃迄にイーストウッドが好んで演じて来た前記一匹狼的な役柄から、徐々にそれ以降のイーストウッド映画にしばしば登場して来た新しいタイプの主人公像・・・柔和でユーモアを解し、汚いジョークを放ち、いつも飲んだくれている憎めない主人公・・・「ダーティファイター ('78)」、「ダーティファイター 燃えよ鉄拳('79)」、 「ブロンコ・ビリー ('80)」、そしてついには「センチメンタル・アドベンチャー ('82)」のイーストウッドへと変貌していくのだ。
ウォルトは、この職もなく学校へも行けず、絶えず悪の道への誘惑に惑わされつづけている根は純真な少年をなんとか一人前の男へと成長させようとし、そこに今自分が生きている意義を見い出していく。この血の繋がっていない少年との父子のような心の交流は「センチメンタル・アドベンチャー」に始まり、飲んだくれて悪態をつくダラシナイ男ではあったが、同時に新米兵にとっては逞しい上官でもあり得た「ハートブレイク・リッジ/勝利の戦場 ('86)」における軍曹役を想い出させる程であり、映画を観ているこちら側はとても心地良い気分になって来る。
やがてギャング・グループの応酬が激しくなり、 少年とその家族の命までもが脅かされ彼等が酷い虐待を受けたその時、ウォルトが取った最後の行動は一体何だったのか?
ここでイーストウッドは、前記第二の師匠であるドン・シーゲル監督作品であり、あの名優ジョン・ウェインが自ら長年に渡って演じ続けて来た数々のヒーロー役と、俳優ジョン・ウェインとを完全にオーヴァーラップさせ伝説にまで昇華させた名作西部劇「ラスト・シューティスト ('76)」にオマージュを捧げることとなる。イーストウッドもジョン・ウェイン同様に身辺整理を済ませ、調髪し、新しい上着まで着込んで、拳銃やマシンガンを携えたギャング・グループの住む一角へと単身赴いていくのだ。
ハリウッド黄金時代の西部劇・・・巨匠ジョン・フォード監督とハワード・ホークス監督の作品群における最も代表的なスターと言えば、誰もが先ずジョン・ウェインの名前を挙げる。
彼等がそれぞれ巨匠や大スターとしてハリウッドに君臨していた1950年代に、イーストウッドはユニヴァーサル映画の若手専属俳優としてデビューを果たし、様々なジャンルの作品で脇役(チョイ役)を演じていたが、当時は一向に芽が出なかった。彼が人々に広く知られるようになるのは、1950年代後半から1960年代半ばまで続いたTV西部劇「ローハイド」であり、そしてその後イタリアへ赴き、
セルジオ・レオーネ監督の下で名も無き賞金稼ぎのアウトロー(「荒野の用心棒 ('64)」, 「夕陽のガンマン ('65)」, 「続・夕陽のガンマン/地獄の決斗 ('66)」を演じ、先ず欧州で人気を博し、やがて逆輸入される形で米国に紹介された頃である。
そして1960年代後半のハリウッドに戻り、多分にマカロニウエスタン的な要素とイメージをアメリカ映画に移植しながら、 新しいタイプの西部劇や刑事アクション物のヒット作を、 1940年代半ばからひたすら低予算のB級フィルムノワール、アクション映画、西部劇等を撮り続け、映画作りの真髄を会得していた類稀なる名匠ドン・シーゲルと組むことによって生み出し、スターダムへと登って行ったのである。
イーストウッド自身があるインタビューで、自分が演出されたかった監督として、ジョン・フォードとハワード・ホークスの名前を挙げている。
イーストウッドもシーゲルも素晴らしい才能を持ちながら、共にアメリカ映画の黄金時代の終焉に現れた若い世代であったが為に、随分と遠回りをしたり、辛酸を舐めつくしたりもしており、 決して恵まれた世代には属していない。彼等の作品に見られる確かな技術力と強い精神力、そして商魂的な逞しさをも含め、全てはこの時代を生き抜いて来た叩き上げならでは実力によるものなのだが、登場する主人公のイメージはいつも王道とは異なる非王道を歩んだが故のアンチヒーロー的な臭いを漂わせている。
「グラン・トリノ」を観終わって、アメリカ映画史そのものとさして変わらない程の長い年月に渡り, 余りにも偉大な功績を残して来た彼等・・・ジョン・フォード、ハワード・ホークス、ドン・シーゲル、ジョン・ウェイン、クリント・イーストウッド・・・という幾つかの素晴らしい固有名詞が、今、一貫してエンドレスなメビウスの輪のような一纏まりのイメージとなってスッキリと我々の前に提示されたような気がする。
昔からの古い古いイーストウッド映画ファンにとっても、また最近の若いイーストウッド映画ファンにとっても、この映画は間違いなく必見の傑作である。








 アメリカン・スナイパー
アメリカン・スナイパー 運び屋
運び屋 ハドソン川の奇跡
ハドソン川の奇跡 15時17分、パリ行き
15時17分、パリ行き リチャード・ジュエル
リチャード・ジュエル クライ・マッチョ
クライ・マッチョ ジャージー・ボーイズ
ジャージー・ボーイズ 硫黄島からの手紙
硫黄島からの手紙 ミリオンダラー・ベイビー
ミリオンダラー・ベイビー モリコーネ 映画が恋した音楽家
モリコーネ 映画が恋した音楽家