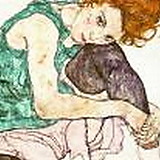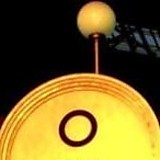イントゥ・ザ・ワイルドのレビュー・感想・評価
全92件中、61~80件目を表示
Happiness only real when shared.
雄大な自然の風景、映画館で見るべきだった。
ドキュメンタリーとして真実に迫るという形の原作だったが、映画ではもっとシンプルに、原作から余計なものをそぎ落として、話の筋・人物の本質を丁寧にすくい上げている。それに映像を肉付けしたという感じ。
映像が訴える力なのかもしれないが、原作以上に、主人公の生の躍動と、逆説的にその愚かさとが、照らし出されていく。
ここでいう愚かさとは、自然に体一つで向き合っていけると信じた主人公の愚かさ、そして、誰かを悲しませることの愚かさ。
一人では、生きていくことはできない。
⋆ favorite
当初ロード•オブ•ドッグタウンを観て、“エミール•ハーシュ” 彼の他の作品が気になり、辿りついたのがこれ。
into the wild
何度鑑賞した事だろう。
これが、実話に基づく話だなんて。
私の映画価値or私の人生を?も?変えた作品の一つ。
ラストは、リアルで怖かった。{いい意味で鳥肌 『生きる。』『生きてる。』
とは?
迷う事なく星5つ。⋆⋆⋆⋆⋆
心に響いた作品。
彼の死は哀しい死であったか?
出生の秘密により心に大きな傷を負った主人公は幼少の頃から夢だった放浪の旅を経て、自分の心の中のわだかまりを打ち消してゆく。その途中で出会う様々な人たちを通して彼の心は変わっていく。
カネも、家族も、名前すら捨て、インチキだらけの社会から脱して正しく、誠実に生きて行こうと必死にもがく主人公の姿には、私のようなスーパー俗物人種も共感を抱かざるを得ない。
そして最期に彼が得たものは何だったのか。
彼は非業の死を遂げたのか?
この作品の舞台はアメリカ全土にわたる。
主眼が置かれるのはアラスカの草原にある「不思議なバス」周辺の美しい自然豊かな土地である。そして複線としてアメリカの砂漠地帯や都市部の光景が描かれる。
その美しい対比描写の中に、実は人類の物質文明に対する懐疑の念と、人間の心の真の美しさとを対比するというテーゼが込められている。
とかく世の中はインチキだらけである。欺瞞、偽善、嘘、経済効果として消費される為だけのモノ、モノ、モノ……。この作品はそんなゆがんだ完全消費型文明に投じられた一石なのである。
作品として非常に難解な命題をはらんだ本作であるが、その映像もまた素晴らしい。
アラスカの山々やそこに生きる生き物たち、アメリカ本土で交流する人々の愛に満ち溢れた姿、山々を下ってゆく濁流、その全ての描写が美しい。
特に眼を見張ったのは、ヘラジカを仕留め解体するシーンであろう。見ようによっては残虐、グロテスク描写にもなりえる動物の解体というシーンを、生命の尊さや神秘性を垣間見せるような表現にまで昇華させている。(グロいけど。)
主人公にほのかに恋心を寄せる役所の少女を演じるクリステン・スチュワートも冷たい水のような美しさを湛えており一見の価値アリだ。
上映時間がやや長く疲れる事を除けば、ほぼ間違いなく名作と言っていいだろう。
全てを支配するもの
主人公の青年は物質的に恵まれて育った。
それが皮肉なことに・・・
親との精神的な繋がりが、希薄であることを強調する結果になる。
若さゆえの純潔さで、自分の中の全てに完璧を求めた。
親の愛、一人で生き抜くこと、自由であること、道徳心。行動力。
自然の厳然たる美しさに、心奪われた青年は何年も旅を続ける。
行く先々で、いろんな人に出会い、愛について学んでいく。
そして、彼は帰ろうとするが・・・
ラストは、ドカーンと叩き落されたような衝撃を覚えた。
自然に1人身を委ねることの、痛々しい現実が牙をむき、
全てを支配する。
どうにもならない、自然の猛威をリアルに描いた作品。
だから、ハッピーエンドでは無いのだ。
個人的に、ラストがリアルすぎて怖さのベクトル振り切れてしまった。
なので、☆3。5。
主役の俳優の演技が鬼気迫るものがあった
社会に帰属するという事
社会に帰属すれば人生は矛盾の連続であろう。
そしてそれを感じ受容できるかという事に関係無く、矛盾は社会の至る所に生まれる可能性を持っている。
社会の基礎と言われる家族の中にもその可能性はあるのだ。
それ故に人の世を離れる事を望む人は多いのかもしれない、他人との関係が無く、矛盾が生まれない場所。
しかし社会に想いが残っていたのならば、例えそれが家族を通したものであれ、その他の人や書物を通したものであっても、人はその矛盾の楽しみと悲しみからは逃れられないのかもしれない。
自然の中にいて社会を感じる事は難しく、また社会の中で自然を感じる事も同様だ。
ただ社会を離れる事、そして自然で生きる事と他人との関係を断つというのは等しいものでないのかもしれない。
既に3度観たが、未だ繰り返し見たい決して見飽きない作品だ
この映画が実話だなんて到底信じたくは無かった!
それではあまりにも残酷だ!何故、こんなにも恵まれた何不自由無い青年の人生の歯車が狂いだすのだろうか?しかもこの若さで、こともあろうに、餓死するなんて!しかも、僅か2週間後に発見されるのだ!もし2週間早くに誰かが彼の存在に気付いていたなら、彼は死なずに済んでいたのだ。
神も仏もあったものでは無い!衝撃と怒りで、打ちのめされた!
彼の人生・彼の家族の人生とは一体何の為に存在していたのだろうか?
妹・母・そして父・・・その後のこの家族はどう生きて行くのだろう?
大学生の若い命と引き換えに、彼が生命を賭けて得た人生訓とは一体何だったのか?
これがフクションなら、へぇ~と一言で終わる、しかし実話なのだ。
アメリカで、経済的には恵まれた家庭に生れ育ち、しかし年頃の影響もあるが父親との仲違いあり、家を飛び出し放浪の旅へと向かう。
その中で、彼は様々な人々と出会い、それぞれの人間の持つ生活歴に触れていく。
生真面目で、感受性が強く曲がった事が嫌いで、勤勉でもある。
そんなGoodBoyな性格が裏目に出てしまうのが人生の皮肉な現実なのかも知れない。
彼がことさら廻りの人間を受け入れられない偏屈野郎というのでもなく、
むしろどちらかと言えば、人が良くて付き合い易いタイプ
これは神さまに気に入られ、この薄汚れた社会で生かすには勿体無いとその命が天に
召されたとしか考えられないような話だった。
自然は厳しく美しい そして変わる事の無い一定の秩序を保ちながら存在し続けている。
その自然の営みの中で、人も生かされている。
人間は多くの人との繋がり、関わり合いの中で活かされて生きるのだ。
自分で生きているようでも有り、
只、自然と活かされているようでもある。
どちらが本当の姿で、どちらが幻なのかは分からない。
しかし、生きている間には、人や、自然と繋がり、自然を司る神との関わり合いも存在しているのだ。
人が生きると言う事、人の生命が育まれて存在し続けると言う事、
都市型生活を送っていると中々、自然から切り離されてしまい、
基本的な人間も動物の一種で、この惑星地球の中で活かされて生きる種の一つに過ぎない事にぶち当たる。
それゆえに、人にとり愛する事、人生の総てに愛と感謝を持って暮す素晴らしさが身に沁みた感動の映画だった。
全ての物は正しい名前で
1ミリも共感できず
こういう映画は主人公に感情移入、自己投影できるか否かが評価の決め手になるが、私はできなかった。
結局は両親との確執がことの発端なわけで、そこに大義名分かぶせて自分をごまかしてるだけの現実逃避。
相当なエネルギーはいるけど、さっさと家に帰って家族と対話をしなさいよ。
金を燃やしたり車を捨てたりと「自分ひとりの力で」と意気込むわりには、文明の捨て方が中途半端すぎて、
なんか単なる自己陶酔だな〜と。
彼が身につける衣服やバッグやナイフや本は他人が作ったもの。
他人のこしらえた文明の力のお世話になってるという時点で、間接的に他人の力に依存してることになり、
たとえ地の果てまで行ったとしてもそれは街の中にいることと本質は何も変わらない。
そこまで言うなら原始人のような暮らししてみろよ。
少なくともバスに住み着いちゃダメだろ!って感じですよ。
彼が「ああはなりたくねえ」と蔑視する人間、つまり都市に住み、会社に就職し、
モノに囲まれ現代の利便性の中にどっぷりつかって生きる人間、
彼らが汗水垂らして作った「植物の本」に主人公は最後の最後に頼り、裏切られ、そして死ぬ。
中途半端な覚悟で文明を敵視した人間にふさわしいなんとも情けない最後で、そこは納得。自然の摂理ですね。
自分探しの旅、、というか。
友達に勧められて観てみた映画。
ノンフィクション映画は好きで、こんな重い結末だと知らずに、ふんわりした気分で観てました。
映画の進行は、時間を行ったり来たりします。
旅の後半、バスを見つけそこを拠点にした生活をするのだけど、
そのバス生活を軸に、
●何故家を飛び出たか、
○バス生活、
●初めに出会った人との生活、
○バス生活、
●次に出会った人との生活、、
○バス生活、、、
といったように。
ただ、この時空の飛びの必要性はあまり要らなかったような、、、
この映画を3行で言えば、
裕福で頭の良い、将来有望男子。
ある日、何もかもが嫌になって『自分探しの旅』へ、家を出る。
あ、自然の中で暮らしてみるかー!
みたいな流れ。
つまり、とっても親不孝者です。
家族には散々な心配をかけさせたけれど、
道中に出会う人達との出会いで、人間として愛を育んで足跡を残していたと思う。
どっちが良い選択肢かは分からないけれど、
私の考えでは、どんなに他人を幸せな気分にさせようと、親家族を悲しませるのは一番の罪だと思う。
例え、どんな家族だとしても。
だから、彼のしたことは良いことだったとは思えない。
だけど、彼は旅の2年半で、普通の人間が生きる残りの人生分、楽しんだと思う。
Happiness is only real when shared.
「幸福が現実となるのはそれを誰かとわかちあったときだ。」
家族と離れ、”孤独”への後悔の気持ちで書いたのか。
それとも、
道中”誰かと分かち合った”時を思い出して、幸せをかみしめて書いたのか。
主役の役者魂は素晴らしい。
まるでドキュメンタリーを見ているようでした。
エミール・ハーシュの演技力に、+0.5で総合4.0です。
自由気ままな旅は、気分を高揚させる
映画「インツゥ・ザ・ワイルド」(ショーン・ペン監督)から。
ストーリーとしては、重たい作品だったが心に残った。
「一度は自分を試すこと」の大切さは伝わった。
「一度は太古の人間のような環境に身をおくこと」の大切さも。
「自分の頭と手しか頼れない、過酷な状況に1人で立ち向かうこと」
それがどんなに人間を強くするか、も理解できた。
しかし、その経験で、死んでしまっては、何も残らない。
こんなメモも、残っている。
「金は必要ない。疑い深くなるしね」
「クリスタルガラスは、もろいからこそ、美しい」
「子どもは親を厳しい目で見るものだ」
「キャリアは20世紀の遺物、僕は興味がない」
「新しい経験が心を豊かにするんです」
「人生の楽しみは、人間関係だけじゃない」
「幸せが現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だ」
一つずつは、私のアンテナに引っかかるのだが、
どれもが「気になる一言」に選ぶには首をかしげた。
そして選んだのは「自由気ままな旅は、気分を高揚させる」。
「どこか逃避を思わせるからだ」の注釈が気に入ったので。
自己犠牲の精神
人生は、究極の「自分探し」の旅なのかもしれない。しかし、旅の途中でいつしか「存在の本質(意味)」に背を向け、瑣末な日常に埋没して生きる人々が大半ではないか。「自分探し」の旅は、「幸福探し」の道程でもあるのだ。この世に生を受けた意味を深く考えた時に、「幸福とは何か?」の答えを手にするのだと思う。怠惰な日常から一歩前に踏み出した時に、私達は新しい自分を発見できるのだ。
この映画の主人公・クリスは、両親の欺瞞性や腐敗した現代社会に疑問を抱き、大学卒業後にアラスカの荒野を目指す。自分自身と真摯に向き合うために、過酷な環境が必要だったのだろう。退路を断つために、途中で車を乗り捨て、手にしていた紙幣も燃やす。バックパックを背負い、「自分探し」の旅が始まる。
お金や出世に関心がなく、旅の途中で出会う人々に癒しを与え、ひたすら荒野を目指すクリスの姿は、まるでキリストを彷彿させる。クリスは愛称で、本名はクリストファーと言うのだが、少年に姿を変えたキリストを背負って、川向こうまで運んだとされる、半伝説的な殉教者(クリストフォロス)の英語形なのだ。キリスト教の精神を担うことの高貴さを表す名称だという。
アラスカの荒野を目指したクリスだが、キリストもまた荒野で修行している。新約聖書に書かれているのだが、40日間の断食を終えて空腹になったキリストの前に、悪魔が現れる。悪魔の誘惑を退けた後、彼は宣教の旅を始めたという。
旅の途上で、クリスも様々な悪魔?の誘惑を受けるのだ。16歳の女の子からの性的な誘惑を断ったり、麻薬常習者がたむろするヌーディストグループにも加わらず、ストイックな生き方を貫くのだ。アラスカの荒野に着いて数ヵ月後、狩りをしても獲物が見つからず、何日間も断食状態が続く。ある日、空腹を満たすために「ワイルド・ポテトの根」を食べて飢えを凌ぐのだが、それは葉形がよく似た毒性のある別の植物だった。
その後、ヘラジカ狩りの猟師によって彼は遺体となって発見される。死因は餓死だった。彼を題材にした「荒野へ」という作品は全米ベストセラー・ノンフィクションに選ばれ、この映画もアカデミー賞にノミネートされた。それぞれの作品から、多くの人々が勇気と希望をもらったと思えば、キリスト教の精神である「自己犠牲」を担った死だったのかもしれないのだ。
彼が読んでいた本の行間に「幸福が現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だ」というメモがあったという。彼は「自分探し」の旅を完結させて、別の新たな旅に向かったのだろうか?
映画作家ショーン・ペン、ここまで到達しましたか。
俳優としても監督としても大の苦手なショーン・ペン。
それでも本作の評価は全般的に良く、DVDで拝見させて頂きました。
経済的には恵まれているが、精神的に不遇な家族で育った若者が大学卒業と同時に、放浪の旅に出る。目的は「大量消費社会から脱し、荒野の世界で人生の『真理』を見つける」こと。それは若者なら誰もが持つであろう大志であり、それを実行に移す実在した主人公の熱意には共感するものあり。(世の中で使われている『熱意』という言葉は苦手だが。。。)
もちろんそんな若者は、見方を変えれば自分勝手である。
そんな葛藤からある意味、逃避するように彼は荒野へ突き進んでいくが、そこには心の必然性があるからそうしているのだ。誰も止めることが出来ません。そんな世間知らずな主人公の情熱を見ることで、逆に大切なことも学ばされるのです。
旅路で出会う人々との触れ合いや、大自然に囲まれて成長していく主人公の姿を描くと同時に、残された&残されていく彼を愛した人々の声が描かれているのが、それまでショーン・ペン監督になかった感性だと思います。
そうか、この監督さんも色々な葛藤と悩みを抱えながら、少しずつ成長していったんだね。。。そう思えると、他人なのに励まされているのはわたくしだけではないと思います。
あの最後をどう解釈すべきなのでしょうか?
それはもちろん千差万別であるが、途中から導入された「神」の視点を入れると、人生は残酷なのか愛に満ちているのかという二律背反に悩まされてしまう。この作品は、普段の日常感覚を抜け出して、大きな視点で人生を、世界を見つめることに誘います。
ここまで親身になって考えながら鑑賞した作品は久しぶり。
でも、なぜか評価にAはあげたくないんだな~。
それはやはりあの終わらせ方にあるのだと思う。だってわたくしは仙人になるつもりはないのですから。
目が覚めた!
ストイックな者だけが得る事の出来る世界
好き嫌いが分かれる作品かも。。。
皆さんの評価は高いんですね・・・。
2時間半という長編で、中盤からは彼の日記を元にロードムービー風の
ただひたすら主人公の日々が流れていような感じ・・・。
ショーン・ペン監督最高傑作!との噂。
”荒野へ”というのがこの作品の原作です。
正直、久々に中盤睡魔に負けちゃいました・・・。
中盤以降は、アラスカの大自然が美しかったり、
老人との温かい交流があったり感動の場面も色々ありました。
が、最終的には私には理解しきれず、結末には
「何で死ななきゃいけないんだよっっ!」という
怒りに似た感情さえ残っちゃいました・・・。
なんだか、自ら命を粗末にしているようにしか思えなくて。。。
正直、こういう死に方を美化する作品はあまり好きではありません。
好き勝手して、残された人の気にもなってみてよ!
もっと頑張って生きようよ!!と言いたくなります。
心に残ったのはこの言葉です。
「幸福が現実となるのはそれを誰かとわかちあったときだ」
気付くのがあまりにも遅すぎて・・・命がもったいないです。
主演のエミール・ハーシュはかなりの演技力で今後の彼に期待ですね~、
楽しみ。
好き嫌いがとっても分かれる作品だと思いました。
全92件中、61~80件目を表示