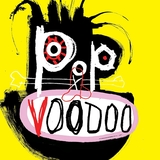プライベート・ライアンのレビュー・感想・評価
全192件中、81~100件目を表示
何回見ても色褪せない
模範解答
まあ、歴史の教科書を読めば「米国×ナチ=米国勝利」やけど、要するに、そのまんま模範解答。そんなん、誰でも知ってるし、他の視点の結論が観たかったんやけどな。
ていうか、ドイツ側の兵士の「ストーリー(人生)」や「人となり」も描いたれよ。こういう描き方やと、米兵だけ「人間的な悩みや葛藤」があって、ドイツ兵は脚本上、ほぼ沈黙させられてるが故に、殆ど「殺人機械」でしかないし。実際、ドイツ兵にも、色々(例えば家族いるとか)あったやろ。別にナチを美化しろとは言わんけど、現場の徴兵士の苦悩は万国共通やろうし。
結局、「戦争」を「善と悪の闘い」に「矮小化」してる作品で、故に結論も丸見え。観念的な創作物で、現場感覚の欠如。ラスト・シーンで星条旗が、はためいてるのが、サブ過ぎるし。
戦争での殺され方がリアル
面白かった
面白かった
主人公が”部下数人を死なせても結果何千人救えればいい。そう割り切るしか無い” と述べるが
本作は”ライアン一人を救うため、自分と部下がほぼ全員死ぬ”結果になっている。
そこに無情さと皮肉が効いてて面白いなと感じた。
また、そもそも戦争で命の数の釣り合いが取れないことを見せ続けることでその中でも繋いだライアンにへのメッセージ。 ”しっかり生きろ” がより強く説得力ある言葉となっていた。
見せたいものがはっきりしている映画は好きですね
おすすめの映画
1998年の映画とは思えないほどのクオリティ
リアルだ、リアルだ、と今まで映画を見て評価する時に使っていたけれども、今まで自分が言っていたリアルは、リアルではなかったかもしれない。
これこそがリアルだったのか。
それほど現実味のある表現力。
身に付けている服や、風景や、音や空気感、演技、全てがリアルだった。
船で浜に向かうシーンの、緊張や強張り。
死にたくない、覚悟と祈り。
容赦なく連射される銃弾。
銃声、爆発、悲鳴、叫び、水中に貫く弾丸、血、傷跡、失われる身体、耳鳴り、混乱、炎、震え、怒り、悲しみ。
自分がそこにいる様な感覚に陥るカメラワーク。
あえて、ブレる様にしているのか、それによって焦りや恐怖が伝わる。
冒頭の戦争シーンが本当にむごくて怖くて、泣けた。
とにかく「音」が、本当にすごかった。
今回はDVDで観たけどこれを映画館で観たら、もっと凄いだろう。
耳鳴りや水面から上がったり潜ったりするときのシーンが、特に印象的だった。
リアルな戦争描写
選ばれた精鋭は8人ー彼らに与えられた使命は若きライアン2等兵を救出する事だった…
原題
Saving Private Ryan
感想
冒頭30分の上陸作戦は迫力があり何回観ても飽きないです。
片腕を失った兵士が腕を探してたり、はらわたが飛び出した兵士がママーと泣き叫んでたり、隣にいてさっき話した通信兵が死んでたりと戦争の悲惨さ感じました。
精鋭8人を紹介します。
ミラー大尉ー頼りがいのある大尉、高校教師
ホーバス軍曹ー小太り、鈍足、土コレクター
ライベン一等兵ー口が悪い、直情的で短気
ジャクソン二等兵ー狙撃手、カトリック
メリッシュ二等兵ー口髭、ユダヤ系
カパーゾ二等兵ー大柄、人情味溢れる
ウェイド四等技能兵ー衛生兵、人当たりのいい青年
アパム五等技能兵ー通訳、気弱
一人の為に八人の命をかける意味はあるのかと考えさせられます。
※フーバー
それぞれのライアンを救うこと
ノルマンディー上陸後、兄弟が全て亡くなったライアンを母親の元に返せという任務のため戦場へライアンを探しに行く兵士たちの話。
.
Privateは名前の前につけると「二等兵」って意味になるらしいんだけど、一般的に使う「私的な、個人の」意味とこの映画の内容的にかかってるんかなと思った。
.
ライアンを救うことは、ミラー隊長にとって胸を張って家に帰れるようになるための任務。そのためには、1人死んだらその倍の人数を救っているという信念とは真逆の1人のためにたくさんの犠牲を払うことをする。
.
そしてアパムにとってライアンを救うことは、男になることかなと思った。仲間を殺した敵兵でも丸腰の捕虜を殺さないという信念に背いて、最後自分が助けられなかった仲間を殺した捕虜を撃ち殺す。
.
他の人に関しては分からなかったけど、それぞれ胸の内に自分にとってのライアンを救うことの意味があって、それがタイトルとかかってるのが良い。
.
まぁ、冒頭の戦場のシーンでぐっと引き込まれるだけに途中間延びしちゃって、さすがに3時間は長い(笑).
面白かったです
序盤のノルマンディー上陸作戦の描写。とてもリアリティを感じました。血に染まった海水や、千切れた腕を持って正気を失っている兵隊。戦争ってこういうものなのかと考えさせられました。
でも実際どうなんでしょう…。実際に戦争を経験したことのない自分がこの描写を観て「戦争は残酷だ」と評価することは正しいのだろうか…。久々に戦争映画を観てこんな余韻に浸っています。
それと、この作品で最後まで気になったことが2点。
一つ目は「なぜライアンを救出すること」が最重要の任務になったのか、普通に考えればそんな費用対効果が低いことはしないはず。ライアンとはいったい何なのだろうか…。ただの救出作戦ではないなんらかのメタファーなんじゃないか。わかりません。
二つ目はミラー大尉の手の震えについて。最初は「この人はパーキンソン病を患っているにでは?」と思っていましたが、結局語られることはなく…。彼の過去と繋がりがあるのか、単純に戦争のせいなのか、ゆっくり考えてみます。
特にラストが秀逸
アメリカ映画的な要素が残念
序盤のノルマンディー上陸作戦の戦闘シーンは圧巻。
兵士目線で海の水面に出たりもぐったりするカメラワーク、その時の音。
「生きて帰れない」「多分全滅する」と直感しつつも、その浜に投げ込まれたら退路も無く、地獄の光景の中をただただ這って前に進むしかない。どう行動すれば生き残れるわけでもなく、弾に当たるか当たらないかは運としか言えない。すさまじい臨場感。戦争映画は数あれど、ここまでの映像は他にはないのではないだろうか。
ただ、映画の終盤、絶体絶命のところに味方の戦闘機が来てサラッと形勢が大逆転して勝利する点や、映画の始まりと終わりに戦没者の墓や星条旗をもってくる演出が、やはり「ヒーロー映画」を求める「アメリカ映画」だなと感じて、終盤にサーと冷めてしまいました。
I'm a schoolteacher. I teach English composition...
人には温度差があって、わたしがいいと思った映画でも、相手にはそれほどでもない、ということは、よくある。わたしはまだ若く、いいと思った映画を周囲に喧伝するたちだった。当時、この映画に感動し、何人かに「いいから見ろよ」と言ったのをよく覚えている。それを、この映画以降、しなくなった。人は、人それぞれであることを知ったからだ。くわえて、この映画に感じないなら、じぶんと他者の壁など、とうてい克服できないと思ったからでもある。そういう映画だと思う。
高校教師だと明かすシーンが好きで、なんどもなんども見る。
フーバー!
この作品が本当に反戦映画か?という議論があった。それはある意味正しく、ある意味正しくない。ストーリーの展開でライアン(マット・デイモン)を見つけてから“橋を守る”ということが中心となってしまい、単なるアメリカ万歳の戦記モノに成り下がってる雰囲気があるからだ。トム・ハンクスやエドワード・バーンズ、そしてマット・デイモンの視点で見てしまうと、どうしてもそう感じる。
ところが、実戦経験がないのにドイツ語・フランス語が話せるというアプム(ジェレミー・デイヴィス)の視点に立つと、戦争の恐怖、嫌悪感がグサリと突き刺さってくるのだ。捕虜に対する扱いにおいて、ともかく「違法だ」と他の復讐に燃える兵を戒める姿。なぜだか印象に残ってしまう。そして、最後に彼がとった行動・・・降伏したドイツ兵が「アプム」と叫ぶ。そしてその彼を撃ってしまう・・・途中の廃レーダー基地で逃がしてしまったドイツ兵だ。
さらに映像・音響面、冒頭のオマハビーチではとにかくアッという間に味方が殺されていく様子。阿鼻叫喚という言葉がピタリとくる残虐な戦争。これが戦争なんだよと訴えてくる映像には反戦意志そのものがあるんだけど・・・
ヴィン・ディーゼルとかポール・ジアマッティとかいい味だしてたし、上陸作戦では顔すらわからなかったけど、それぞれの人物像などがわかりやすい。それが救出作戦というヒューマニズムに繋がってしまうのは残念。ライアンは無情にも死んだほうがいいはず。プロローグとエピローグで登場する老人がアプムであることを祈ったのに・・・
全192件中、81~100件目を表示