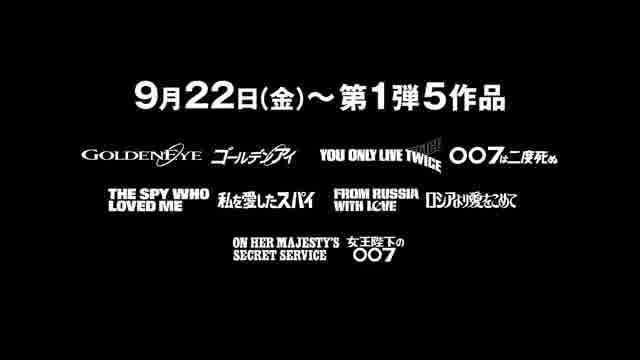「気迫と本気が全編にみなぎるシリーズ屈指の大傑作」女王陛下の007 村山章さんの映画レビュー(感想・評価)
気迫と本気が全編にみなぎるシリーズ屈指の大傑作
クリックして本文を読む
本作一作だけで終わった二代目ボンドのジョージ・レーゼンビーは、昔は「ハズレのボンド」扱いでさんざんバカにされていた印象があるのだが、その後、本作をクリストファー・ノーランとかソダーバーグとかが絶賛したり、ダニエル・クレイグ時代にも元ネタにされまくったりで、最近ではすっかり傑作認定されている。あまりのギャップに戸惑いもありつつ、個人的には一番好きなボンド映画であり、シリーズがマンネリに陥るごとにこの作品を手本にしたハード路線に回帰するのも納得だ。
ショーン・コネリー時代は最初期にはハードボイルド風味もあったものの、たちまちシリーズのテイストはユルくなり、ロジャー・ムーア時代も併せてふざけたアクション・コメディと呼ぶのが順当だと思うが、そこにいきなりハードコアな描写をぶっ込んできたのが本作。それまで監督のピーター・ハントはシリーズの編集を担当しており、「自分ならこうする!」というアイデアを溜め込んでいたらしい。
実際、始まった瞬間から「なんだこのキビキビした映像と編集は!」と、明らかにそれまでと路線が違うことが伝わってくる。当時の低評価はテイストが激変したことへの抵抗感だったんじゃないか。いまの感覚から見るとまだまだのどかに感じられるかも知れないし、特に前半は多少のタルさはある。が、特にボンドの脱出劇以降は映像、編集、演技のすべてに気迫がみなぎっているし、ラストシーンは数あるボンド映画で唯一、何回観ても涙ぐんでしまう。あの最後の表情が出せただけで「レーゼンビーを大根役者とは呼ばせないぞ!」と息巻いております。
コメントする