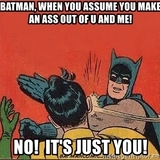市民ケーンのレビュー・感想・評価
全42件中、1~20件目を表示
後の映画関係者に多くの影響を与えた名作
男は孤独だった。
技術的なことは多々あるが
そこを超えて感じるのは
人の世、貧しさの幸せとは
富を掴んだ男の幸せとは何か
メディアの時代
富を築いた男の死
その活力の秘密
なぜ、何故、なぜ
それを探る物語。
収集した多くの物
男が最後に思った
いちばん大切なもの
他人には分からないもの
その姿に気持ち動く。
あの雪の日
あの温かさ
あの呼び声
※
本当に欲しかったもの
『市民ケーン』は、単なる映画史上の金字塔ではなく、人間存在と社会構造を多層的に暴き出す作品だと感じました。
第一に、これは心理劇です。主人公ケーンは幼少期、母親の意思で銀行に「売られ」、父からは暴力を受けて育ちました。その結果、安全基地を失い、愛を信じることも他者に愛を与えることもできなくなってしまう。彼が愛した女性たちも、結局「愛」ではなく「依存」の対象となり、相手の主体性を認めることができなかったのです。幼少期に愛を失った人間は、その欠如を埋めるために権力・財力・支配を求める。しかし本当の愛とは、他者を他者として受け入れることであり、支配や依存ではない。ケーンはその差を生涯越えられませんでした。ローズバッドとは、彼が唯一「無垢に愛された時間」の象徴であり、最後まで求め続けた両親からの愛(特に母の愛)の記憶だったのだと思います。
第二に、これは社会批判です。新聞というメディアが世論を動かし、戦争すら作り出す力を持った時代に、ケーンはメディア王として頂点に立ちます。しかし富と影響力を得れば得るほど、人生は空虚になっていく。権力と名声の裏側に「愛の不在」という決定的な空洞があり、公私の境界を失った孤独な姿が描かれています。
第三に、本作は歴史的寓話としても読めます。アメリカが台頭し、物質主義が倫理を凌駕していった時代、その矛盾と影を一人の男の生涯に凝縮させた。実際の新聞王ハーストをモデルにしていること自体が、現実の権力闘争と直結していました。
ディープフォーカスやローアングルの多用、緻密なミザンセーヌ(舞台装置)といった技法的革新はよく語られますが、それらは決して実験に終わらず、この三層構造を支えるために統合されています。『市民ケーン』は、人間の心理・社会の構造・時代の寓話が重なり合い、映画という表現の可能性を一気に切り開いた思想的傑作だと思います。
鑑賞方法: Blu-ray
評価: 93点
哀れな権力者を描いたオーソン・ウェルズの処女作
ケーン(オーソン・ウェルズ)の一生を描いている物語。ケーンは架空の人物であるが、製作・監督・主演を務めた当時25歳のオーソン・ウェルズは、メディア界隈の有名人を敵に回すような内容を無名の俳優だけで映画にしてしまい、干されるきっかけになった伝説的処女作。
「バラのつぼみ」というキーワードも、実は皮肉じみており、メディア界隈の有名人の逆鱗に触れてしまった。
オーソン・ウェルズ自身も主人公ケーンを悪人とハッキリ言っている(円盤の特典映像より)。
その当時は斬新な撮影方法など話題になり、しばらく何年もの間、評論家達からも絶賛され続けたらしい。
面白くないのに何度も観れる。
全部を知り尽くしたくなるような魅力がある。
孤独な男の肖像
はじめ、この題名を聞いたとき何それ!?
原題と邦題は同じ
普段そんな言葉を見聞きしないですよね。
「私、市民naokiです」(←共産主義の方でも使わない)
題名が「新聞王ケーン」なら分かりやすいんですけど陳腐ですね・・・
やっぱり市民ケーンは、しっくりきます。
私この映画を30年程前に池袋文芸坐で「第三の男」と二本立てで
鑑賞したのですが、あろう事か市民ケーンを途中から観てしまいました。
それでも、スクリーンから放たれる光と影に圧倒されたのを覚えております。
話は単縦でしたから、だいたいの流れは理解できました。
のちに深夜TVで市民ケーンが放送されてましたが、
あれ、影の色がつぶれてる・・・に気づき観るのをうせてしまいました。
私は、そこでシナリオや俳優の魅力以外に映像の役割に気づかせるきっかけとなった作品でした。(映画館で観れたものがTVでは観れないて・・・)
今やYou tubeで全編観れますが、それでは意味がないので、
待ちに待って今回のフィルム上映を鑑賞する事ができました。
(日本初公開時の清水邦夫さん字幕監修)
この映画館では、たいてい字幕のついていない直輸入フィルムのせいか
日本語をスライドで投影する(すごい手間!)ので
少し画面が切れていたりします。(これは、これでしょうがないんですけどね)
しかし今回は切れる事なく画面がビシッと決まってました。
フィルム上映て何回も通っていると今回の映像技師さんは最初から
ピントが合っているので上手いなぁとか気づいてきます。
日本語字幕のフォントもきれいに映りこんで手書きの美しさなのでしょうかね。
本題ですが、まぁただ圧倒されてしまったの一言です。
はじめ懐古趣味で観ましたが、この映画が80年以上前に作られたなんて
信じられません。この前観た「シビル・ウォー」以上に興奮しております。
今、You Tubeで市民ケーンに関する考察をいろいろ参照しております。
特に町山智浩さんのローズバッド🌹の解釈について冒頭のケーンの唇のアップは、あぁなるほどなぁ納得しました。
小津安二郎監督は、このカット割には怒っておりました。
途中、エクスファイア社での祝賀パーティー🎉で
ケーンとダンサーが踊るシーンはジョン・オルコット(「時計じかけのオレンジ🍊」の撮影監督」が助手として撮ってるんじゃないかと錯覚しました。
この映画は技術的には、もちろん優れているのですが、
ケーンという男の孤独が色濃く描かれています。
愛人スーザン主役のオペラで拍手しているのはケーンだけ、
ザナドゥという城で寒々しく響くケーンとスーザンの声。
スーザンが去って行った後にケーンが彼女の部屋を散乱するシーンは、
ただただ悲しかったです。(若い時に観たときは何も感じなかったんですけどね)これに比べたら「野いちご」のイサク・ボイル医師は孤独じゃないなぁ。
まだ二十代の若さで人生を見渡した、こんな脚本書けるなんて凄いんですが、
共同脚本のハーマン・J・マンキウィッツよる功績が大きいです。
Netfelix「マンク(監督:デヴィッド・フィンチャー)」参照
後世に多大な影響を与えた、一大人間ドラマの傑作。
「バラのつぼみ」という言葉を残して死んだメディア王、チャールズ・フォスター・ケーンの生涯を、彼を知る関係者に次々と取材する、ニュース新聞の編集記者を通して描いたドラマ。
本作以前にも無かったことはないだろうが、主人公の稀有な生い立ちや、成功から挫折に至る人生を取り上げ、関係者の証言を通じた回想という形で描くのも、本格的に明確に提示した、初めての作品では無いかなと。
狂言回しの存在や、「バラのつぼみ」の結末も、後の映画やドラマで、頻繁に使われている手法だ。
後世の作品に、非常に多大な影響を与えた作品と思う。
個人的には、時の流れをゆるやかに、ゆったり描いた映画だと思った。公開当時としては、画期的かつ独創的なストーリー運びで、メディア王の生涯を実に興味深く、壮大かつ大胆に描いた、一大人間ドラマの傑作だ。
映画史に残る大傑作???
よくわからんので2回観た(笑)
いや、ちょっと違いますね、分からなかったのは間違いないのですが、印象的なシーンが多かったのでもう一度…という気持ちも。
この映画を観るに至った経緯ですが、「映画史に残る名作」で検索したら出てきたのですよ。「2001年宇宙の旅」と「8 1/2」と一緒に。で、思ったのが検索方法間違えたかなーということ(笑)いや、つまらなかったとかそういうことではなく、この「映画史に残る」っていう検索方法だと、制作サイドの観点から選ばれた作品が多く挙がるんですね。撮影技法だとかに焦点を当てた作品です。はっきり言って素人にはさっぱりわかりません!(笑)でもこの「市民ケーン」はそういう技術の話を抜きにしても楽しめました。
全てを手に入れ、全てを失った男が最後に残した言葉…。その真相を目の当たりにし、愕然としました。なんと哀れな男。ラストシーンではそれまでのケーンに対する印象をちゃぶ台返しされたような衝撃。しばらく口開けて放心状態でした(笑)
随所に散りばめられた工夫を凝らした撮影方法…私は片手で数えれる程度しか気付けませんでしたが(笑)でもそれ以上に純粋に喜悲劇として楽しめました。
映画史上最高作
モノクローム時代の大傑作
オーソン・ウェルズ主演脚本監督作。
【ストーリー】
メディア王チャールズ・フォスター・ケーン(オーソン・ウェルズ)が、ザナドゥ城と呼ばれた自らの邸宅で死んだ。
スノードームを手に、たった一言「バラのつぼみ」と言い遺して。
その言葉の謎を解くべく、ニュース映画の編集者ジェリー・トンプスンはケーンの過去を暴きにかかるのだが、浮かび上がるのは、空虚で悪趣味な邸宅にこもる、孤独な男の姿だった。
それは、かつて栄華をほこったメディア王のイメージとは、大きくかけ離れたものであった。
シミケンこと市民ケーンです。
主演脚本監督すべてを手がけたオーソン・ウェルズの事をほぼほぼ知らずに鑑賞しましたが、これが面白いのなんの。
場面をいろんなアングルから撮影し、カメラを自由に動かし多彩な演出を展開しつつ、白黒なのにレイアウトも分かりやすく工夫されているので、退屈せず理解もしやすく作られております。
この人、映像作家としても優秀なんだなと。
英語教材『家出のドリッピー』が代表作じゃなかった。当たり前だ。
かなり興味をかきたてられてWikipediaの記事を読んで、この映画への評価の不遇さに腹を立てるも、そこからさらにオーソン・ウェルズを調べてダメだコリャと笑ってしまいました。
なんというか、天性のエンターテイナーで稀代の詐欺師ですね。
初ステージに上がったエピソードもそうですが、あっさりと人気者になって都会に移り、この映画を撮るまでの経緯も破天荒で、どんだけ無茶するんだこの人と。
この映画も、当時のメディア王ウィリアム・ランドルフ・ハーストを思いっきりモデルにして、最期を孤独に終わらせるとか、そりゃ激怒されますわ。
個人的な感想としては、ハーストを悪く描いたとは思いません。
ハーストって人はこんなもんじゃない、自分のメディアで酷いことしでかしまくった超悪党ですから。
ぴっちり2時間の長編ですが、それに堪えうる画面づくりで退屈を吹き飛ばしてくれる一大ドラマ。
空き時間に流し見するつもりでしたけど、Amazonプライムでは吹き替えがなくて、結局ガッツリ世界観に取りこまれてしまいました。
映画に浸りたい休日前の夜に、ピッタリの一本ですよ。
今は昔のドラマツルギー作品とマクガフィン
とんでもない予算をかけて作られた映画だと分かったけれど,今の時代に...
とんでもない予算をかけて作られた映画だと分かったけれど,今の時代にこれを見てそれほど感嘆するべきことがあるのかどうか自分にはわからない.野心と志を持って財を成した人物が,実は自分がかわいいだけであると周囲の人々から見透かされてしがない生涯を終えるという話はそれほど珍しく盛んなくなってしまった.女性を美しく撮影するような光の当て方と,ケーンの顔を切り取るように光と影が横断しているところは面白いと思ったけれど,それ以上に映像として印象深いところはないかな.Rose Budという言葉は結局幼少期のサッチャーに引き渡されたシーンに回帰して,すべての始まりだったあの別れが無ければというたらればを回想したという話だったのかもしれない.
実在の大物実業家の心理を探求
激しいジャーナリズム戦争を巻き起こしたメディア王の生い立ちをミステリーのようにたどることで、何が彼をそこまで追い立てたのか、その心の内を明らかにしていった意欲的な作品。実在の大物人物を扱うのはなかなかできることではない。25才と若かったからできたのかも。ラストに明らかになるオーソン・ウェルズの出した結論には納得だった。
技術的には映画の教科書とされているそうだけど、主人公の老け顔がメイクで上手くできてること以外は特に意識しないで見てしまった。
思い込みが激しい新聞王
玄人向けの復習映画
名作中の名作。THE映画。
って感じの映画でした。
正直一回観ただけではこれがすごいとはならない。
根源的映画だからこそ、予習のための映画ではなく、色々な作品を観た後で復習として観た方が、この映画の偉大さが分かる気がしました。
とりあえず、これでいつでも『Mank』は観れそうですが。出直してきます。
ストーリーは至ってシンプル。
アメリカの新聞王、チャールズ・フォスター・ケーンが死に際につぶやいた『Rose bud』ーバラのつぼみ、という言葉の謎を追うために生前調査を行い、彼がどんな人物で「バラのつぼみ」とは何を指すのかを、回想を交えながら探っていく119分。
非常に多くの映画に影響を与えた作品のようで、成功者の成功からの堕落というよくあるストーリーは、まさにアメリカン・ドリーム。
メディアによって形成されたアメリカという国を非常によく表した映画なのだと、町山さんの解説をチョロっと聞いて知りました。なるほど。
素人の自分でも、映像技術が素晴らしいということはよく分かりました。
次はどんな撮り方をしてくるんだと、ワクワク。
観ているこちらを飽きさせない、工夫に富んだ映像の数々は影響を与えたどころか、現代の撮影方法を持ってしても敵わないような気がします。
当時こんなものをスクリーンで観たら、衝撃どころでは済みませんね。
映像・音響は100点満点でしょう。
登場人物が多くてこんがらがったのも事実。
何度も観て深めたい一本です。
市民ケーンの市民権
なんでもないです。
バラのつぼみ-ROSEBUD-
アカデミー賞では脚本賞を受賞したようですが、最も印象に残るのは編集や撮影の妙。亡くなった新聞王の過去を“バラのつぼみ”という謎の言葉を解き明かすためにインタビューを続けるニュース映画記者。インタビュアーの姿がまったく印象に残らないほど、インタビューに答える元妻や同僚たちが引き立たせているのもドキュメンタリータッチにするためか。その過去のエピソードが年代もバラバラに扱っている編集と、全てを演じ分けているオーソン・ウェルズの姿が面白い。この編集者が『サウンド・オブ・ミュージック』や『ウエストサイド物語』のロバート・ワイズだったことも興味深い。
撮影でも、後の『第三の男』に使われる影の多用。不自然なくらいにウェルズ本人に影がかかったり、奥行きの深さを出すためだけに影だらけの手前の人だったり、特撮のような効果さえ出していた。
大富豪になり、何もかも手に入れることができた男の人生。しかし、そこにはポッカリと空いたピースがあるのだ。それが妻の愛か、亡き母との思い出か、それとも市民の心だったのかはわからない。州知事選で敗れたことで、直前の情事が暴かれた事実があったにせよ、その空虚・孤独がケーンの心を占めたに違いない。何もかも思い通りにできると思い上がりは見え隠れするものの、正直であることが彼の信条。ところが、やはり何もかも手に入れた後に、足りないものに気づかされたのだろうか・・・エンディングの焼却炉にくべられるガラクタ美術品の中から子供時代に遊び親しんできたソリに“ROSEBUD”の文字がくっきり浮かび上がる映像が凄い。
それにしても何度も登場する“城”。権力や財産の象徴であるかのような大邸宅ザナドゥに圧倒された。モンゴル(元)皇帝クビライ・カーンの作った都が語源。ミュージカルや色んな会社の名前にもなっているけど、今ではビル・ゲイツの私邸が「ザナドゥ2.0」と呼ばれているらしい。彼もまたケーンのような孤独を感じているのだろうか・・・と思ってたら、昨日離婚したらしい。
見返す度に、いろいろな思索にはまってしまう。中毒性のある映画。
「No.1映画」と紹介される作品。
でも、余程の映画通でなければ、初見では「どこが?」となる。
まるでこの映画の主人公のようだ。
新聞王・広大で豪勢な(ノアの箱舟にも比される)館の主・世界で〇番目の金持ち。権力をふるい人や世間を思うがまま操った人物。人がうらやむ成功者。だが、その実体は?
一人の男の一生をたどる旅、「薔薇のつぼみ」というキーワードでひっぱる。面白そうな設定なのだが、「No.1映画」として期待すると、今一つ面白くない。
何より、人たらしのウェルズ氏がコミカルに演じている人たらしな男の話のはずなのだが…。
エンタテイメント的な面白さを期待すると「つまらない」になってしまう。
しかも、特殊メイクが発達していない頃の作品。若干20代のウェルズ氏が、老年まで演じるのだが、メイクや体の恰幅の良さを出すため?力士の着ぐるみ着ているようで動きがぎこちなくて、せっかくの名演を殺してしまって…。
でも、何度も観ているうちに、初見では軽く見過ごしてしまったところが見えてきて、解説等も参考にすると、そこかしこに唸ってしまう箇所等、宝の山だらけ。
今普通に使われている撮影技法や演出等を始めて採用したのだとか。
ああ、専門家に評価が高いのが納得してしまう。
でも、そのような技法だけではない。
テーマ。
人の一生は所詮スノードーム?欠けている何か。生涯かけて取り戻したいもの…。
成りたい自分と、期待される自分、そして成った自分。そのせめぎ合い。
虚と実。「あなたは約束守らないでしょ」なのに、表明したがる”宣言”と”公約”。
中身がない、何も実のある事を言っていないのに、立派なことを言っているようで。しかもそれをありがたがる大衆。
世論操作。ちょっとしたきっかけで変転する大衆が信じる”真実”。
パズルの一片。そして全体像。
何が重要で何がガラクタなのか。その人にとっての価値。他人から判定される価値。
等々、万華鏡のように、鑑賞者がどこに焦点を当てるかによって、様々なイシューが立ち現れてきて、心と思索の罠にはまってしまう。
きっと、これからも観返す度に、上記に上げたこと以外にも、もしくは上記に上げたことでも感じ方・考え等が変わっていくのだろう。
まるで、深淵なる哲学書を紐解くようだ。
そして、工夫を凝らした映像。
ホラー的な映像で始まり、何が起こるのか期待値を高める冒頭映像。
スノードームのガラスの破片越しに見えるドア・看護師の動きが、とても意味深…。
リーランドから歴史的に価値があるともてはやされた後の、ひきつった笑顔が表現するもの(これはDVDの特典映像で、ウェルズ氏が意図を語っている)
同じシチュエーションで物語る年月。最初の妻、二番目の妻との関係性の変化。
スーザンの顔に移る影で表現する牢獄。
アリスの世界に誘われそうなドア、鏡。
梱包されたままに放置されたものの間を蟻のようにうごめく人間たち。
一つ一つのシーンを止めて”研究・鑑賞”したくなる数々のシーン。
解説者が必ず例示する有名なシーンでも、その人なりの発見(意味付け)がありそうな。
まるで、おもちゃ箱。
興味が尽きることがなさそうだ。
そんな興味深い映画で、人たらしのウェルズ氏が作って演じているのだからおもしろいエンタティメントになるはずなのだが、
ケーンの、そこまでするかというパワハラ・モラハラ度が前面に出すぎてしまって、その奥に隠れている空虚さ・わびしさはわかるが、カタルシスが得られる流れになっていない。
実在の人物をモデルにしていると言われているが、リスペクトがまったく感じられずに、コケにしているようにも見える。
世間的にもてはやされ、何もかもを手に入れた男の、隠された内面の叫びを映画を通して体験できたと思える時と、
世間的にもてはやされ、何もかもを手に入れた男だが、内面は、空虚感に支配された、ガラクタ(芸術品でも梱包されたままならガラクタ同然)だけを手にした、つまらない男というオチにも見える。
ベビーフェイスを活かした、もっと魅力的な男としてのキャラクターを出した場面と、そうでない場面を見せてくれればいいのに、どの場面を見返しても、唯一の味方?理解者?のバーンステインの回想場面でさえ、ケーンのいやらしさがまき散らされていて、ケーンに共感できない。
だから鑑賞後感が悪くなる。
どうしてこんな風に作ったのだろう。
『マンク』を見ると謎が解けるらしい。
MANKに備えて『市民ケーン』を鑑賞。 こんな映画だったのね。一般...
全42件中、1~20件目を表示